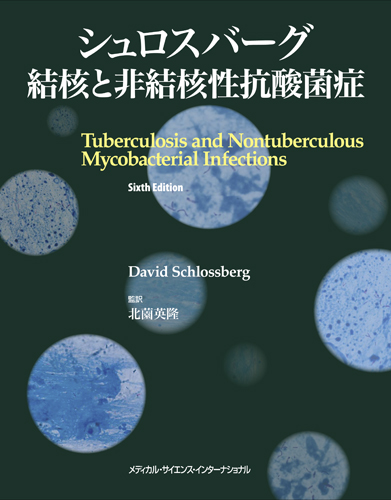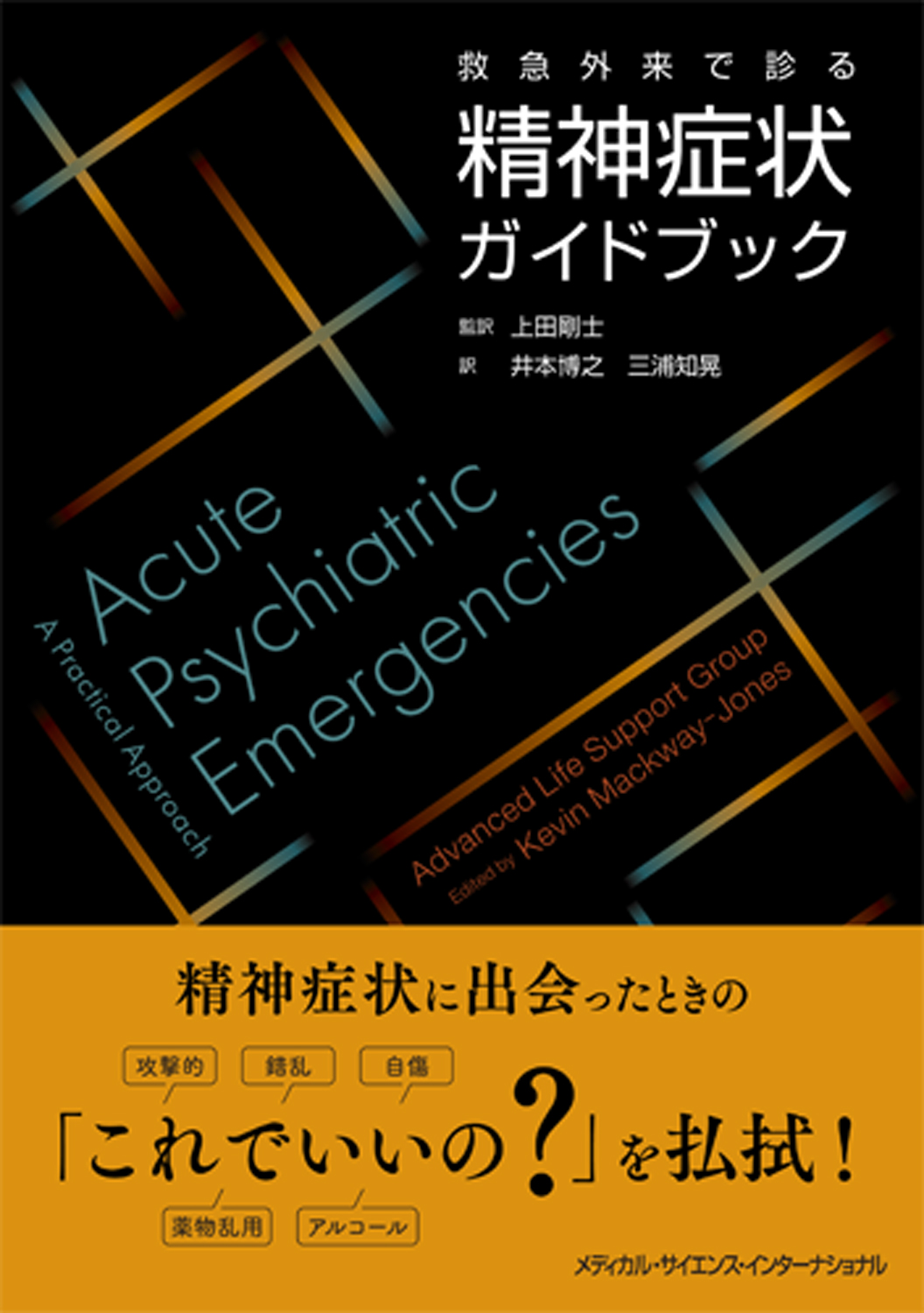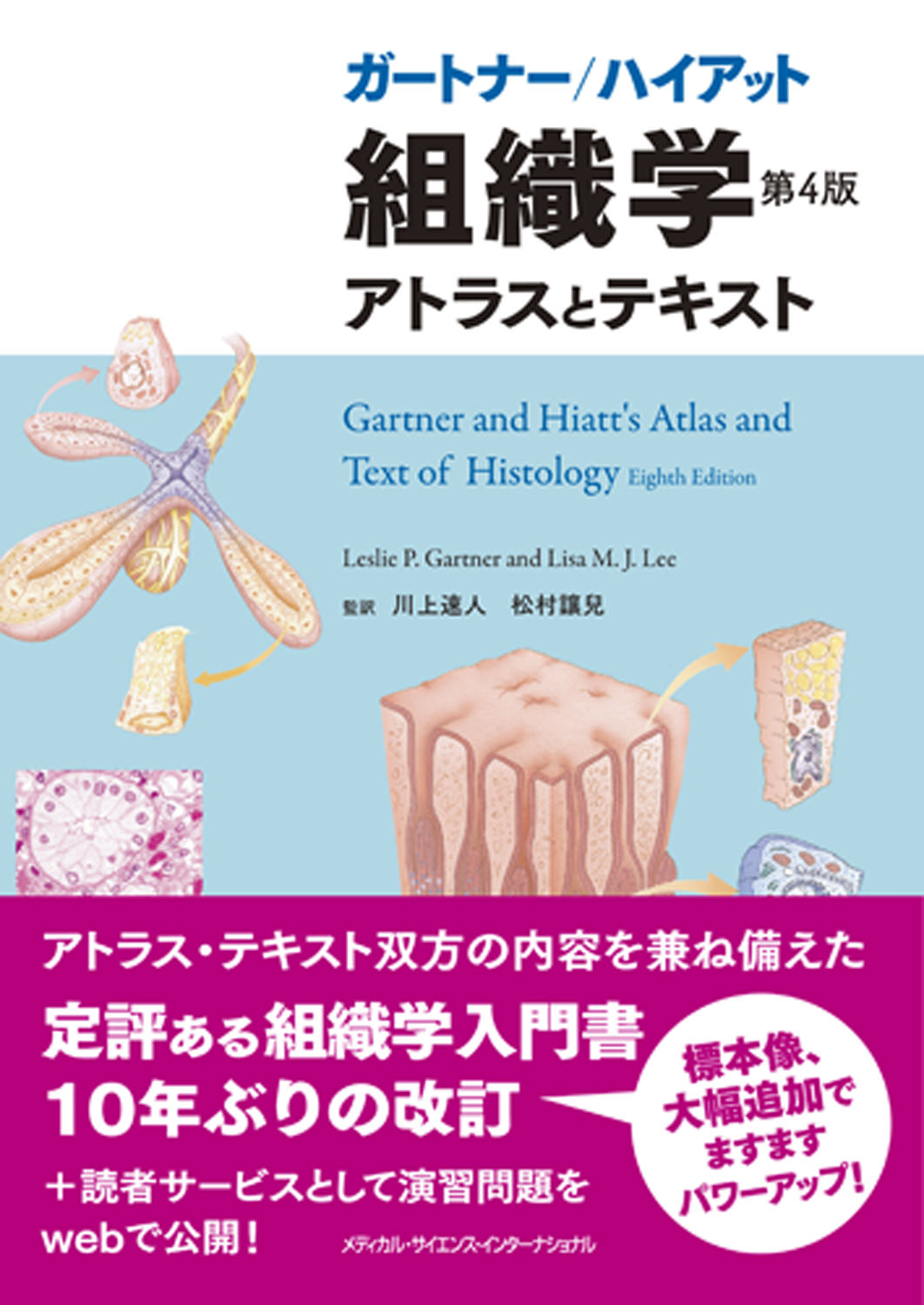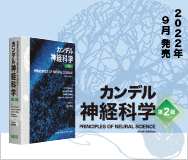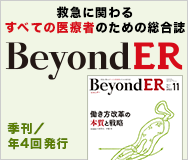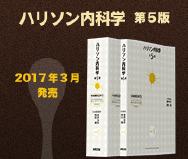シュロスバーグの臨床感染症学
全25Part、211項目で網羅的に感染症の診断・治療を解説。臓器・部位別、微生物ごとの各論のほか、感染しやすい宿主、院内感染、感染予防、旅行・レクリエーションなどに関しても扱い、最後に抗菌薬療法の概論をまとめる。コンテンツは臨床的、実践的に絞り込んだ通読できる分量で、テキストとしてもレファランスとしても役立つ。感染症専門医のみならず、感染症診療に関わる全ての医師に有用。
Part I さまざまな臨床像:総論
Part II さまざまな臨床像:頭頸部
Part III さまざまな臨床像:眼
Part IV さまざまな臨床像:皮膚およびリンパ節
Part V さまざまな臨床像:呼吸器
Part VI さまざまな臨床像:心血管
Part VII さまざまな臨床像:消化管,肝臓,腹部
Part VIII さまざまな臨床像:泌尿生殖器
Part IX さまざまな臨床像:筋骨格系
Part X さまざまな臨床像:神経系
Part XI 感染しやすい宿主
Part XII HIV
Part XIII 院内感染
Part XIV 手術と外傷に関連した感染症
Part XV 感染予防
Part XVI 旅行・レクリエーション
Part XVII バイオテロリズム
Part XVIII 微生物各論:細菌
Part XIX 微生物各論:スピロヘータ
Part XX 微生物各論:Mycoplasma とChlamydia
Part XXII 微生物各論:真菌
Part XXIII 微生物各論:ウイルス
Part XXIV 微生物各論:寄生虫
Part XXV 抗菌薬療法:概論
監訳者序文
『シュロスバーグの臨床感染症学』を訳出,刊行できるのは望外の喜びだ。
内科の定番教科書といえばまず『ハリソン内科学』(MEDSi刊)(以下,「ハリソン」)を思い浮かべる方が多いだろう。「ハリソン」で一番ページを割いているのは心臓学でも消化器学でもなく,感染症だ。だから感染症のほうが価値がより高い,と主張しているのではない。が,内科領域で最もコンテンツ・リッチなのが感染症なのである。風邪,エイズ,エボラ,アニサキスなど多種多様なカテゴリーを臓器横断的に網羅する感染症の世界は,とにかくコンテンツが多いのだ。
「ハリソン」に収まりきらない,感染症のプロ向けの教科書といえば,「Mandell」にとどめを刺す。感染症後期研修医が毎日開いて勉強すべきは本書である(してますよねー)。
しかし,「Mandell」だと分量が多すぎる……も本音であろう。英語のハードルももちろんあるし。
そこで,本書「シュロスバーグ」だ。「ハリソン」と「Mandell」の中間にあるようなほどよい分量のテキストだ。しかも「Clinical=臨床」と銘打っているだけに,臨床家に必要不可欠な最低限の情報に抑えに抑えており,「知識はつくけど臨床的にはさほど重要でない」コンテンツはとことん,捨象されている。もっとも,抑えに抑えてそれでもこんなに分厚いのか!とツッコミが入りそうな気もするが,これこそが感染症の世界なのである。たとえば,「感染症の疫学」は公衆衛生的コンテンツではあるが,臨床家にとって知らないと仕事ができない必須コンテンツでもある。薬理学や微生物学も同様だ。むろん,抗菌薬学,微生物学すべてを扱う必要はないが,臨床的に関係の深い事柄は扱わなければ臨床ができない。よって,厳選したミニマムなテキストなのにそこそこ分厚くなってしまう。 時々,「もはや教科書なんて読まなくてもよい」という意見を耳にする。これほど情報化が進んだ現在,教科書のコンテンツは遅すぎる。最新の文献をネットで入手したほうがよい,というわけだ。
短見である。情報化が進んだ現在であっても教科書の価値は少しも損なわれていないし,むしろその価値は増している部分すらあると思う。
最新の論文をサーチして,「こんなネタがある」とみつけ出すことにも,もちろん価値はある。が,時にそれはマニアックにして周辺の「重箱の隅つつき」になってしまうリスクがある。例外事項に引っ張られて患者マネジメントをするとしばしば診断,治療で失敗する。「◎◎の所見が認められないなんとか病」というケースレポートの存在は,「◎◎の所見はめったにみられない(だから,ケースレポートはアクセプトされた)という逆説的な意味をもつのだ。やはり臨床症状は教科書的な記載をしっかり把握するのが大事なのである。治療も同様,「なんとかマイシンで著効した症例」を根拠に一般的な治療を行ってはならない。
最新の臨床試験が後の臨床試験によりひっくり返される。珍しくないことだ。よって,何十年経っても変わらない普遍的な事項……教科書的記載……にこそ大きな価値があることがわかる。HIV 感染の治療薬はとっかえひっかえどんどん新薬が登場しており,とても教科書が追いつけるものではないが,抗レトロウイルス療法(ART)の治療戦略の基本骨格はすでに1990年代に完成しており,その骨格自体は現在も全く変わっていない。あるのは数限りない「非劣勢試験」の連打であり,革命的に既存の治療薬を上回るレジメンは全く出現していない。なのに,我々は最新の,長期の安全性もわからない新薬にいともエゲツナク安易に飛びつく。ちゃんとプリンシプルを学んでいない,ちゃんと教科書を読むような勉強をせずに最新情報に安易に飛びつきすぎているからではなかろうか。
昨今,医学部教育では「アクティブラーニング」だの,「成人学習理論」だのといわれ,古い教育手法の弊害が批判され,新しい教育スタイルが導入されつつある。アクティブラーニングは文字どおり積極的な学びのことだが,各医学部は小グループの議論(small group discussion:SGD)だの,problem based learning(PBL)だの,team based learning(TBL)だの,プロレス団体さながらの略語を連打してアクティブラーニングを推奨し,子どもとは違う「大人の学習」を促している。皮肉なのは,そのような教育環境整備を手取り足取り行い,議論討論によって学ばせようというきめ細かい心配りがまさにパターナリスティックであり,学生はまことに受動的に与えられたプログラムを器用にこなし,しかし教科書をきちんと読むといった基本的な学習すらしないので基本知識がすっからかんなままでベッドサイド実習に移行し,そこで全く役に立たないという悲しい現象が起きている。本来なら,自分で教科書を吟味して質の高いテキストを手に入れ,図書館や自室で静かにていねいに教科書を読み学ぶのが一番アクティブな学びであり,かつ大人な学びではなかろうか。繰り返すが,教科書を読み込まないような成人学習はありえない。パワポのハンドアウトだけちょいちょいと読んで「学んだふり」をしていてはダメだ。
だんだん序文が説教くさく,年寄りくさくもなってきたのでそろそろ止めにするが,要は教科書の価値はいまだに高いということだ。プロの感染症指導医が絶対的に不足しており,直接指導を受けられない研修医がとても多い日本ではなおさらだ。本書が日本で日本語で出される意味は,そういうことだと思っている。ぜひ活用されたい。
2018 年7 月 震災と豪雨の後の見通し不明な日本にて
岩田健太郎
原著序文
本書への反響は素晴らしく,すぐに第2 版をつくることにした。初版のときと,我々のゴールは同じである。網羅的にしてユーザーフレンドリーな感染症の診断と治療のガイドブックである。
本書は10 のセクションに分けられる。最初は臨床像。全身,および伝統的な解剖学による臓器別だ。また,このセクションではさらに,特に難しい,しばしば研究困難な領域について章を加えている。たとえば,感染性甲状腺炎,深部頸部感染,眼周囲感染,リンパ節腫脹,縦隔炎,ペースメーカー感染,性感染する腸管感染,滑液包炎,多関節炎,腸腰筋膿瘍,脾膿瘍,硬膜外膿瘍,髄液シャント感染,脊髄炎,末梢ニューロパチー,そしてプリオン病である。
第2 のセクションでは,特定の宿主(ホスト)を取り上げている。たとえば,いろいろな免疫抑制がある場合の感染について,糖尿病,移植,好中球減少症,透析,妊娠,無脾症など,個別の章をつくっている。その後のセクションでは,HIV,院内感染,手術や外傷,予防,旅行や娯楽,そしてバイオテロリズムを扱っている。
臓器特異的な章がさらに続く。個々の章は特定の細菌,ウイルス,真菌,寄生虫その他を扱う。最後に,抗菌薬療法に関する大きなセクションが続く。抗菌薬療法,抗真菌薬療法,抗ウイルス薬療法の原則を扱う章があり,抗菌薬過敏反応を扱う章が続く。最終章では抗菌薬を表にしてまとめている。投与量や副作用,値段,妊娠時の安全性,食事の影響,腎機能低下時の投与量調節といった役に立つ情報をまとめている。すべての章には参考文献を添えた。
この新しい版においては,すべての章は改定されている。そして,新たに4 つの章が加えられた。皮膚,リンパ節のところでスナノミ症とトコジラミを扱い,易感染性宿主のところで生物製剤を扱い,抗菌薬療法のところで抗菌薬とプロバイオティクスの章を追加した。
本書が今回も,実践的で臨床的で,使いやすいものであり,感染症診断・治療に資することを希望する。
ケンブリッジ大学出版局のスタッフの優れた見識,才能,そして献身に感謝の申し上げようもない。特にRichard Marley,Jane Seakins,Rob Sykes,Ross Higman,Sarah Payne,Anne Kenton,そしてEd Robinson である。
2019-04-09
【正誤表】下記の箇所に誤りがございました。ここに訂正するとともに, 読者の方々に深くお詫びいたします。
185ページ 右段の上から11行目
(誤)胃内容物による誤嚥性肺臓炎
(正)胃液による化学的肺臓炎
-
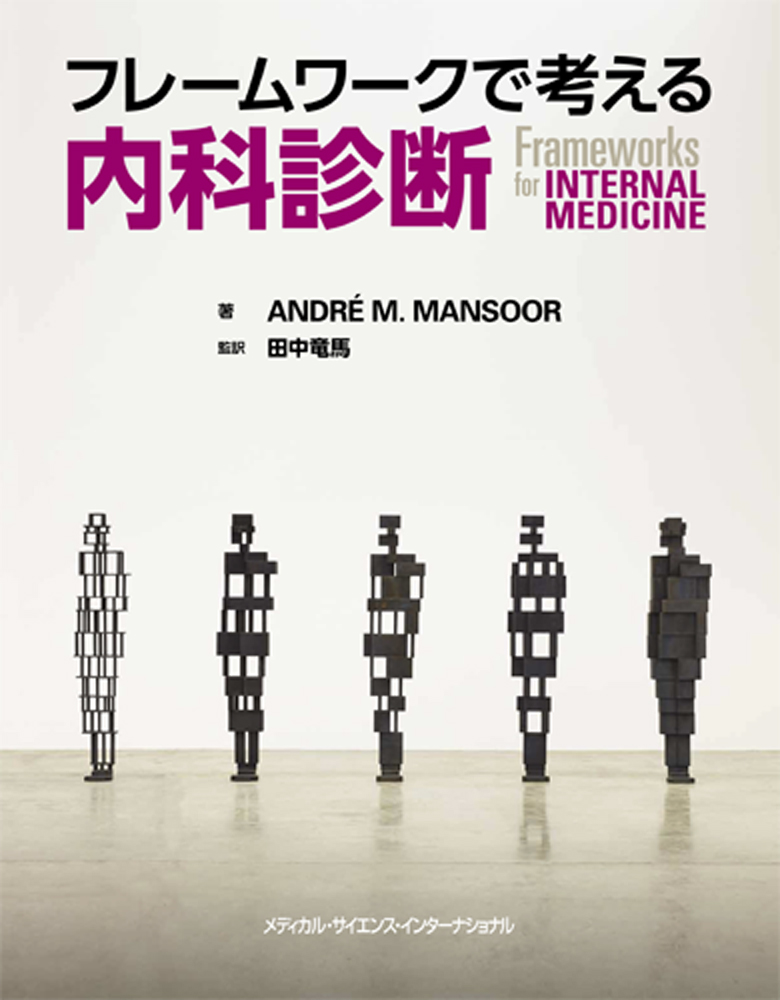
- フレームワークで考える内科診断
- ¥9,130
-
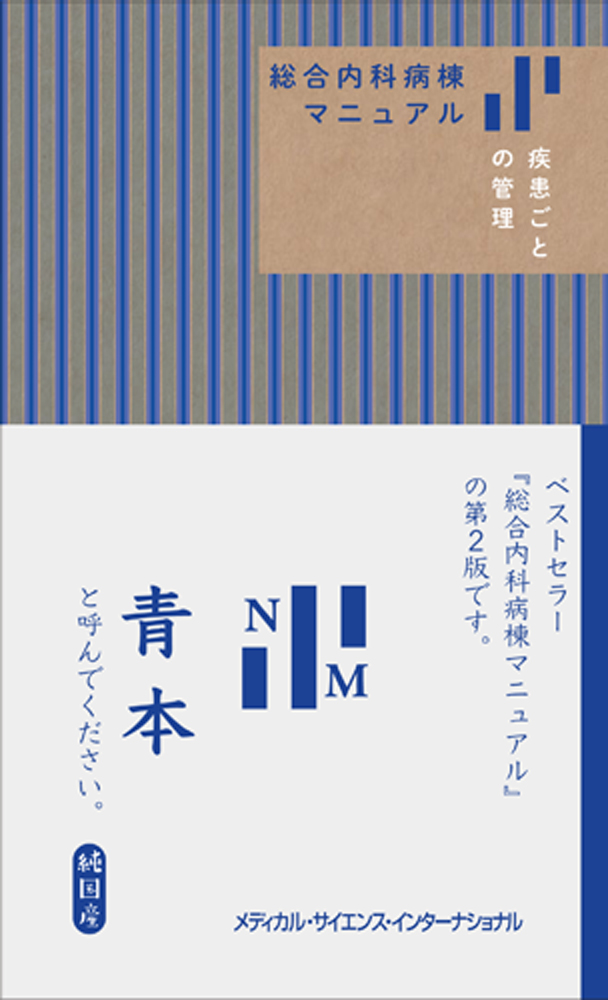
- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-
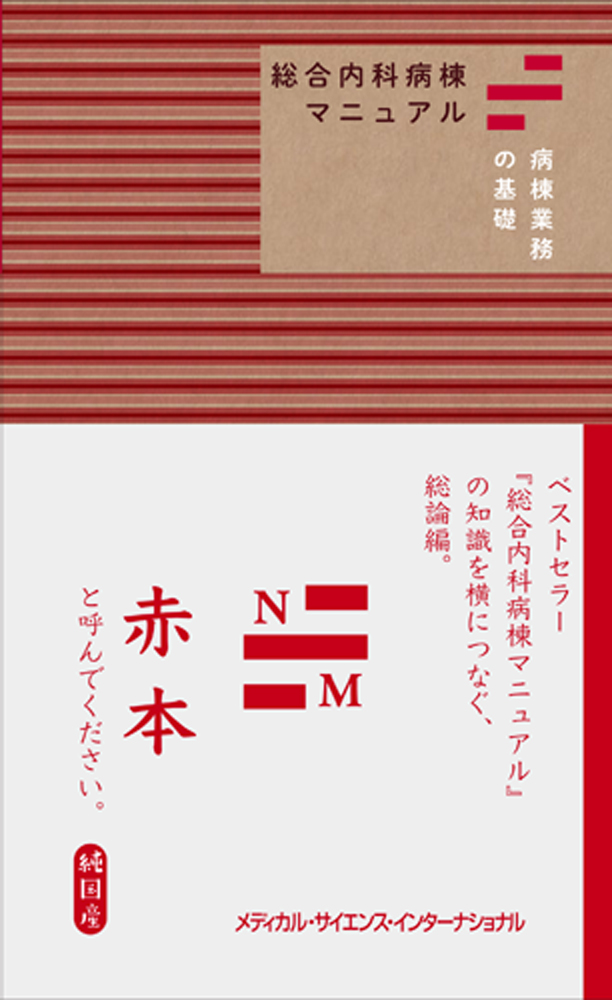
- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-
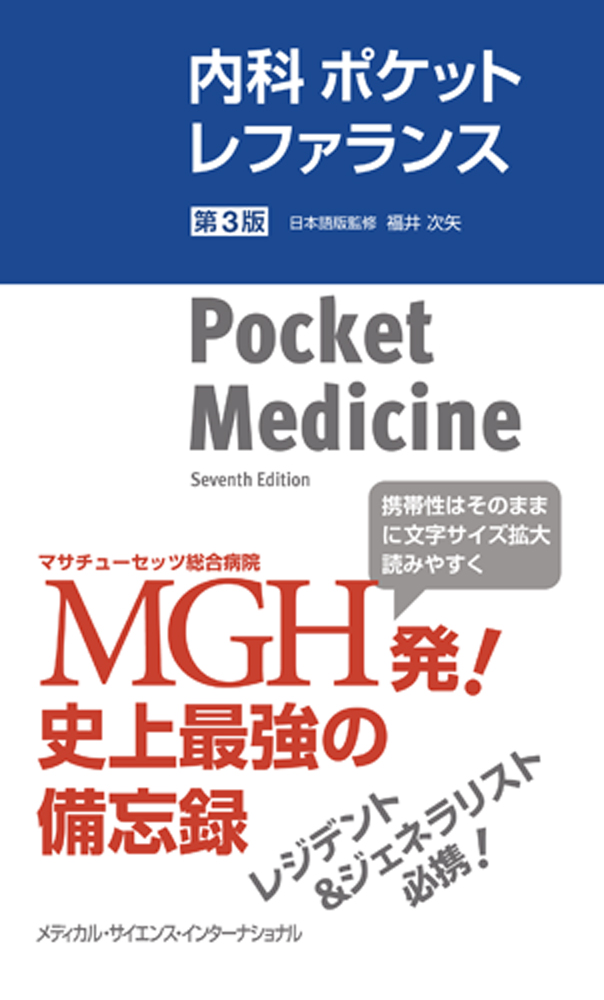
- 内科ポケットレファランス 第3版
- ¥4,620
-
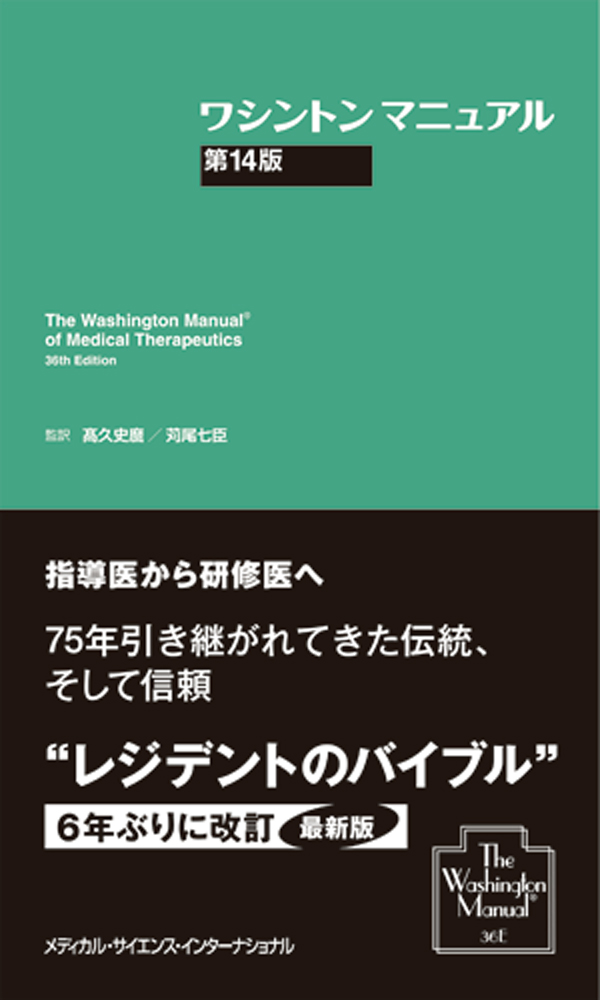
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-

- Hospitalist(ホスピタリスト)2020年4号
- ¥5,060
-
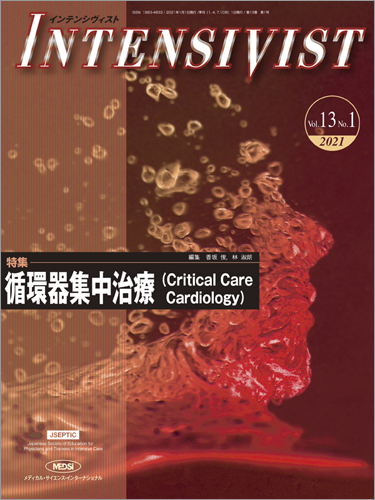
- INTENSIVIST(インテンシヴィスト) 2021年1号
- ¥5,060
-

- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-
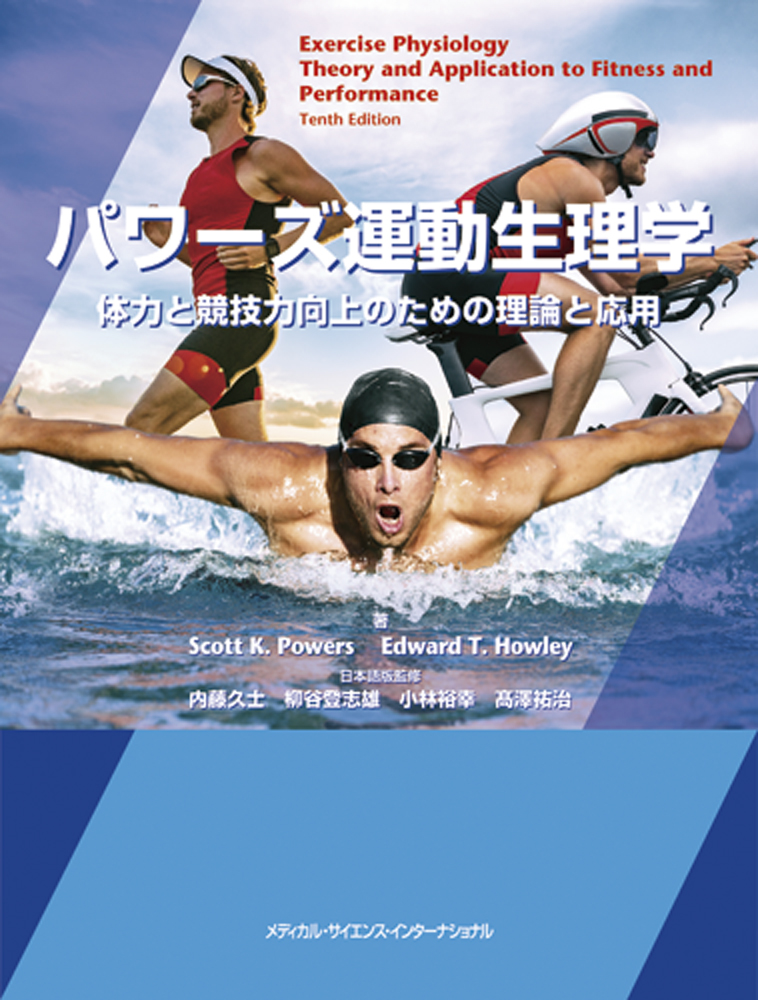
- パワーズ運動生理学
- ¥11,000
-
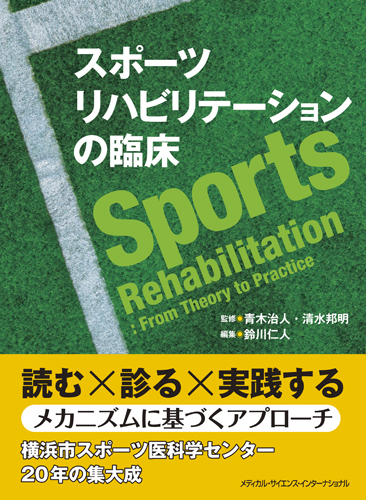
- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-
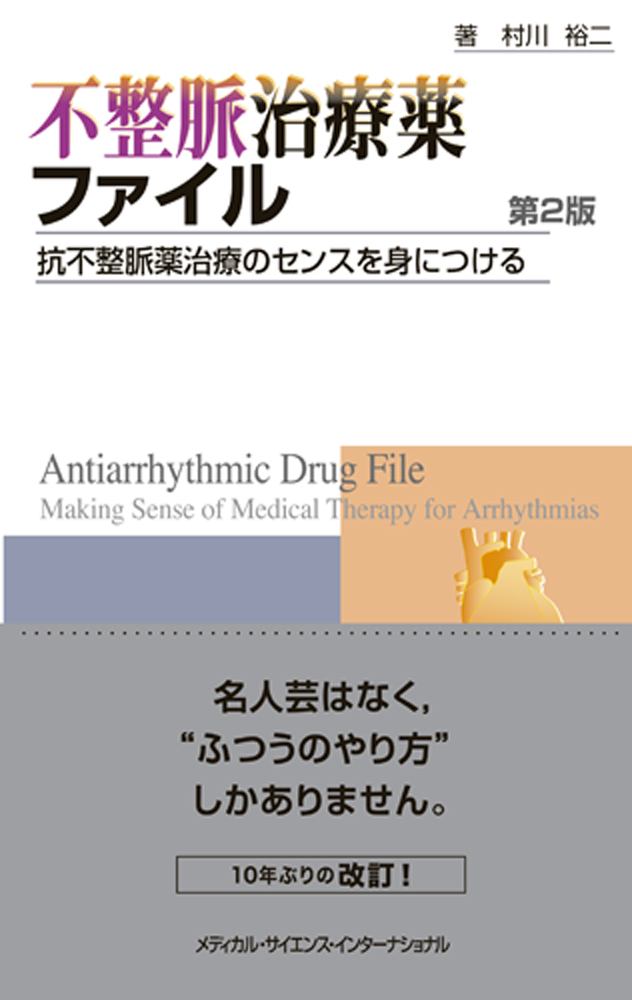
- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
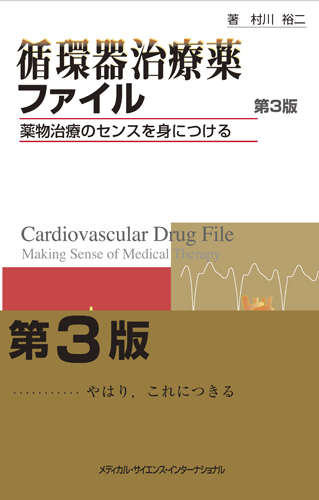
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-
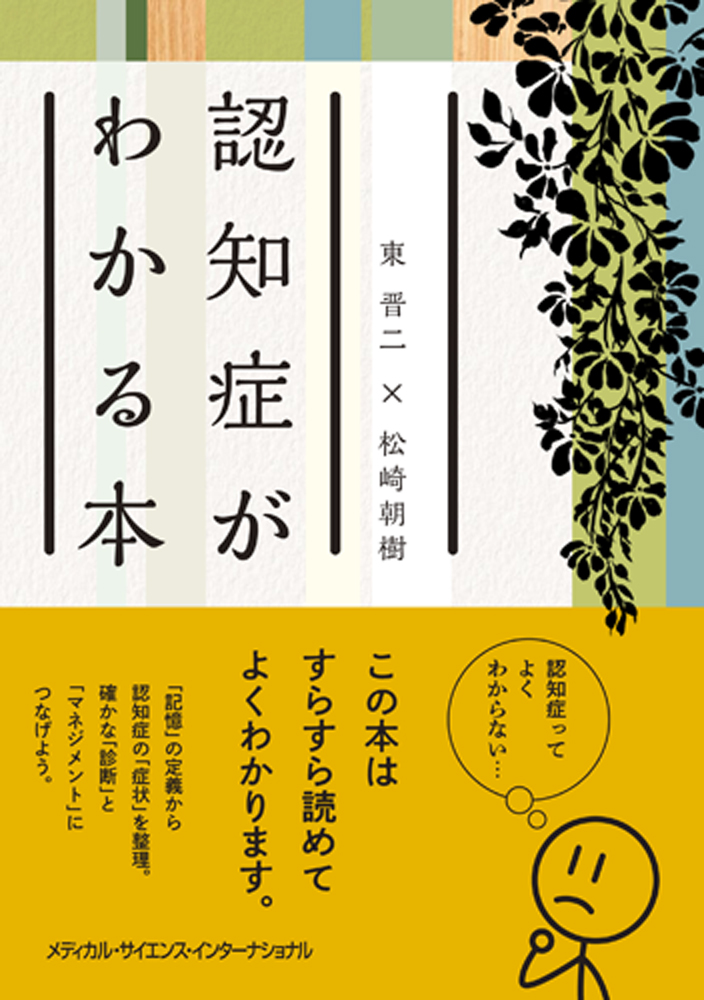
- 認知症がわかる本
- ¥3,740
-
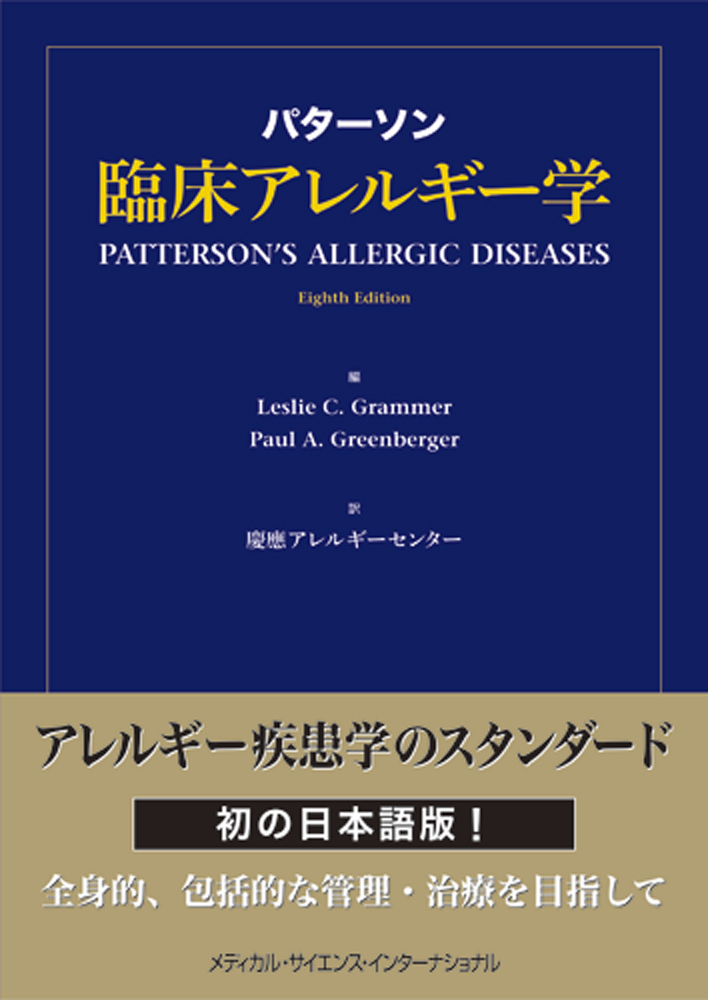
- パターソン臨床アレルギー学
- ¥17,600
-
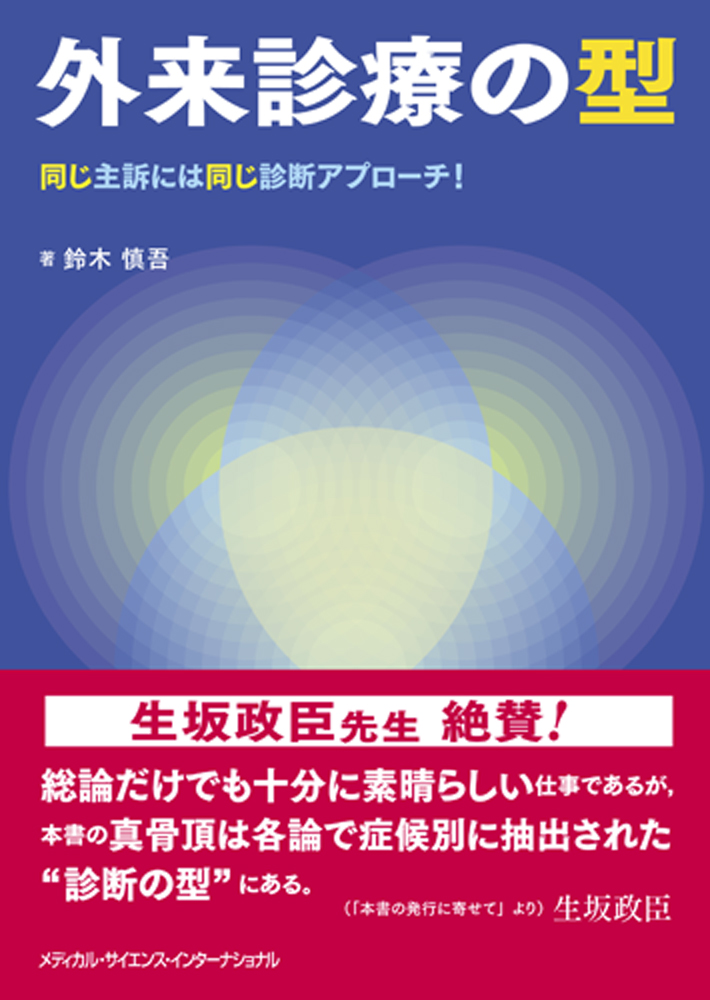
- 外来診療の型
- ¥4,950
-
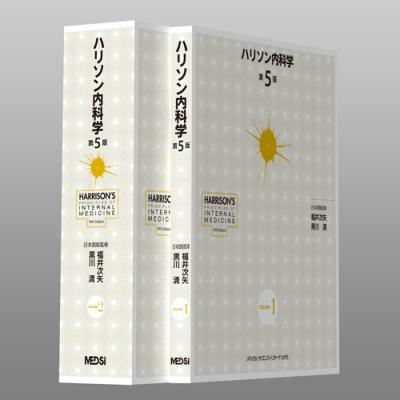
- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
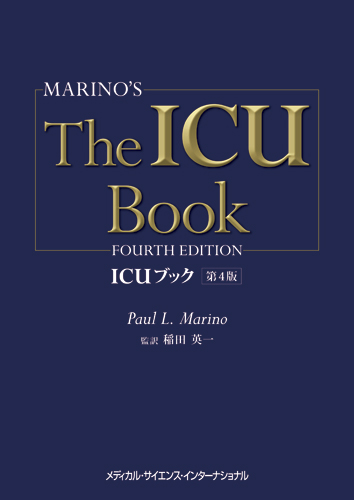
- ICUブック 第4版
- ¥12,100
-
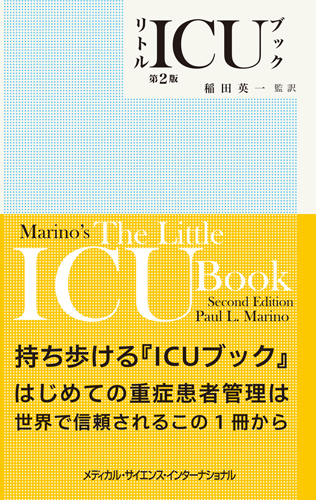
- リトルICUブック 第2版
- ¥5,500
-
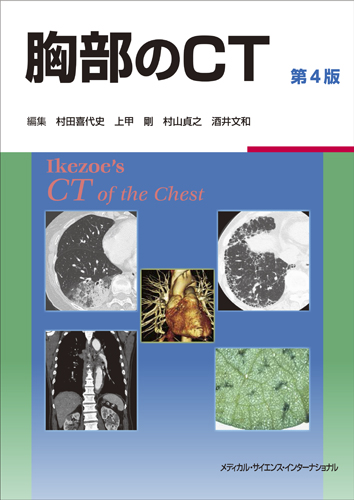
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
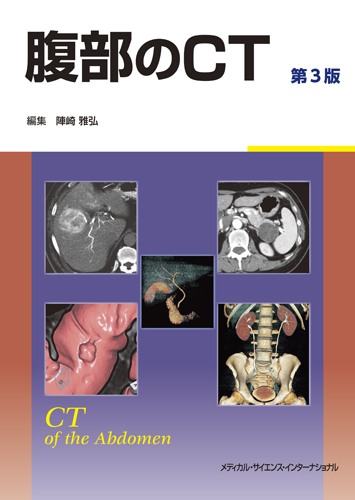
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
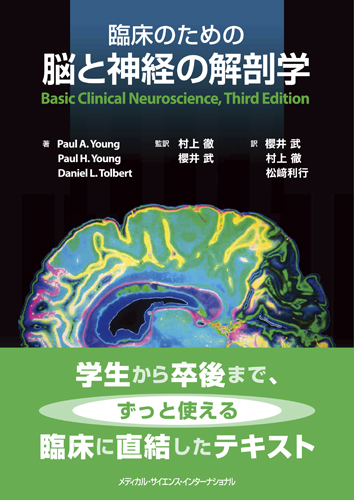
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-
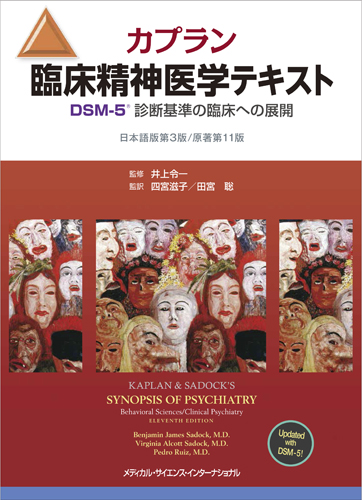
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000
-
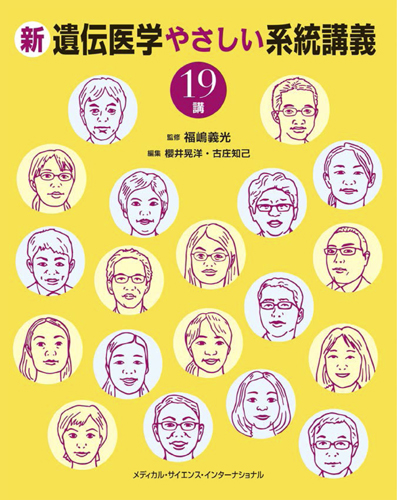
- 新 遺伝医学やさしい系統講義19講
- ¥5,060
-
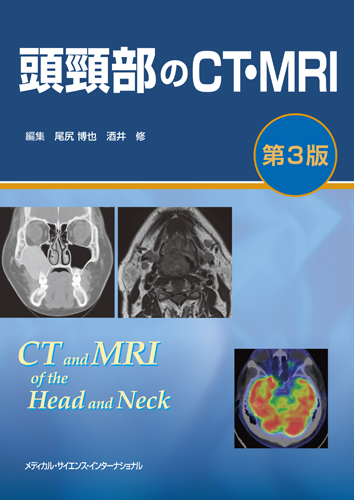
- 頭頸部のCT・MRI 第3版
- ¥16,500
-
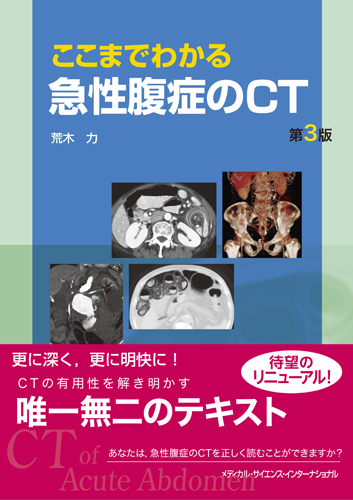
- ここまでわかる急性腹症のCT 第3版
- ¥7,920
-
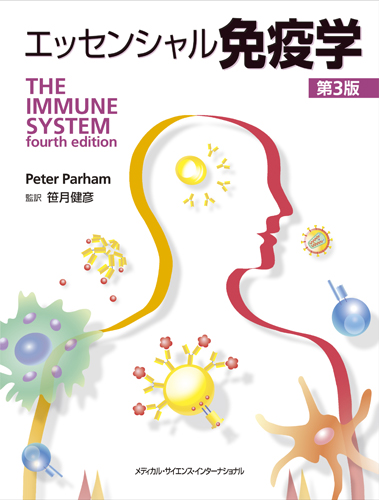
- エッセンシャル免疫学 第3版
- ¥7,040
-
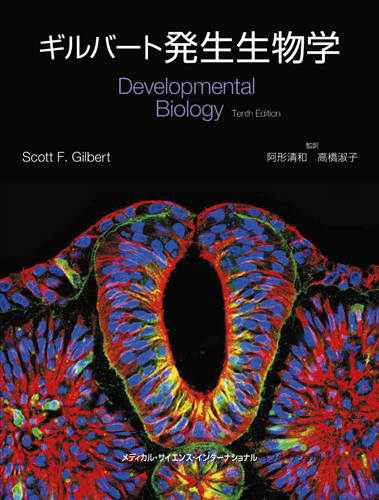
- ギルバート発生生物学
- ¥11,000
-
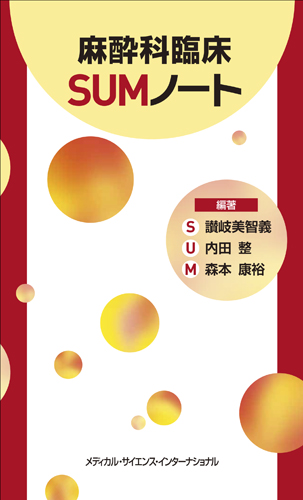
- 麻酔科臨床SUMノート
- ¥8,250
-
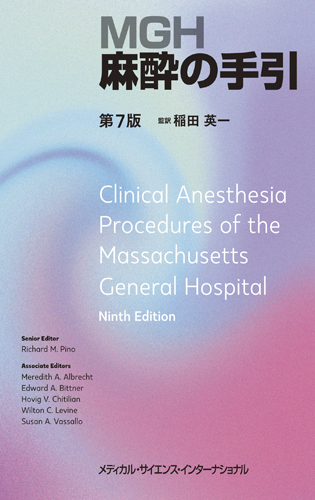
- MGH麻酔の手引 第7版
- ¥8,800
-
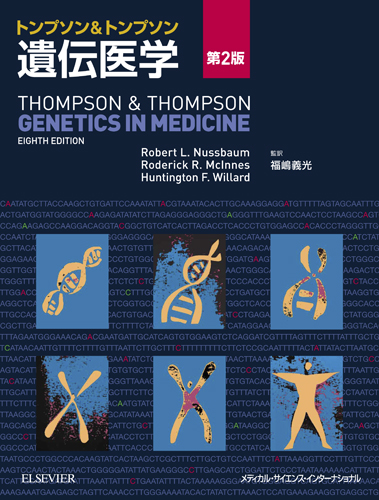
- トンプソン&トンプソン遺伝医学 第2版
- ¥11,000
-
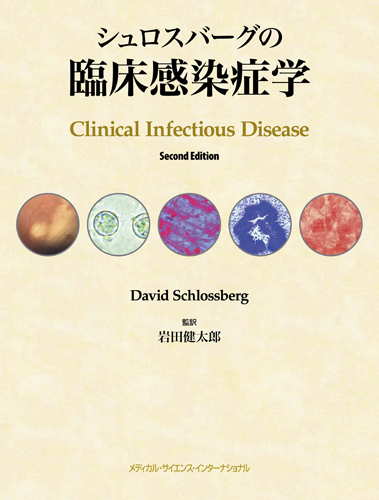
- シュロスバーグの臨床感染症学
- ¥22,000