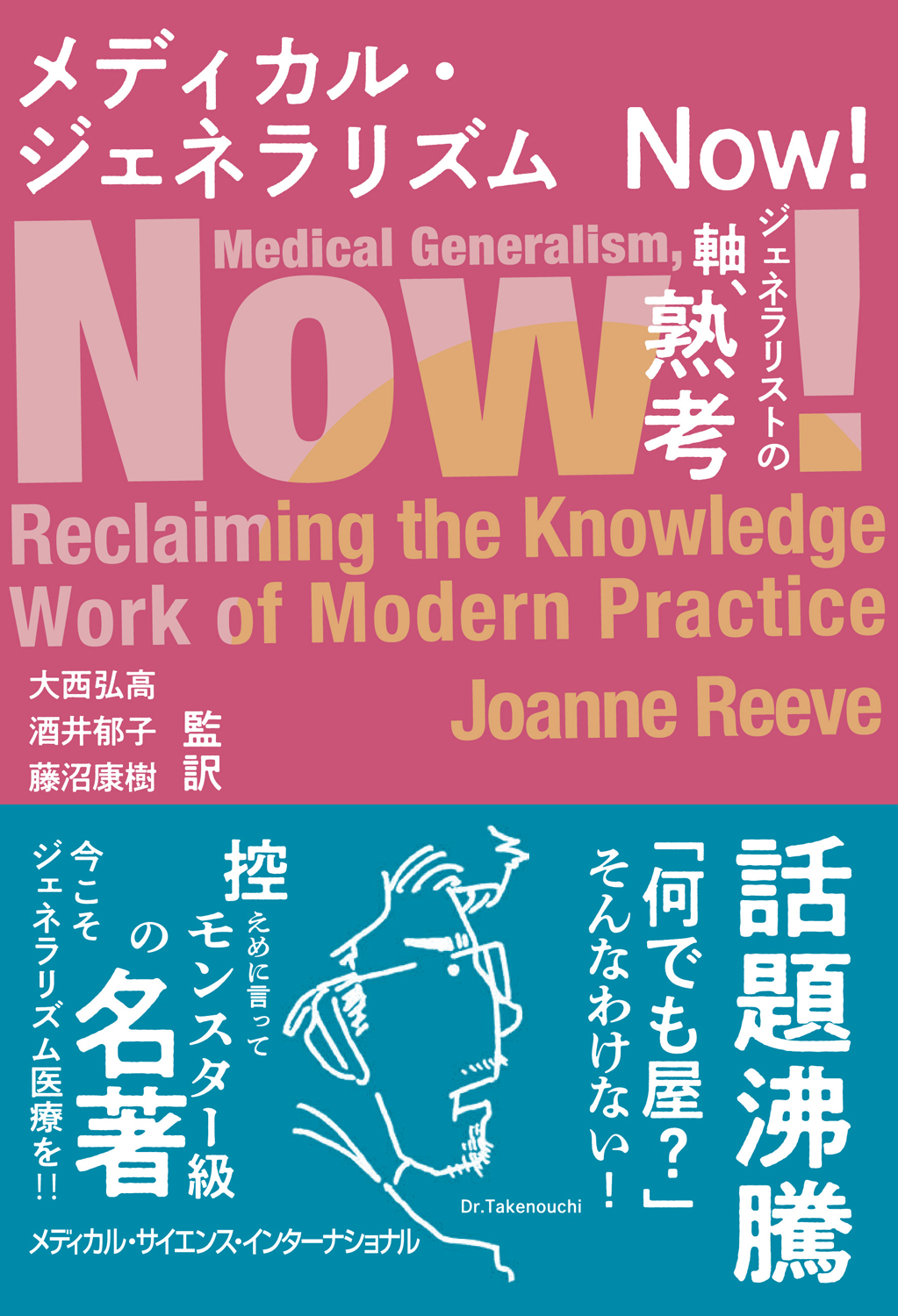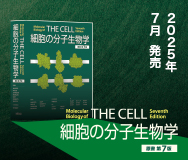メディカル・ジェネラリズムNow! - ジェネラリストの軸、熟考 -
「ジェネラリストのスキルとは,結局なんなのだろう…?」の答えがここにある
日本の総合診療専門医制度開始から約8年、ジェネラリストの役割やスキルは模索され続けている。本書では、20年にわたりジェネラリズム医療に取り組んできた著者が、ジェネラリストの医療行為を「患者の生活文脈を含めた全人的医療」と捉え、既存の知を用いて新たな知を生み出す「ナレッジワーク」として可視化する。EBMだけでは補えない現代医療の課題に応えるべく、総合診療医のみならず、すべての臨床医にとって自らの実践を再考する視座を提供する。
第1章 全人的な医療の原則
1.1 ジェネラリズム医療の目的:全人的に理解すること
1.2 全人的医療の重点:創造的自己
1.3 全人的医療の目標:日常生活のために健康を増進すること
1.4 全人的医療のナレッジワーク:コンテクストのなかで理解する
1.5 全人的医療のコンテクスト:複雑な介入
1.6 まとめ
第2章 賢明(ワイズ)な基礎:診療のナレッジワーク
2.1 臨床実践のナレッジワーク
2.2 スペシャリスト医療のナレッジワーク
2.3 ジェネラリスト診療で用いられる新たなナレッジワーク
2.4 ジェネラリズムを行動に移す際の障壁
2.5 ジェネラリズムを行動に移す:ベストプラクティスの4E
2.6 高度なジェネラリズム:裸の王様か,それとも本当に意味があるのか?
2.7 ナレッジワーク:当人中心のヘルスケアの再設計に欠けているピース
第3章 賢明(ワイズ)な人々:ジェネラリストの高度な実践のナレッジワークを提供する
3.1 反転診療
3.2 ゴルディロックス医療
3.3 ヒースの“ジェネラリスト・ゲートキーパー”または“グールー”
3.4 まとめ
第4章 賢明(ワイズ)な実践の場:熟達者ジェネラリストのナレッジワークを支える診療
4.1 ジェネラリストによる高度実践というナレッジワークを可能にする:ジェネラリスト診療の再設計
4.2 立ち直りプロジェクト:コンテクストでナレッジワークを可能にする
4.3 複雑ニーズ:多疾患併存のコンテクストでナレッジワークを可能にする
4.4 患者連携ケアチーム:テーラード・ケアのナレッジワークに向けた場づくり
4.5 結論:賢明な実践の場を創造する
第5章 賢明(ワイズ)なシステム:ジェネラリストによる高度なヘルスケアシステム
5.1 舞台設定:新公共経営
5.2 触媒プログラム:システム変革のためのナレッジワークの推進力,医療人材の例
5.3 TAILOR:ナレッジワークがシステム変革の原動力,職場の例
5.4 ユナイテッド・ジェネラリズム:政策例
5.5 ジェネラリズム医療への示唆
第6章 今こそ,ジェネラリズム医療を
6.1 プライマリ・ケアから始める
6.2 賢明な政策
6.3 賢明な診療所
6.4 賢明な人々
6.5 今こそジェネラリズム医療を
第7章 ジェネラリズム医療は世界中で実現できるのか
7.1 世界の家庭医との会話
7.2 話し手の紹介
7.3 はじめに:場面設定
索引
はじめに
本書は,ジェネラリスト診療の日常業務に関する書籍である。
私は,25年以上にわたって家庭医療に従事してきた臨床医である。研究を含む学術的な業績は,私のキャリアを通じて臨床業務の不可欠な一部であり,この本における考え方や議論の形成に影響を与えてきた。しかし,私の目標は,きわめて実践的な書籍の執筆であった。我々の働き方に関する現在の時代遅れな考え方に疑問を投げかけ,読者の皆さんに現在そして将来の診療に対する新しいビジョンを喚起することを目指した。
なぜ,そしてどのようにして私がこの本を書くに至ったのかについて,少しお話ししておきたい。30年前,私は医学部に,非常にシンプルなある考えをもって入学した。物事をより良く理解できれば,より人々の役に立てるだろう,と。
どうしたいのかはっきりとはわかっていなかった。医学部の面接で17歳の私が,おそらくためらいがちに口にしたのは,「人々がより快適に過ごせるように役立ちたい」というような考えだっただろう。それが実際に何を意味するのかについては,それほど心配はしていなかった。時が経ち,経験を積めば,その意味が明らかになるだろうと漠然と考えていたのだ。そして,公平にみて,そのとおりになった。しかし,完全に変わったのは,“理解”の意味に対する私の認識である。
医学部に入り,他の学生と同様,私は何かを理解したいなら,それを“学びにいく”ものだと思っていた。年齢がバレてしまうが,当時それは最高の教科書を読み,最高の専門家と話し,その知恵を記憶することを意味していた。知識を得ることこそが理解だった。
医学部入学後の経験から,他の扉が開き始めた。英国で問題基盤型学習(problem—based learning)が確立される前に,私は医学を学び始めた。当初1年半の間は,応用科学の基礎を教えてくれる第一線の科学者たちとよく過ごしていた。研究室で基礎科学実験に時間を費やしたが,計画通りに進むことはまれだった。私は,実験のような手技は下手だと思っていた(確かにその要素もあった)が,“学んでいた”すべての“事実”を裏付ける科学的手法の限界にも気づき始めていた。
医学部の2年次修了後,私は1年間他学部に移ることにした。医学部を辞めようと考えていたからだ。医師という職業に就くことに自信がなく,1年間ずっと研究室に籠り,素晴らしいチームの一員として自分の研究プロジェクトに取り組んだ。でも,その1年間に実施した実験のほとんどは,私や指導教官が意図した通りには進まなかった。どんなに慎重に,実験方法の細部に注意を払って実験を繰り返しても,だ。でも後になって気づいたのは,その1年間を通して,私は“理解する”ことを学んでいた,ということだった。理解とは,物事を“知っている”ことよりもはるかに深いものである。その時はそう気づいていなかったが,これが私のキャリア全体を形作るテーマとなった。
それ以降,他学部での研究を続けることはなく,1年間の研究生活を終えて医師のトレーニングに戻ったことはお察しの通りである。臨床実習に入ったとき,エビデンスに基づく医療(EBM)という考え方が,マクマスター大学のデビッド・サケット率いるチームから提唱され始めていた。個々の患者の治療に関する意思決定において,最新・最良のエビデンスを意識的に,明確に,賢明に利用することを可能にし,保証する新しいアプローチを提示するという考え方が,臨床教育や最良の実践のモデルとして定着しつつあった。でも,誰か反論する人はいないのだろうか?なぜ我々はこれまでにそれを実践していなかったのだろうか?という第一印象をもった。
英国王立内科医協会(Royal College of Physicians)で開かれるカンファレンスで,デビッド・サケットがこの新しいアプローチについて講演するという話を耳にした。ぜひ参加しなければならないと感じ,会議の主催者に手紙を書いた。「私は学生で,会議の参加費を払う余裕はないが,ぜひ参加したい」と説明し,参加を許可してもらった。
私の記憶にあるのは,サケット氏とそのチームが提示した,力強く明解な未来像である。会場の人々は,マニュアル的医療のリスクに対する不安を口にした。サケットは,差し迫った懸念をうまく解消した。しかし,私には何かが欠けているように感じられた。おそらく論理上の問題や欠陥が議論されていなかったのだ。私はそこで語られていたことに違和感を覚えたが,医学部で学んでいる途中であり,自分の感じていることを明確に表現できるだけの経験も言語能力も持ち合わせていなかった。
それから数年が経ち,私は公衆衛生学で研修を受けることにした。臨床医学に(再び)失望したのだ。我々は“部分”を修復しているようではあるが,“全体”,すなわち問題のある部分を超えた人間全体をみるという仕事を,私は経験していなかったと感じたのである。そこで,患者と向き合う臨床から公衆衛生学へと方向転換したのだ。公衆衛生は,人々が病気になる背景に非常に注意を払っている点で,私にとって魅力的だった。しかし,実践において矛盾しあう“エビデンス”に悩まされるうちに,私はまたも問題にぶつかった。EBMを通じて提示される科学は,“最善の実践”の1つの見解を提供していた。しかし,患者中心の研究から得られる科学は,異なる見解を提供していた。私は,患者の経験という四角い釘をEBMという丸い穴に合わせることを求められているように感じた。
そうした苛立ちが創造的な力をもたらすことに気づきはじめた私は,今度は家庭医療の形で臨床医学に戻った。EBMで重視される生物医学的エビデンスを批判的かつ安全に跳び超え,患者の声を統合する方法を探究する機会として,全人的ケアのナレッジワークを理解するために博士課程にも入った。博士号は,サケットの話を聞いていた学生時代に感じた違和感を明確に表現するための言語を私に与えてくれた。対応策と代替案を構築するのに役立つ概念とツールについて学んだことが,ジェネラリズムの概念を生涯にわたって探究するきっかけとなり,この本で紹介する研究を生み出すことになった。
この仕事のおかげで,全人的医療を理解し,提供し,支援するには新しいアプローチが必要であると認識するに至った。EBMは数十年にわたって臨床実践のナレッジワーク,すなわち,どのようなデータを使用し,それをどのように使用するかを定義し,専門的実践と患者ケアの改善に貢献してきた。しかし,人口統計学,疫学,ケアに対する社会の期待の変化により,EBMだけでは現代のヘルスケアには不十分となっている。実際,構造的医原性および認識的不利益(第1章と第2章で再び取り上げる概念)への寄与を通じて,EBMは医原性被害の一因となっている可能性がある。我々は,医療従事者の日常業務である,データの検索,作成,使用,生成,学習の方法といったナレッジワークについて,改めて見直す必要がある。EBMは,疾患中心のケアのために専門教育,診療,システム設計を変革した。本書は,全人的医療のために同様の変革を目指している。
変革は心地のよいものではない。25年にわたる診療経験のなかで,私は人々がジェネラリズム医療について抱く信念が,彼らの職業的アイデンティティに不可欠であることを繰り返し経験してきた。本書では,少なくとも強調したい点として,皆さんがジェネラリズム医療について考えるのとは異なるジェネラリスト診療のビジョンを提示する。第3章,第4章,第5章では,私が日常業務で経験している現実的な課題のいくつかに,この異なるジェネラリストの実践の考え方がどのように役立っているかを示す実例を紹介する。第6章では,この仕事から学んだことをまとめ,専門研修と実践の有機体がどう変わるべきかについて説明する。そして第7章では,国際的な専門家を招き,本書で概説した考えについて,各自の状況や職業的アイデンティティへの影響,検討すべき変化について考察してもらう。
本書は,臆することなく変革を求める。かつてサケットがそうしたように,本書が変革のきっかけとなることを願っている。EBMが普及した理由は,サケットとそのチームが当時の課題に取り組むための論理的かつ体系的なアプローチを明確に説明できたこと,EBMが現れたとき変化を求める政策や方向性があったことの2つである。後者は,EBMの原則を政策に統合することで,従来不可能だった方法で医療行為を標準化し管理できるようになった(第5章で詳しく述べる)ともいえる。EBMを医療政策に導入したことで,医療情報の管理は医療従事者から政府の管理下にある外部機関,国立医療技術評価機構(NICE)に移行した。その結果,今日の医療における臨床実践のナレッジワークに対する理解,トレーニング,サポート,評価の方法に変化が生じた。意図せざる結果として,地域社会が直面する疫学的変化に対処するために最も必要とされる時期に,全人的ケアが衰退した。慢性疾患と多疾患併存の増加,そして全人的ケアの能力低下は,問題を孕むポリファーマシー,治療負担,持続的な身体症状に関する未充足のニーズなど,新たな拡大しつつある現象に加担している。本書が,医療サービスの方向転換を求める声が高まるような,国際的なうねりになって欲しいと考えている。
本書は,変革への青写真でもある。全人的医療,ジェネラリスト診療は,新しい考え方ではない。多くの人々がジェネラリストのアプローチを高く評価している。本書を読んでいる方々の多くは,すでに日常業務においてここで紹介されているスキルのいくつかを利用していることだろう。しかし,この分野で25年間働いてきた経験から,多くの人々にとって,医療におけるジェネラリズムは依然として隠れた診療形態に留まることが分かった。経験豊富なジェネラリストの医師でさえ,自分たちの行っていることを説明しようとすると苦労し,代わりに患者との“関係性”に裏打ちされた“直感”について語る場合が多い。いずれの考え方も,この分野に新たに参入する医師が自信をもって自分のスキルと診療を発展させる,あるいは政策立案
者が新しい医療提供モデルの設計をサポートするには不十分である。
よって,サケットが専門医療に対して行ったように,本書はジェネラリストの医療行為を可視化することを目指している。第1章では,全人的ケアの英知の明確なビジョン,すなわちジェネラリスト診療における明確なナレッジワークについて説明する。全人的ケアの提供を支援し持続するために必要な専門職トレーニング,診療設計,医療政策における具体的な変化についても説明する。本書は,今こそ医療ジェネラリズムを実現するための枠組みを提供するものである。
推薦の言葉
「ジェネラリズムは専門性が低い」―もし,いまなおこのような言説が無自覚に語られているとすれば,それは現代医療が抱える最も根深い誤解の一つである。本書は,その誤解を正面から打ち砕くための書物である。複数の慢性疾患,曖昧な症状,社会的困難,価値観の揺らぎが絡み合う現実の中で,著者はジェネラリズムを情緒的な理想論としてではなく,卓越したジェネラリストが日常的に行っている思考と判断の営みとして,冷静かつ厳密に描き出している。
第1章において著者は,全人的医療を,スペシャリスト医療の効率的な統合にとどまらず,個人が日常生活を営むための創造的能力を高める支援と定義し,その実現のために,患者の「創造的自己」を想像しながら診療を行うことの重要性を説いている。創造的自己とは,行動を駆動するエネルギー,安定をもたらす要因,不均衡を生み出す要因,そして揺らぐ日常生活の流れの中で前進するための創意工夫を含む概念である。これらを明らかにするには広範な情報収集が不可欠であるが,著者は特に「いかにやり繰りしているか」を問うことの有用性を指摘する。この点は,私がBATHE法(短時間の心理社会的介入技法)において,医療化の要否を判断する際に重視している,不均衡を生み出す主要な要因(Trouble)への対処(Handle)を尋ねる医療面接とも深く共鳴するものであった。
第2章では,ジェネラリストを,他産業と同様に「非定型的な問題解決」を担う能力によって評価されるナレッジワーカーとして位置づけた上で,複数の慢性疾患に関連する症状を呈する患者や,基礎疾患が特定されないまま症状が持続する患者への診療方略が論じられる。こうした複雑な状況に対しては,演繹的推論では十分に対応できないことが多く,情報を探索しながら病いの全体像を理解していく帰納的推論が重要となる。著者はこの診療の営みを,4E(認識論,探索,説明,試行と学習)として体系化している。帰納的探索から生じる仮説生成はアブダクション(発見的推論)と呼ばれ,その正当性は演繹的推論によって導かれた仮説ほど自明ではない。そのため,仮説に基づく試行的介入と,その結果を見届け,学習へとつなげるプロセスまでを一連の実践として捉える必要がある。さらに4Eの核となる認識論において,著者は,疾患管理を中心とした医療から,日常生活の健康を最適化するケアの開発と提供へと視点を移行させる必要性を論じている。重要なのは,これを単なる価値観や意見としてではなく,病態生理に基づく演繹的推論と同様に正当な臨床的判断として位置づけることであり,そのために著者は,徹底したデータ収集と検証を組み込むことで質を担保する「解釈的医療」を提案している。もっとも,帰納的推論を中核とする診療には,現行の保険診療制度では許容されていない診察時間を要することも事実であり,こうした実践をいかに制度の中で実装していくかは,今後の重要な課題であろう。
著者はまた,ジェネラリストの暗黙知を,日常診療の複雑さや,コンテクストに根ざした診療の中で生成される「日常的な知」として捉えている。専門性とは,特定の対象を反復的に扱うことで獲得される技能を指すが,深刻な「疾患」ではなく,複雑な「状況」に繰り返し向き合い,省察を重ねることで獲得される暗黙知こそ,ジェネラリストの専門性であると言えよう。その言語化にはジェネラリスト特有の工夫が求められ,著者は企業のナレッジワーク理論であるSECIサイクル(共同化・表出化・連結化・内面化)を援用している。類似の言語化方略を実践してきた者として,私もこの視点に強く賛同する。
第3章・第4章では,診療所の現場におけるジェネラリストのナレッジワークの具体が描かれる。緊急性を要する生物医学的問題に対しては,まずその対応が優先されるべきであるが,そうでない患者に対しても,まず生物医学的問題の有無が検討され,心理社会的要因の探索は後回しにされるのが現状である。本来は医療ではなく,創造的自己を介した日常生活の最適化が求められていた人も,いったん医療化されると,自らを医療が必要な“候補者”と認識し,結果として解決困難な医療依存に陥る危険がある。これを回避するため,著者は社会・心理的要因への介入を先行させる「反転診療」を紹介している。これは,私自身が総合外来で数年来取り組んできたサイコソシオ・バイオロジカルアプローチと軌を一にしており,深く共感するところである。言うまでもなく,心理社会的な課題が前景に立つ場合であっても,生物学的問題の拾い上げは不可欠である。しかし,主として臓器専門医がプライマリ・ケアを担い,国民が医療機関を受診した時点で医療化が既定路線となるわが国の医療体制においては,そうした過剰な医療化から患者を救済するための「反転診療」のような場の必要性を,大学総合診療部門に紹介される患者の診察を通して,私は痛切に感じている。
第5章・第6章では政策的課題とその対応が論じられ,第7章には各国のプライマリ・ケアを牽引するリーダーとの対話が収められている。いずれも,わが国の総合診療を展開するうえで多くの示唆を与える内容である。本書ではGeneral Practitioner(GP)を家庭医と訳しているが,総合診療に関わる者のみならず,現行の医療のあり方に不全感を覚える臨床家,教育者,政策担当者に広く推薦したい。将来,人による演繹的問題解決の多くはAIに代替されるであろう。そのような時代背景の中で,ジェネラリストが担うべき知的労働の本質を丁寧に言語化した本書は,少なくとも私に
とって,今世紀に入って最も大きな知的衝撃を受けた一冊である。
千葉大学名誉教授
生坂政臣
-
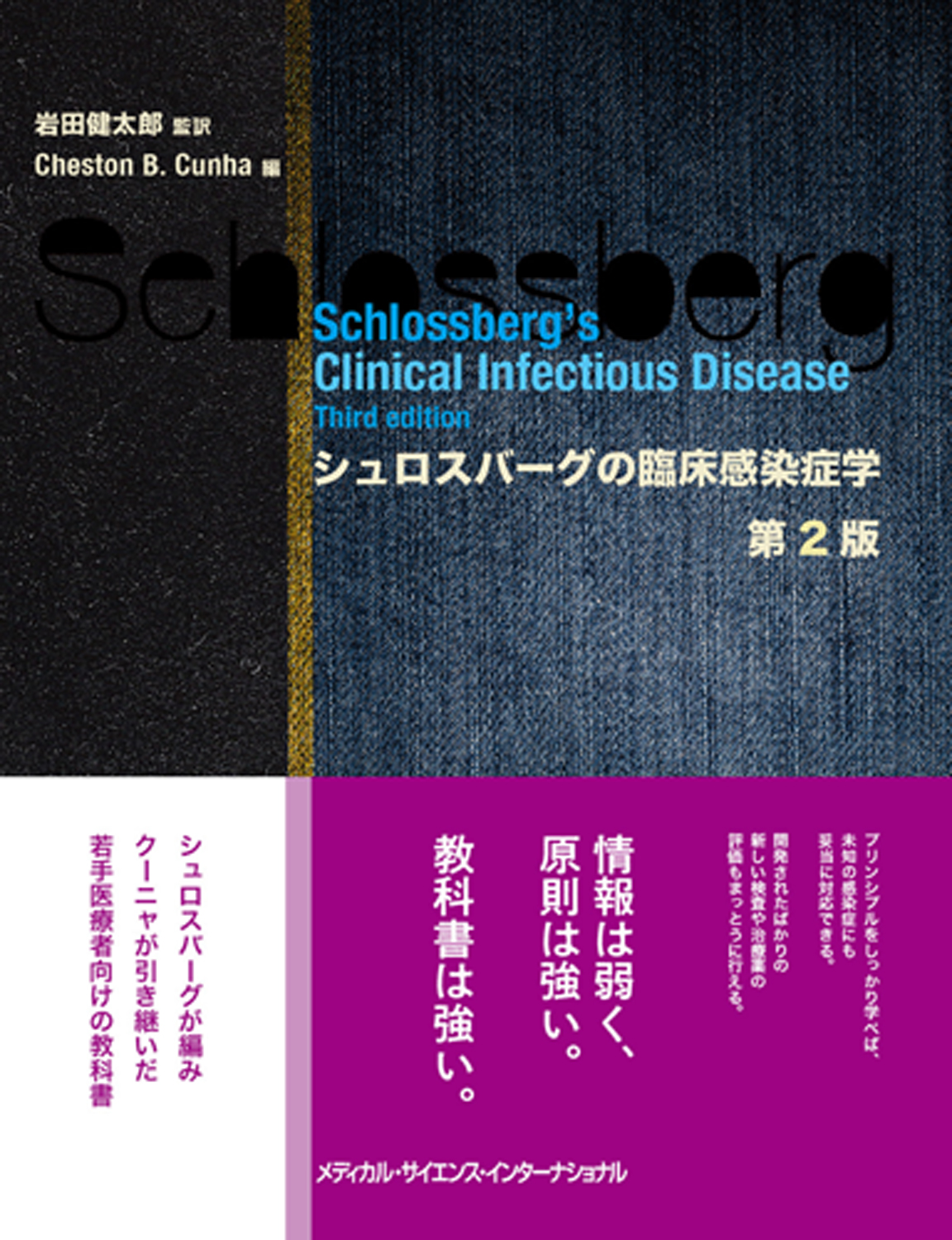
- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版
- ¥25,850
-

- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版
- ¥12,100
-

- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande
- ¥4,180
-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版
- ¥8,250
-

- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版
- ¥3,960
-

- 循環器のトビラ
- ¥5,940
-
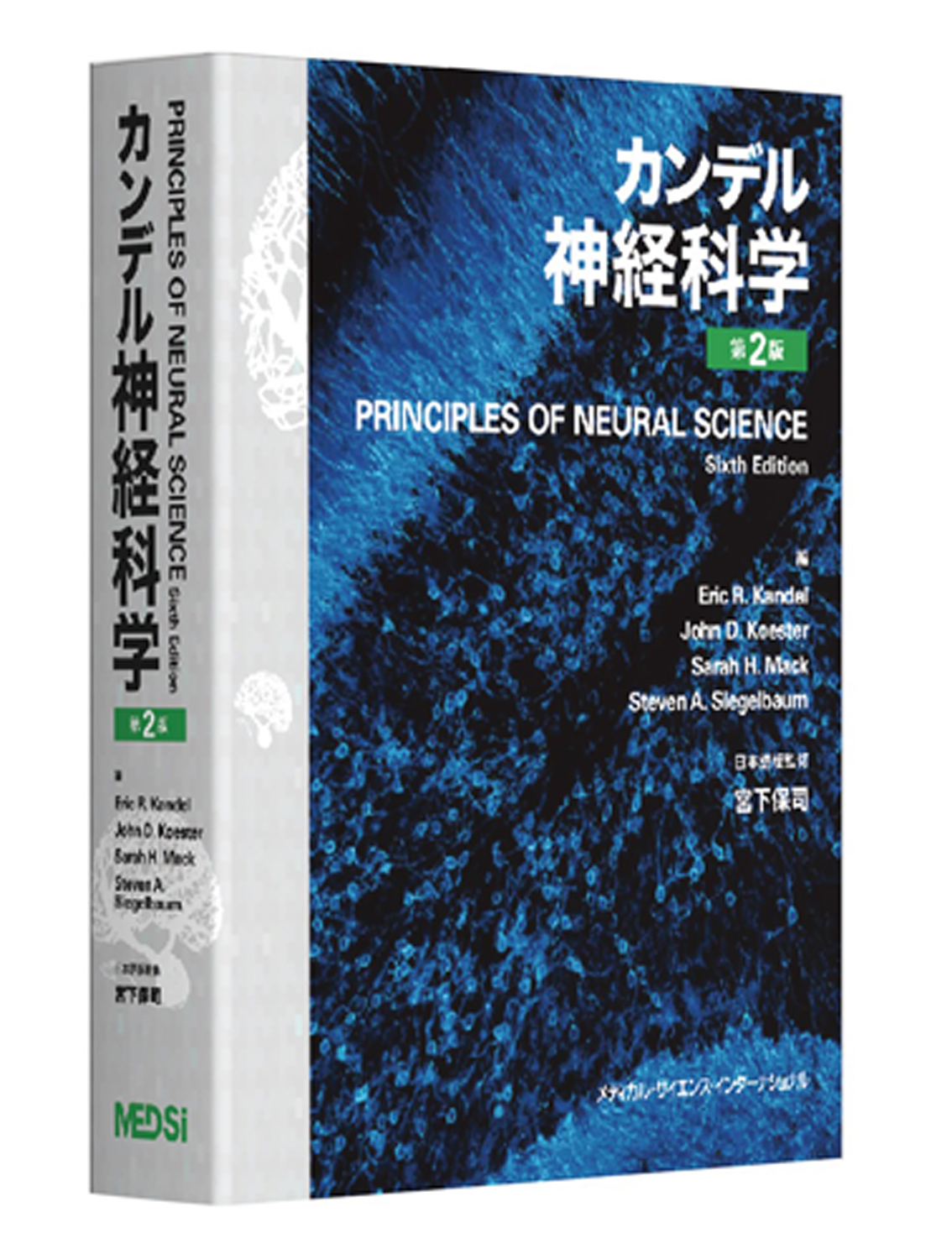
- カンデル神経科学 第2版
- ¥15,950
-
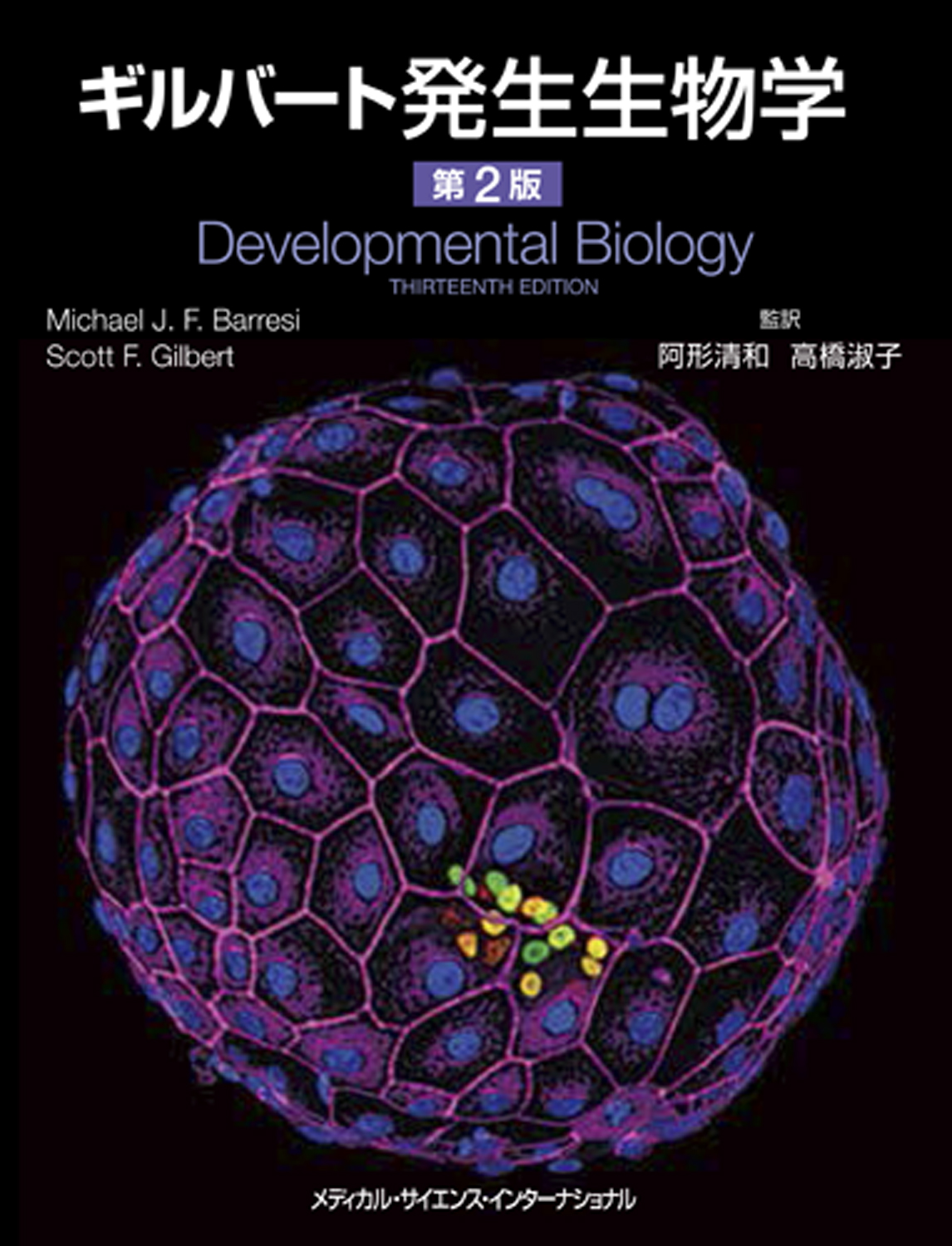
- ギルバート発生生物学 第2版
- ¥13,750
-

- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版
- ¥12,100
-

- 医学的研究のデザイン 第5版
- ¥6,270
-
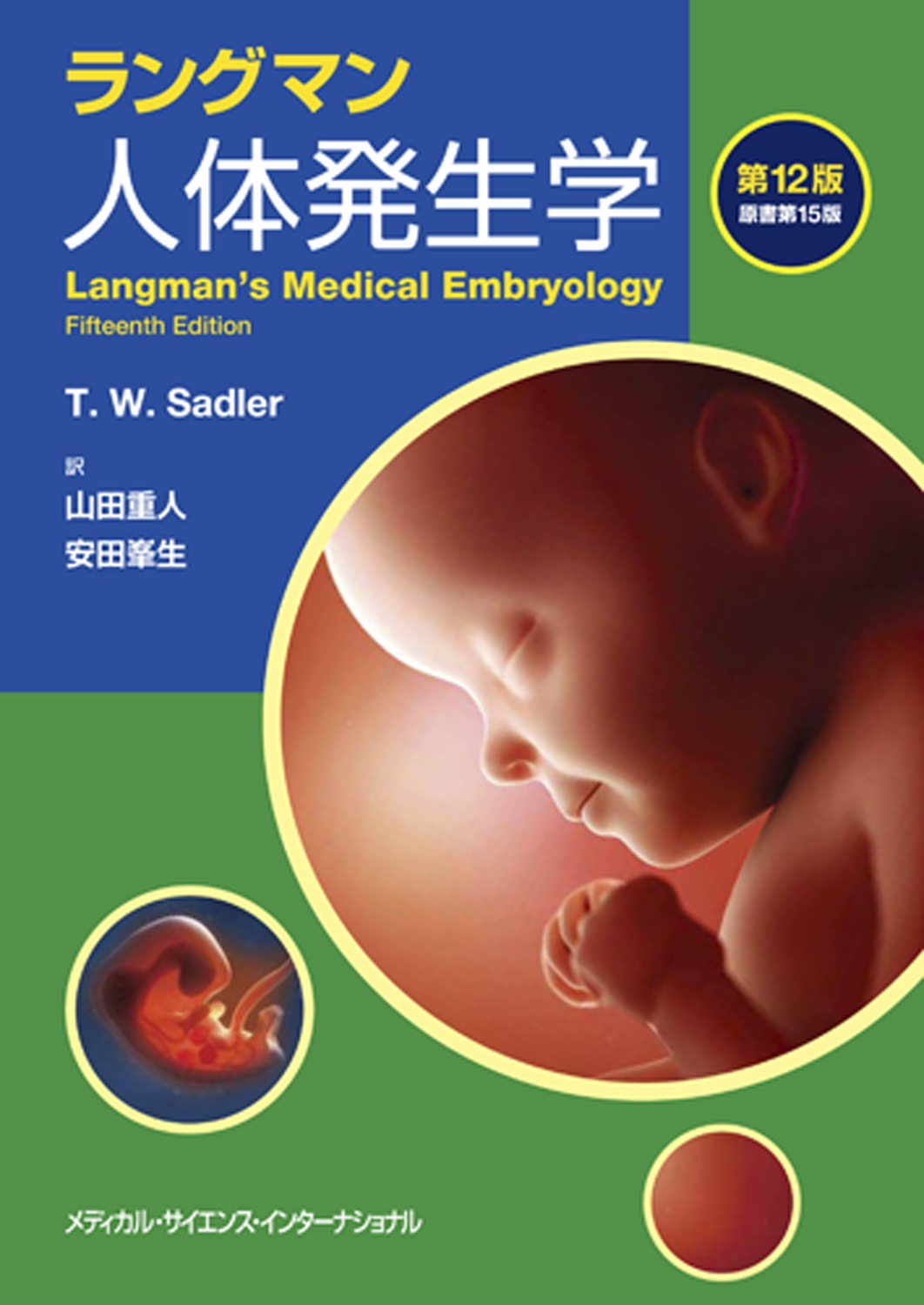
- ラングマン人体発生学 第12版
- ¥9,350
-
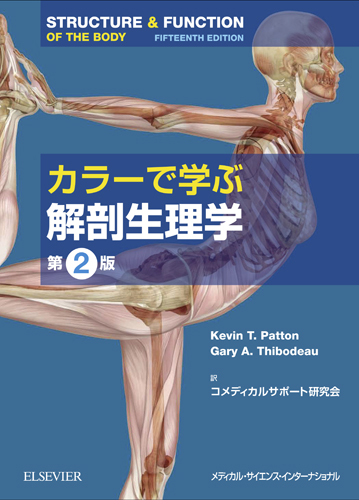
- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版
- ¥6,160
-
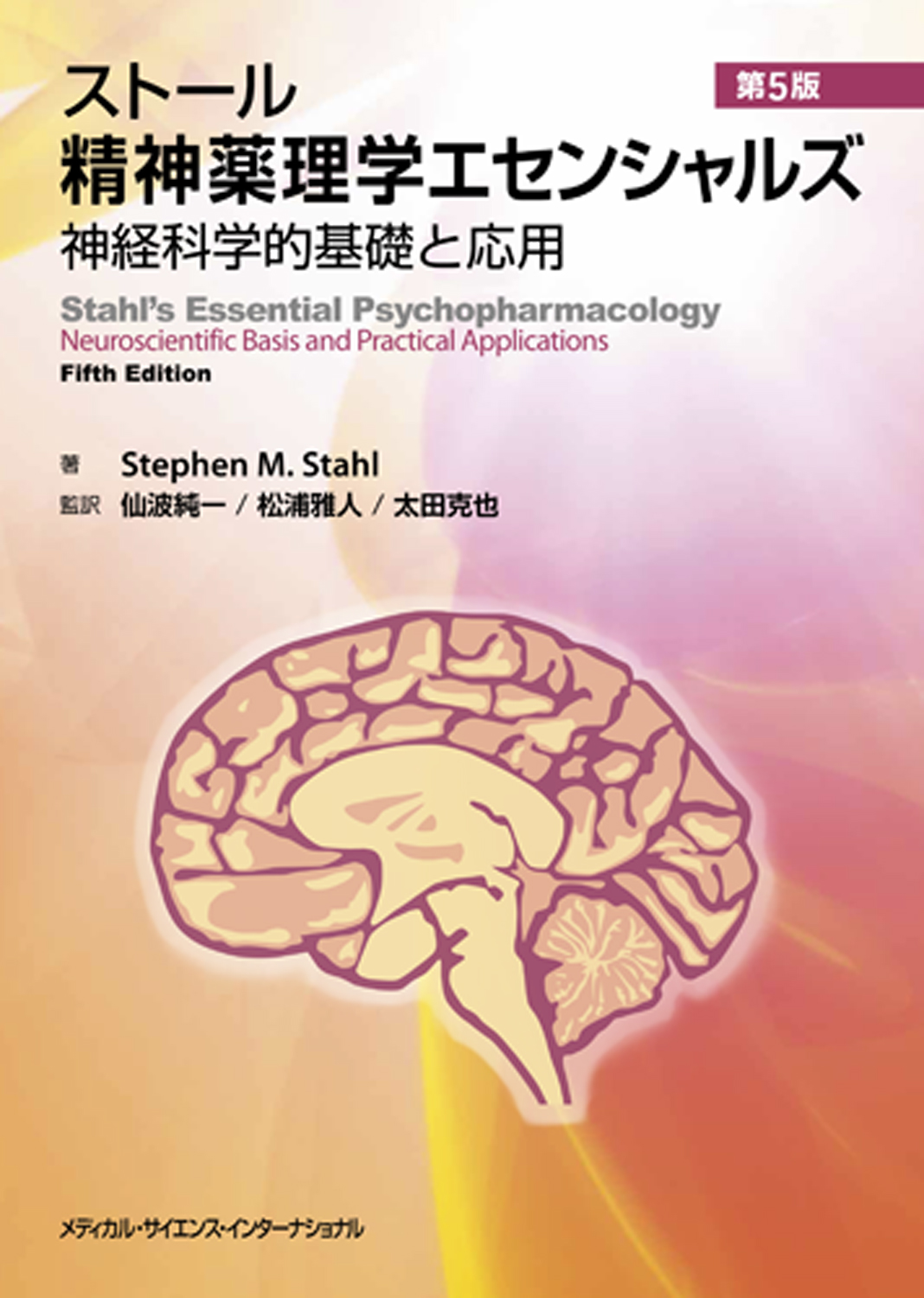
- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版
- ¥13,750
-

- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-

- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-

- エッセンシャル免疫学 第4版
- ¥7,150
-

- 臨床のための解剖学 第3版
- ¥15,950
-
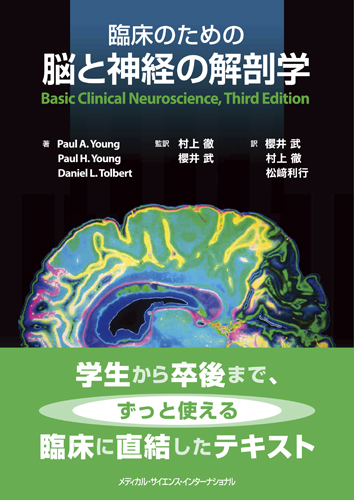
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-

- MRIの基本パワーテキスト 第4版
- ¥7,150
-
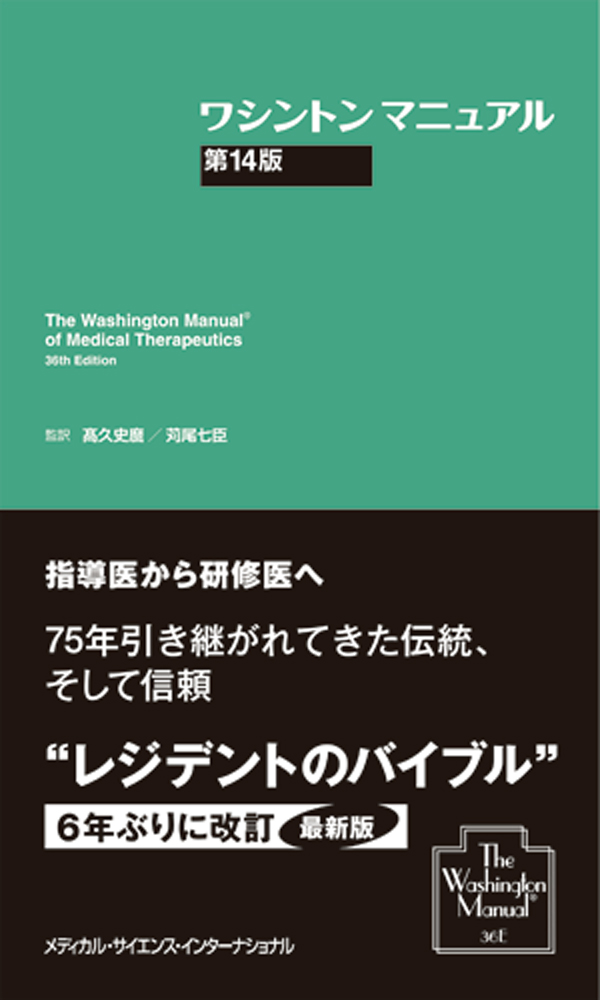
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-

- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-

- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-

- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
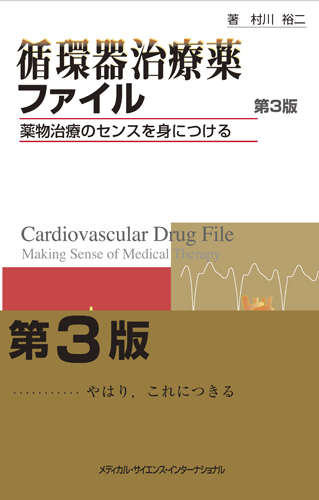
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-

- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
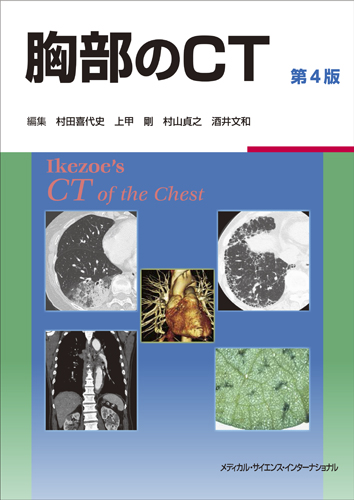
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
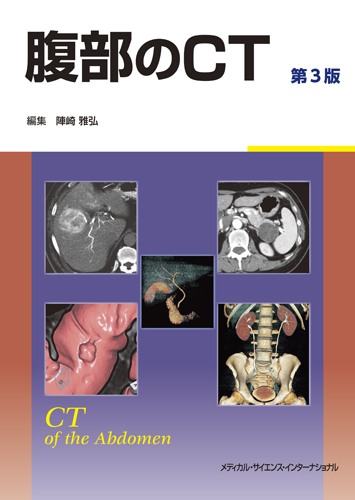
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
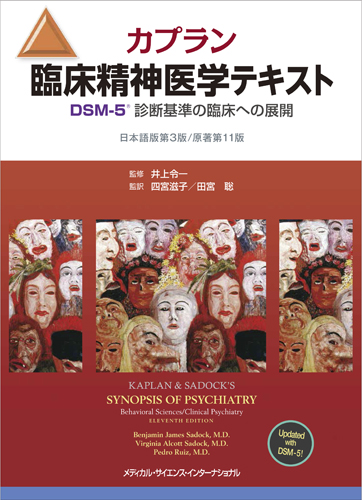
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000