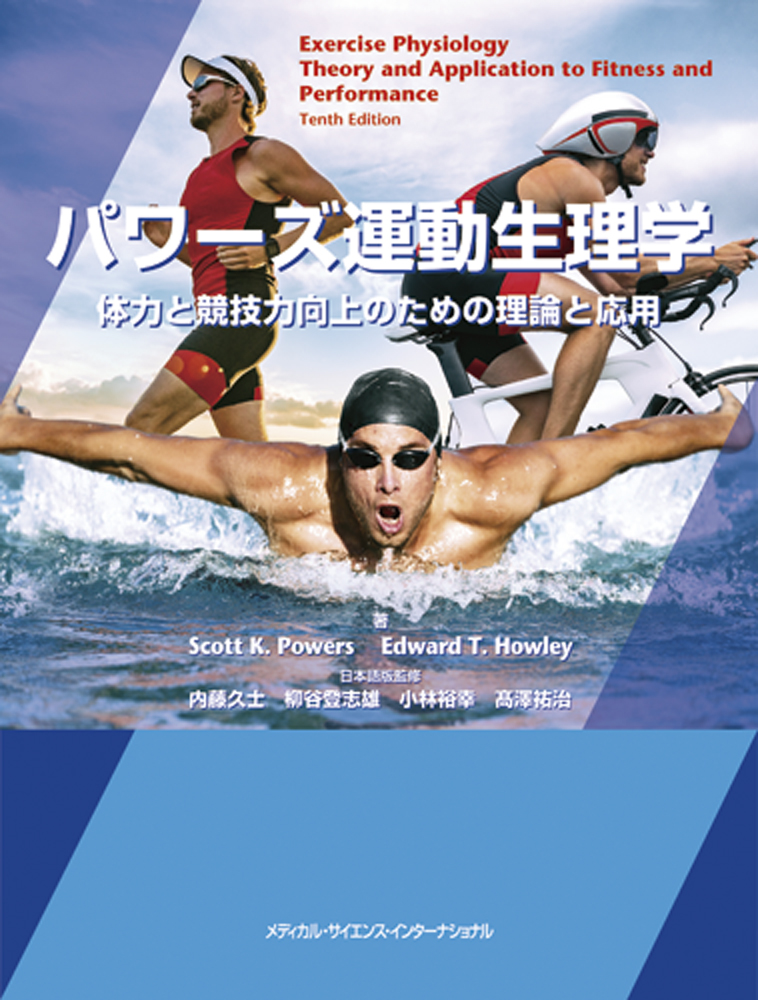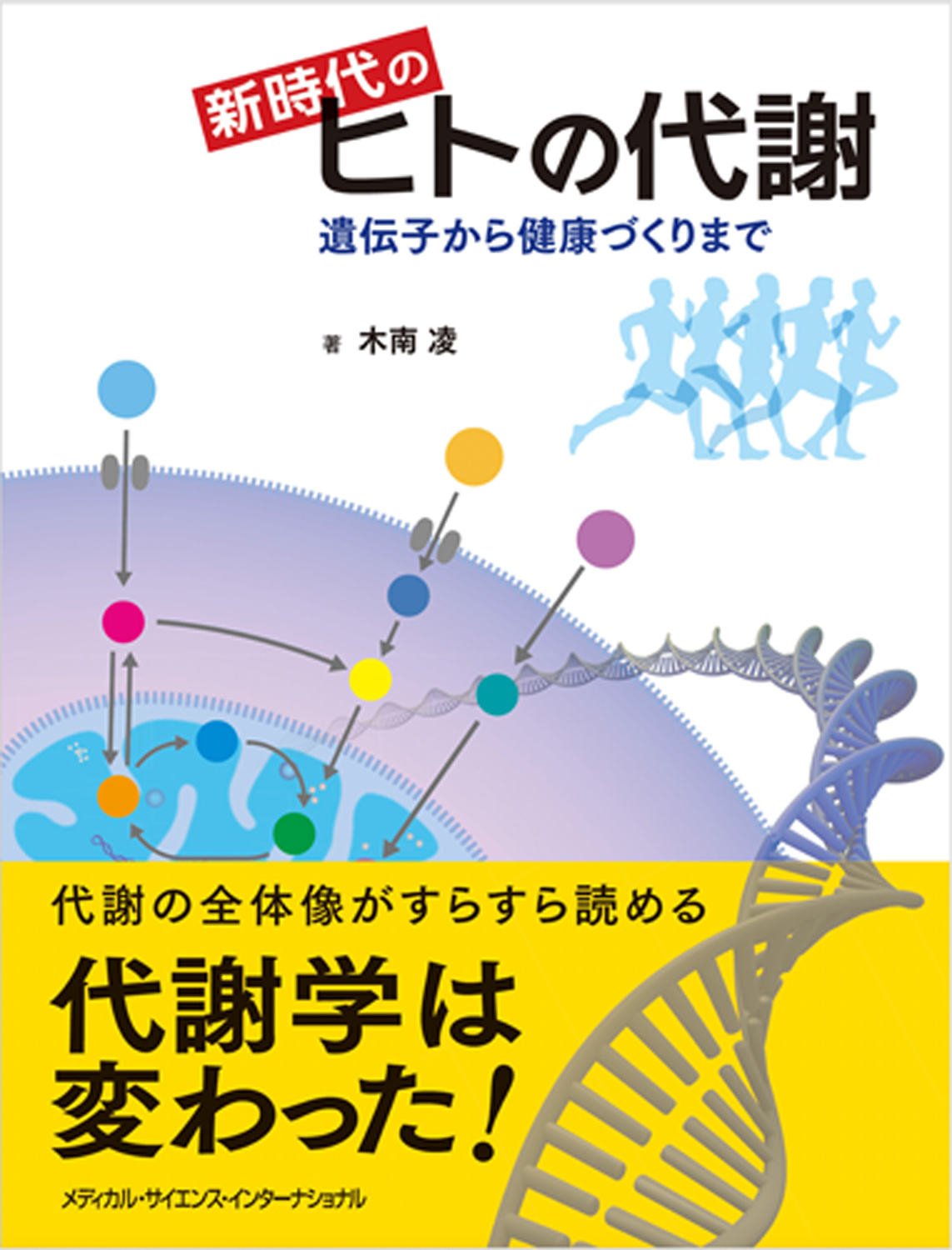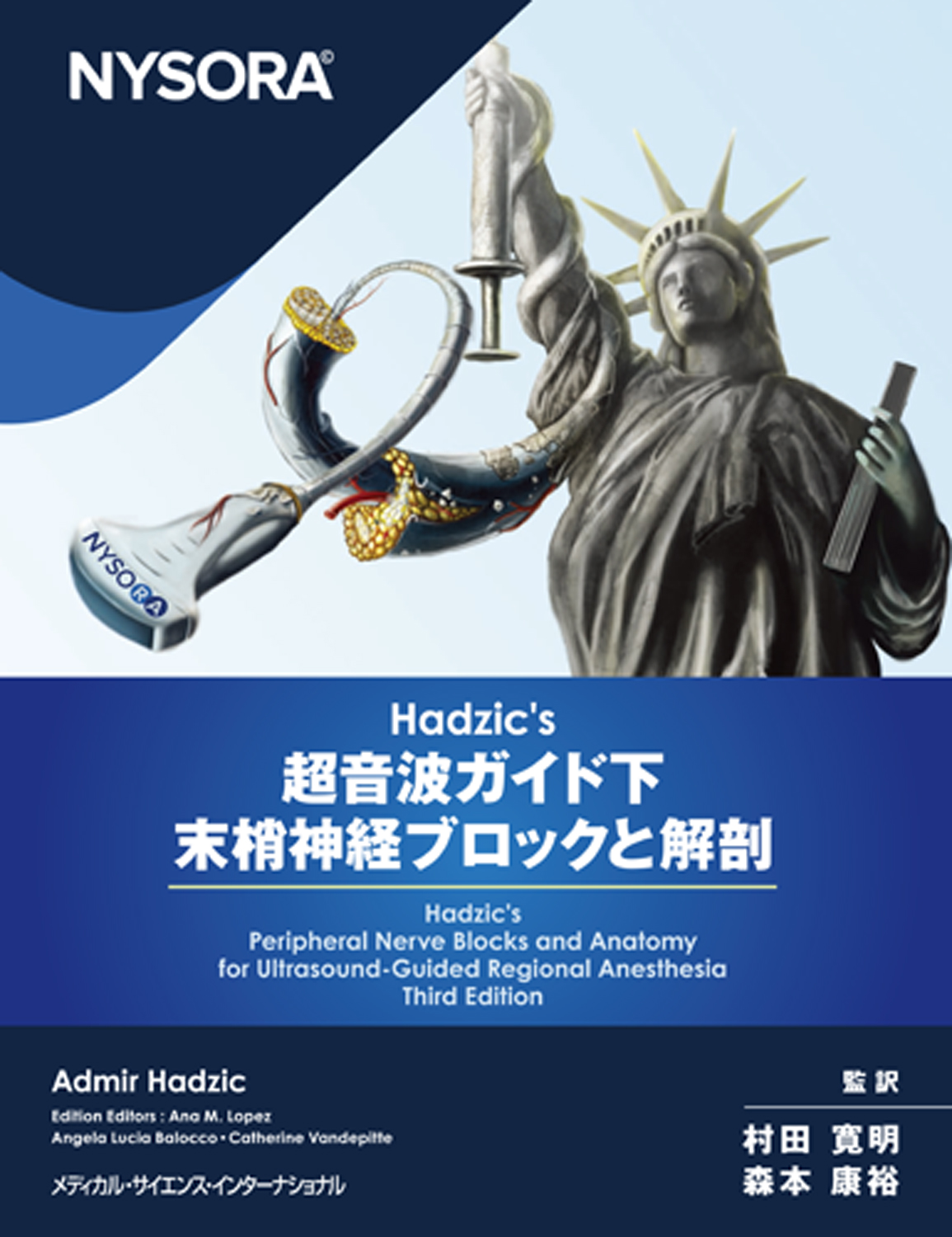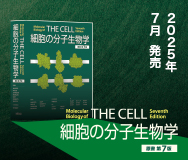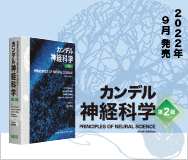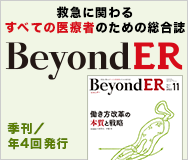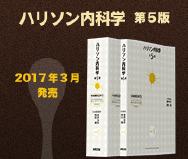ギルバート発生生物学 第2版
世界的に圧倒的な知名度を誇る『定本テキスト』、待望の改訂!
古典から現代的トピックまで、発生生物学を体系的に解説したロングセラーテキスト、10年ぶりの改訂。改訂にともない「ヒト初期胚発生」の章が新たに追加され、また、共著者バレシ博士による植物に関する知見も盛り込まれた。わかりやすい・親しみやすい文章、410点もの美しい写真という本書の特長は堅持しつつ、913点の図については大幅に改訂・アップグレード。今版より章の冒頭で重要なポイントを箇条書きで列挙、また動画などのオンラインコンテンツも提供するなど、学習意欲を増進させる工夫が付与された。生物・農学などバイオ系や、医学・薬学・歯学系・獣医学などの学生、研究者のためのスタンダードテキスト。
※動画準備中です
Part I 生成のパターンとプロセス:動物発生を理解するための枠組み
1 からだと場をつくる:発生生物学入門
2 細胞アイデンティティの特定化:発生学的パターンのメカニズム
3 差次的遺伝子発現:細胞分化のメカニズム
4 細胞間コミュニケーション:形態形成の仕組み
5 幹細胞:その潜在力,そのニッチ
Part II 配偶子形成と受精:性のサイクル
6 性決定と配偶子形成
7 受精:新たなる命の始まり
Part III 初期発生:卵割,原腸形成,体軸の特定化
8 初期発生の概念:発生の必須過程の概観
9 巻貝,花,線虫:細胞運命特定化の類似したパターンへの異なるメカニズム
10 ショウジョウバエにおける体軸形成の遺伝学
11 ウニ類とホヤ類:後口動物の無脊椎動物
12 両生類と魚類
13 鳥類と哺乳類
14 ヒト初期胚発生
Part IV 外胚葉の構築:脊椎動物の神経系と表皮
15 神経管の形成とパターン形成
16 脳の成長
17 神経堤細胞と軸索特異性
18 外胚葉プラコードと表皮
Part V 中胚葉と外胚葉の構築:器官形成
19 沿軸中胚葉:体節と体節由来組織の発生
20 中間中胚葉と側板中胚葉:心臓,血球,腎臓
21 四肢動物の肢の発生
22 内胚葉:消化・呼吸を担う管構造と器官
Part VI 後胚発生
23 変態:ホルモンによる発生の再活性化
24 再生:発生過程における再構築
Part VII より広い文脈における発生
25 発生の環境的および共生的な調節
26 進化的変化をもたらす発生メカニズム
監訳者の序
進化する発生生物学
発生生物学は,ダーウィンの『種の起源』にはじまった19 世紀の進化研究をその起源としている。すなわち,進化の道筋を推測するにあたり,成体の形態をもとに推測するのではなく,初期発生の胚の形態を比較することで進化の道筋を推測することからはじまった。一番よく知られている例は,二枚貝とミミズの仲間の関係である。成体の形は似ても似つかないのに,初期胚を比べるとどちらもトロコフォア幼生というきわめて似た形態を経て成体へと変態することから,2 つの動物は近縁関係にあることが推察された。このように,発生生物学は進化の道筋を体系だって推察するための「比較形態発生学」としてスタートを切ることになる。
記載学問としてスタートした発生生物学であるが,20 世紀に入ると実験サイエンスとしての発生生物学が勃興する。すなわち,「比較形態発生学」は博物学としての確固たる地位は築いたものの,あくまでも記載学問であり,物理学者や化学者にはサイエンスとしては認知されなかった。そんな記載学問としての発生生物学と決別して,発生のメカニズムを解明する「実験発生学」が20世紀になると誕生する。それは意図的な決別であり,博物学としての「比較形態発生学」と同じ“くくり”にされることを拒否した。そして,「実験発生学」は,Hans Spemann(ハンス・シュペーマン)によって,発生は“誘導の連続”によって遂行されることを示すことに成功する。今まで,サイエンスとして扱われてこなかった発生生物学はサイエンスとしての学問地位を確立する。Spemannは,その功績によって,1935年に発生生物学者として初めてノーベル賞の栄冠に輝く。それは,「比較形態発生学」と決別した「実験発生学」の勝利宣言にも近いものであり,20 世紀は「実験発生学」の世紀となり,「比較形態発生学」は19 世紀の学問へと閉じ込められた。
しかし,「実験発生学」もSpemannの神経誘導物質の同定にてこずっている間に,ショウジョウバエ,線虫,ゼブラフィッシュを用いた「発生遺伝学」にその主役の座を奪われていく。そして,80 年代から隆盛を迎えた分子生物学的手法の導入によって,クラスタータイプのホメオボックス遺伝子群が同定され,ホメオティック突然変異体を精力的に集めたEdward Lewis(エドワード・ルイス)らは,1995 年に発生生物学分野での2 度目のノーベル賞に輝く。20 世紀の発生生物学は,主流になるはずの「実験発生学」ではなく,「発生遺伝学」によって締めくくられようとしていた。
一方で,クラスタータイプのホメオボックス遺伝子群の発見は,発生生物学の「比較形態発生学」への回帰をもたらすことになる。なぜなら,19 世紀に隆盛を誇った「比較形態発生学」の記載を,クラスタータイプのホメオボックス遺伝子群はまるでゲノム科学として記載したかのようだったからである。ここに「進化発生学(Evolutionary Developmental Biology : EvoDevo)」が花咲き,20 世紀が終わる前に,マウスのゲノム上で遺伝子クラスターを形成している38 個のホメオボックス遺伝子のそれぞれすべてを遺伝子ノックアウトしたマウスがつくられ,前後軸に応じたパターン形成とゲノム進化をつなぐ実験研究が展開された。さらに背腹軸のパターン形成にもゲノム上に保存されている一連の遺伝群があることがわかり,すべての左右相称動物は,共通の起源をもつ生物によってその発生遺伝子プログラムをゲノム上に保存しながら進化してきたことを提示した。そればかりか,Spemannの“神経誘導物質”も“背側をつくる因子”として背側に神経を作ることで,まるで神経を誘導するかのように振る舞っていたことを明らかにした。20世紀も終盤を迎えたところで,発生生物学は葛藤を繰り返してきた歴史に終止符を打ち,「進化発生学」の登場によって過去の「比較形態発生学」「実験発生学」「発生遺伝学」の3 つをつなぐ新たな統一的な学問として理解されるようになったのである。
ギルバートの“Developmental Biology”は発生生物学の急速な変革の予兆が始まった1985 年に第1 版が出版されている。彼の序文にあるように,第1 版の刊行の時期から発生生物学はいろんな学問分野を取り込みながら,急速に新たなサイエンスとしての地位を築いていくことになる。この急激な変化についていくために,ギルバートは平均して2 年に一度新たな版を重ねて教科書として時代遅れにならないように心がけている。そして,挙げ句の果てには,新たな時代の発生生物学を先取りして教科書を執筆することを第10版から始めた。すなわち,ギルバートは第10版からEcological Developmental Biologyという章を設け“Eco‒Evo‒Devo”がこれからの発生生物学の新たな方向性であることを黙示した。さらにこの第13 版では,ヒトの発生を章立てすることで,ヒトiPS 細胞の登場によってヒトの発生を構成的に調べられる時代の到来を先取りすることを始めている。そういった意味では,医学領域の若い研究者にもこの改訂版のギルバートの“Developmental Biology”は是非とも読んでもらいたい。そこには,ヒトの発生のみならず老化や病気を理解するのに不可欠な知識が沢山盛り込まれているからだ。また,第10 版から第13 版の間に植物の発生も動物の発生と比較しながら取り上げられているのも大きな特徴だ。
監訳者の一人である小生が,50 年前に発生生物学に身を投じたときは,Spemannのオーガナイザー研究が主流であったころの末期で,新たな発生生物学への模索がすでに始まっていた。監訳者の二人が師事した岡田節人氏は,オーガナイザー研究との決別を早期に掲げ,細胞レベルでの発生生物学的研究を奨励すべく,日本の発生生物学の変革に乗り出していた。細胞を生命の単位としてとらえる発生生物学を展開するために細胞培養技術を日本に導入し,さらには分子生物学的手法をもいち早く導入し,日本の発生生物学の近代化を図った。小生などは,再生研究を目指して岡田研に入ったにもかかわらず,最初にしたことは制限酵素の精製だった。高橋淑子さんに至っては,マウスES細胞にニワトリのク
リスタリン遺伝子を導入して,キメラ作製によるトランスジェニック・マウスの作製を80年代に大学院生として行っていた。我々とほぼ同世代のギルバートが,我々と同じ体験・感覚を共有しながら細胞・遺伝子レベルの解析によって明らかにされてきた発生生物学を柱に教科書を書き上げた。本書は,我々が50 年間かけてリアルタイムで学んできたことを,次世代を担う若者が1 か月で習得することを目的に書かれている。そして,その若者たちが,これからの49 年と11 か月を新しいサイエンスに専念できるようにすることが狙いである。我々がリアルタイムで感動したオリジナル写真がふんだんに使われていることも本書の特色である。文章のみならず写真から味わう感動も是非とも未来へつなげてもら
いたい。これが翻訳に携わったすべてのメンバーの共通の思いである。
翻訳者・監訳者を代表して,
阿形清和(元日本発生生物学会会長)
-
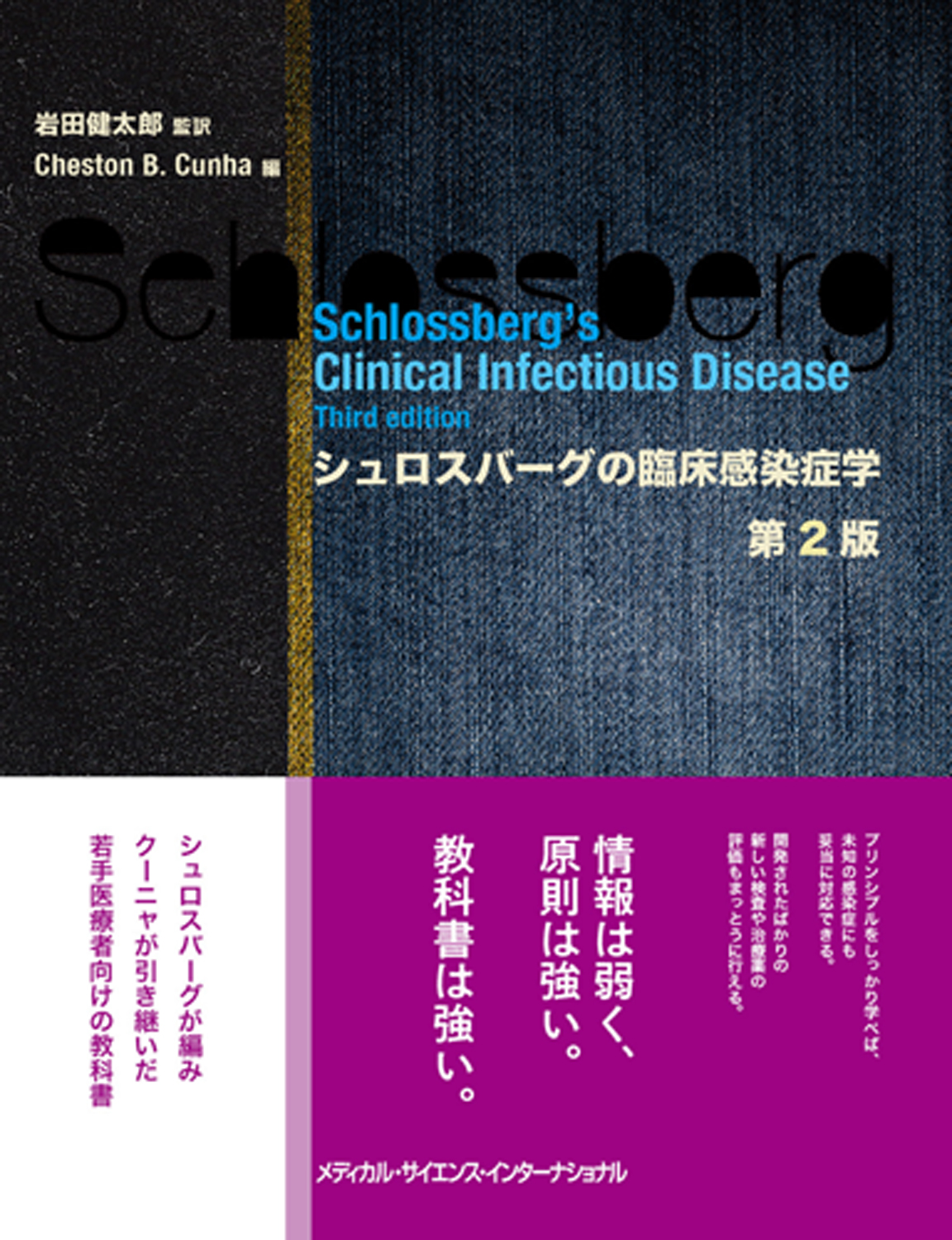
- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版
- ¥25,850
-
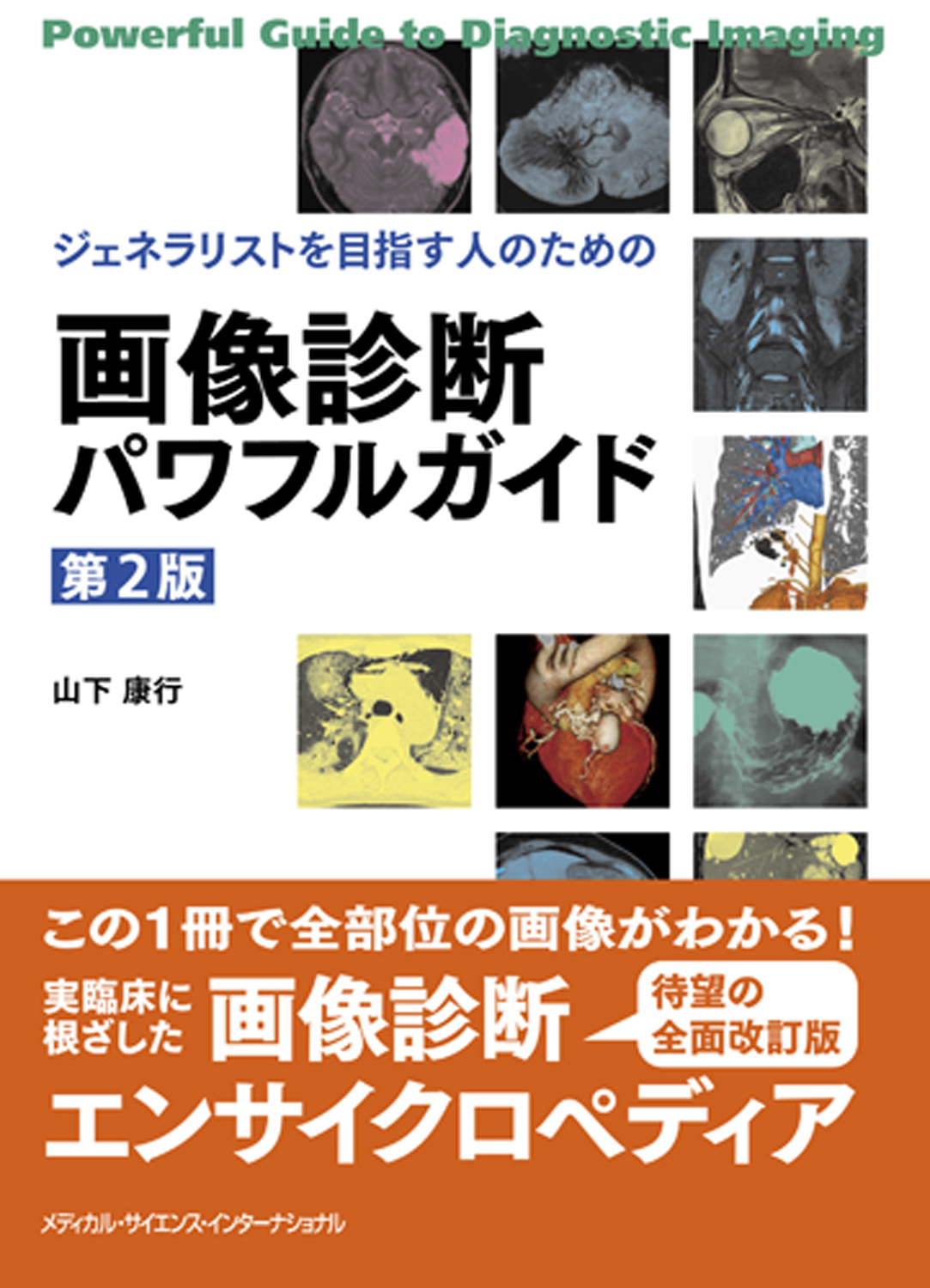
- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版
- ¥12,100
-
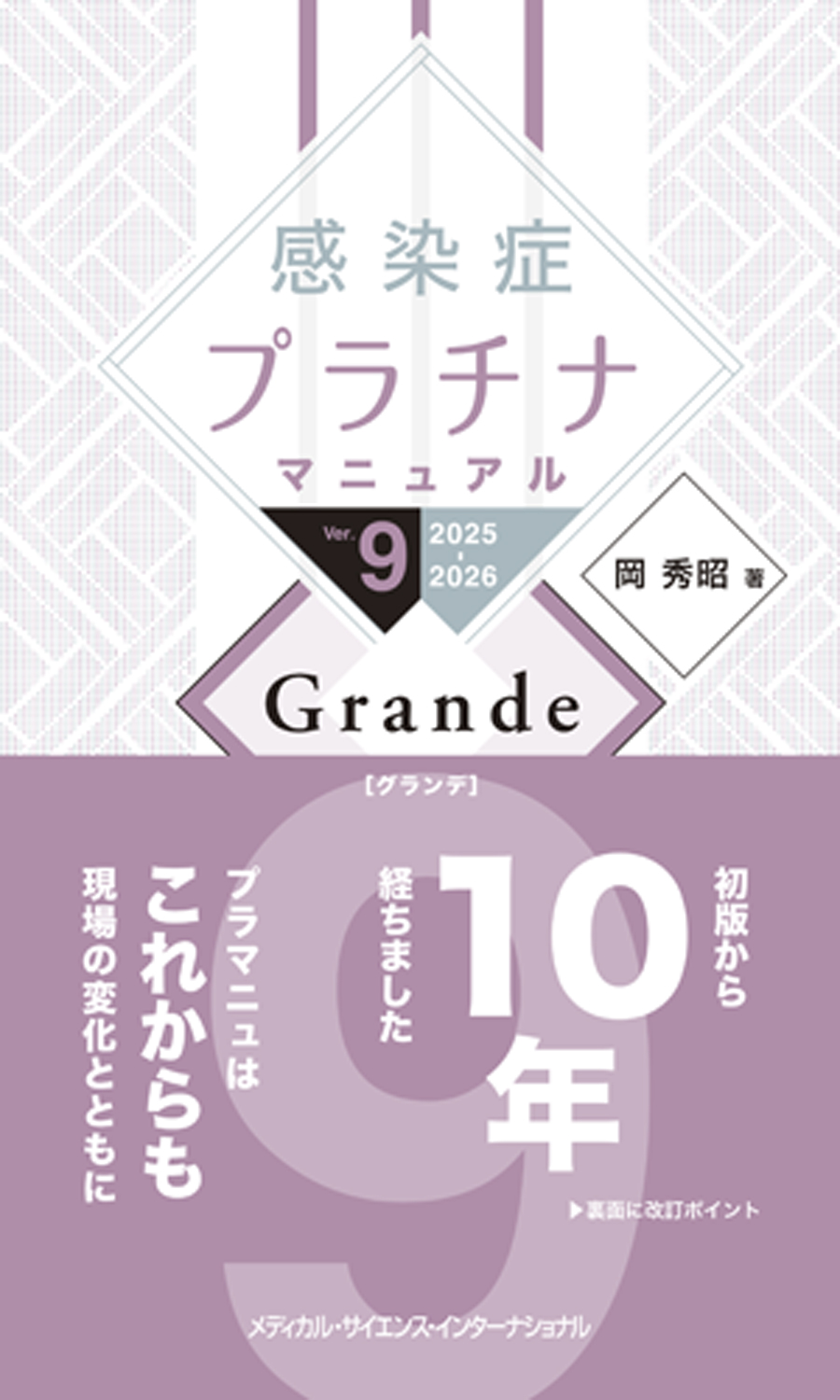
- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande
- ¥4,180
-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版
- ¥8,250
-
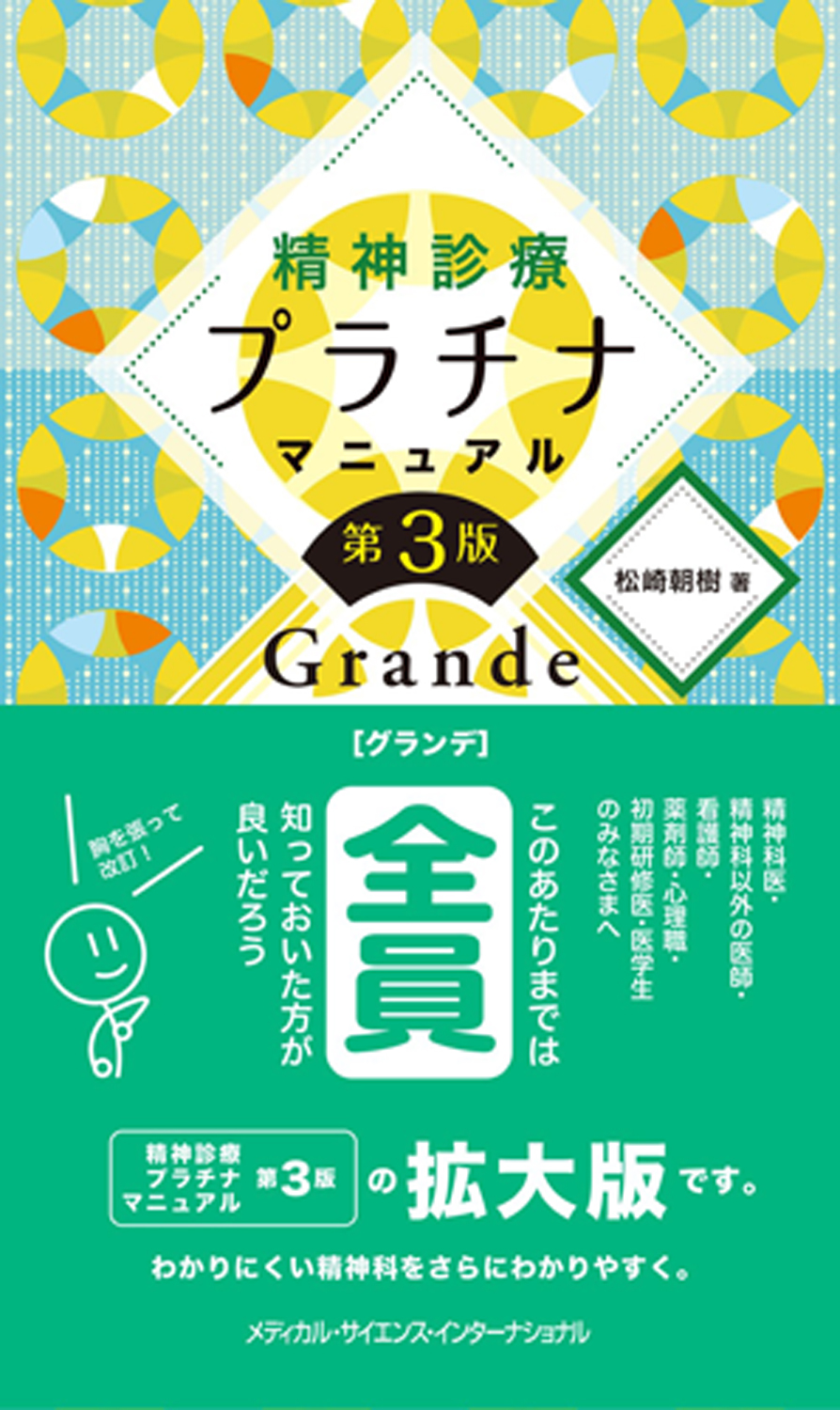
- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版
- ¥3,960
-
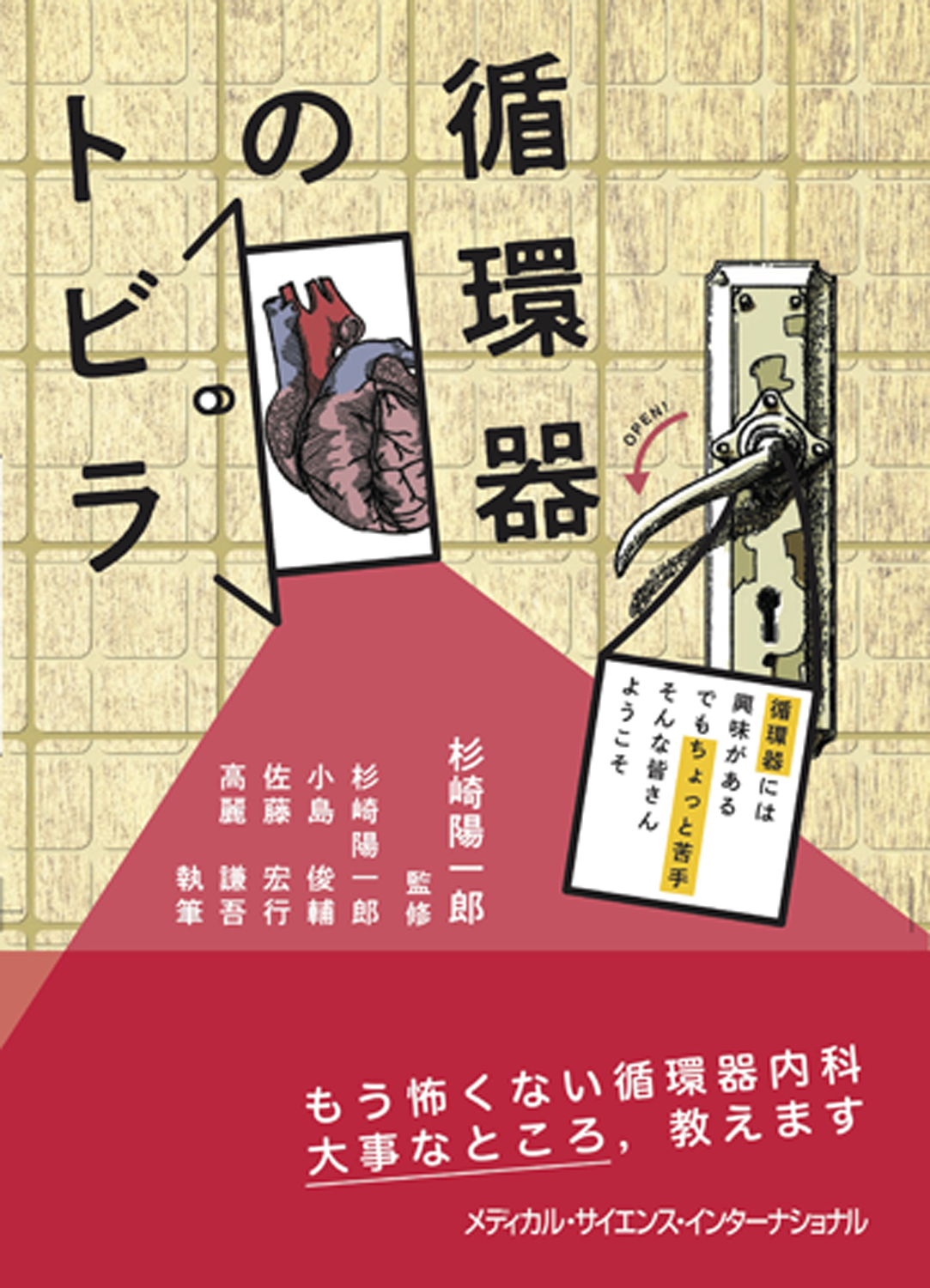
- 循環器のトビラ
- ¥5,940
-
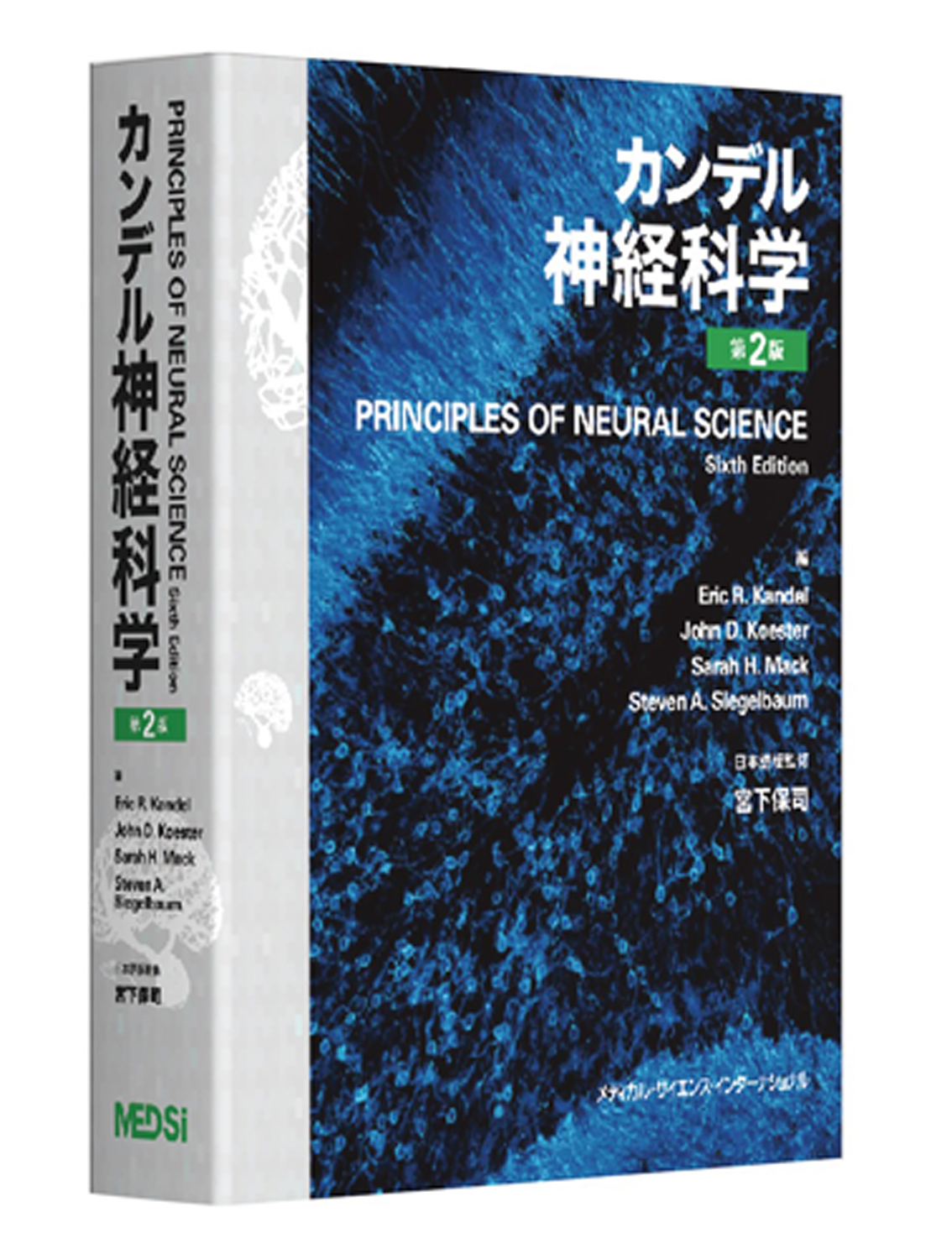
- カンデル神経科学 第2版
- ¥15,950
-
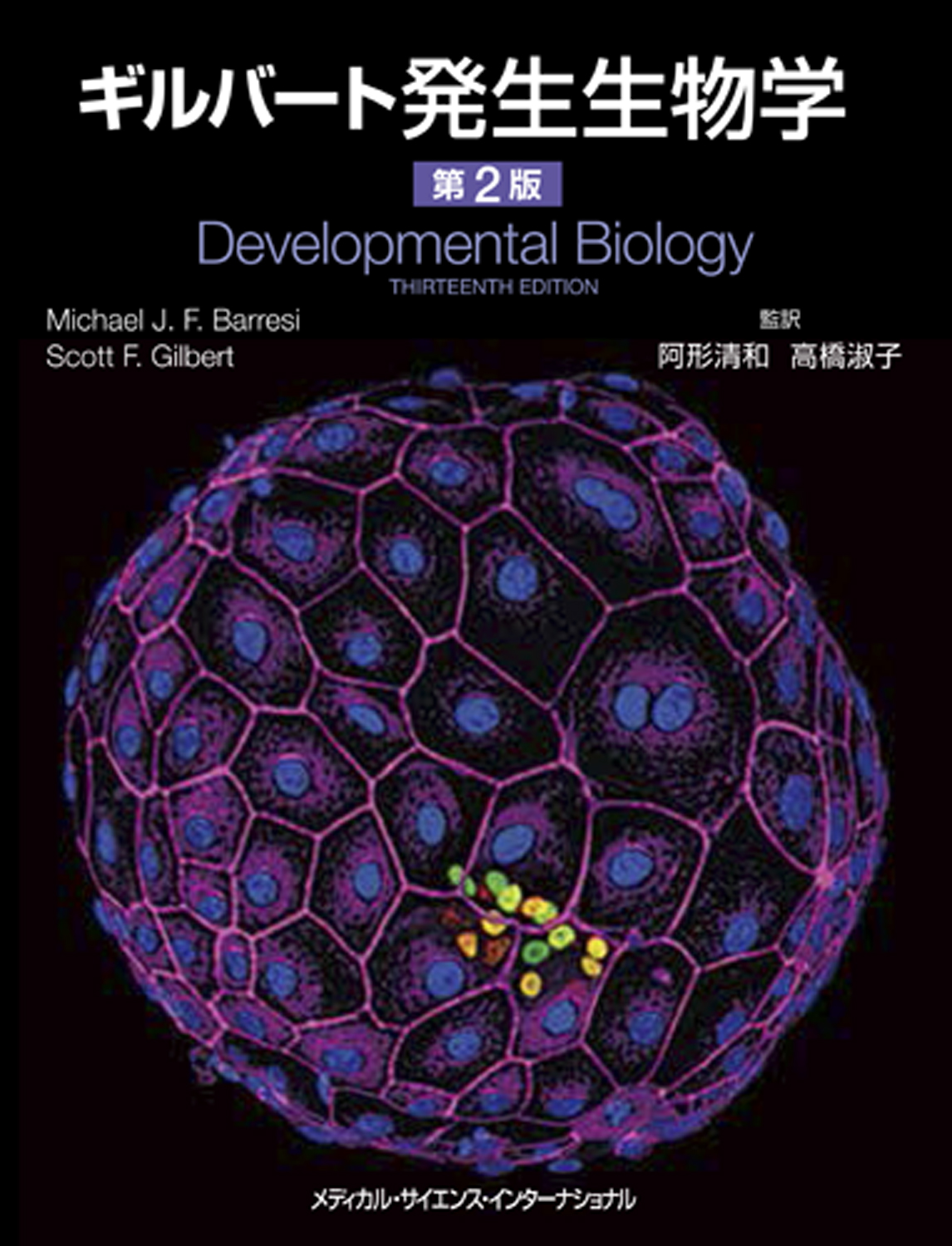
- ギルバート発生生物学 第2版
- ¥13,750
-
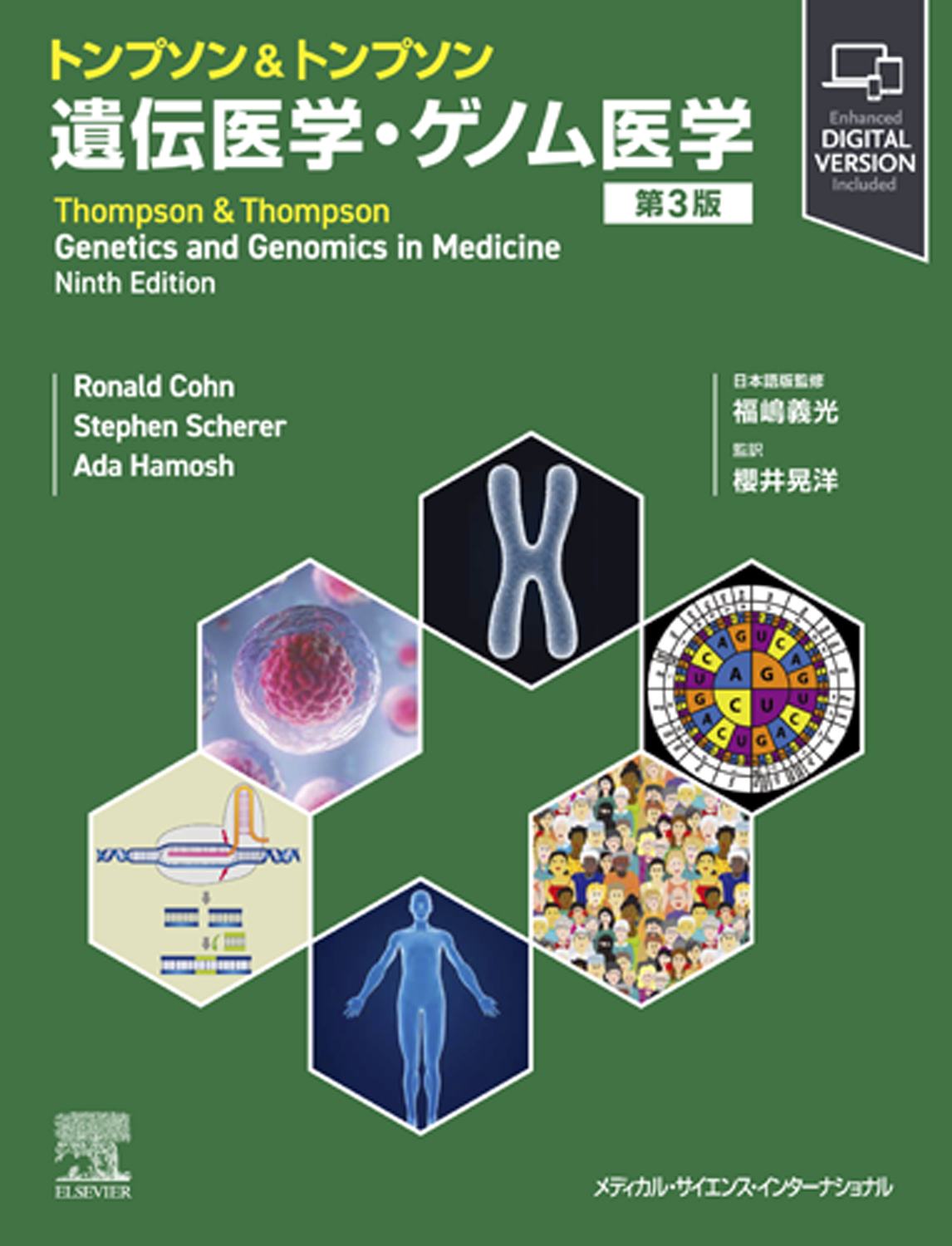
- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版
- ¥12,100
-
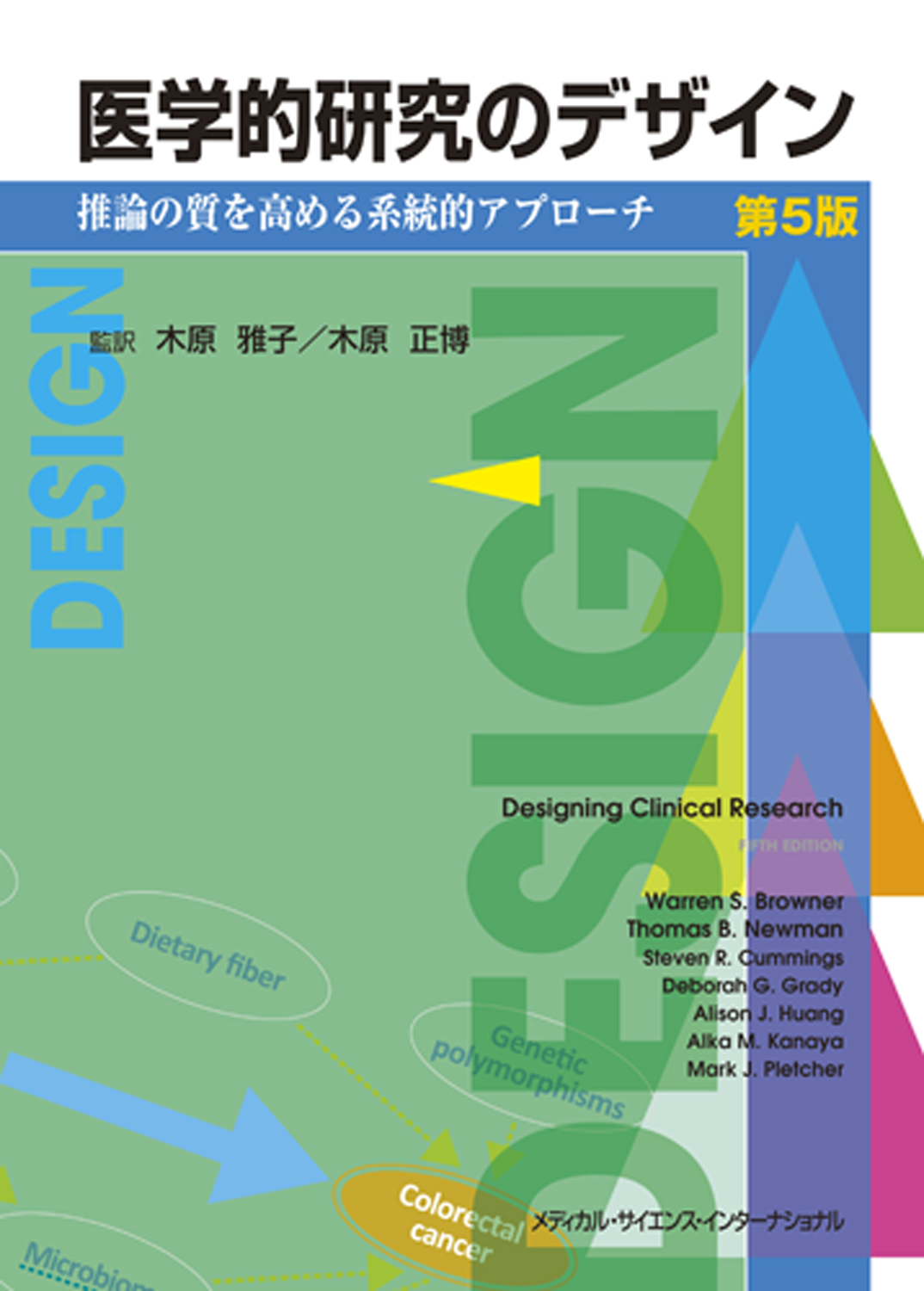
- 医学的研究のデザイン 第5版
- ¥6,270
-
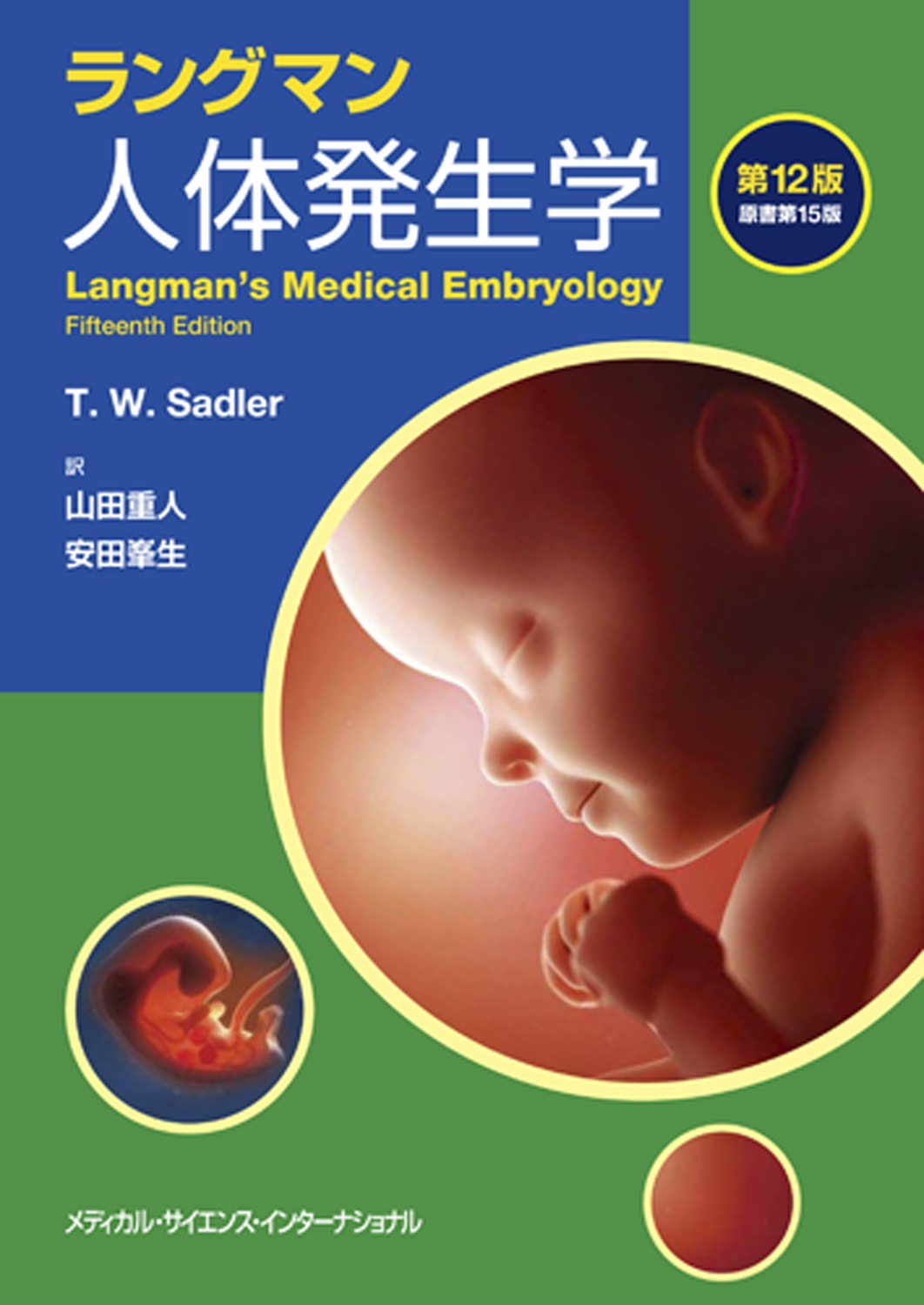
- ラングマン人体発生学 第12版
- ¥9,350
-
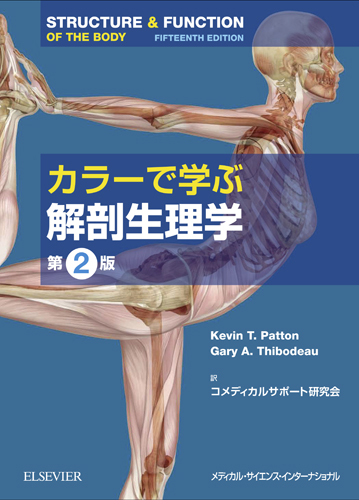
- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版
- ¥6,160
-
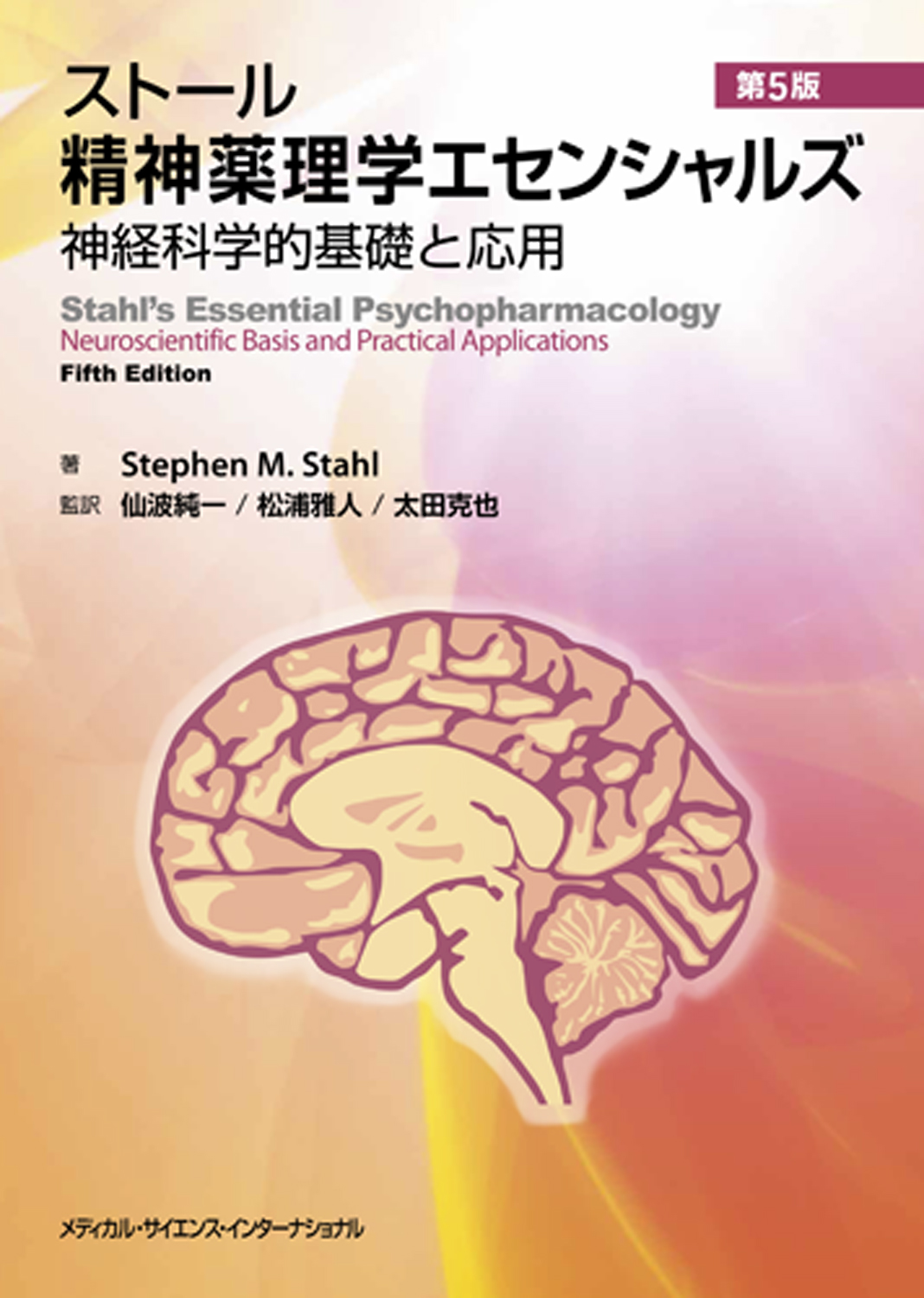
- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版
- ¥13,750
-
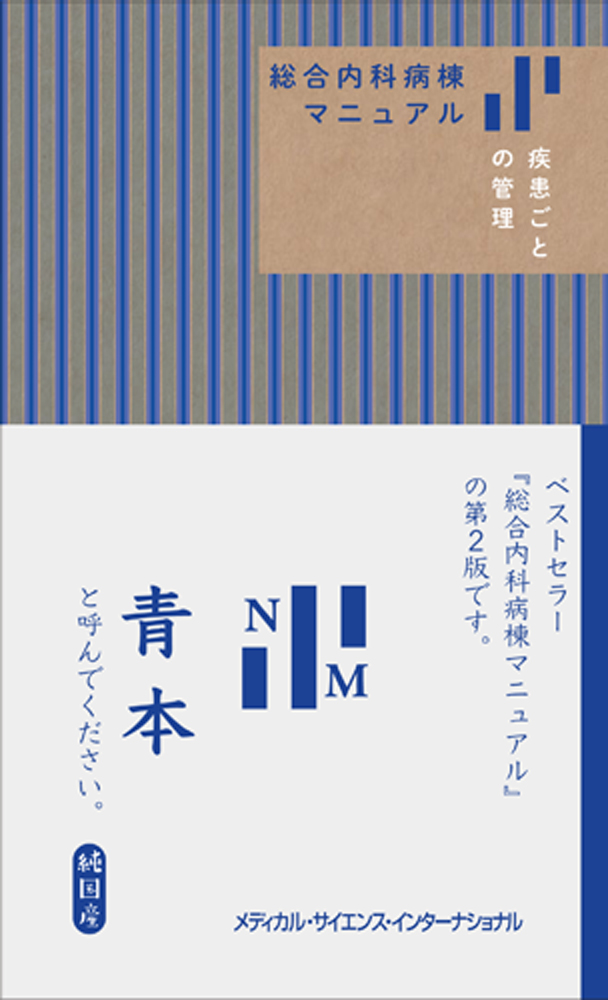
- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-
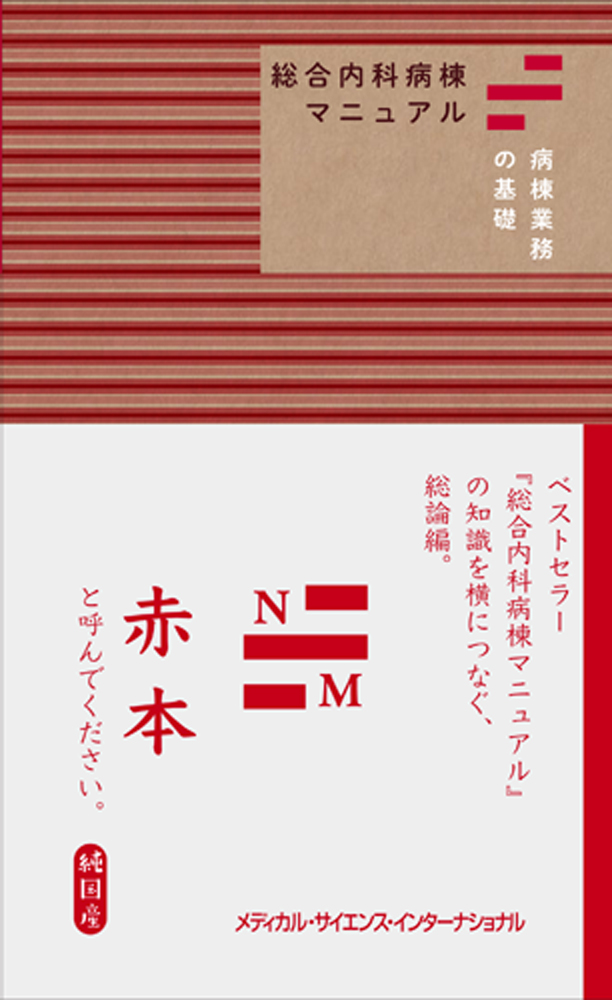
- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-
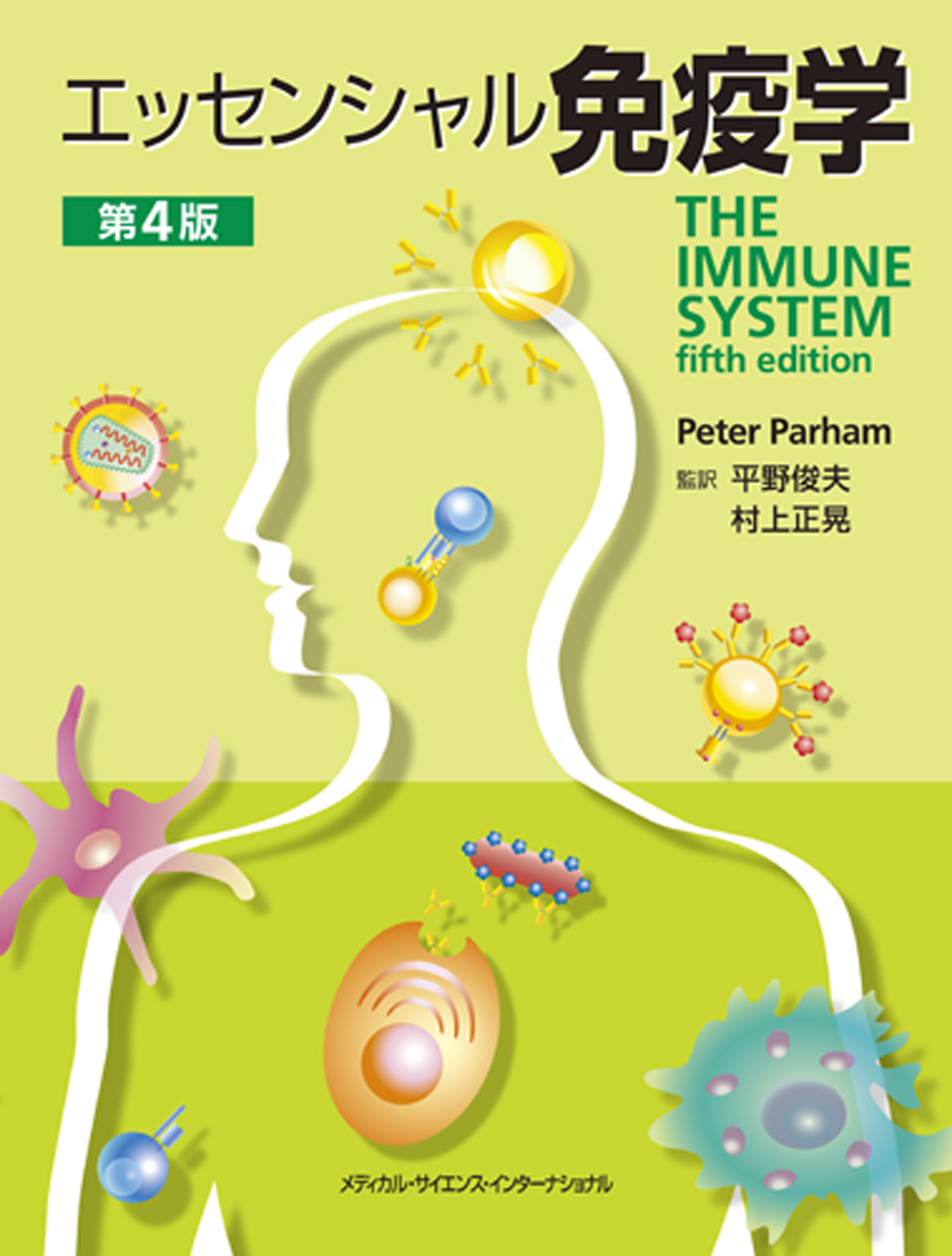
- エッセンシャル免疫学 第4版
- ¥7,150
-
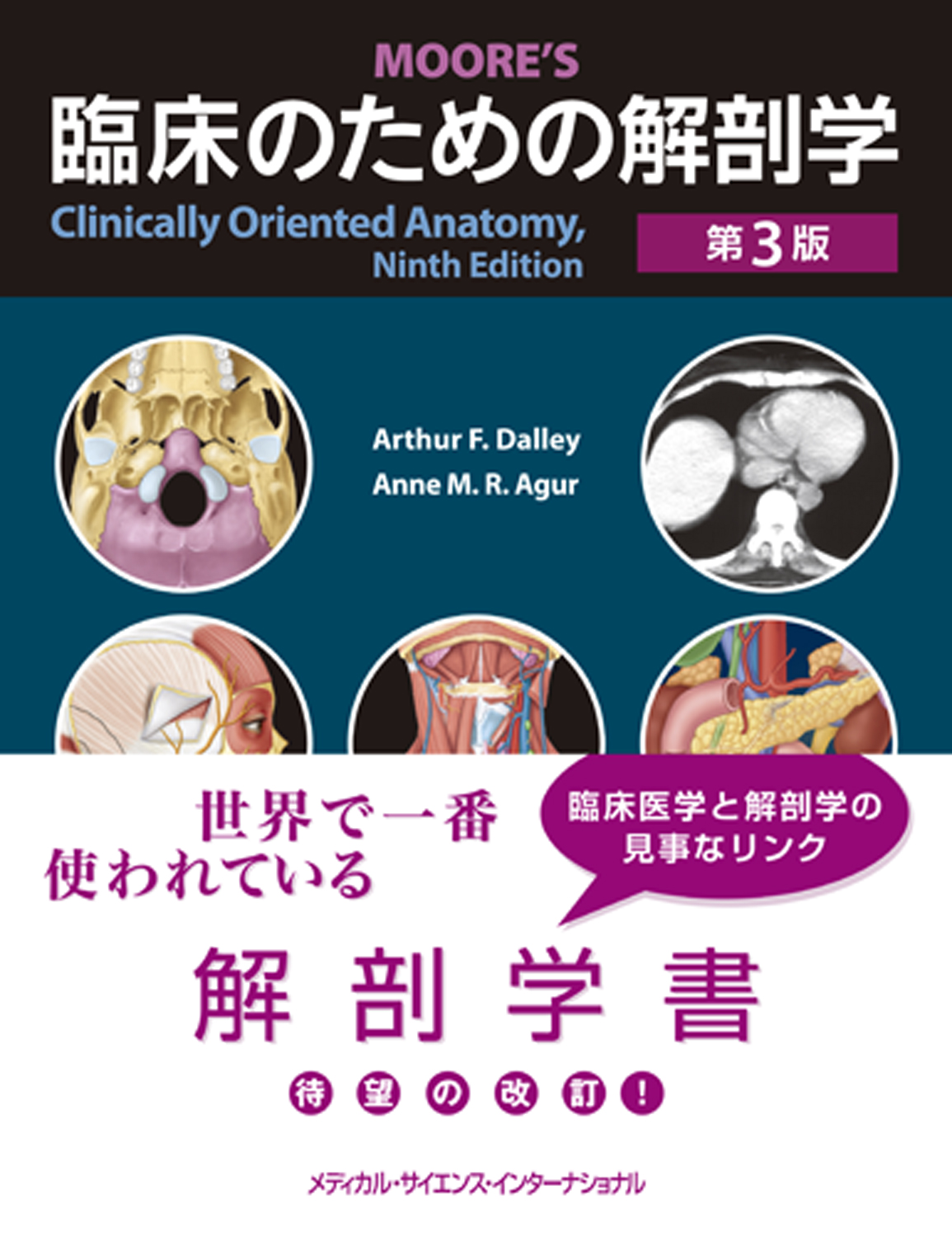
- 臨床のための解剖学 第3版
- ¥15,950
-
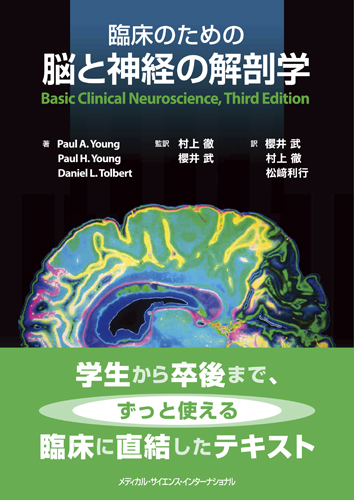
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-
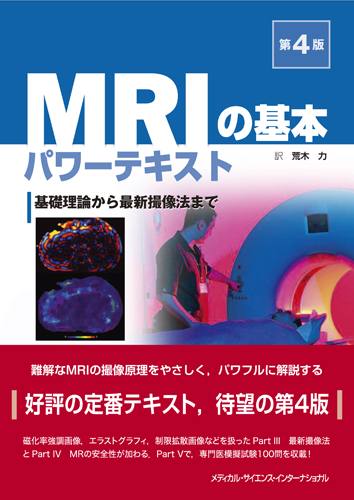
- MRIの基本パワーテキスト 第4版
- ¥7,150
-
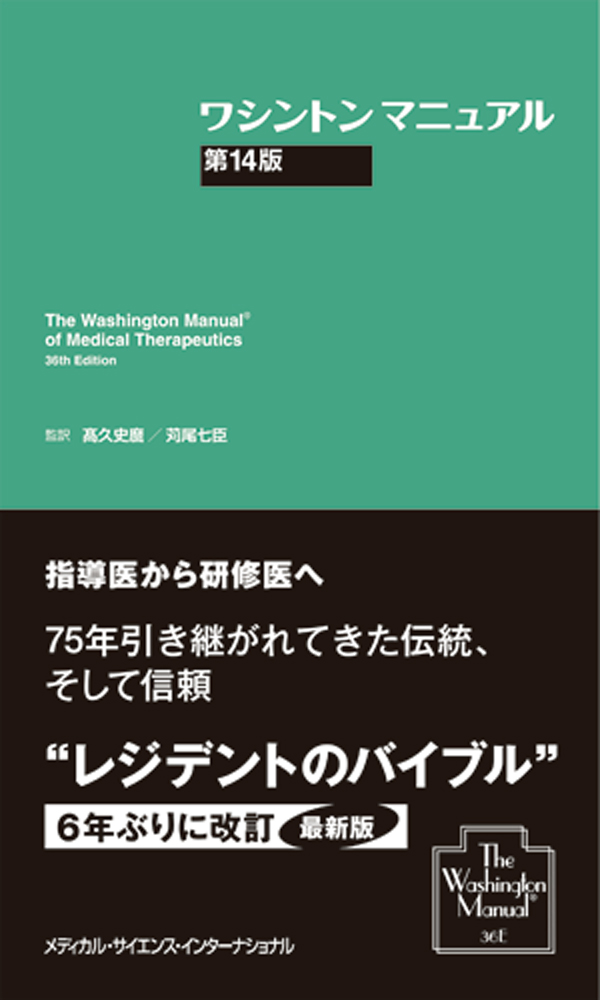
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-

- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-
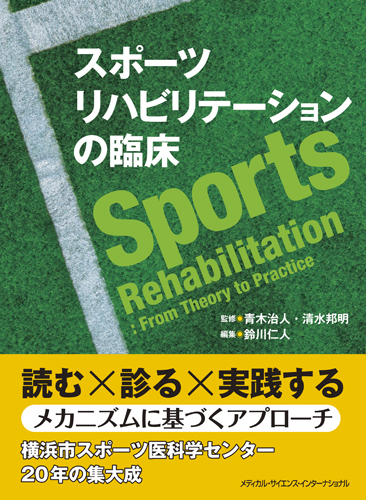
- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-
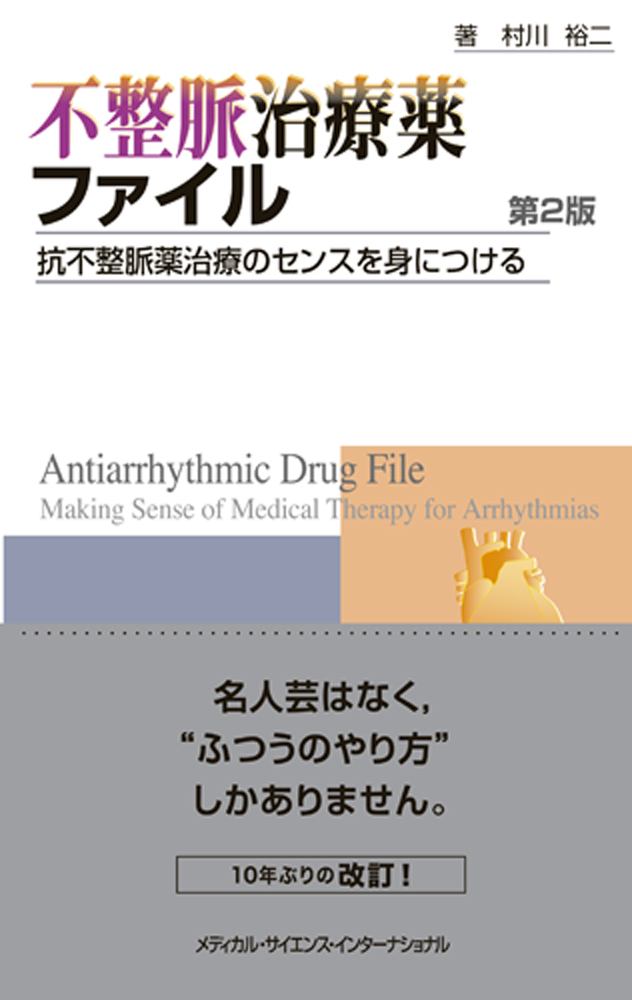
- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
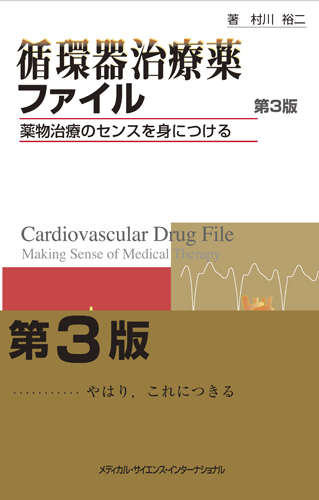
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-
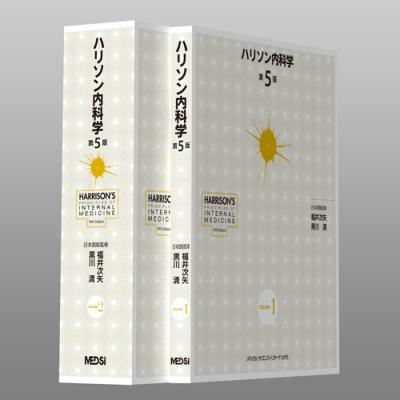
- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
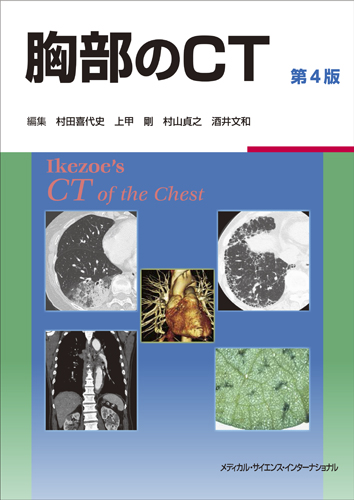
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
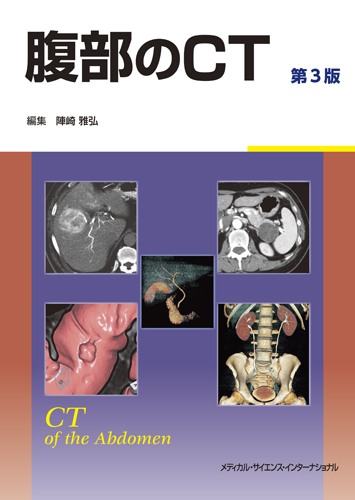
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
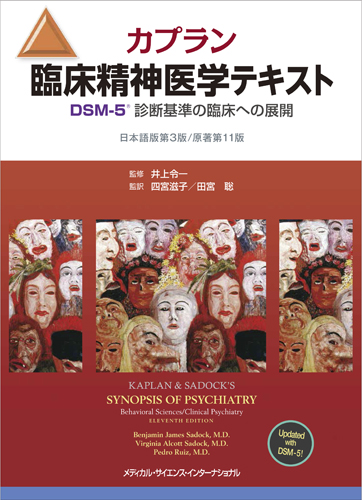
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000