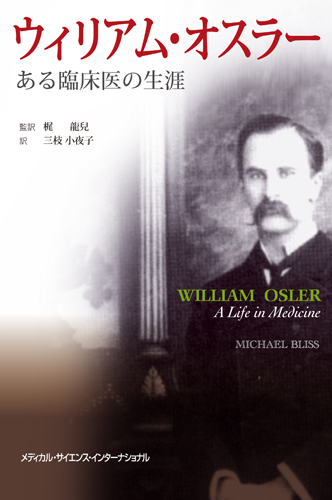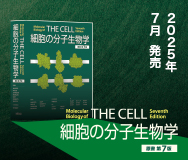ウィリアム・オスラー ある臨床医の生涯
最も偉大な医師であったと言えるか?
本書は19〜20世紀にかけて米国の医学教育の基礎をつくり、日本にも多大な影響を与えたウィリアム・オスラー博士のこれまでにない伝記である。ややもすると神格化されがちなオスラーを、膨大な資料の検証ときめ細かな調査に基づき、公正かつ客観的に、魅力的な"生身の人間"として描出。当時の社会や文化的背景も踏まえた医学史としても興味深い。医学生や臨床家が、現代医学の根底にある「医の哲学」を学び、考えるのに格好の書。またその生き方は、ひろく一般の読者をも魅了して止まない。
監訳者序:いまなぜオスラーなのか?
序:オスラーを解剖する
第1 章 アメリカ人のようにエネルギッシュな英国紳士
第2 章 ものの見方を知る:学生時代
第3 章 ベイビー・プロフェッサー
第4 章 最高の人材:フィラデルフィア
第5 章 ジョンズ・ホプキンズへ
第6 章 誰もが彼を崇拝している
第7 章 アメリカを代表する偉大な医師
第8 章 さらば,アメリカ
第9 章 快適な暮らしと快適な場所
第10 章 ウィリアム卿
第11 章 若者も,名のある人も
第12 章 杖を使うべからず
第13 章 オスラーの死後の生
注記と出典 534
【監訳者序】
いまなぜオスラーなのか?
本書は,米国の医学教育の基礎をつくった19 世紀から20 世紀初頭にかけて活躍したウィリアム・オスラー博士の伝記である。彼の伝記としては,弟子でもあった有名な脳外科医であるハーヴェイ・クッシング博士による大部の著作が20 世紀前半に上梓され,当時ピューリッツァー賞を受賞している。わが国でも,これを基にしたオスラーの伝記が私の大学の先輩でもある日野原重明先生によって書かれており,詳しく紹介されている。
では,なぜまた新たに伝記を日本語で出す必要を感じたか,ここで述べておきたい。
私事にわたるが,私は京都大学を卒業して1985 年に米国に渡り,ペンシルベニア大学でクリニカルフェローを終え,アシスタントプロフェッサー(日本の助教にあたる)として医学部の学生の教育にも参加することになった。そのとき,ペンシルベニア大学で独自に作成した分厚いシラバス(医学教育の資料で教科書ぐらいの分厚さがある)を渡されたのだが,その1 ページ目に,次のような文章が書かれてあった。
患者を目の前にして,次のことを常に念頭におくこと
1.患者はどのような問題でやってきているのか?
2.それに対して何ができるのか?
3.そうした場合,患者のこれからの人生はどうなるのか?
これは当時オスラーの3 原則とよばれ,オスラーがペンシルベニア大学で内科の教授をしていたころの教えを引き継いでいるのだという。それまで私が日本で受けた医学教育ではまったく聞いたことがない言葉である。私は一学生にもどって,オスラーについて勉強する機会を得た。
解説には,次のようなことが書いてあった。
患者は何らかの問題を抱えて外来にやってくる。それは一生の一大事であることもある。また,その本当の問題は主訴とイコールであるとは限らない。たとえば,ストレスで起こるとされる緊張性頭痛でやってくる人の本当の問題は頭痛ではなく,周りの環境にある。このような患者に医師としてできることとは,単に頭痛の薬を与えて帰すことだけではない。患者の話を真剣に聞いてその背景にある問題を見抜き,適切なアドバイスをすることも重要な「できること」の一つである。人生とは,人間としての存在である。目の前にいる患者は,自分の過去を背中にしょってやってきている。諸君が精いっぱい努力して患者のために尽くすことは当然として,いまからやろうとしていることがその患者の人生,単に長さだけではなく,その質まで含めてどのような影響を及ぼすかについて真剣に考え,患者に説明せよ。
おどろいたことに,近年,日本の医学教育でしばしば強調されるインフォームドコンセントという言葉は,一度もこの総論には出てこない。上記の3 原則を守っていれば,これから起こりうる悪いシナリオについても,患者やその家族に説明しておくことは当たり前であるとのことであった。現在,医療訴訟が急激に増えているが,その多くは「告知義務違反」が争われている。特にこの3 つ目の言葉は,現在でもさらに重みを増している。
また,オスラーがペンシルベニア大学を去るときに卒業生を前に話した,「平静の心(Aequanimitas)」という有名な講演の要約についてもふれてあった。
医師にとって,沈着な姿勢,これに勝る資質はありえない。諸君の中には,これまで幾度か危機に遭遇してはきたが,いまだに沈着な姿勢を身につけることができなかった方がおられるかもしれない。そういう人達のために,その重要性について述べたい。沈着な姿勢とは,状況の如何にかかわらず冷静さと心の落着きを失わないことを意味する。嵐の真っただ中での平静さ,重大な危機に直面した際に下す判断の明晰さ,何事にも動じず,感情に左右されないこと,不幸にもそのような資質を欠いた医師,すなわち優柔不断でいつもくよくよし,それを表面に出す医師,日常生じる緊急事態に狼狽し,取り乱す医師,こういう医師はたちどころに患者の信頼を失うことであろう。
これも日野原重明先生訳の日本語版でおなじみであるが,当然日本の医学教育にもその教えは取り入れられていることと思う。さらにペンシルベニア大学のシラバスでは,
平静の心とは,オスラーがしばしば強調したように患者との目線を同じレベルに合わせながら一定の距離を保つことをも意味する。
と,あった。オスラーは,患者を理解することにはあらゆる努力を惜しまなかった。まさに目線を患者のレベルに合わせることを常に実行していた。そのため回診ではベッドのわきに腰を掛け,患者と同じ目線を保っていた。本書には,死の床に臥す幼い患者ジャネットちゃんの診察においても,小さな子どもである患者のためには背中をまるめてかがんで部屋に入ってくることが書かれている。物理的な目線はもちろんのこと,心の目線まで同じにすることを教えている。
近年わが国では,患者と医師の距離を縮めることが重要視され,患者の気持ちをくみ,患者と喜怒哀楽をともにし,いかなるサービスも厭わない医師が社会的に求められる傾向にある。しかしオスラーは,最も効果的(effective)な臨床医であるためには,患者の求めに応じて何でもすることがよいとは決して言っていない。一定の距離を保てない医師が,わが国では増えているのではないか?
日本の医学教育は,この十数年大きな変革を遂げてきた。現在,日本の多くの医学部で取り入れられているチュートリアルやクリニカルクラークシップなど,形は米国のものがそのまま移入されてそれなりの効果を得ている。しかし,「クリニカルクラークシップ」ということばを最初につくったオスラーのことは,あまり教育されていない。その理由の一つは,教材があまりに少ないためではないかと感じていた。本書はカナダの文筆家・歴史家であるブリス博士による,まったく新しいオスラーの伝記である。米国の友人から勧められて読んでみたところ,とても面白くてすぐに読了してしまった。本書は膨大な資料に基づいて,ややもすると神格化されがちなオスラーが「生身の人間」として描かれている。例えば,オスラーが限られた給料で,教育・研究のほか,患者を診ることに時間をどのように振り分けるかについて悩んでいることも書かれている。私のように現在大学に勤める者にも,大変身近な等身大のオスラーがそこにいる。おそらく現在の医学生・医師の諸氏にとっても,読み物として気楽に読んでいただけるのではないかと思う。
本書を翻訳しようと考えたもう一つの理由がある。20 世紀初頭,オスラーのころの医学の置かれた状況が,21 世紀初頭の現代の医学が直面している状態と酷似しており,その抱えている問題点も共通しているためである。本書ではそれらがきわめて客観的に,また明確に述べられている。
当時は,医学そのものが経験と患者の観察だけに基づき,現代でいう科学というよりも迷信とでもいうべき先入見に満ちていた。とくに病気の治療に関しては,肺炎の治療に瀉血が勧められていたことをみてもわかるように,現代でいう科学的エビデンスに基づいた医学とは程遠い状態であった。オスラーは学生時代,顕微鏡に興味をもち,原虫を含む種々の微生物を観察することを非常に好んだが,このような科学的な探究心はそののちに医学を志すきっかけとなった。マギル大学では当初,生理学教授としてこの方面で存分に活躍している。のちに彼が内科医・病理学者としての1000例にも及ぶ解剖を行なった最大の動機は,おそらく人々を苦しめる病気は実は病める臓器にあり,その臓器をこの目で確かめようと思ったのかもしれない。そして病める臓器を徹底的に調べることによって,多くの病気が克服できると信じていた節がある。折しもコッホの細菌学など画期的な科学的な発見があり,感染症は克服できるのではないかという科学万能主義が蔓延する兆しがあった。しかし,当時は抗生物質の時代ではなく,画期的な科学的知見にもかかわらず患者は次々と死んでいった。このようなことから結局オスラーは,「治療ニヒリスト」としての評判が立つようになる。大半を占める治せない病気の患者をどうするか,という課題が持ち上がったに違いない。ペンシルベニア大学時代の同僚で神経学者でもある内科医ウィアー・ミッチェル博士らの影響をうけ,患者を看取ることの重要性に気づき,彼なりの結論を得る。その一端が,当時,不治の床についた幼い女の子ジャネットちゃんの診療の姿に表れている。すなわち「幸せな死などありえないが,少なくとも不幸でない死を迎えさせてあげることができるはずだ」と。
現代の医学は,これまでにも増して急激な変貌を遂げている。全ゲノムが解読され,次々と新しい疾患遺伝子が毎月のように発見され,遺伝子改変動物が作成され,種々の治療薬が開発されている。本来,細胞が消滅してしまう神経難病などでも,iPS 細胞を用いた神経再生治療が現実に開発されようとしてきており,それはちょうどオスラーの時代に匹敵する医学革命が進行しているように見えるのである。ヒトの病気のすべてが,各臓器において遺伝子をはじめとする分子レベルまで,すべて解明されてしまうような幻想が医学界を支配しているといっても過言ではない。
病める臓器を治せる医師が,整然としたカリキュラムに従って大量に生産されている。ところが,問題も多く残されている。私の大学では,神経内科の臨床実習に回ってくる学生には「人間とは何ですか?」という意地の悪い質問を最初にすることにしている。学生諸君は不意を突かれたようで,しばし考え込んでいるが,少し討論をしているといろいろな答えが返ってきて面白い。ところが,最近とくに「臓器の集合体」という見方に基づいた答えが返ってくることが多いのには驚かされる。いまほど人間全体を診る医師が求められている時代はないにもかかわらず,些細な医学的知識をつめこむ現在のカリキュラムのなかで,真剣に「人間とは何か?」を考える余裕がなくなってきているように感じるのは杞憂であろうか?
現代の医学は万能ではない。私の専門でいえば,脳についてはその正常の機能すらおそらく10%もわかっていない。脳の病気をすべて克服することは,未来永劫にわたって不可能であろう。いまのところ癌についてもそうである。いろいろな最先端の科学的な発見が新聞紙上をにぎわせ,常にその治療面への希望的なコメントがつけられている。しかしそのほとんどは実現されていない。アップル社のCEO であったスティーブ・ジョブスがいっていたように,人間にとって「死」とは避けがたいものであり,またそれは生命が生み出した最大の発明でもある。この本を通して,現代の医学生諸君にとって,医師として,いま一番大切なことでありながら現在の医学教育で十分に扱われていないこと,すなわち「治らない病気・死に至る病気の患者に,いかに接するか」ということが,この本に描かれたオスラーの人生の中に見いだせると確信している。
本書は偉大な医師の伝記にはとどまらない。ひろく一般の読者に読んでいただいても興味深く,さわやかな読後感を味わっていただけるものと思う。確かに,オスラーが米国の臨床医学およびその教育に与えた影響は大きい。しかし本書には,彼の業績や医学とのかかわりとは別に,子どものころからいたずら好きで茶目っ気があって,魅力的な「人間オスラー」が見事に描かれている。19 世紀のドイツを中心とする近代医学の成果を取り入れて,彼は医学者・臨床家・教育者としての世界的な成功をおさめる。また晩婚ではあったが一人息子リヴィアを得て,夫婦で溺愛するようになる。しかし,その大切な家族を近代科学の成果を取り入れて毒ガスまで用いた悲惨な第一次世界大戦で失うことになる。「平静の心」ではいられなかった様子も痛々しい。その時代を懸命に生きた「一人の人間の物語」ともいえる。
最後に,本書の出版を快諾していただいたメディカル・サイエンス・インターナショナルの若松博社長,担当の染谷繁實さん,横川浩司さん,工藤亮子さん,そして最大の功労者である翻訳者,三枝小夜子さんに深謝申し上げます。
平成24 年3 月
徳島にて
梶 龍兒
【序:オスラーを解剖する】
いまなぜオスラーなのか?
ウィリアム・オスラーは,世界の歴史上,最も偉大な医師であったと言えるか? 冗談かと思われるかもしれないが,1919 年にオックスフォードでオスラーが死去したあとにこう問いかけた人々は,大まじめだった。
それは厳しい競争だろう。オスラーの崇拝者の大半は,彼がその時代で最も有名で,最も愛され,最も大きな影響力をもつ医師だったと主張するだけで満足した。けれどもそれは,並々ならぬ称賛でもあった。オスラーと同じ時代を生きた作家,芸術家,政治家,科学者のなかで,これだけの知名度,人望,影響力を兼ね備え,誰もがそのことを認めていたような人物がいただろうか?
カナダの辺境の地に生まれたオスラーは,70 年の生涯の間に,モントリオールのマギル大学,フィラデルフィアのペンシルバニア大学,ボルティモアのジョンズ・ホプキンズ病院および同大学で診療,著述,医学教育を行い,イギリスに渡ってオックスフォード大学医学部欽定講座担当教授になってからも精力的に活動を続けた。彼は,才気あふれる革新的な教師であり,学生たち,特に,ジョンズ・ホプキンズの男女学生から深く慕われた。彼らはジョンズ・ホプキンズから北米各地へと巣立ってゆき,医学における北米優位の新時代を築くリーダーとなった。
オスラーは,文字どおり自分が興味の対象としていたことについて本を書いた。彼が1892 年に出版した『医学の原則と実践』は,近代医学の最初のすばらしい教科書だった。この教科書は市場を独占し,大ベストセラーとなり,多くの版を重ねた。それはまた,1 人の著者がすべての内臓疾患を解説する教科書としては最後のものとなった。オスラーは,教科書のほかにも数百本の研究論文を執筆し,腸チフスや梅毒のような主要な疾患から,ありとあらゆるめずらしい状態まで(その一部には彼の名前が付されている),驚くほど多様な疾患,症候群,症例について,その特徴,診断法,治療法を報告した。
オスラーは,具体的には何を発見したのだろうか? 実は,彼の発見はほとんどない。しかし,当時の医学の各分野についてフロンティアの地図を作成したら,しばしばオスラーが先駆者の一人としてそこにいるのを見いだすことになるだろう。オスラーが何を発見したかという質問が不適切なのだ。彼は,発見を職務とする実験科学者ではなく,疾患の自然経過の観察者・研究者・教師であり,現場で働く医師だったからである。彼は,医学が科学にもとづかなければならないことを理解し,基礎医学研究者による画期的な発見を称賛し,その成果を積極的に取り入れた。臨床医としては,こうした知見を利用して患者を治療しようとしたし,教師としては,学生に科学と治療術を教えた。基礎医学研究者とその発見は,患者の治療にあたる臨床医を補助し,道具を提供することはできるが,その代わりになることはできない。オスラーは教師として,アメリカに病院実習制度(医学生をベッドサイドで働かせることで医師としての仕事を学ばせる制度)をもたらすという革命も起こした。
学生や同僚が病気になったとき,彼らを診るのはたいていオスラーだった。個人診療では,詩人,政治家,王室の人々のほか,特にめずらしい症状を示す一般人も診た。医師としても友人としても,彼はカリスマ的な性格の持ち主だった。友人は数えきれないほど多く,彼らが彼に捧げる賛辞は,存命中はもちろん,その死から何十年たっても途切れることがなかった。オスラーは,アメリカとイギリスの両方に最高の患者と友人をもち,自分がカナダ出身であることを決して忘れなかった。誰もがオスラーを知っていて,ほぼ全員が彼を愛していた。弟子のうち数人は,文字通り彼を崇拝した。
オスラーは単なる医師ではなく,文学に通じ,人々にインスピレーションを与える,科学のヒューマニストだった。医師の生き方や過去・現在・未来に関する彼のエッセイや講演は広く読まれ,高く評価された。そこには,科学と文学の知識と,理想主義と,慌ただしい日常を送る人々のための分別ある助言があった。オスラーは,その著作においても私生活においても,さらには,第一次世界大戦という悲劇を通してみたときにさえ,人間の生き方の見本だった。ある友人は,人生についてまじめに考える人ならだれでも,オスラーの物話に興味を感じるだろうと言った。オスラーの同僚で,同じく医学界の大御所の一人だったウィリアム・ウェルチは,オスラーの経歴は,その性格と状況の見事な一致であり,彼は,「その才能と気質を,人生に降りかかった事件や状況に,ほぼ完璧に適応させた」と言っている1。
本書の最終章で見ていくように,オスラーの生前に彼を偶像視していた人々は,彼が不滅のロールモデルとして後世の人々にインスピレーションを与え続けるように手を尽くした。偉大な神経外科医のハーヴェイ・クッシングは,1400 ページからなる2 分冊の公式伝記『サー・ウィリアム・オスラーの生涯』を執筆して,今日も続くオスラーの神話化に中心的な役割を果たした。この伝記は,1925 年の出版から70 年以上の間,権威あるテキストとして尊重され,オスラー自身の見事な歴史的エッセイに次ぐ重要性を認められてきた。『サー・ウィリアム・オスラーの生涯』自体も傑作とされ,アメリカではピューリッツァー賞を受賞した。オスラーの生涯のガイドとして,クッシングに取って代わろうとする者などいるだろうか? そんな大仕事に挑戦したがる者などいるだろうか?
後世の神経外科医たちは,クッシングの手術手技をどんどん改良していった。クッシングの存命中でさえ,彼が書いた伝記は,冗長で反復が多く,オスラーの信奉者でない人々にはとっつきにくく,最後まで読むのはほとんど不可能だと考えられていた。それはまるで聖人伝のようで,伝記としてはあまりにも無批判だった。さらに,オスラーの生涯と当時の医学界について研究する歴史家が発する問いの多くに答えていないため,しだいに顧みられなくなっていった。
新しい一次資料の発見は,クッシングの本をさらに時代遅れのものにした。オスラーに関する新しい文献の数も増えた。そうした文献のなかには高水準の研究にもとづく客観的なものもあり,少数の著者は,医学界の偶像の修正にのりだした。ウィリアム・オスラーの医学へのアプローチは,長期的に見て妥当なものだったのだろうか? 彼のカリスマ性は本物だったのか,それとも虚構だったのか? 歴史的人物の多くがそうであったように,彼もまた同時代の人々と同じ人種差別や性差別をしていたのではないだろうか? 彼の評判は大げさすぎるのではないか? ヒポクラテスに喩えるのは持ち上げすぎなのではないか? 彼は偽善者で,聖人めいたイメージとは正反対の私生活を営んでいたのではないか?
1980 年代になると,クッシングによる伝記を読もうとする人や,オスラーについて考察しようとする人は皆,新しい伝記の必要性を痛感するようになった2。
私がオスラーの生涯に興味をもったのは,医学史に真剣に取り組むようになり,1982 年に『インスリンの発見』(朝日新聞社 堀田饒 訳)を,1984 年に『バンティング:伝記』を上梓した頃のことだった。カナダ生まれの私が,インスリンとバンティングからオスラーにたどり着くのは当然とも言えた。けれどもすぐに,オスラーの生涯が,業績においても,活動範囲の広さにおいても,その複雑さにおいても,そしておそらく変わることのない重要性においても,ほかのカナダ人をはるかに凌駕していることが明らかになった。医師だけでなく,どんな分野の人と比べてもそうだった。オスラーの新しい伝記の執筆が心身を消耗させる大仕事になることも明らかだった。資料の量は膨大で,3 か国の文書館に散らばっていた。また,医師としてのオスラーの仕事の多くは,技術的に理解するのも,文脈の中で説明するのも困難だ。私は医師ではないので,その困難は2 倍になると言ってよい。オスラーに迫ろうとする者の前には,こまごました事実と著者の直接的な知識がぎっしりと詰め込まれたクッシングの伝記が,うっそうとしたジャングルのように立ちはだかっていた。この危険で厄介なジャングルに分け入ったあげく,オスラーの世界が医学の密林以外の何物でもなく,専門家とその助手以外の人間は通さないことが明らかになったとしたら,どうすればよいのだろうか? 私は出版社から,科学者の伝記に興味をもつ人は少なく,医師の伝記に興味をもつ人はもっと少ないと言われていた。私はすっかり恐れをなし,もっと扱いやすそうなテーマと,親しみやすい領域に向かった。
私はそれから本を3 冊執筆した。そのうちの1 冊は,オスラーの時代にモントリオールで流行した痘瘡についての研究だった。私は再びオスラーのことを考えはじめた。ノートパソコンのすばらしい性能のおかげで,その頃の私は,大量の資料を扱うコツがわかってきていた。また,医学関係の書き物に伴う困難のいくつかも解決できるようになっていた。なによりも私は,オスラーにすっかり親しみ,彼の医師としての人生の豊かさと,彼の夢の大きさに興奮していた。彼の人生と仕事について本を書くことは,人間が置かれている状態を振り返り,生と死の意味を考え,救済を探し求め,不死の形を考えることなのだと,私は理解した。
オスラーの生涯の新しい物語は,興味深く,これまで知られていなかった側面を明らかにするものになるはずだ。そうと決まったら,彼がどんな人間に見えるかは,私にとって重要ではなくなった。私が書いたサー・フレデリック・バンティングの伝記も,インスリンの共同発見者として知られるカナダの偶像を,凡庸な科学者,無作法者,狂信的な愛国主義者として率直に描き出すものだった。実際,バンティングは,ときどき,ろくでなしとしか思えないようなことをしていたからだ。私をなによりも喜ばせたのは,バンティングを愛する人々と,彼を軽蔑する人々の両方が,この本が公正であると称賛してくれたことだった。歴史学者は,常に客観的であるように心がけなければならない。
本書は,私がもっているすべての手段を使って,可能なかぎり公正かつ客観的に描いたオスラーの肖像画である。資料の山に埋もれ,偶像がいくらか破壊されるかもしれないと思っていた私は,オスラーのイメージの強固さに深く打たれた。私は当初,オスラー崇拝は,少数の人々による表面的で利己的な宣伝行為かもしれないと思っていたが,調査を進めていくうちに,多くの人々が,心から彼を慕っていることがわかった。オスラーは,同僚との比較によって,相対的に輝いていたようなところがある。けれども私は,彼なら,どんな集団の中にいても目立ったにちがいないと確信した。実際,そうだった。例外は,彼がときどき遊び相手の子どもを探して集団から抜け出してしまったことだった。オスラーの人柄の美しさを語る数々の逸話のなかでなによりも説得力があったのは,彼が幼児にかけた魔法だった。それは,風変わりで愛情あふれる多くのメモ書きや,彼についての多くの逸話や回想のなかでひときわ輝いていて,ここではとうてい語り尽くすことができない。オスラーは,子どもに対してルイス・キャロル的な感情(ただし,奇癖は除く)をもっていた。
オスラーの手には,一時期,結核菌による小さな結節があった。これは「死体いぼ」と呼ばれるもので,死体を使って研究をしていたときにできたものだった。彼は,病理学者として死体を解剖し,その死因を調べることで,医師としての腕を磨いた。すべての伝記には,ジョイス・キャロル・オーツが「パソグラフィー(病苦などを強調した伝記)」と命名した側面がなければならない。そして,歴史学者を病理学者に喩え,文書館を死体仮置場に喩えることは,しばしば妥当である。驚いたことに,オスラーの「剖検」を行った私は,特に重要ないぼや病的な状態を新たに見いだすことができなかった。彼の生涯は立派すぎて,顕微鏡を使って批判的な解剖を行っても,注目に値する問題は見つからなかった。伝記作者が,その人物の隠れた内障を発見したと主張することで名声を獲得するこの時代に,今回のプロジェクトは,きわめて異例の知的剖検(伝記作者にとっては悪夢とさえ言えるもの)になった。私は,どんなに努力しても,オスラーの評判に傷をつけられるような新事実を見つけることができなかった。彼は,気高く,堂々と,有意義で,聖人めいた人生を送った。基本的に,私はオスラー像を修正することができなかった。うわさの形で伝えられてきた,いかにもヴィクトリア時代的なセックス・スキャンダルも,ねつ造であったようだ。
とはいえ,オスラーの友人や,彼が所属していた組織や,医学界については,多くの点で,従来の見解を修正する新しい見解を提案することができた。オスラーに関する資料も,彼の生涯も,私が事前に予想していたよりはるかに充実していたからである。本書の執筆時期に,医学史研究そのものが爆発的に発展し,驚異的な成果をあげたことも大きく影響している。私は本書を,医療従事者に限らず,一般的な知識のある読者ならすべてのパラグラフを理解できるように書いたつもりだ。高校生から分子生物学者まで,もちろん,日々の仕事に疲れた開業医や自伝の愛好家にも読んでもらいたい。クッシングによる伝記は2 分冊だったが,私は当初から1 冊の本でオスラーの生涯を語ろうと決めていた。今日では,脳外科手術さえ,クッシングの時代ほど時間がかからないからである。
ウィリアム・オスラーの生涯は,彼が生きた時代の医学と文化を印象的に照らし出す。私は,それがわれわれの時代をも照らし出すことを期待している。本書は,近代医学の始まり,医師の教育,医師と患者との関係,医学思想における局所観と全体観,ロールモデル,フェミニズム,ヒューマニズム,自然科学と人文科学,ヴィクトリア時代の道徳,アメリカの勃興,北大西洋を取り囲むイギリス,カナダ,アメリカの文化,第一次世界大戦,キリスト教の凋落,加齢に伴う心身の衰え,医療という宗教,英国国教会気質,およびその他の多くの問題を取り上げる。しかし,どんな伝記も,その人物の生涯を再構成することを核としなければならず,その試みは,知的病理学や社会科学を超えるものだ。ウィリアム・オスラーの患者であったウォルト・ホイットマンは,詩人は「棺から死者を引きずり出して,再びその足で立たせる……彼は過去に,『起きて,私の前を歩きなさい。私があなたを感じられるように』と言う」と書いた3。私は,ホイットマンに倣いたい。オスラーも,このイメージを認めてくれるはずである。
582 ページにて,本書の執筆にあたりお世話になった人々への謝辞を述べる。
1998 年9 月
プリンス・エドワード島スプリングフィールドにて
マイケル・ブリス
-
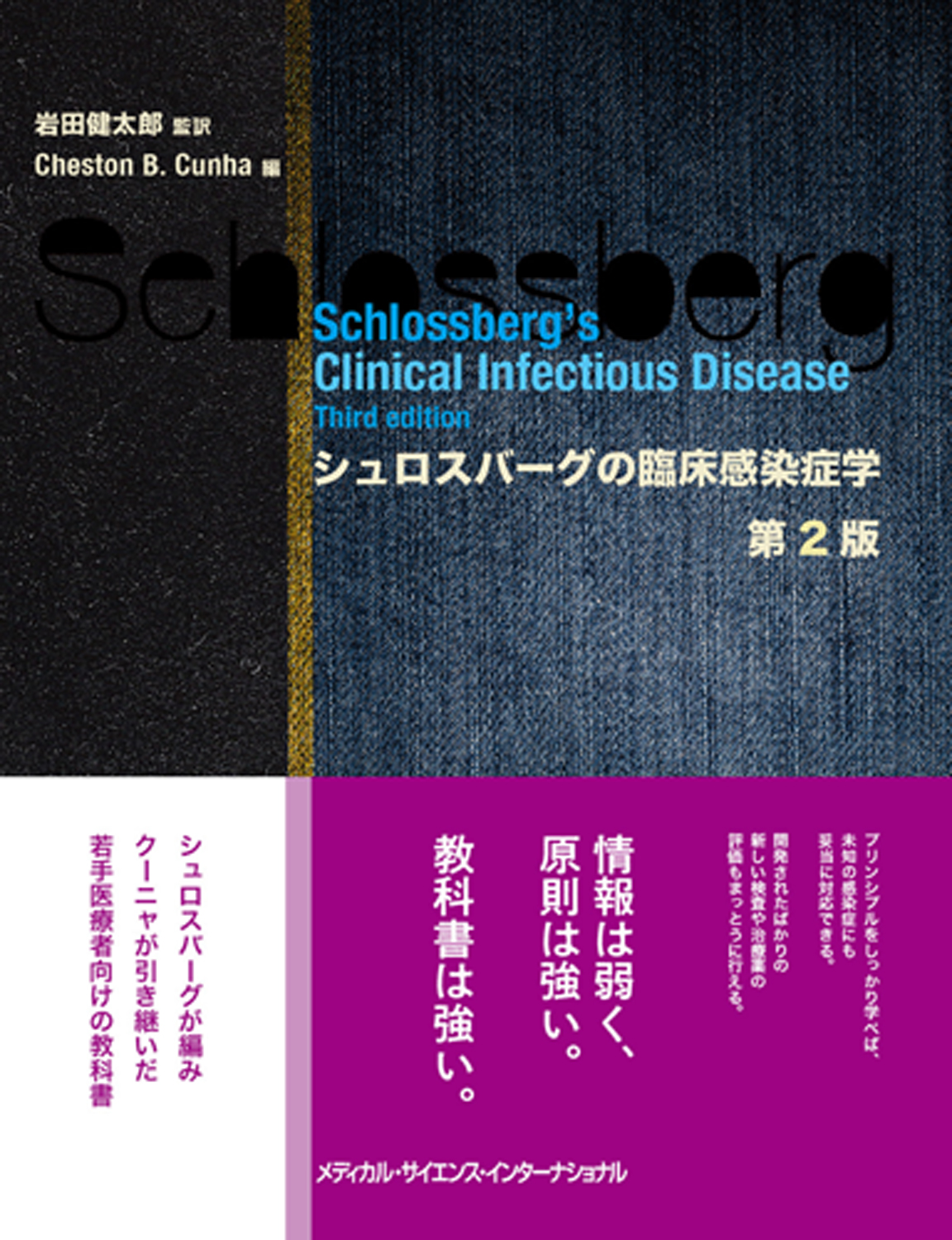
- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版
- ¥25,850
-

- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版
- ¥12,100
-

- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande
- ¥4,180
-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版
- ¥8,250
-

- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版
- ¥3,960
-

- 循環器のトビラ
- ¥5,940
-
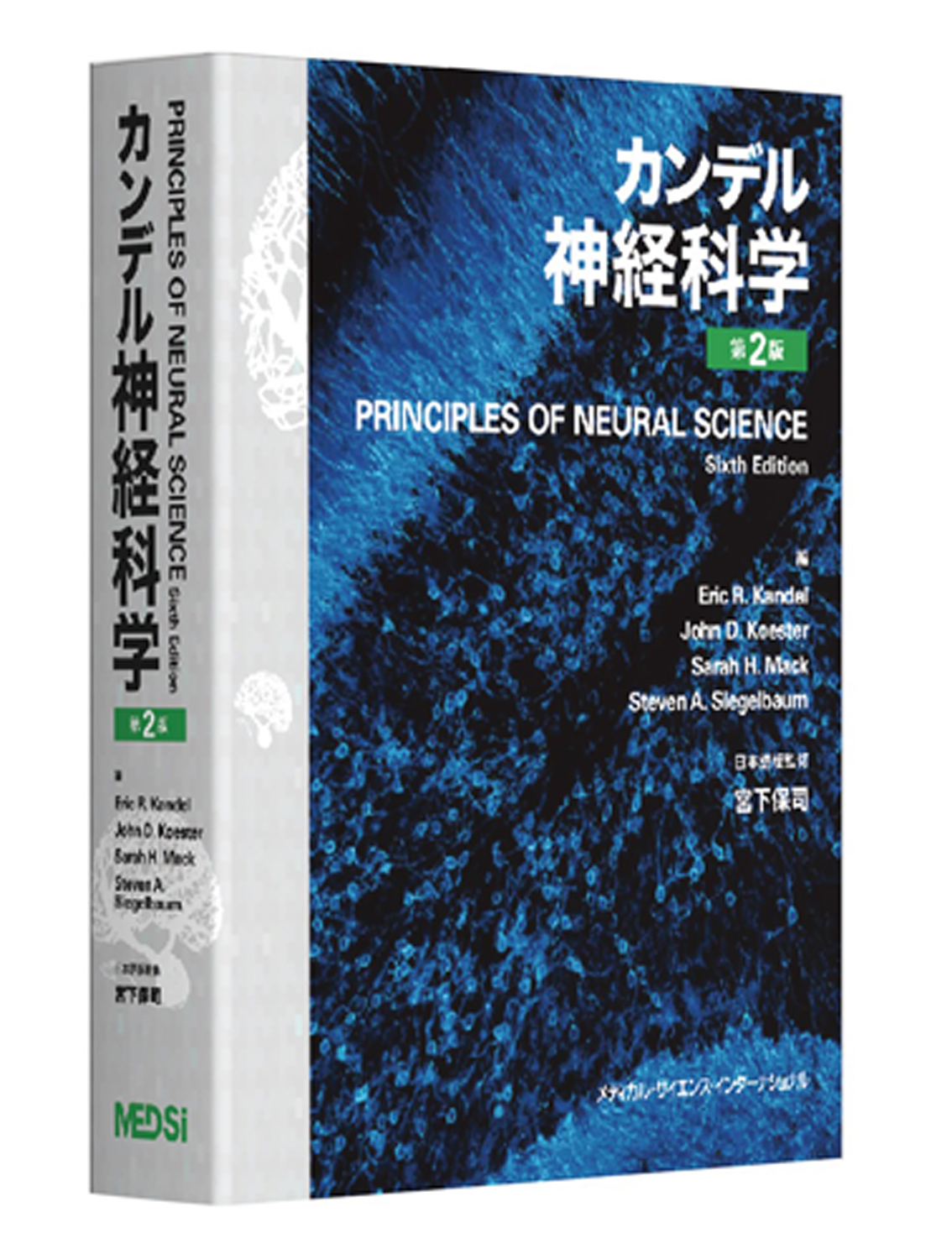
- カンデル神経科学 第2版
- ¥15,950
-
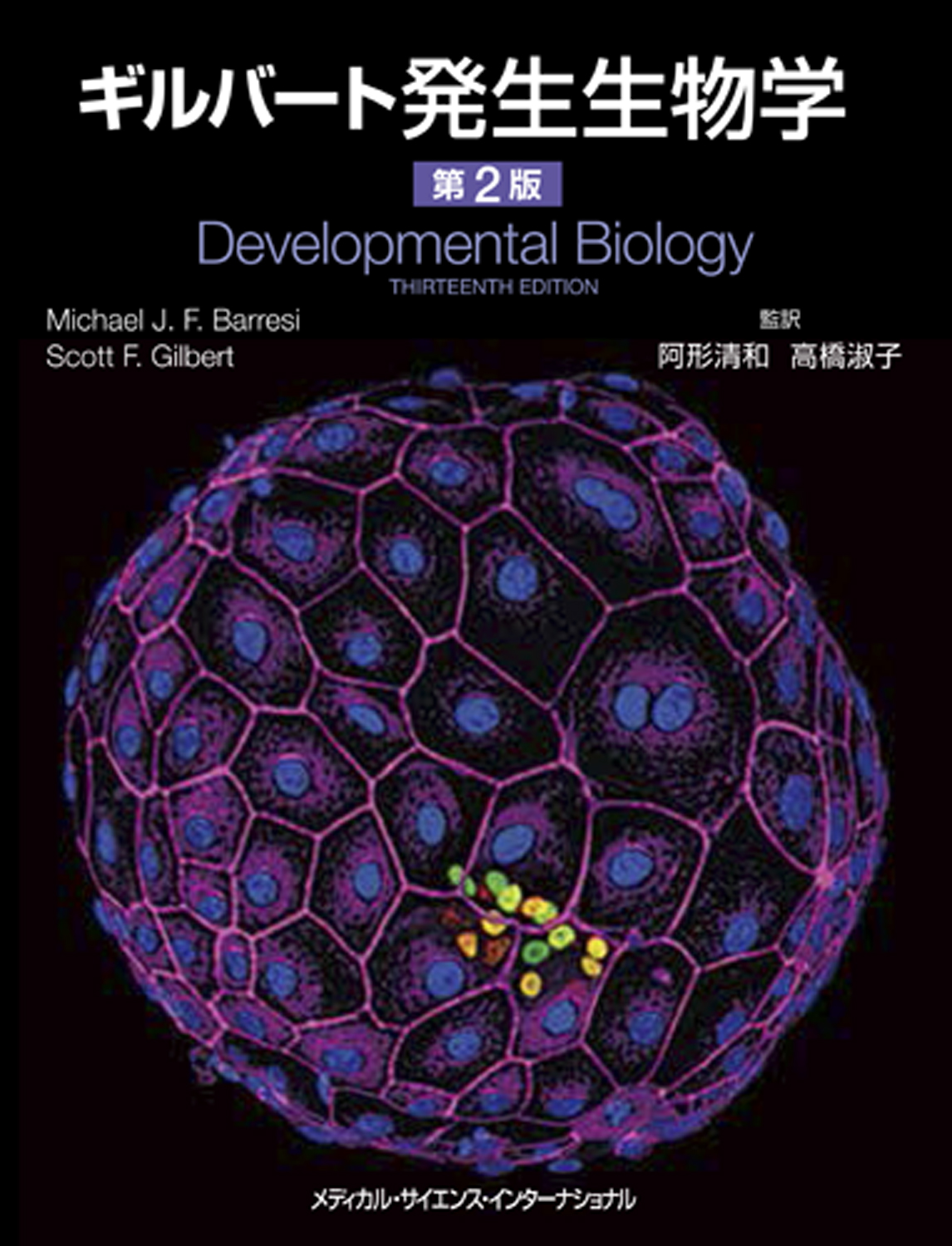
- ギルバート発生生物学 第2版
- ¥13,750
-

- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版
- ¥12,100
-

- 医学的研究のデザイン 第5版
- ¥6,270
-
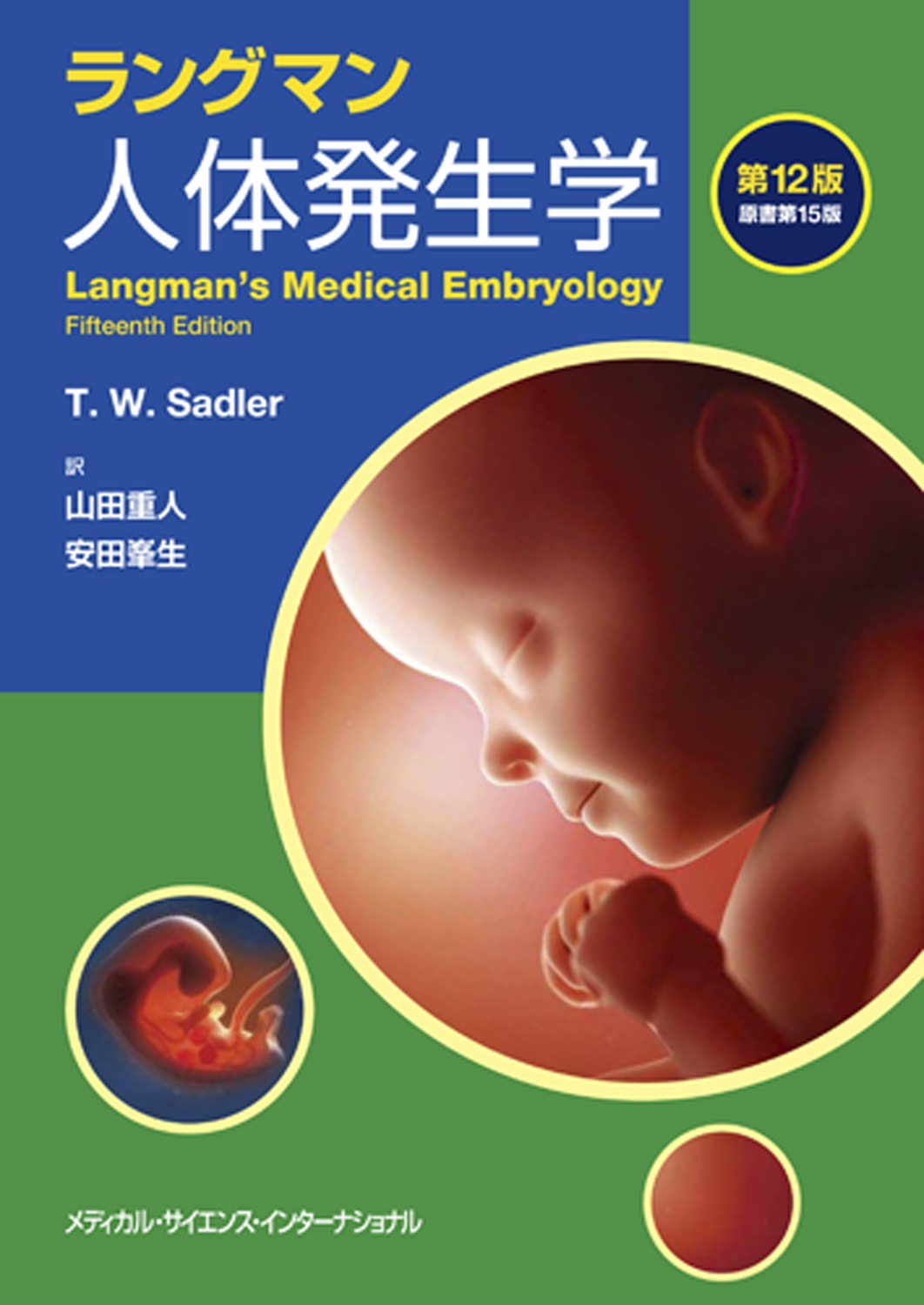
- ラングマン人体発生学 第12版
- ¥9,350
-
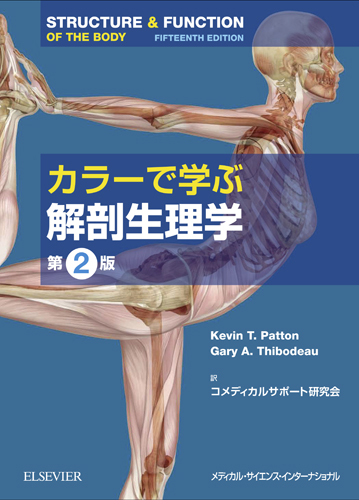
- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版
- ¥6,160
-
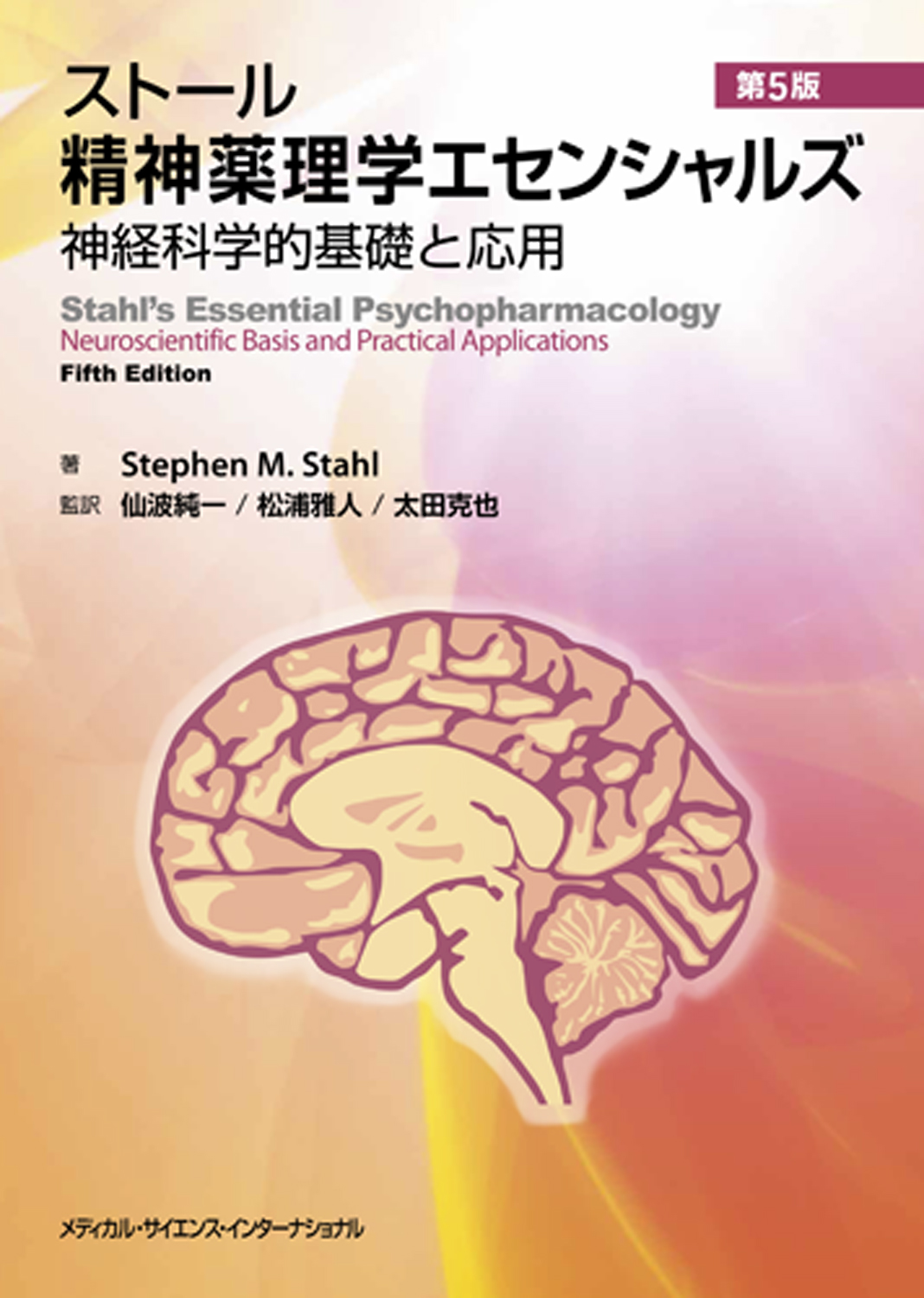
- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版
- ¥13,750
-

- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-

- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-

- エッセンシャル免疫学 第4版
- ¥7,150
-

- 臨床のための解剖学 第3版
- ¥15,950
-
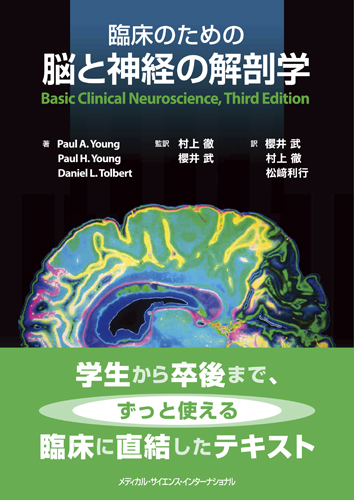
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-

- MRIの基本パワーテキスト 第4版
- ¥7,150
-
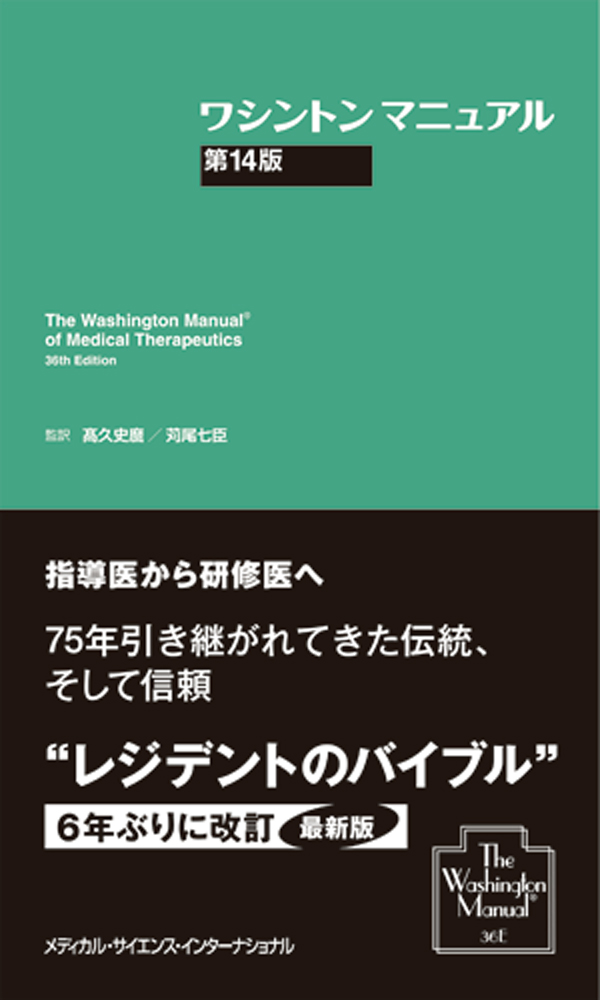
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-

- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-

- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-

- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
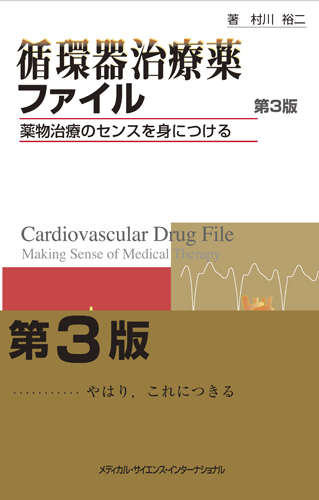
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-

- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
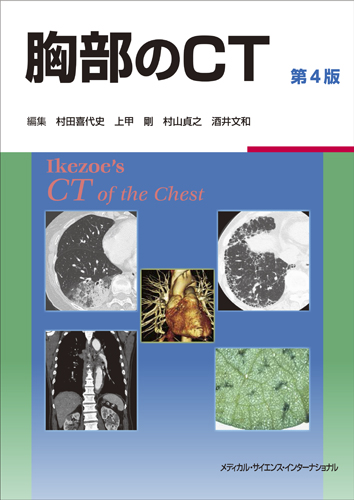
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
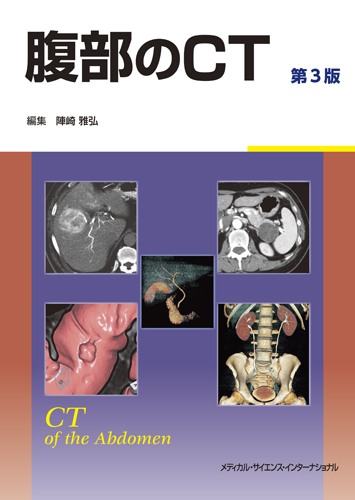
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
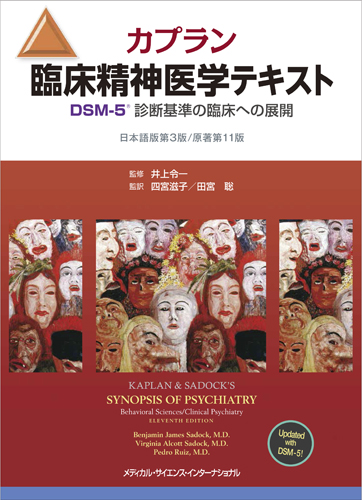
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000