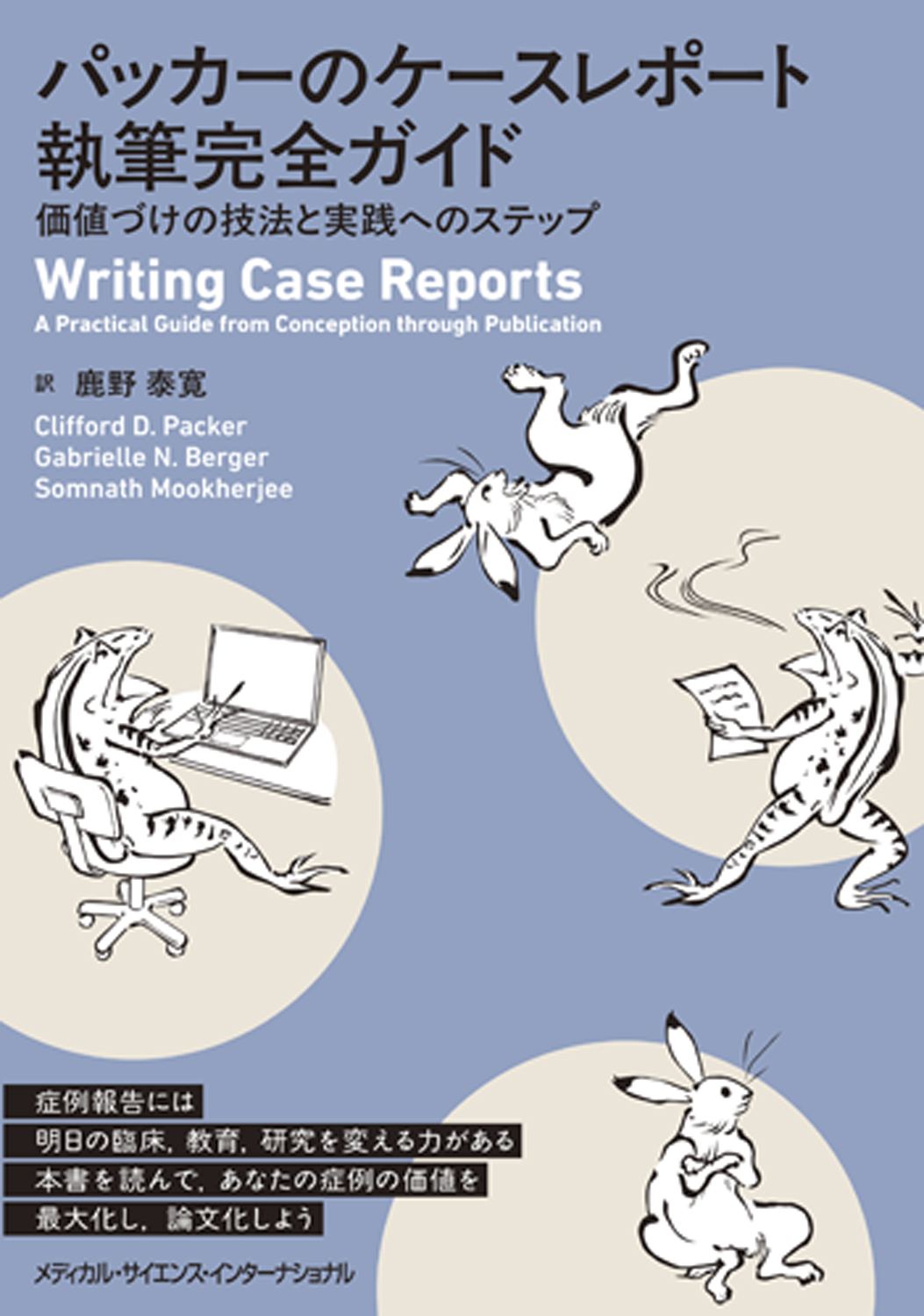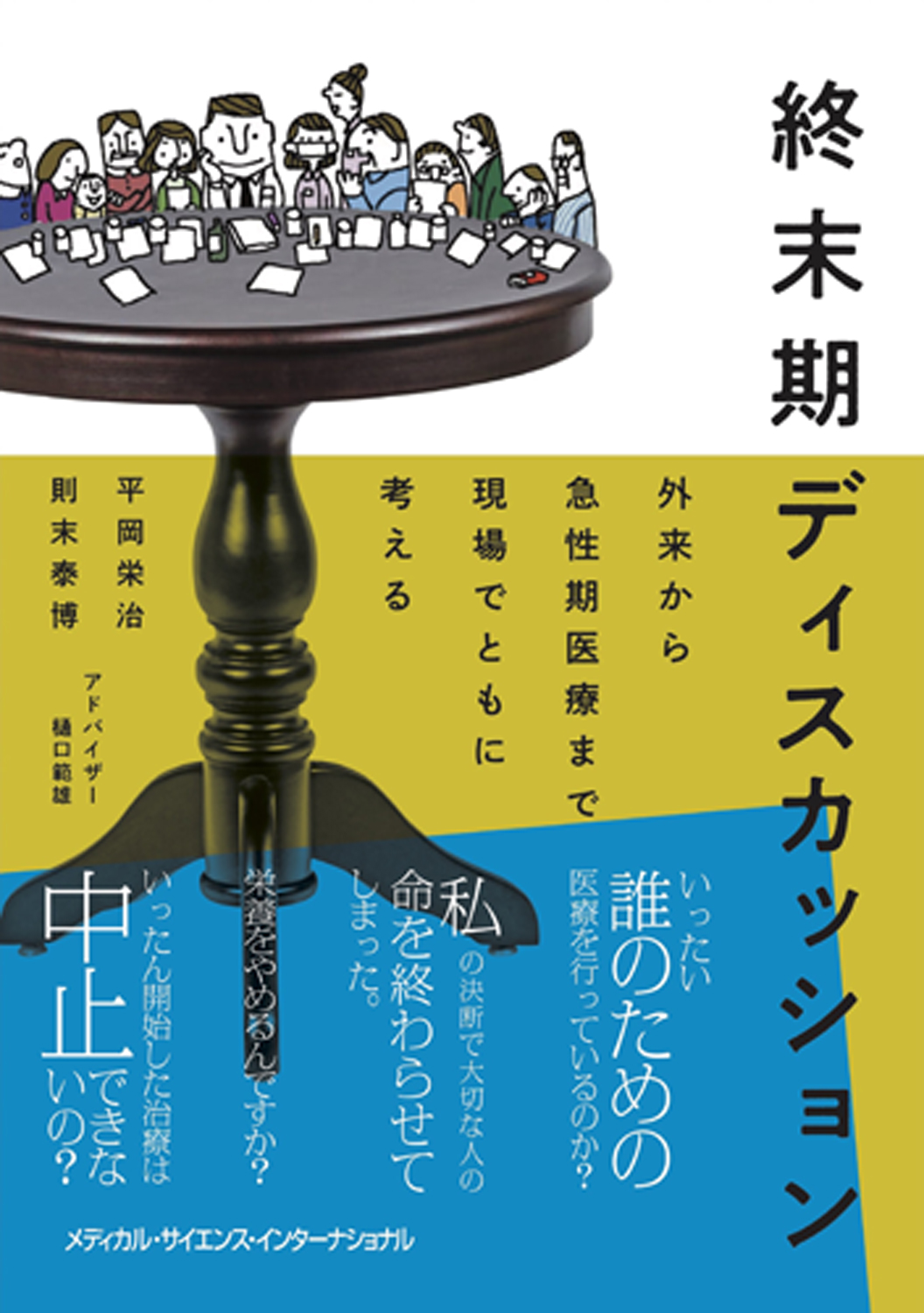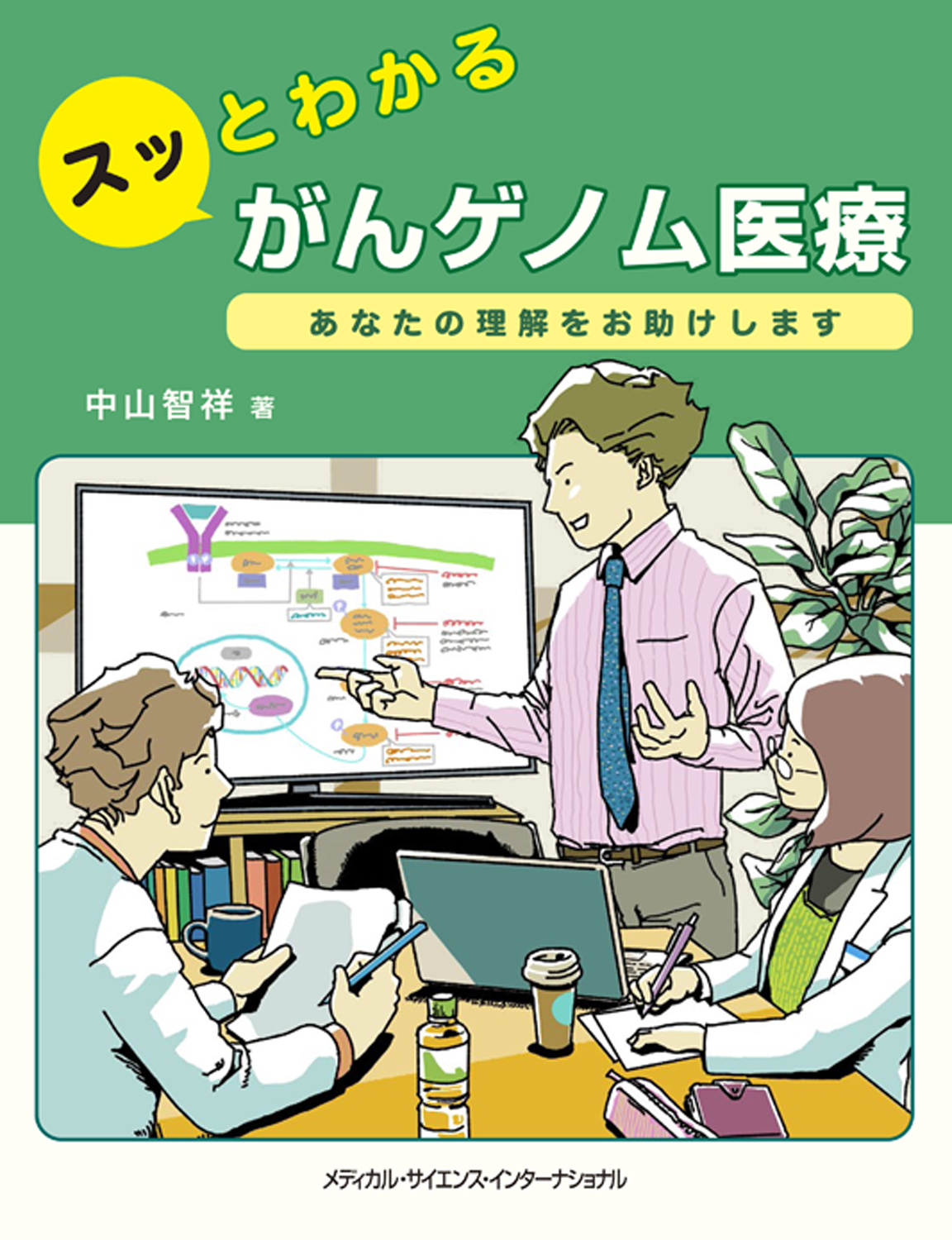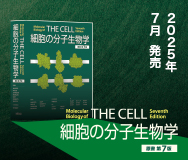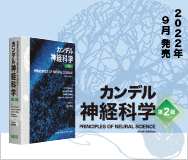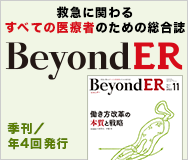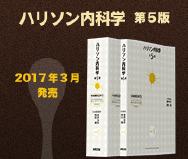パッカーのケースレポート執筆完全ガイド - 価値づけの技法と実践へのステップ -
症例報告には
明日の臨床、教育、研究を変える力がある
本書を読んで、あなたの症例の価値を
最大化し、論文化しよう
単なるケースレポート(症例報告)論文の書き方指南書にとどまらない、症例選びから掲載・出版後までを視野に入れたガイドブック。症例報告の各タイプを初めて体系的に整理し、経験則だけでなくエビデンスに裏打ちされた、本質を突く実践的アドバイスを提供。また、症例報告がもつ“価値”と“実益”をわかりやすく整理・言語化し、症例報告の歴史についても解説。このように指導者層・学習者層それぞれに役立つ情報が盛り込まれている。症例報告論文作成を指導する医師、症例報告論文のアクセプトや掲載を目指す若手医師に最適。
1. 序章
症例報告を書くということ
ビブラートを失ったバイオリニスト
症例報告のエビデンスとしての価値:「実際に何が起こったのか」
症例報告の影響力
21世紀における症例報告の形と機能
2. 症例報告の歴史
古代および中世における症例報告
近代的な症例報告の起源
症例報告の隆盛,衰退,そして(電子的)復活
3. 症例報告の教育的価値
症例報告を読むことの教育的メリット
医学生と研修医にとっての症例報告執筆の教育的メリット
臨床医にとっての症例報告執筆の教育的メリット
4. 症例報告の実益
医学文献としての貢献
ガイドラインの必要性
患者ケアへの貢献
キャリアアップ
5. 私の症例は論文化に値するか?
“良い症例”の条件とは?
あなたの症例を評価するプロセス
6. まず何から始めるべきか?
1. 同意を取得する
2. 画像やデータは早めに集める
3. チームを編成する
4. とにかく何か書こう!
7. トラディショナルな症例報告の書き方
タイトル
抄録(Abstract)
導入(Introduction)
症例記述
タイムライン
考察(Discussion)
1. 症例の文脈
2. 事象の説明:仮説の構築
3. 推論:示唆をさらに広げる
4. 教育的ポイント(Teaching point)
CAREガイドラインとチェックリスト
8. 特殊なタイプの症例報告
薬物有害反応の症例報告
N-of-1試験
症例シリーズ
臨床画像論文
“臨床クイズ”論文や“謎解き画像”論文
9. 臨床ビネット抄録の書き方
1. まずは症例(ストーリー)を語れ! その後,20のTipsに従ってブラッシュアップせよ
2. 良い学習目標を示せ
3. 焦点を絞った考察(Discussion)を書け
10. 問題解決型の症例報告の書き方
症例の選択
計画段階
症例プロトコルの構成
症例ディスカッションの構成
論文原稿の執筆
臨床推論に特に重点を置いたジャーナル
最終ステップ
オーサーシップについての原則
11. 症例報告の原稿を投稿する
読者ターゲットを定める
ジャーナルとフォーマットの選択
ハゲタカ出版社
症例報告の原稿を投稿する
12. ジャーナル側の視点
投稿前チェックリスト
査読への対応
13. 論文が掲載された!
15分間の名声
査読の機会
論説の執筆機会
論文のインデックス化
出版アナリティクスとソーシャルメディア
14. 症例報告の未来
訳者まえがき
原著者と同じく,訳者である私も症例報告の重要性を確信している医師の一人である。図らずも,原著者と同じ動機を抱いて症例報告の本を書こうと考えていた私は,当初,参考資料の一つにするつもりで本書を手にとった。軽い気持ちで読み始めてみると,私がぼんやりと考え,表現したいと思っていた症例報告のアートとサイエンスが,明快に言語化されているのに驚いた。さらに本書には,ハウツー本を超えた,原著者らの症例報告への敬愛と信念,高い見識と内容の深み,広がりがあった。私がまずなすべきことは,本書の翻訳だと直感した。
本書を訳出する過程では,何度も胸の奥に炎が燃え上がり,膝を叩いて思わず椅子から立ち上がりたくなる,そんな気持ちに襲われた。そのせいで感情がほとばしり,つい興が乗って筆が走り,担当編集者から「お願いしたのは翻訳(translation)であって,超訳(transformation)ではありませんよ!」とたしなめられることもあった。いったんは「心に原著者Packer 先生を宿して作業しているのだから,超訳でもいいんです」などとうそぶいてはみたものの,そこは冷静になって,担当者のきめ細かく丁寧な校正作業に従い,原文から外れないよう修正した。ただし,そのまま訳したのでは原著者の意図を理解しづらい箇所は,その旨断ったうえで,意をとって補足したり,訳注を付した。
原著の発刊は2017年だが,本書の内容には時代を越える価値がある。本質を突く数々の助言は明らかに一線を画するもので,現在においてもまったく古びていない。ただ,細部の更新すべき内容や文献に関しては,翻訳の過程で可能なかぎりアップデートしている。翻訳に着手する前は,生成AIがこれほど普及した世の中で,生身の人間が訳すことの意味は何か,という私なりの自問も抱えていたが,作業を進めるなかで徐々に,人が訳すからこそ血の通った言葉となり,伝えられる熱量があるのではないか,また日本の実情に合わせた私なりの補足や更新記載も,皆さんの役に立つのではないかと感じている。
実を言えば,これまで複数の医学書出版社にこの翻訳の素稿を持ち込んではそのたびに断られていた。主な理由は「症例報告本や翻訳本は採算が見込みづらい」というものだった。ほとんど諦めかけていたときに,ありがたいことにこの本の内容に目を留めてくれる人がいた。アクセプトされるまで諦めないのは症例報告と同じだ。そして,商業的な観点で不遇をかこっているのも症例報告と同じだ(原著論文や総説論文に比べれば,症例報告は引用頻度が少ないのでアクセプトされにくい面がある)。しかし,症例報告の真価はそんなところにはないことを,本書を読めば十分に理解していただけるはずである。本書の価値に共感し,企画を採用してくれた株式会社メディカル・サイエンス・インターナショナルと担当編集者 神田奨 氏にはこの場を借りて改めて感謝したい。
いま私は,Packer先生と同じ気持ちだ。たとえ少数であっても,本書の助けを借りて,誰かが首尾よく症例報告を発表できたならば,この本を世に出す価値はあったと思う。
2025年9月3日
鹿野 泰寛 識
-
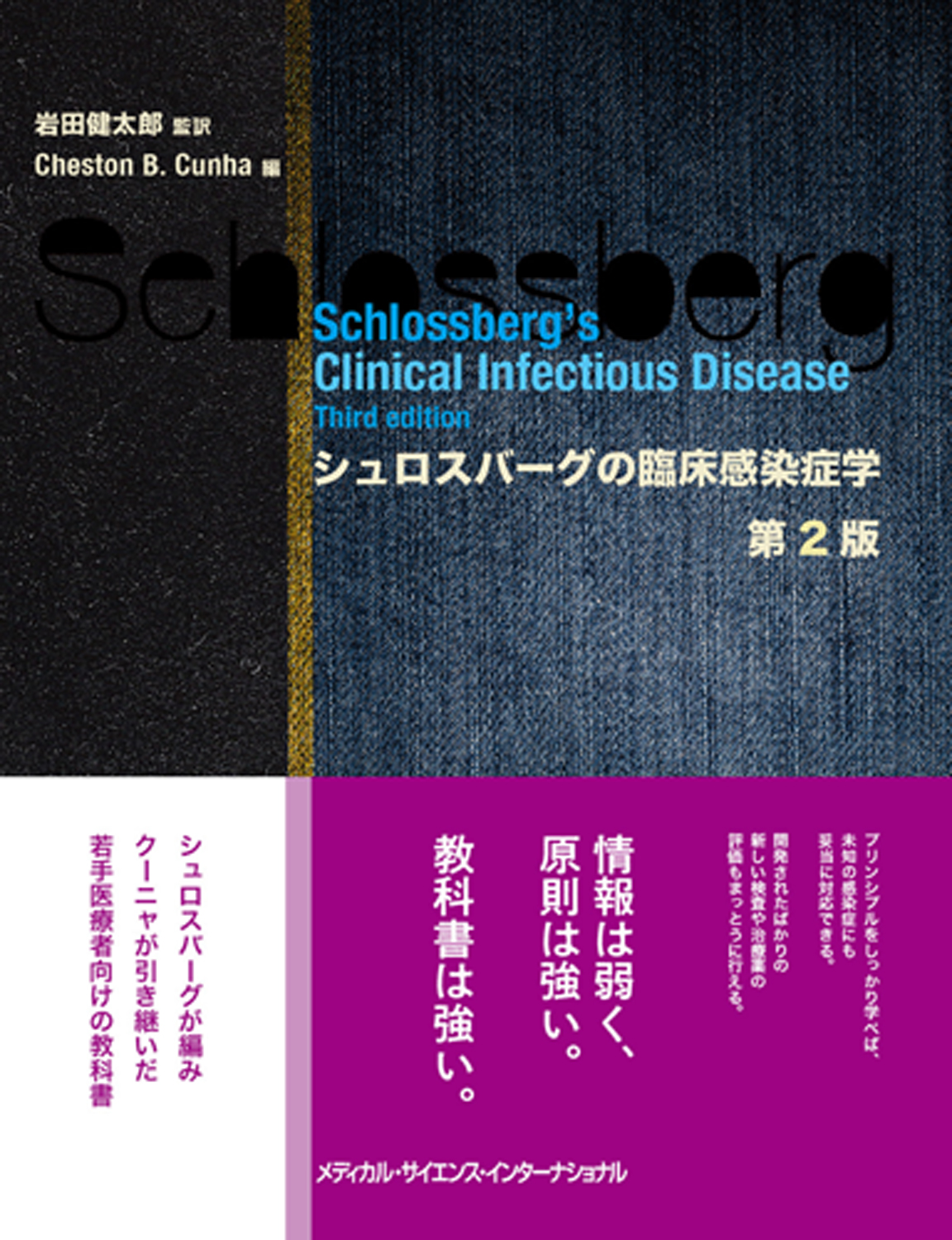
- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版
- ¥25,850
-
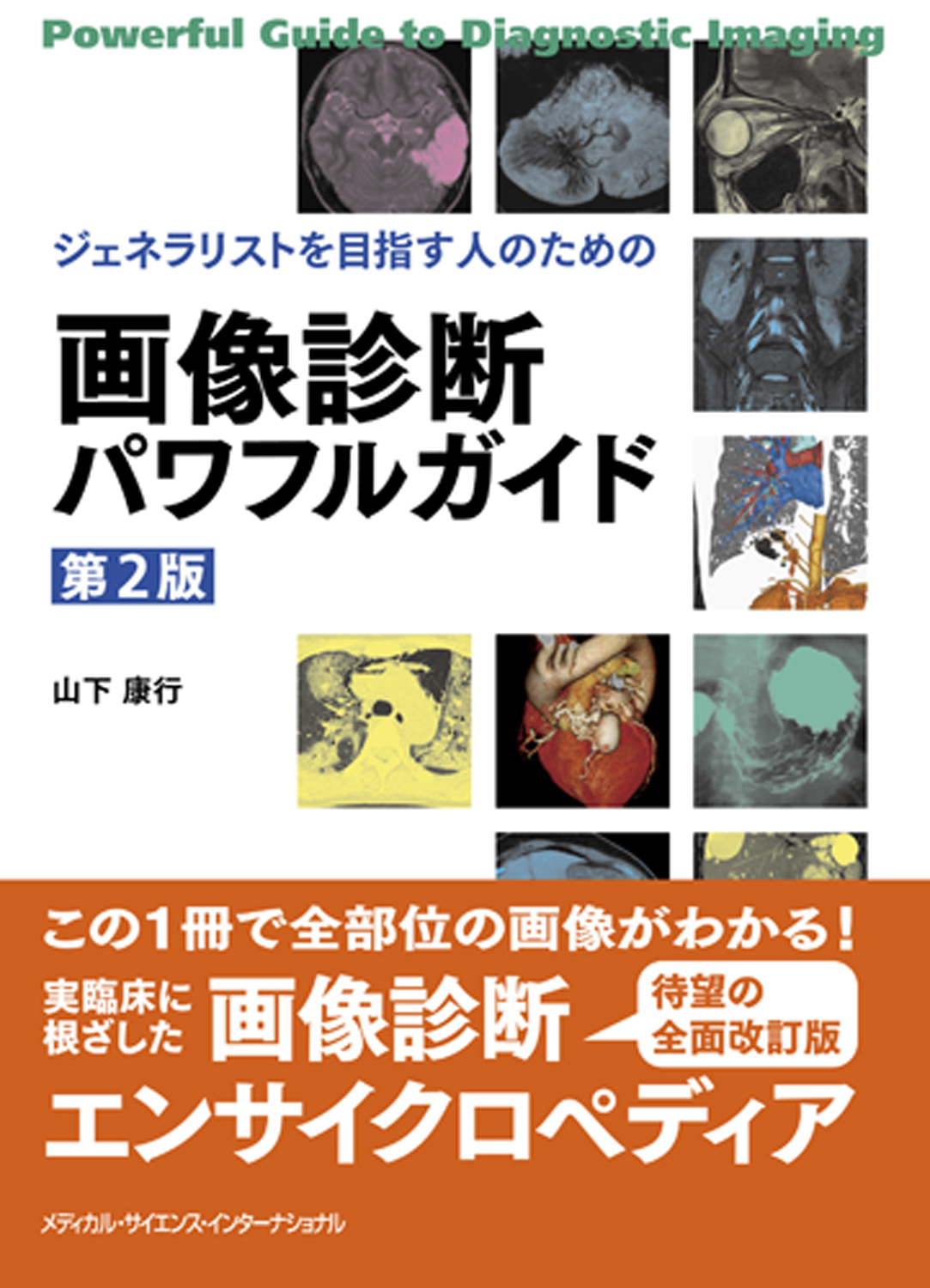
- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版
- ¥12,100
-
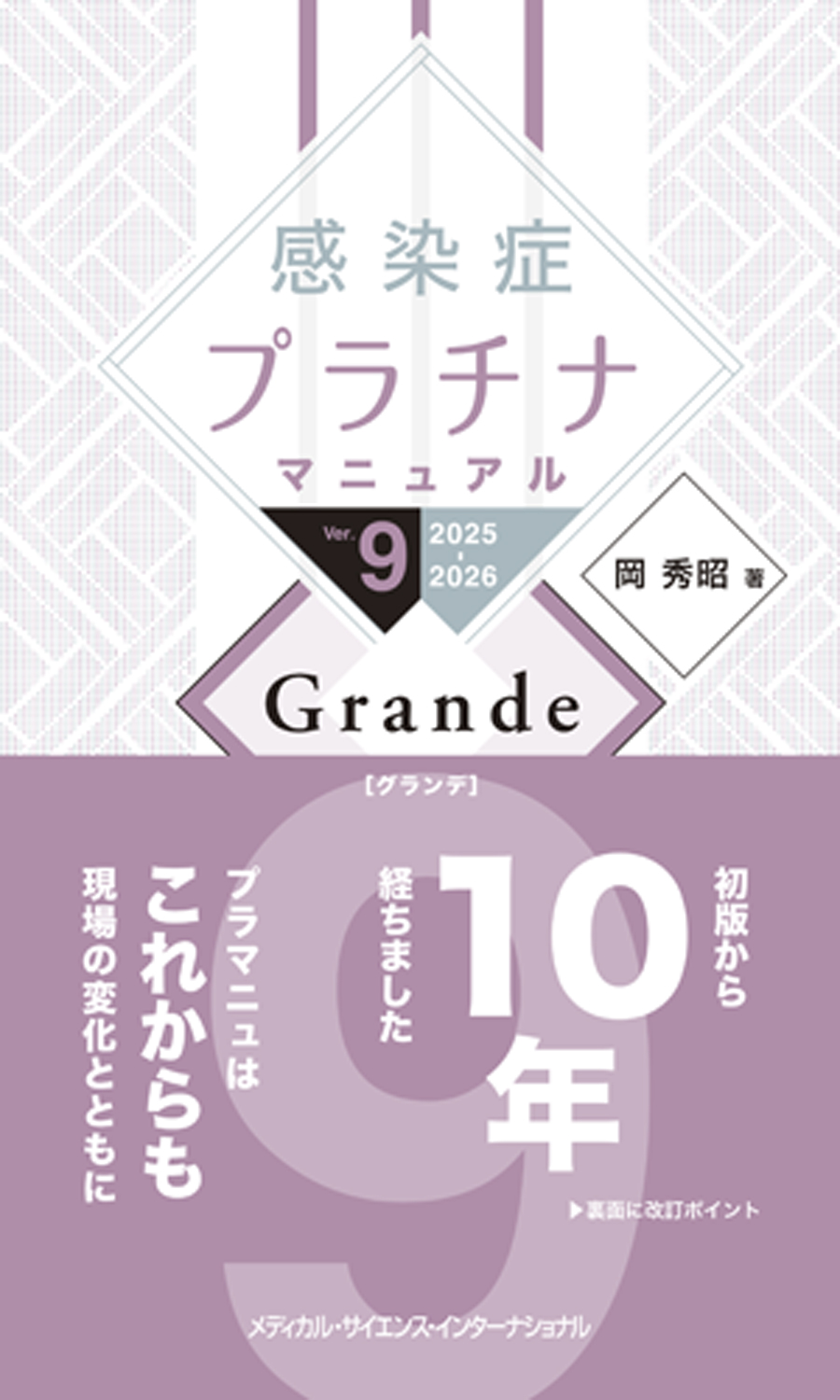
- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande
- ¥4,180
-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版
- ¥8,250
-
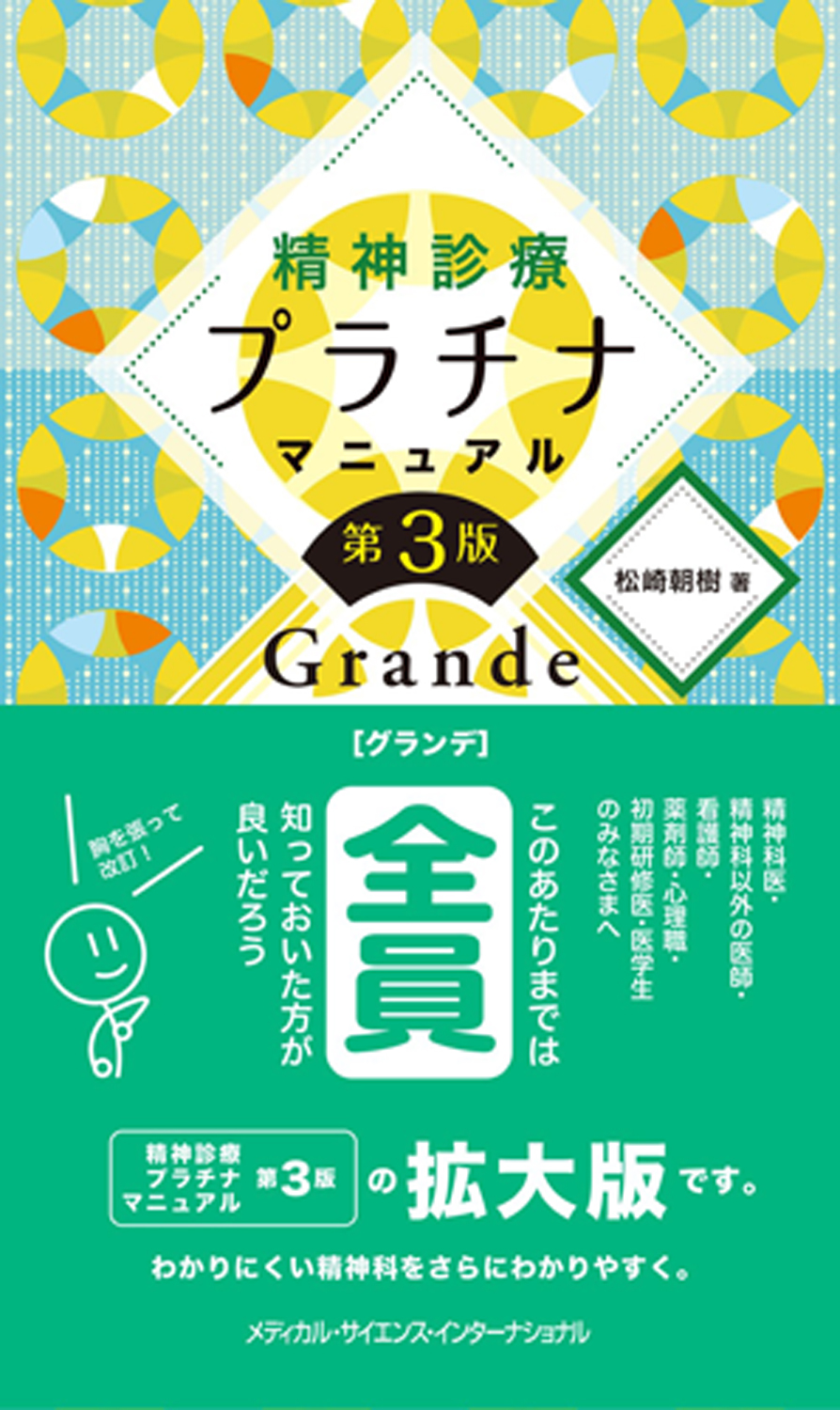
- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版
- ¥3,960
-
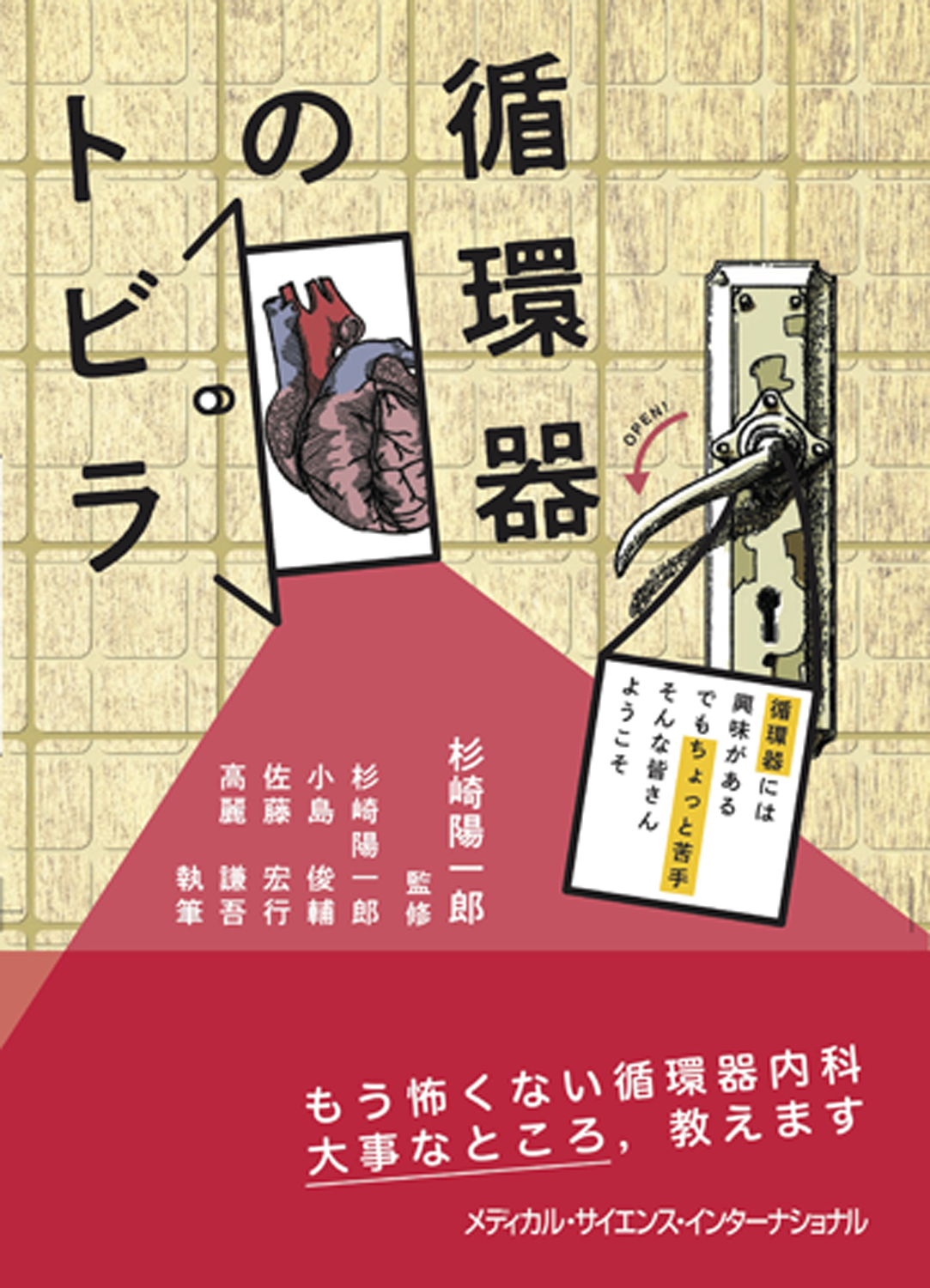
- 循環器のトビラ
- ¥5,940
-
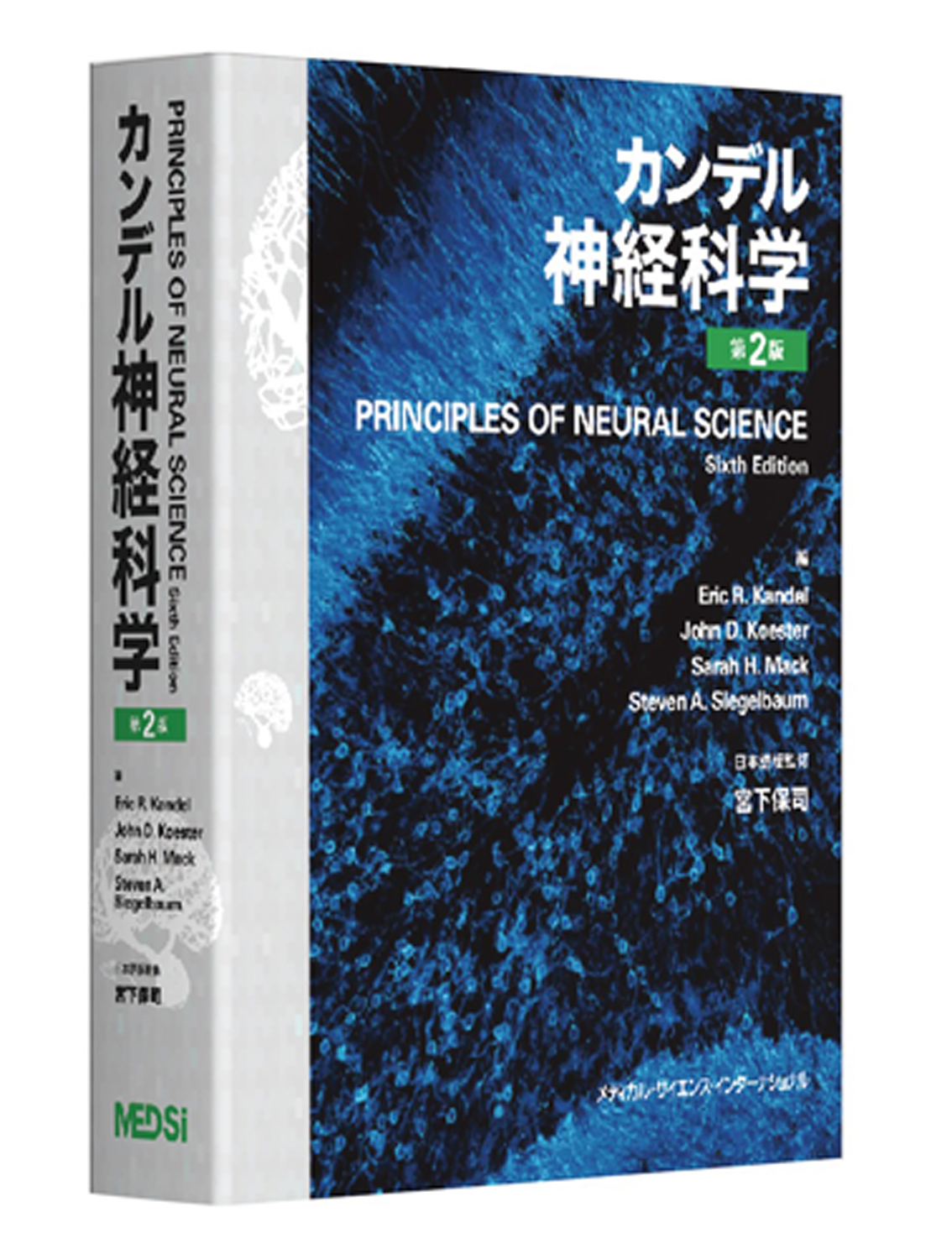
- カンデル神経科学 第2版
- ¥15,950
-
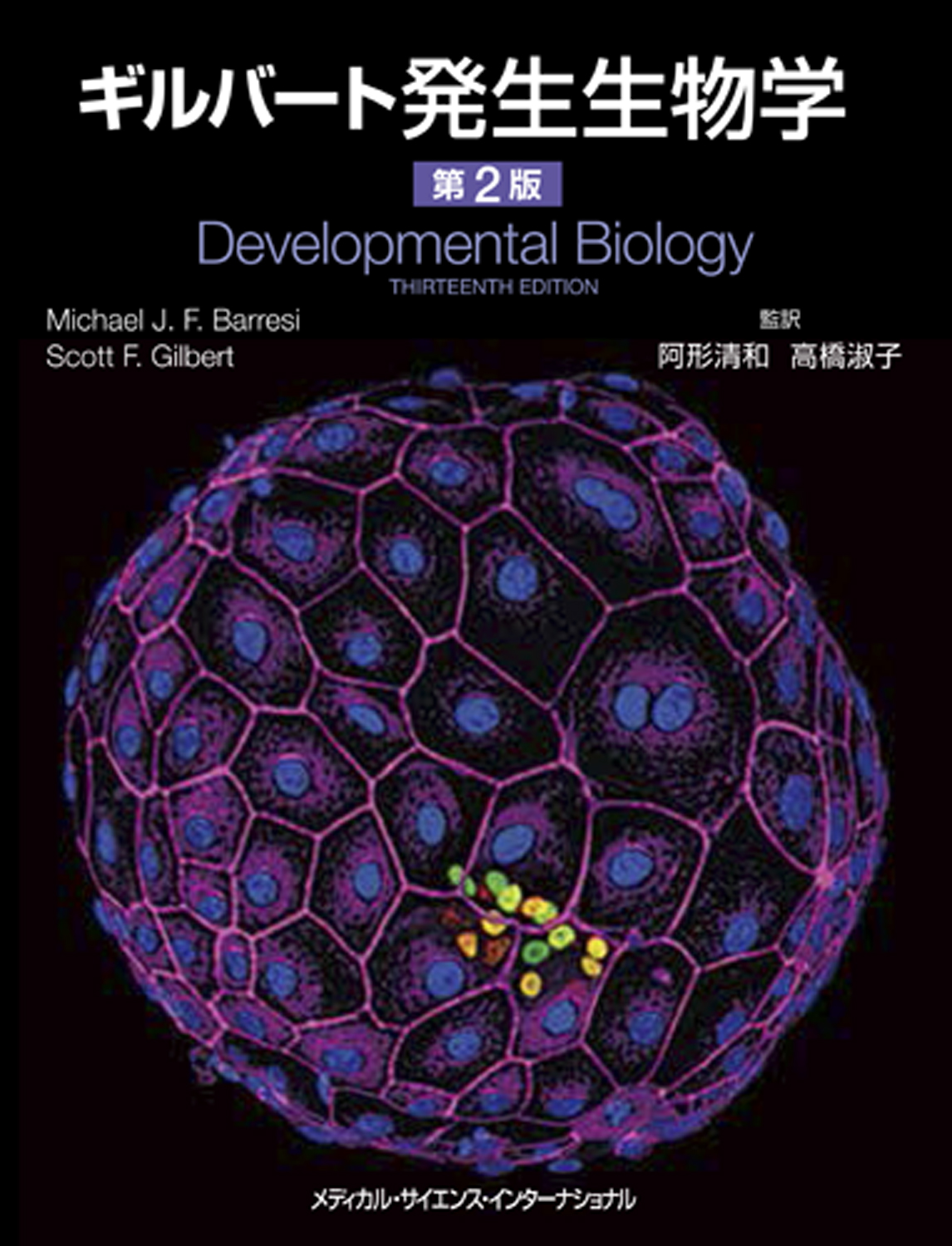
- ギルバート発生生物学 第2版
- ¥13,750
-
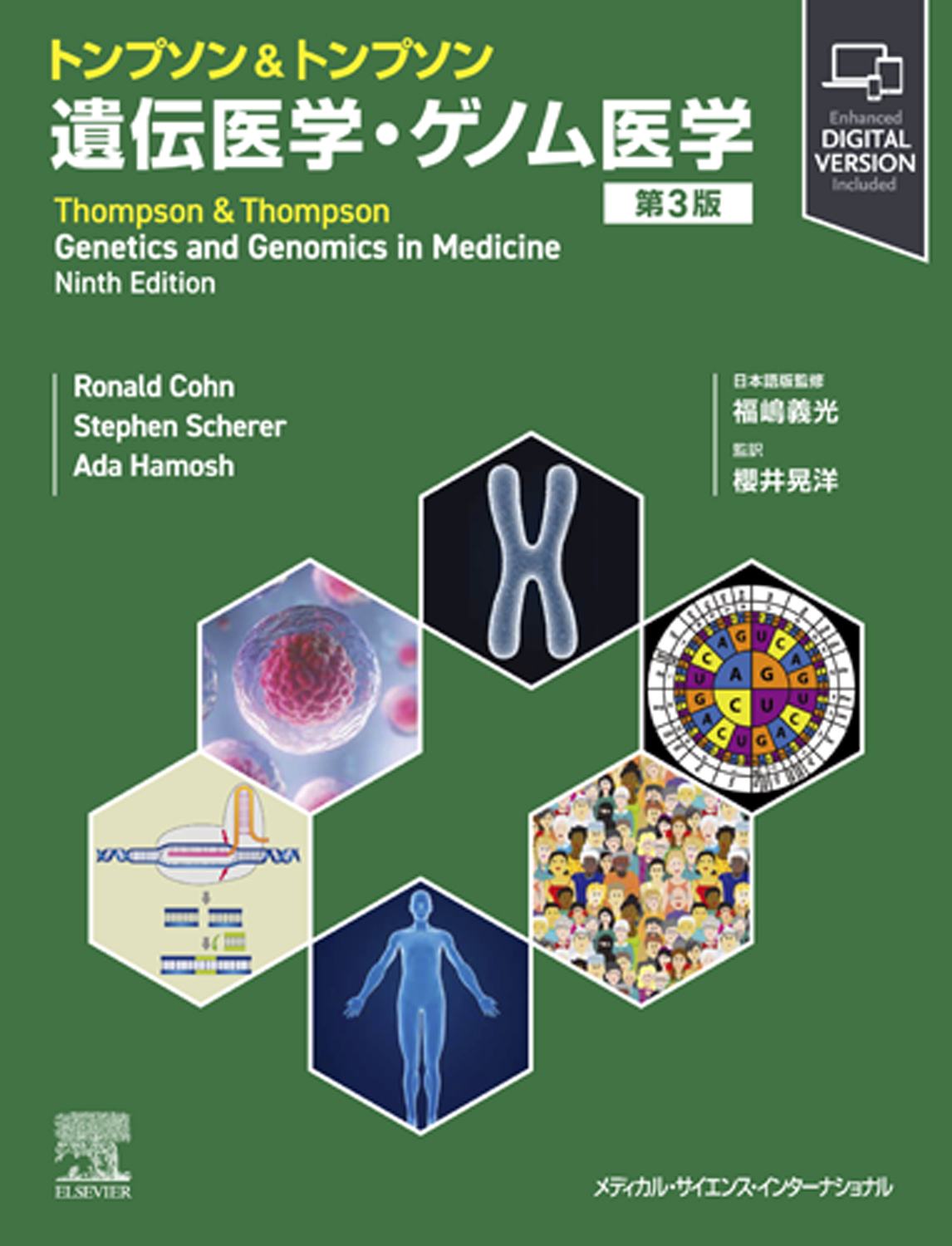
- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版
- ¥12,100
-
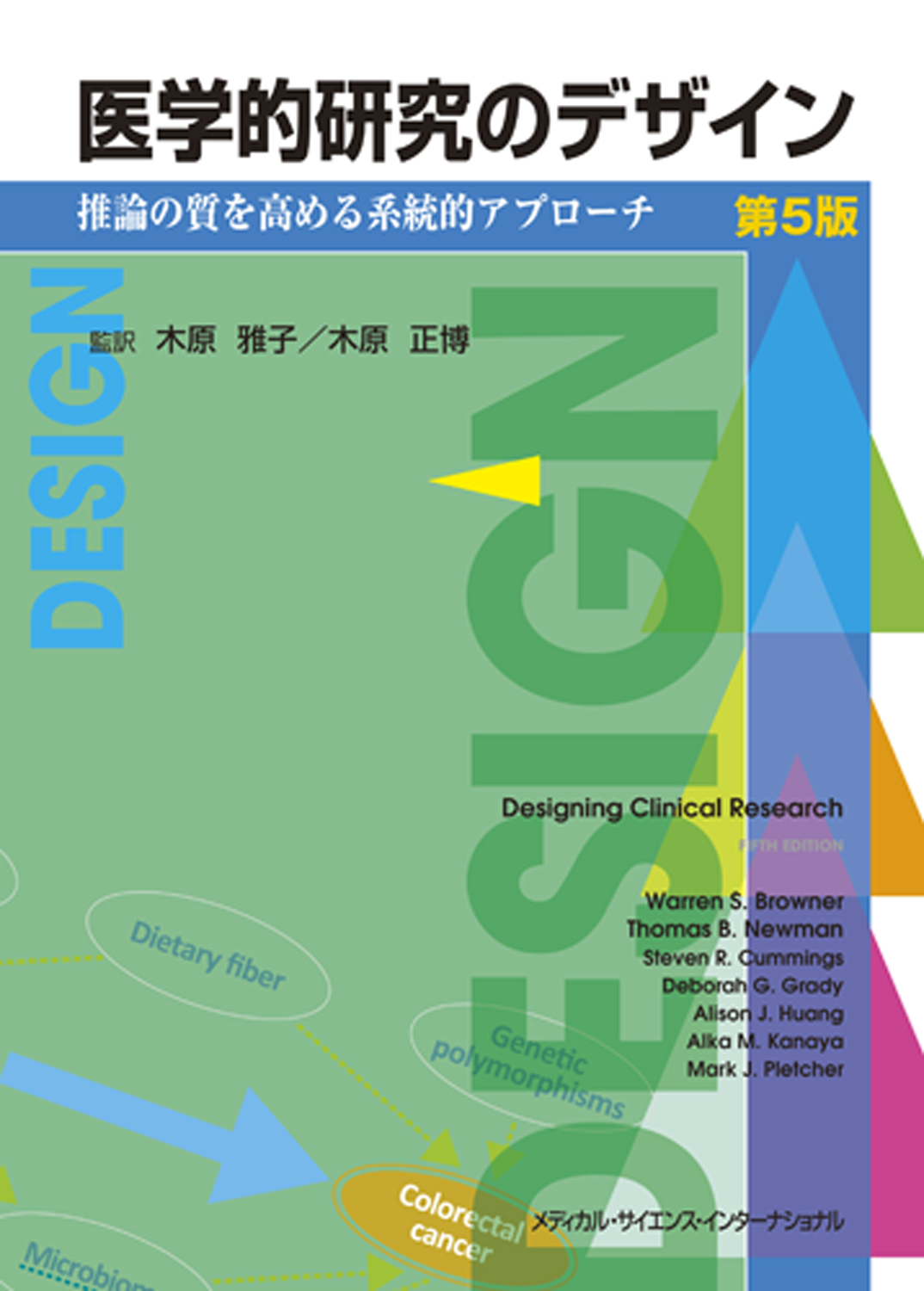
- 医学的研究のデザイン 第5版
- ¥6,270
-
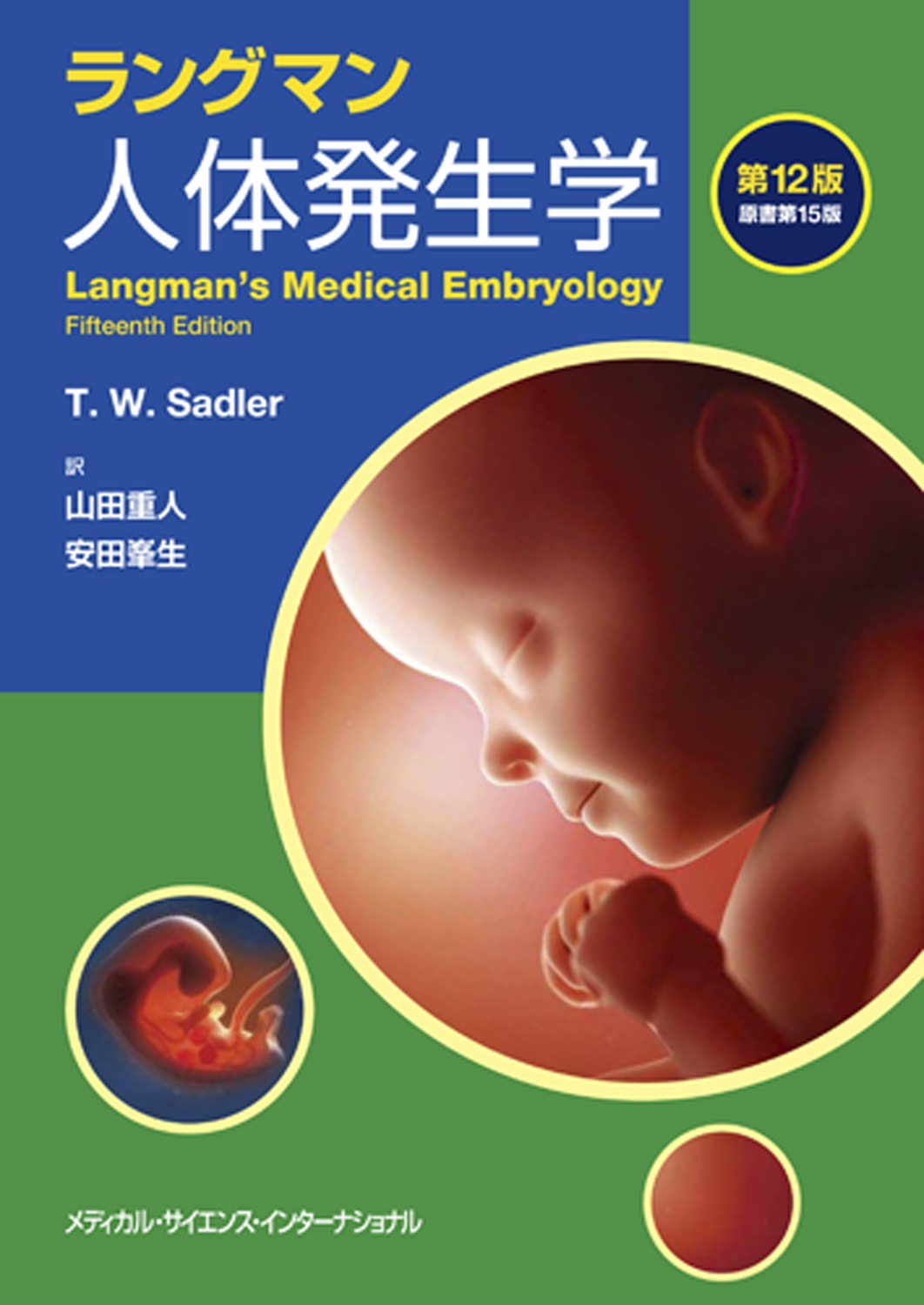
- ラングマン人体発生学 第12版
- ¥9,350
-
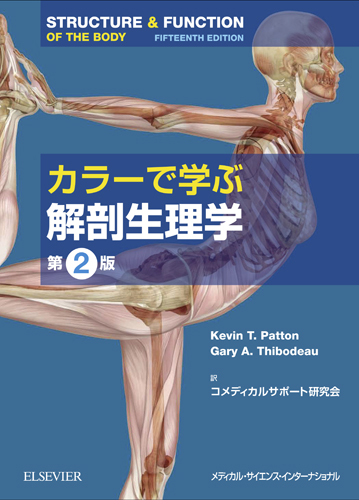
- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版
- ¥6,160
-
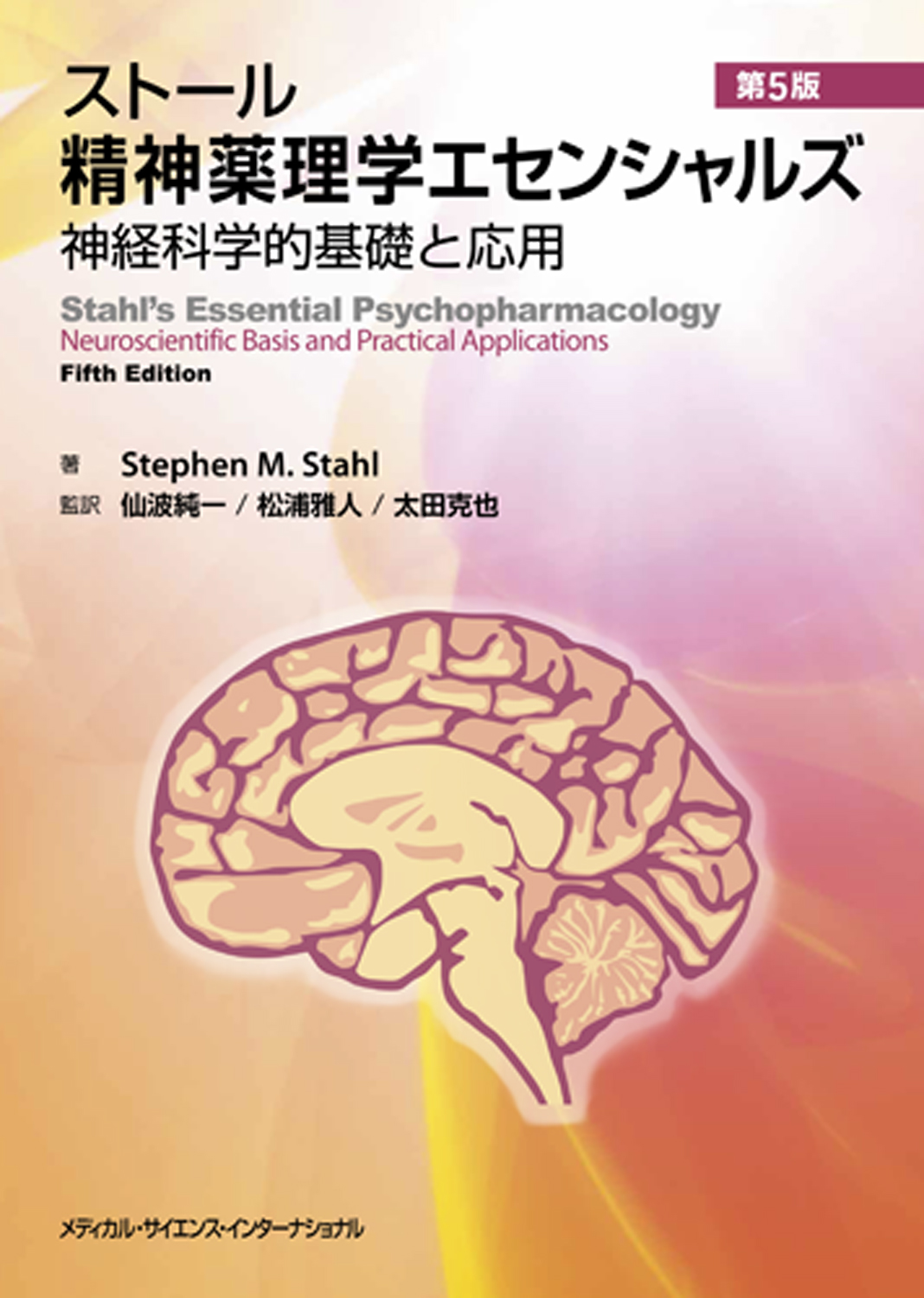
- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版
- ¥13,750
-
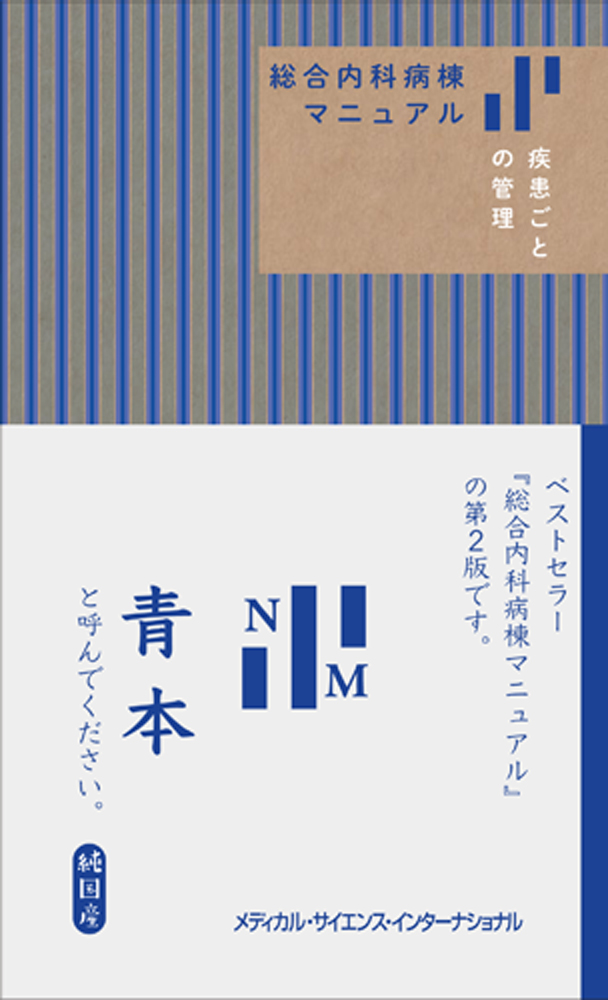
- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-
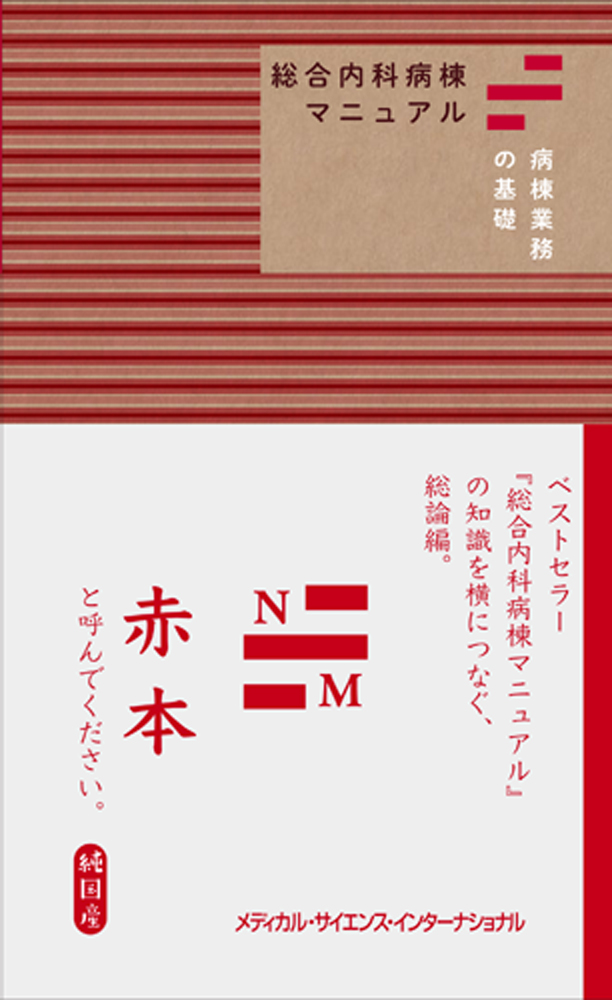
- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-
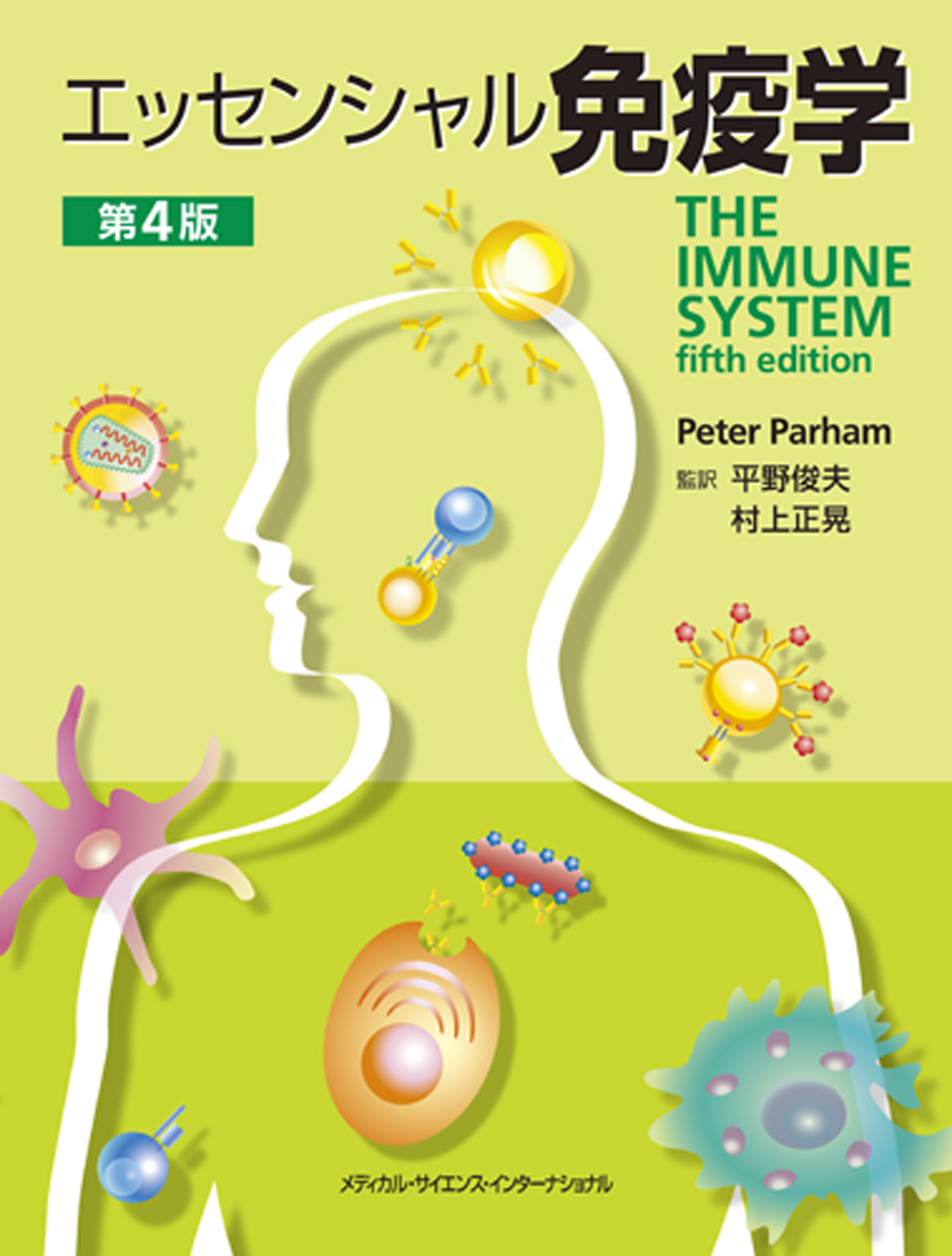
- エッセンシャル免疫学 第4版
- ¥7,150
-
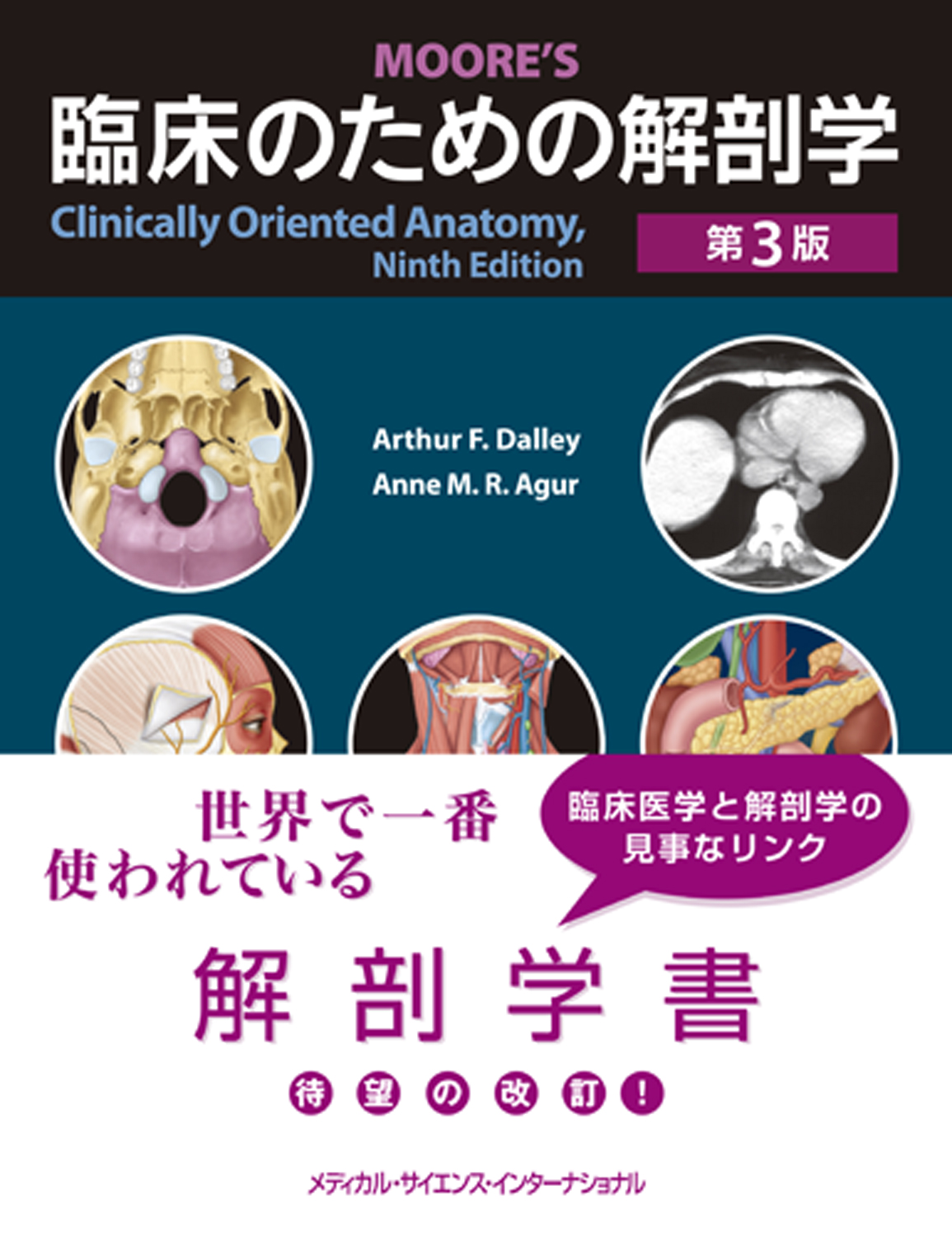
- 臨床のための解剖学 第3版
- ¥15,950
-
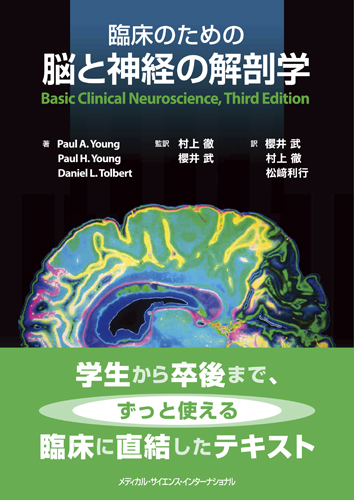
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-
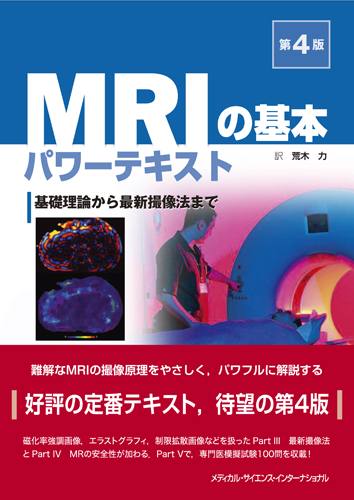
- MRIの基本パワーテキスト 第4版
- ¥7,150
-
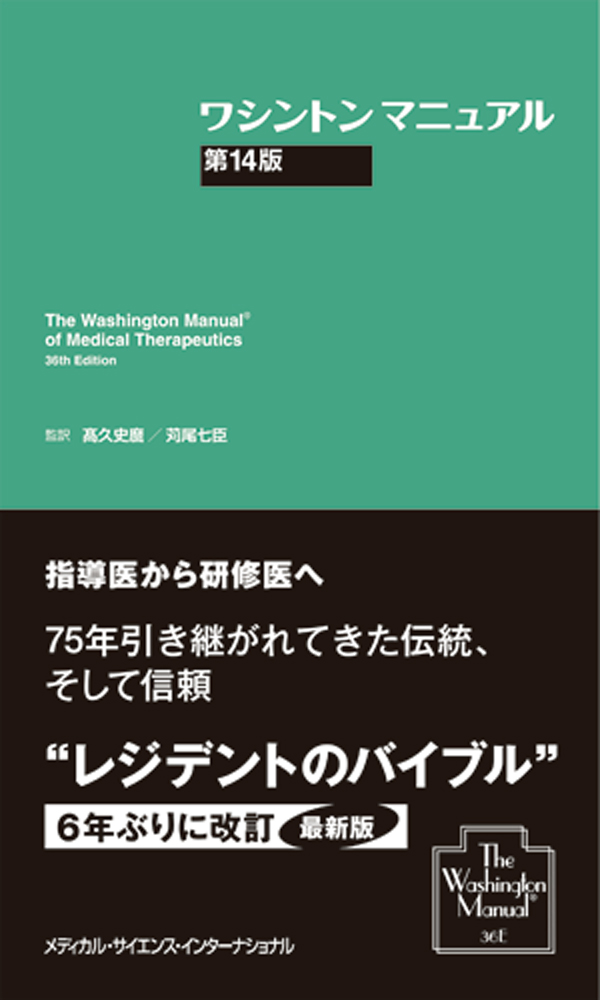
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-

- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-
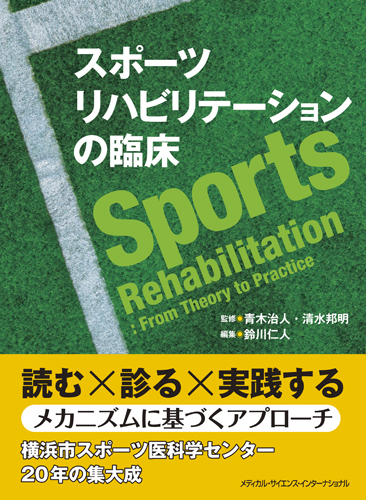
- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-
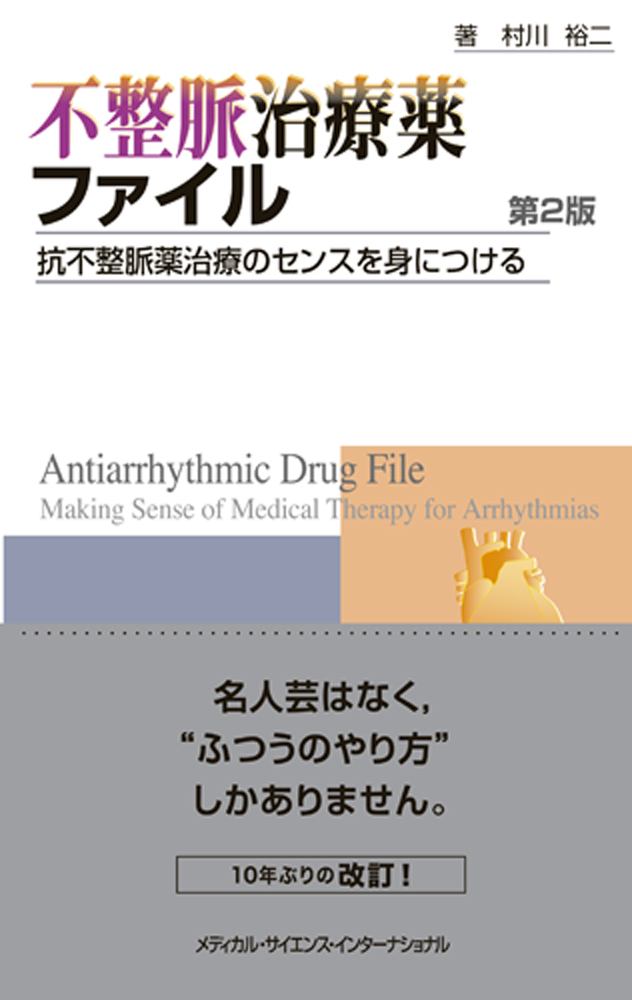
- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
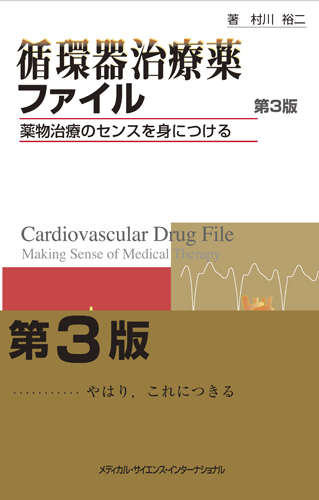
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-
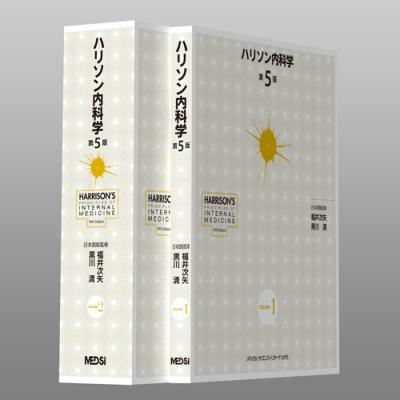
- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
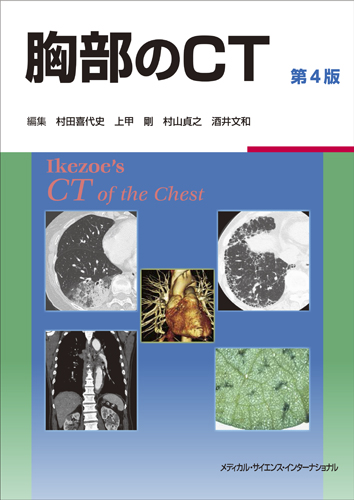
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
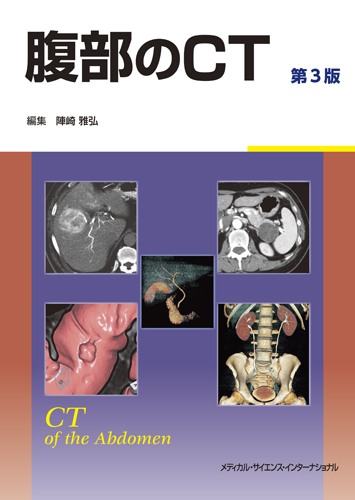
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
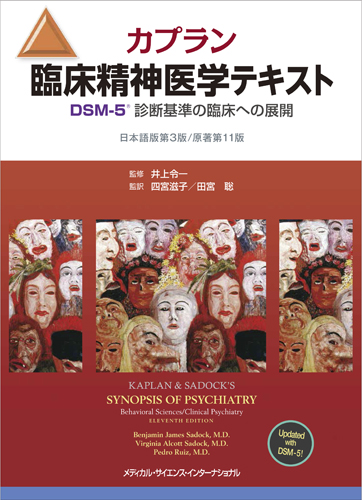
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000