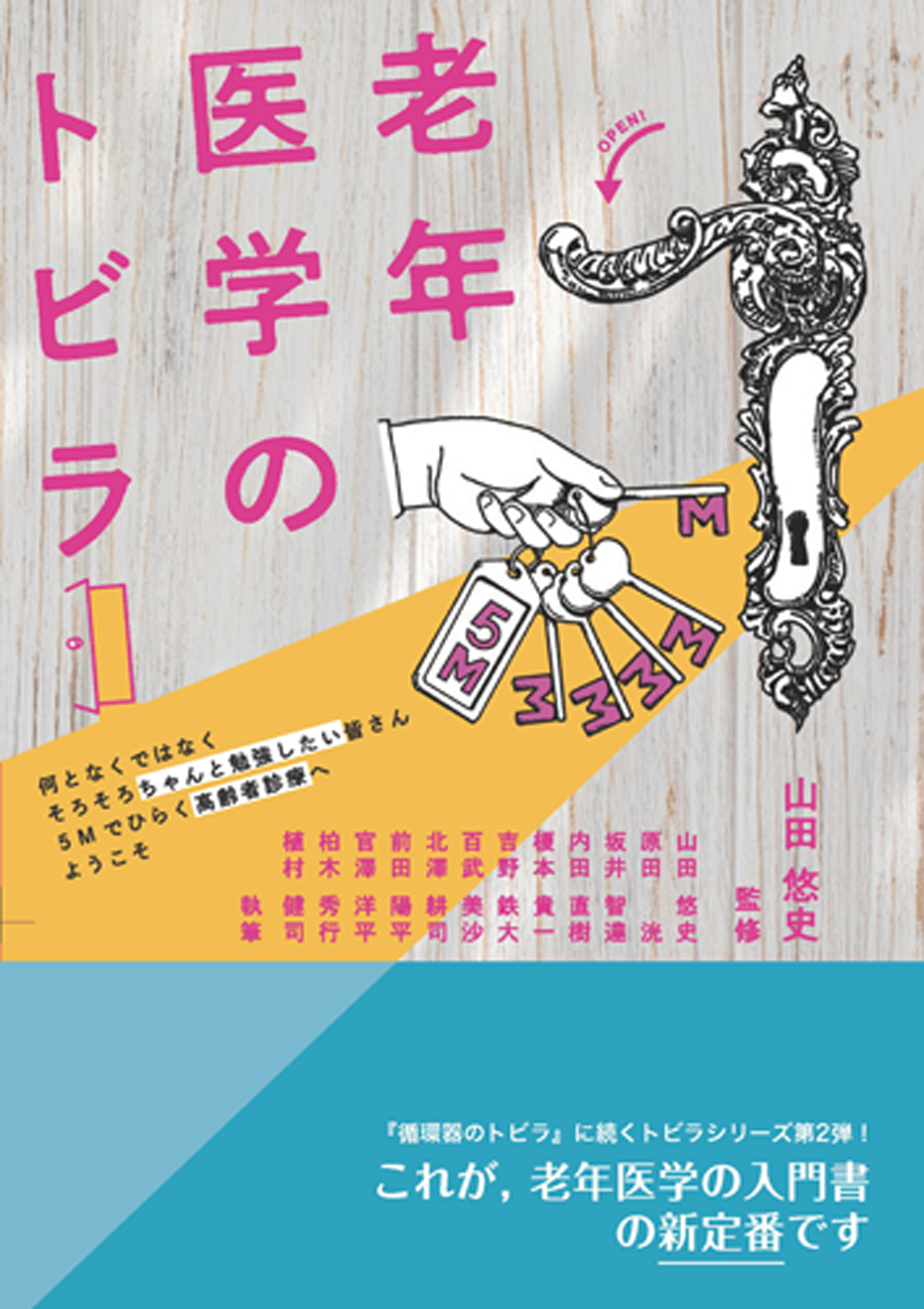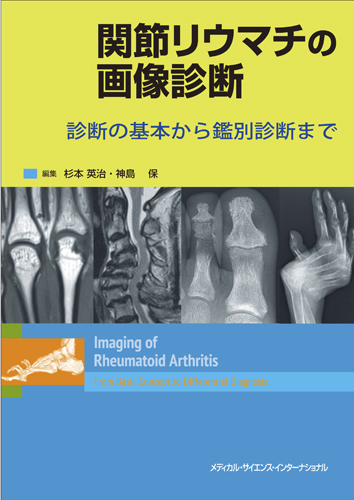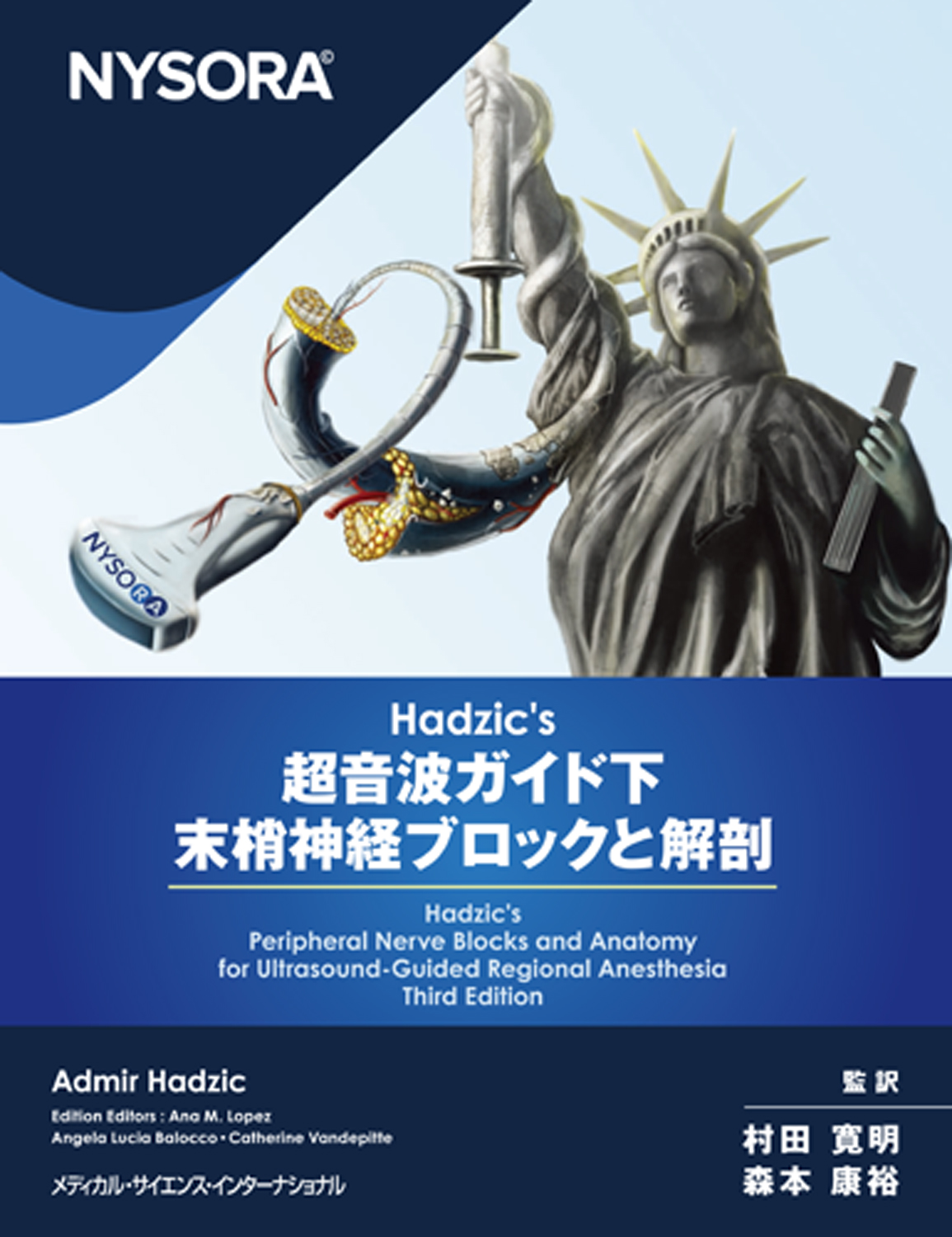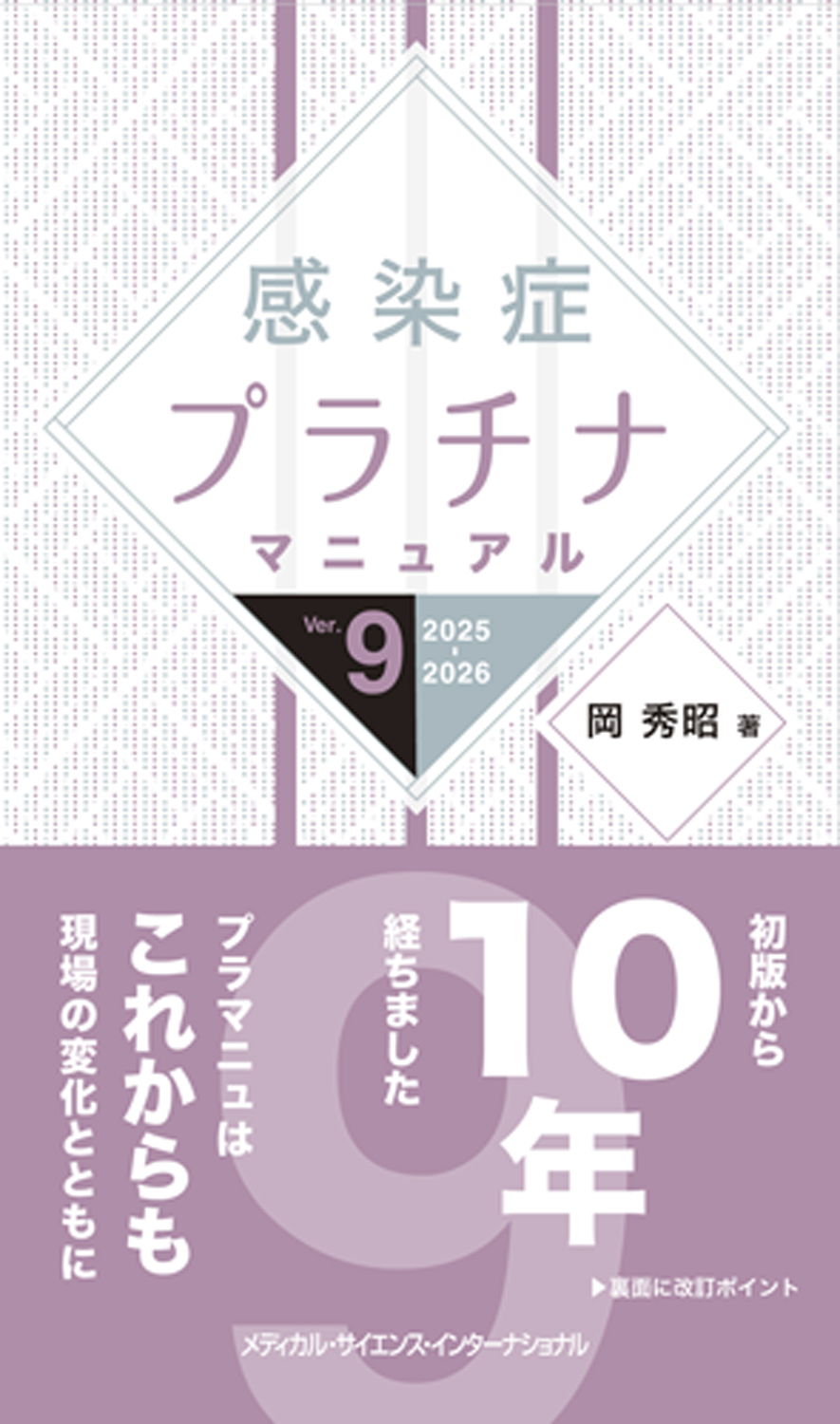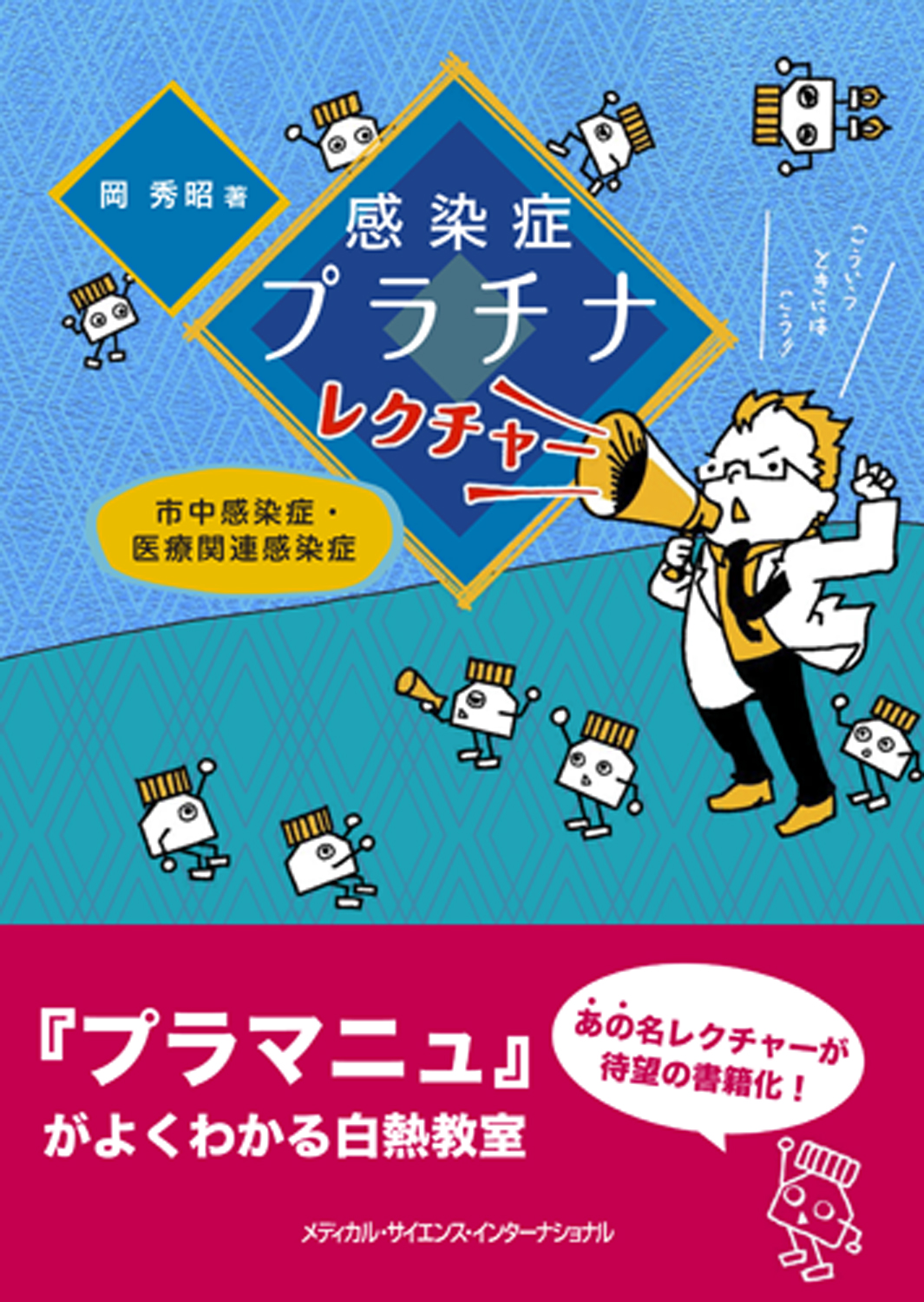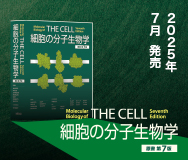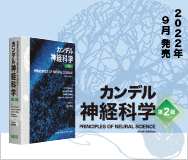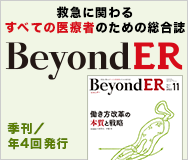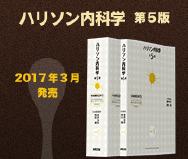老年医学のトビラ - 何となくではなく そろそろちゃんと勉強したい皆さん 5Mでひ らく高齢者診療へようこそ -
これが,老年医学入門書の新定番です
日本における老年医学の新定番となる入門書。高齢者診療の複雑な問題に焦点を当て、「5つのM」:Mobility(身体機能)・Mind(認知機能・精神的側面)、Medications(薬剤)・Multicomplexity(複雑性・多疾患併存)・Matters Most(最も大切なこと)を軸に解説。認知症やフレイル、「見えない」「聞こえない」といった訴えへの対応、スクリーニング・予防、ケアのゴール設定などの14のテーマについて、「5つのM」を鍵にしてそのトビラを開く!
序章 老年医学のトビラを開く鍵
高齢患者を担当することになったら…
主要なプロブレムにフォーカスしすぎず,「5 つのM」で患者の全体像を把握し,真のニーズを見極めよう
第1章 転 倒
転倒した患者をみたら…
原因を特定し,できるだけ取り除き,将来の転倒を防ぐ
第2章 せん妄
「入院患者が暴れている」と呼ばれたら…
すぐに「抗精神病薬」と早合点せず,まず落ち着いて診断し,隠された複数の原因を追究する
第3章 認知症
この患者さん,認知症かもと思ったとき,認知症をもつ患者を受け持ったとき
むやみに機能評価に走らず,生活を診る気持ちで対応しよう
第4章 高齢者のうつ病,不眠
うつ病も不眠も,加齢とともに増加する疾患です
専門医へ紹介する前にできることは?
第5章 ポリファーマシー
「いつもの薬を処方しておこう…」ではなく
その処方の真のアウトカムと不利益を考えて,目の前の患者にとって適切か見直す
第6章 高齢者の漢方薬
漢方薬は「選んで終わり」?
カンポウを求める患者の希望を深掘りしてみよう
第7章 フレイル
聞いたことはあるけれど,いまいち何だかわからない…
高齢者の臨床像の解像度をぐっと押し上げるのに役立つ!
第8章 尿失禁と便秘
よくあること…と侮るなかれ
排尿・排便の問題はQOL に大きく影響する!
第9章 「見えない」
日常生活で各方面に影響を及ぼす視覚
老年期に特有の問題を学ぼう
第10章 「聞こえない」「においがわからない」
コミュニケーションや生活上の困る問題につながる
難聴,嗅覚障害について整理しておこう
第11章 「食べられない」
「全然食べてくれないんです」と相談されたら…
年のせいでしょう,と安直に判断せず,可逆性の要因・病態をしっかりと鑑別しよう
第12章 高齢者のスクリーニングと予防
がん検診や予防接種は「万人向け」でも「◯歳だから」でもありません
「何を」「いつまで」行うか個別化して提案しよう
第13章 事前指示書の作成
「まさかこの患者さんが…」とならないように
作成のプロセスは,患者と家族の人生,価値観にふれる対話でもある
第14章 ケアのゴール設定
患者,患者家族,主治医の意見がすれ違うときは
意思決定者を見極め,共同意思決定(SDM)の考え方に沿ってゴールを設定しよう
付録 加齢による正常な変化
*******
■監修・執筆
山田悠史
(Brookdale Department of Geriatrics and Palliative Medicine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai)
(序章,第2,12章)
■執筆
原田洸
(Brookdale Department of Geriatrics and Palliative Medicine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai)
(第1,8章,付録)
坂井智達
(九州大学大学院医学研究院 地域医療教育ユニット)
(第3章)
内田直樹
(医療法人すずらん会 たろうクリニック)
(第4章)
榎本貴一
(練馬光が丘病院 薬剤室)
(第5章)
吉野鉄大
(慶應義塾大学医学部 漢方医学センター)
(第6章)
百武美沙
〔Division of Geriatrics, University of California Los Angeles(UCLA)/慶應義塾大学医学部医学 教育統轄センター〕
(第7章)
北澤耕司
(京都府立医科大学附属病院 眼科)
(第9章)
前田陽平
(JCHO大阪病院 耳鼻いんこう科)
(第10章)
官澤洋平
(神戸大学医学部附属病院 総合内科)
(第11章)
柏木秀行
(飯塚病院 連携医療・緩和ケア科)
(第13章)
植村健司
(Brookdale Department of Geriatrics and Palliative Medicine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai)
(第14章)
はじめに
医学生・医師としての私たちの歩みは,無数の新しいトビラを開く旅路だったともいえるでしょう。あるトビラには「耳鼻咽喉科」と,またあるトビラには「外科」と記され,私たちはポリクリ(BSL)や初期研修のスーパーローテーションで,教えられたとおりにそのノブに手をかけ,新たな知識の世界へと足を踏み入れてきました。
前作『循環器のトビラ』で紹介されたのは,おそらく皆さんが一度はノックしたり,少し開いてみたりしたことがあるトビラだったでしょう。しかし,それが重厚に感じられ,完全に開くことなく苦手意識をもっていた人たちにとって,大きな手助けになったに違いありません。
では,『老年医学のトビラ』はどうでしょうか。おそらく多くの皆さんが,医学生や研修医の時代に出会うことすらなかったトビラなのではないでしょうか。あるいは,「ごく当たり前に毎日そのトビラを開いている」「開き方などとっくにわかっている」と信じられているかもしれません。なぜなら,私たちの目の前には,常に高齢の患者さんがいるからです。だからこそ,医学書のタイトルに「老年」と書かれるだけで売れなくなってしまうのかもしれません。
でも,もしそれが本物のトビラとよく似た別のトビラだったとしたら? すぐ隣にある本物のトビラの存在に気づかぬまま,診療を続けているとしたら?
実は私自身,その「よく似た別のトビラ」の前に立ち,それが本物だと信じて疑わなかった時期がありました。私が日本で総合内科診療に従事していたときのことです。高齢者の診療には,自信すらもっていたように覚えています。しかし,ニューヨークに来て,それが間違いだったと気づかされました。老年医学の道を究めた同僚たちとの交流のなかで,私は静かに,しかしはっきりと悟りました。自分が知っていると思っていた高齢者診療は,まったく別ものだったのだと。そして,本物の『老年医学のトビラ』を開くには,そのための鍵が必要だったのだと。
だからこそ私は,ここニューヨークの地で,『循環器のトビラ』をまとめあげ
た杉崎陽一郎先生からこのシリーズのお話を伺ったとき,しっかりとバトンを受
け取ることができました。
本書は,その鍵をあなたにお渡しするためのものです。「5 つのM」という名のその鍵は,驚くほどシンプルでありながら,老年医学という複雑な問題を整理していくための確かな手がかりになるのです。
これを手にしているあなたが研修医の先生なら,これからどのような道を歩むとしても,本書が必ず助けになってくれるときがくるはずです。一方で,本書は特に「高齢者診療の経験は十分にある」と考えている医師に向けた招待状でもあります。かつて日本にいた頃の私のように,「開いているつもり」のトビラの前で,少しでも違和感を覚えたことがあるのなら,ぜひ本書で本物の老年医学の世界を味わってください。
本書では文中に,
まずはここから:初期研修医もしっかりチェック
もう一歩踏み込んで:内科専攻医は知っておこう
トビラの向こう:役立つ老年医学の知識
というまとめや解説を適宜設けています。読者の皆さんの「今」に合わせて,大事な知識を整理してください。
老年医学のトビラとそれを開く鍵は,ここにあります。さあ,私たちとともにその鍵を差し込み,ゆっくりとトビラを開いてみませんか。その向こうには,まったく新しい景色が広がっているはずです。
2025年8月
Brookdale Department of Geriatrics and Palliative Medicine,
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
山田悠史
-
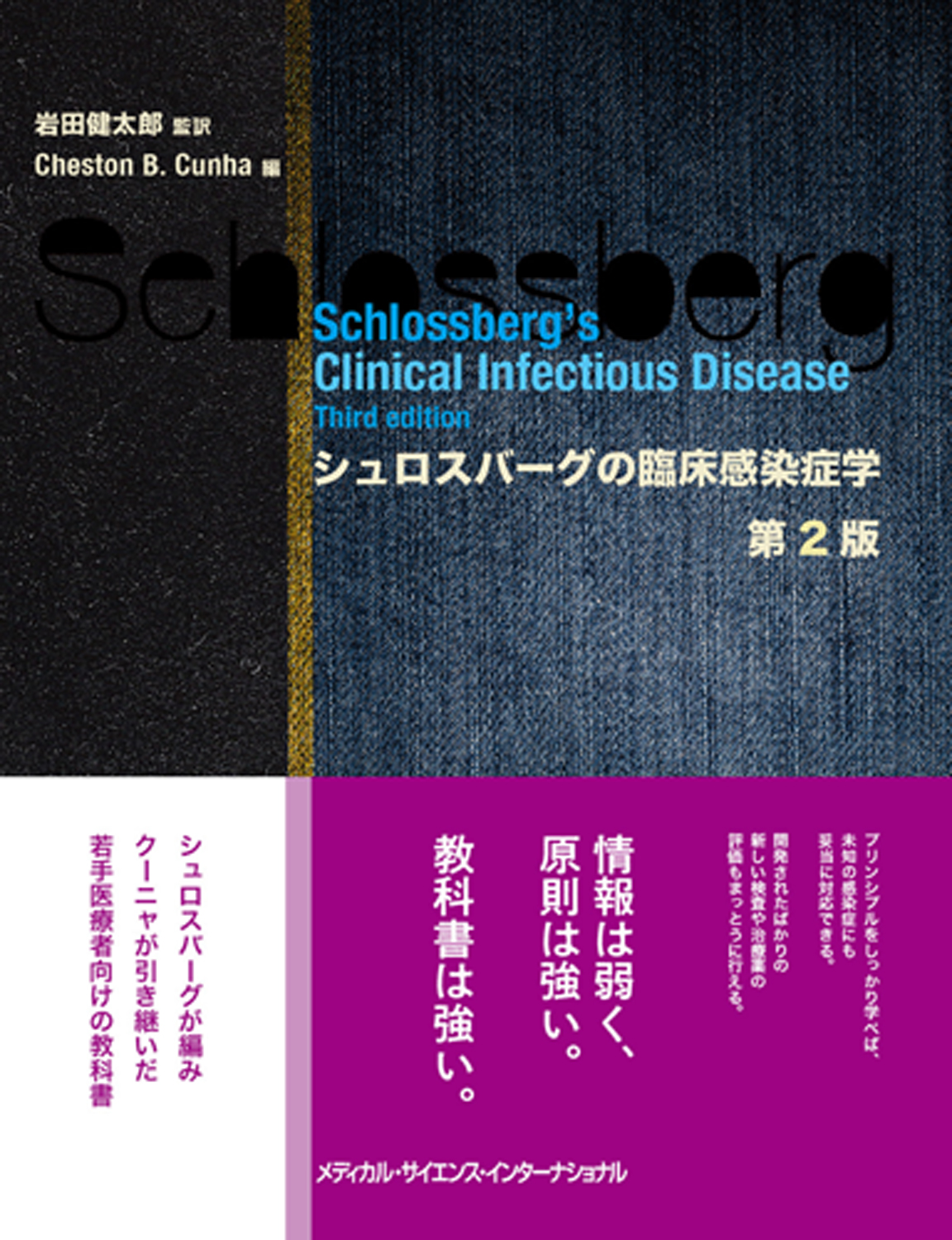
- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版
- ¥25,850
-
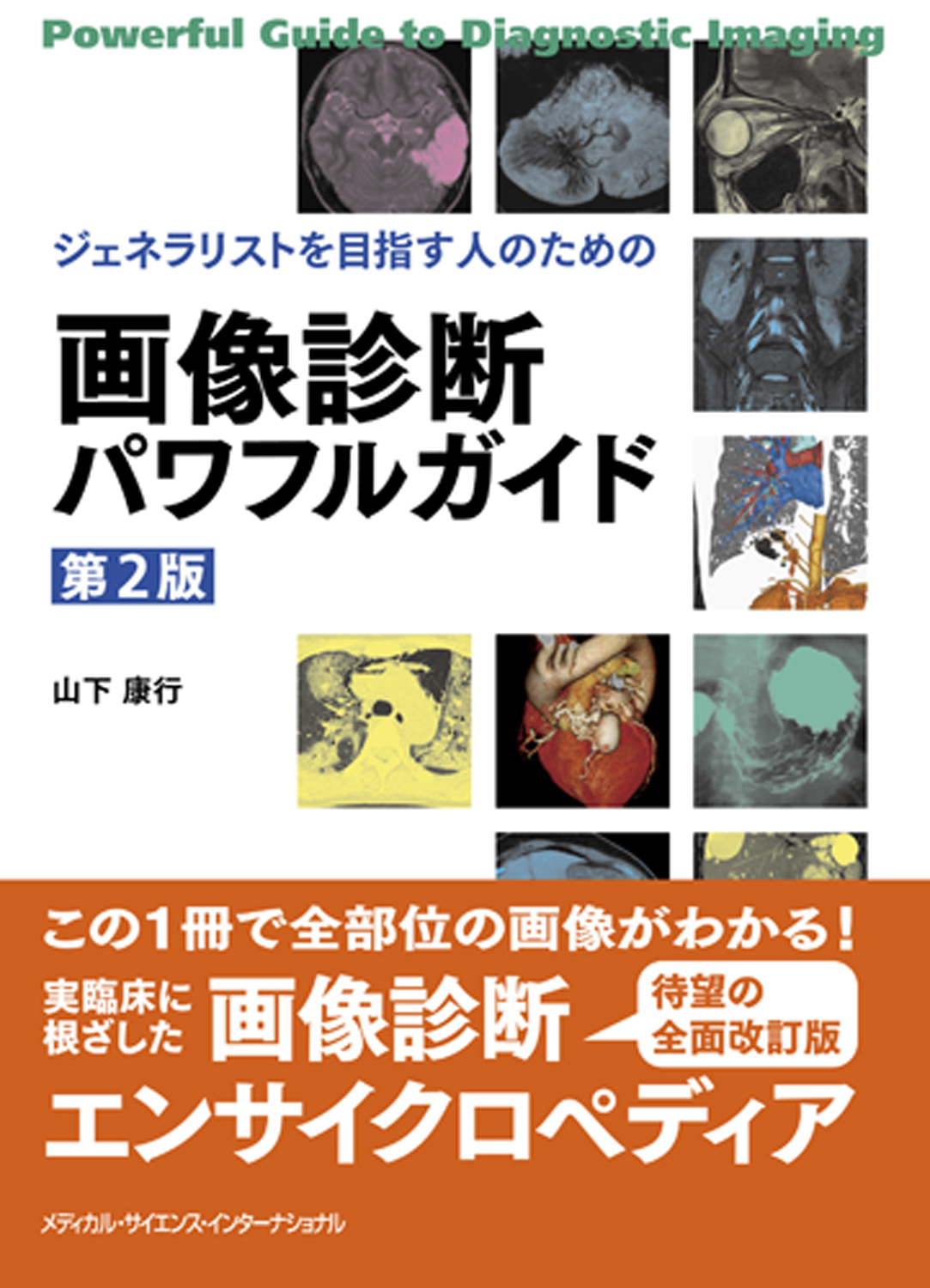
- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版
- ¥12,100
-
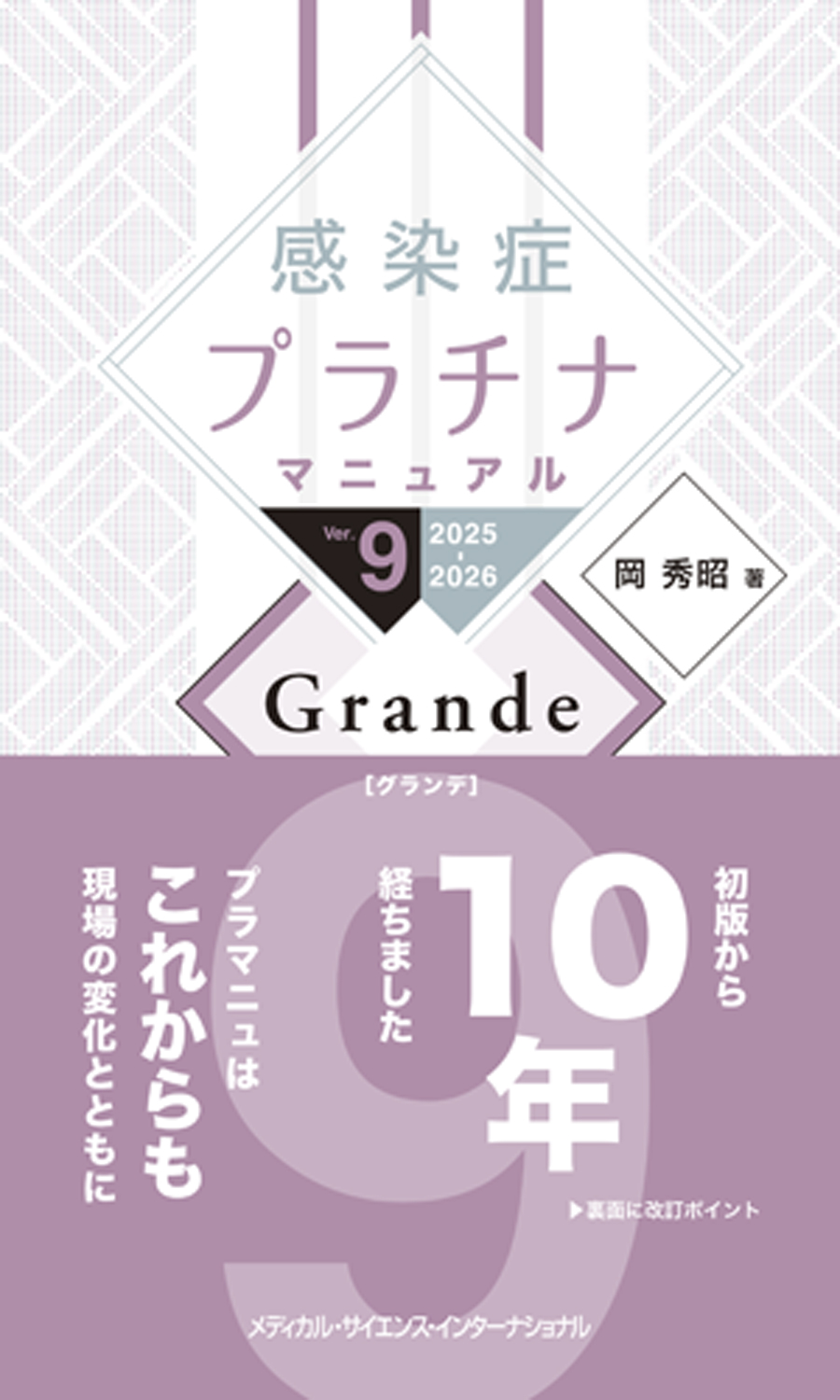
- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande
- ¥4,180
-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版
- ¥8,250
-
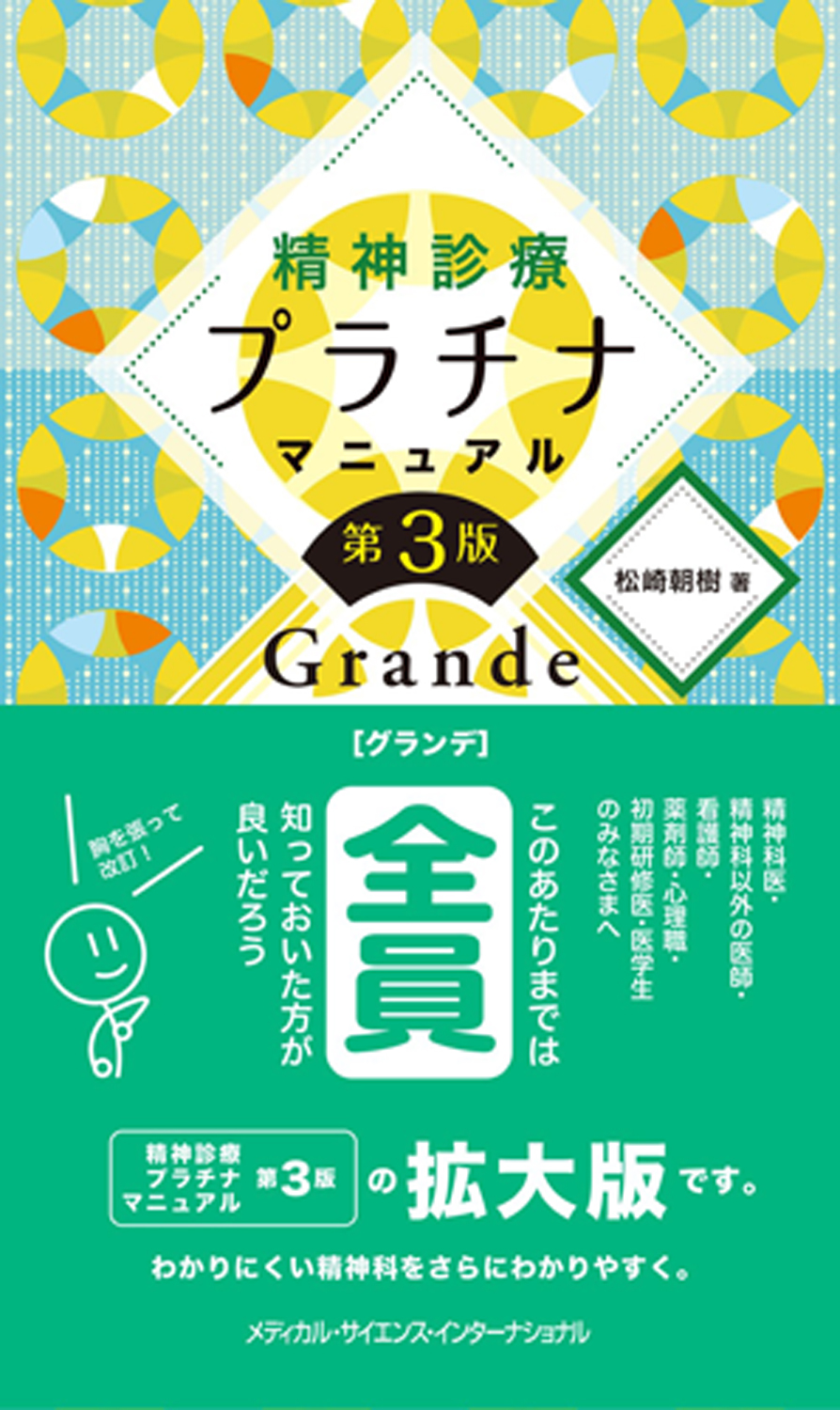
- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版
- ¥3,960
-
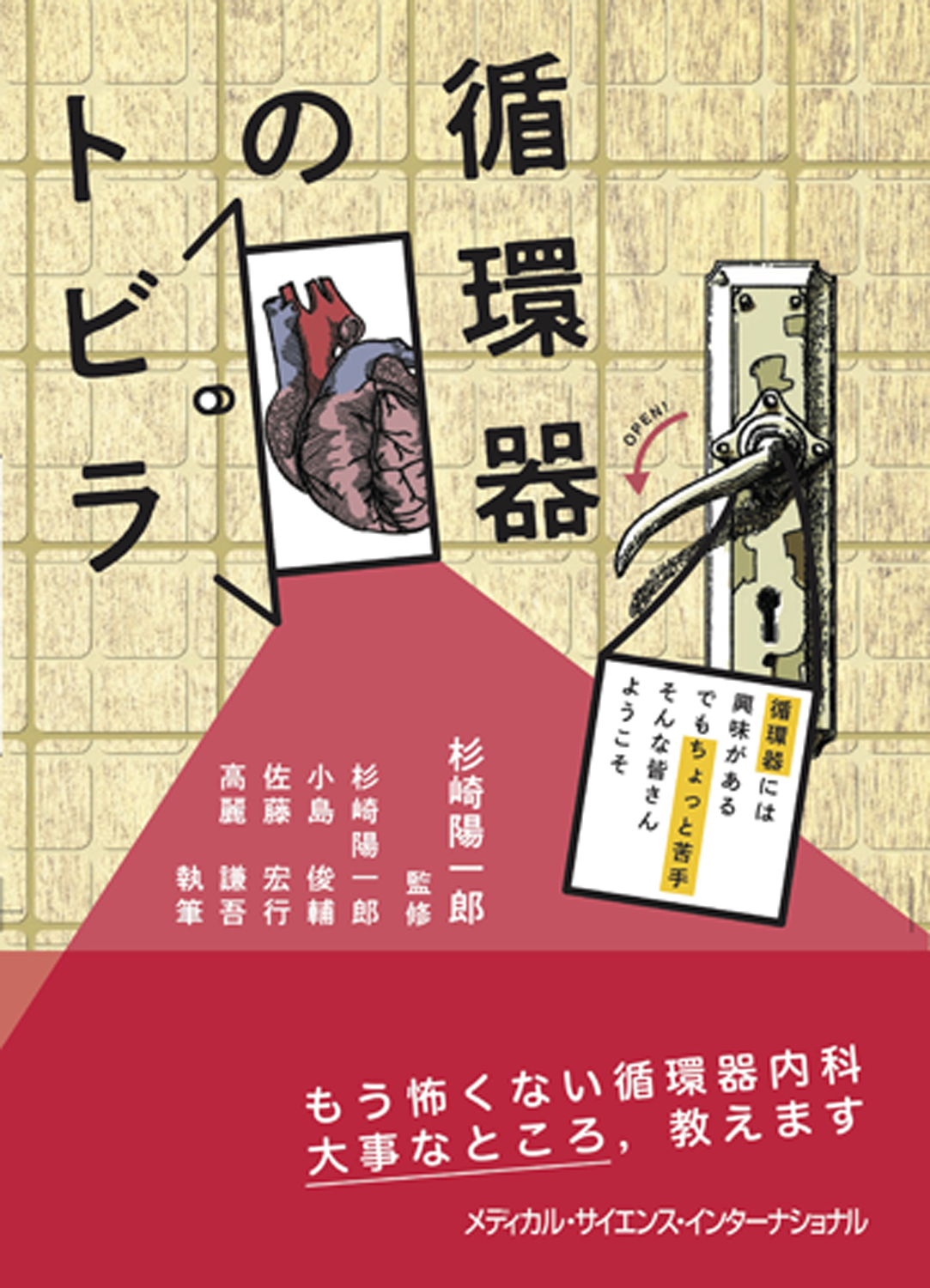
- 循環器のトビラ
- ¥5,940
-
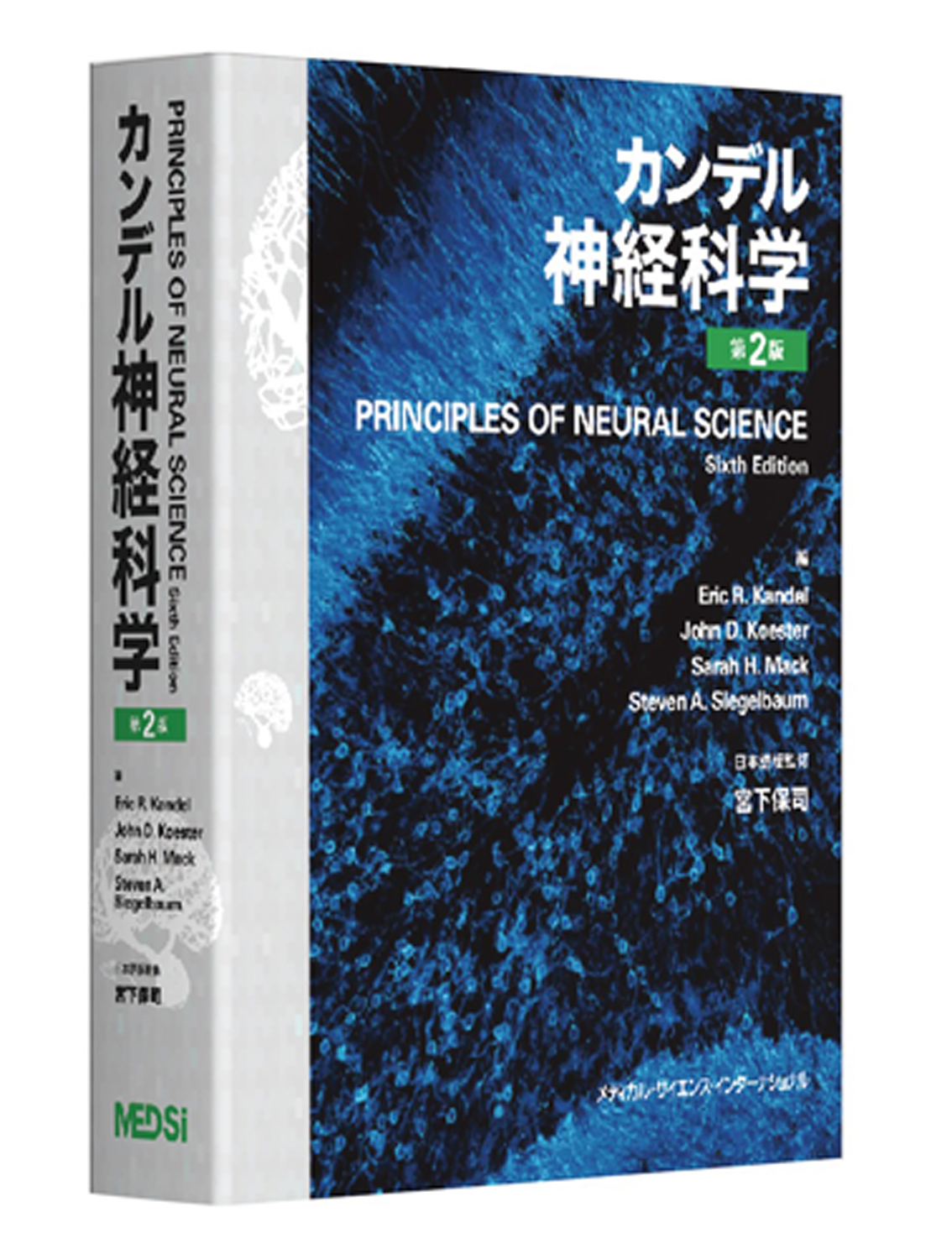
- カンデル神経科学 第2版
- ¥15,950
-
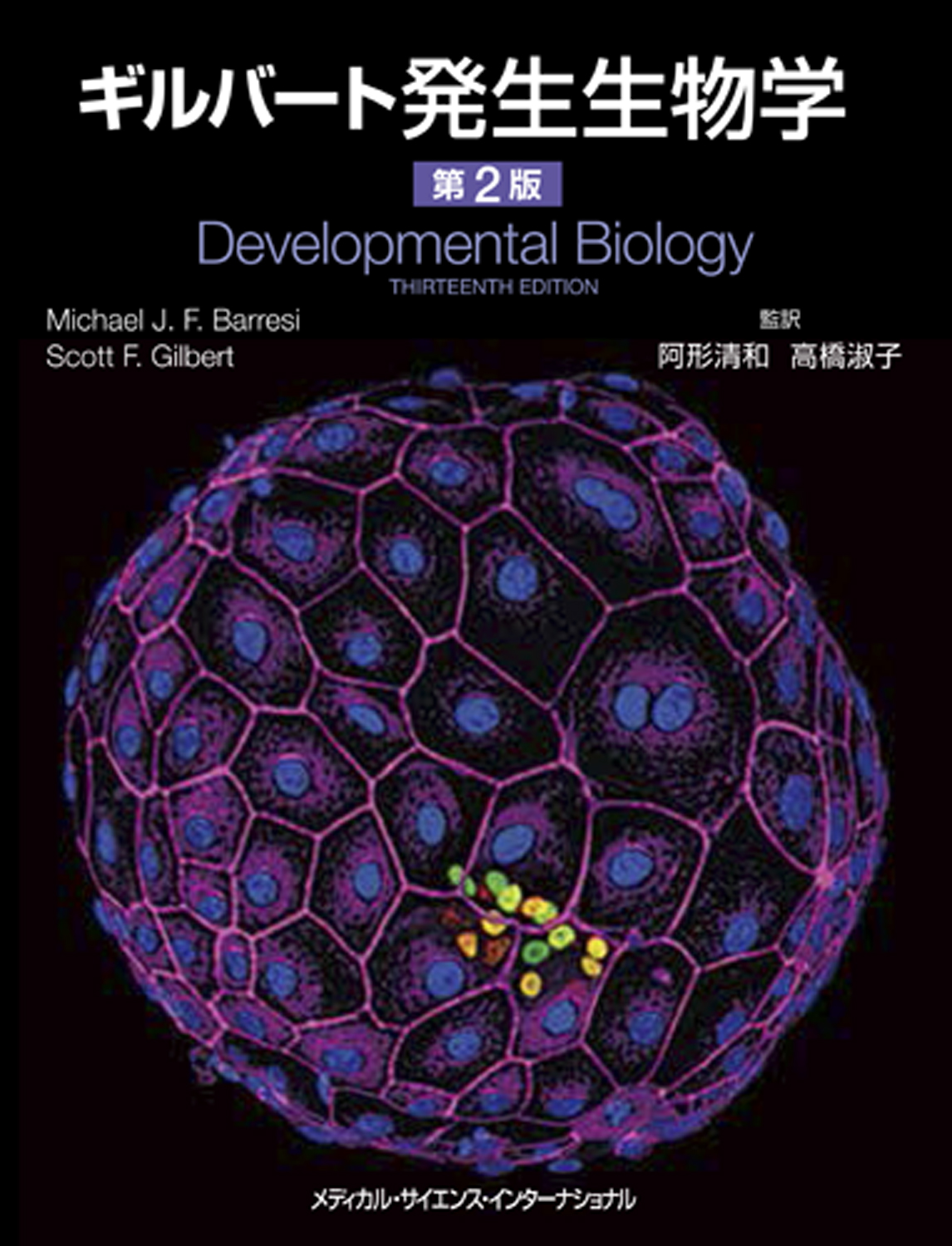
- ギルバート発生生物学 第2版
- ¥13,750
-
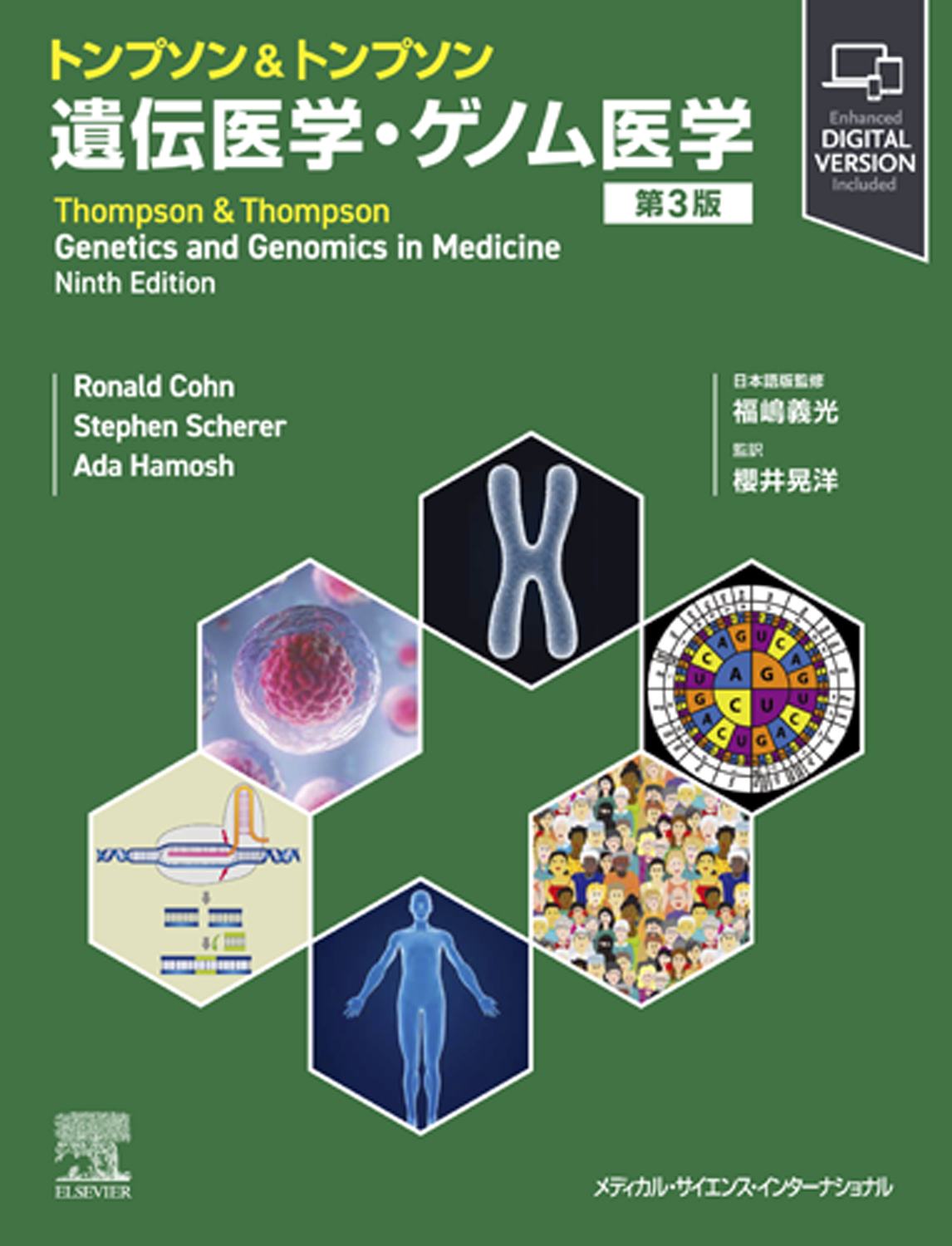
- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版
- ¥12,100
-
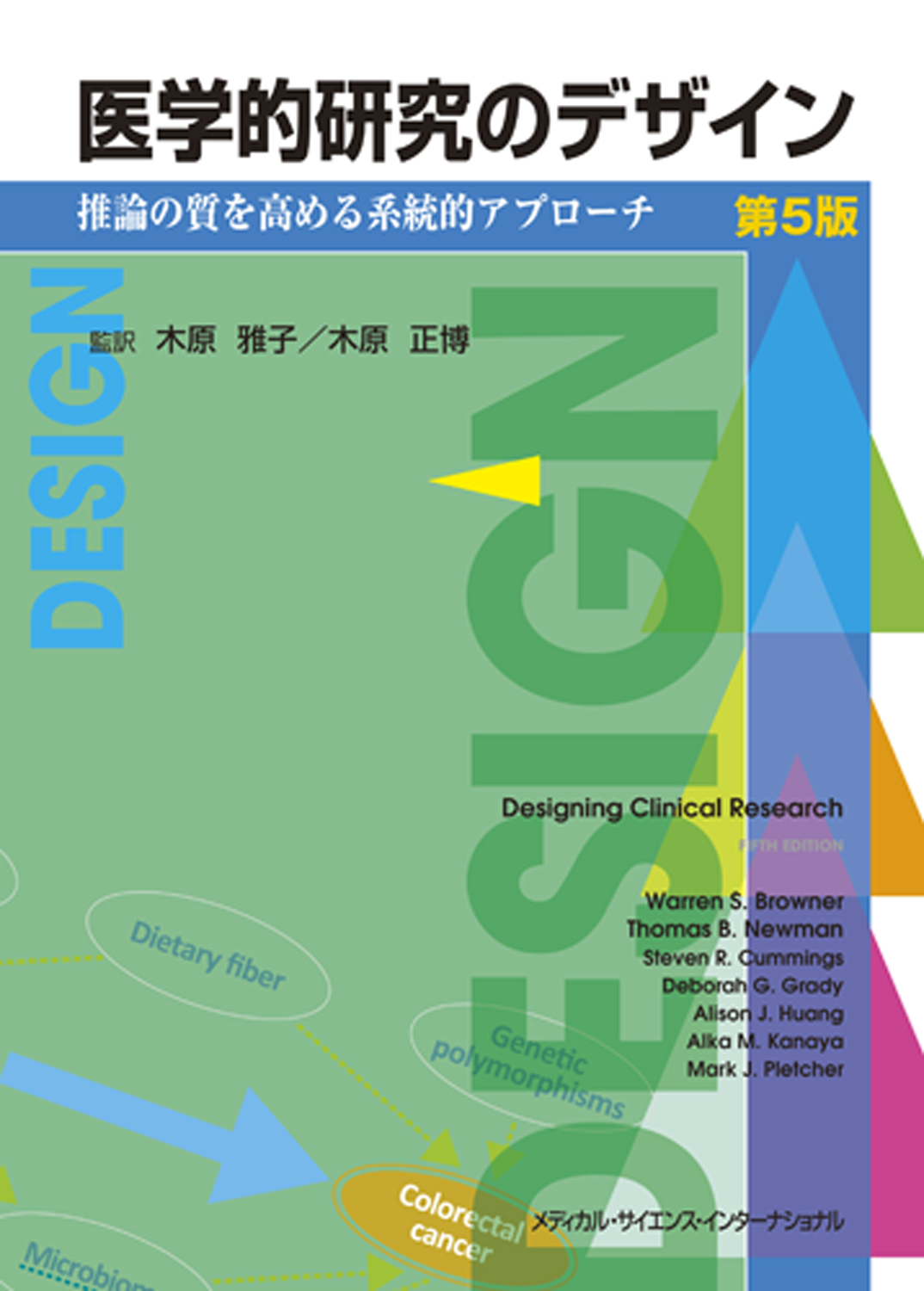
- 医学的研究のデザイン 第5版
- ¥6,270
-
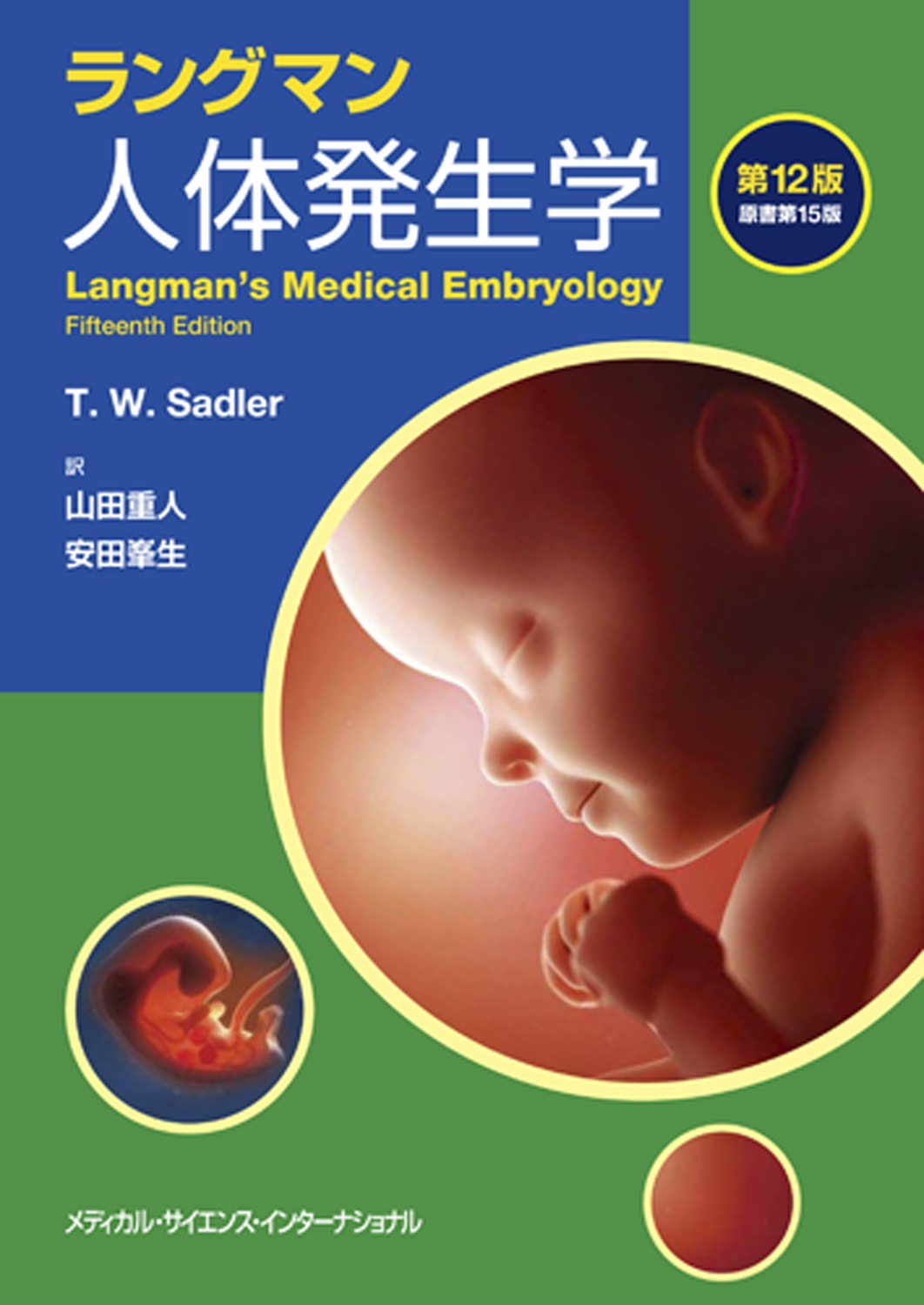
- ラングマン人体発生学 第12版
- ¥9,350
-
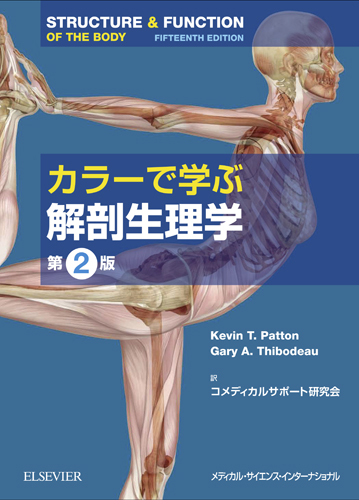
- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版
- ¥6,160
-
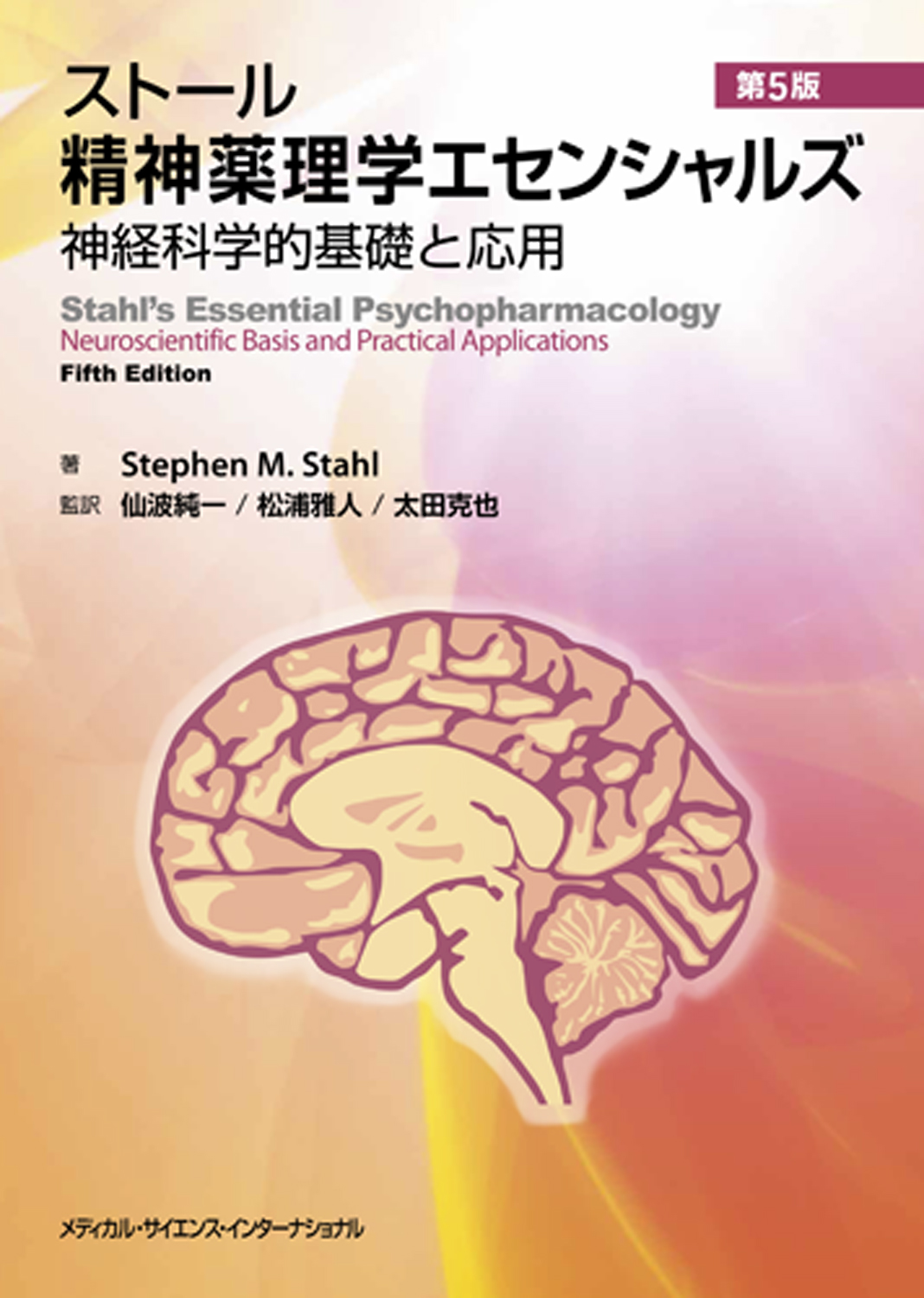
- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版
- ¥13,750
-
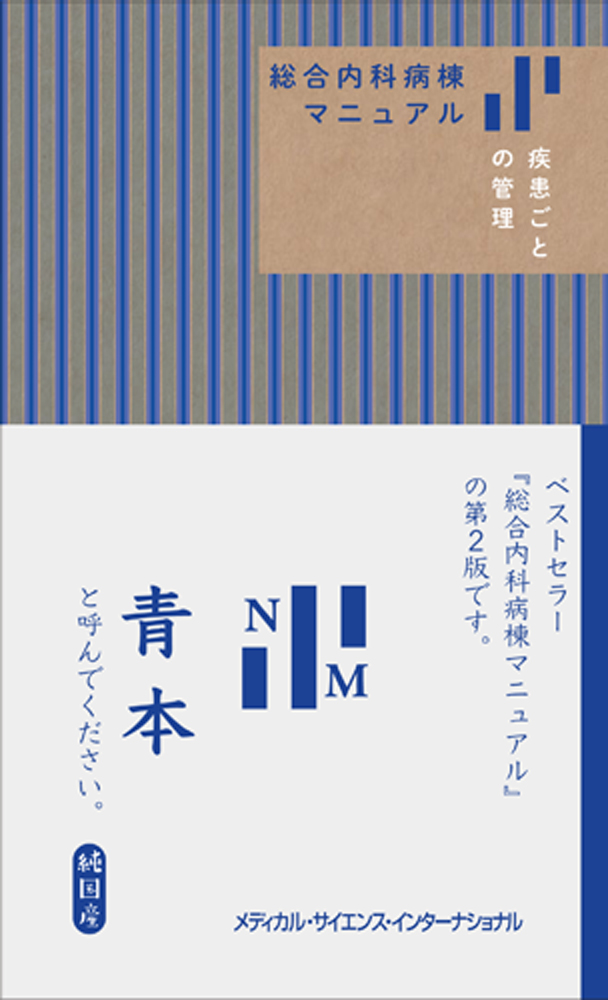
- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-
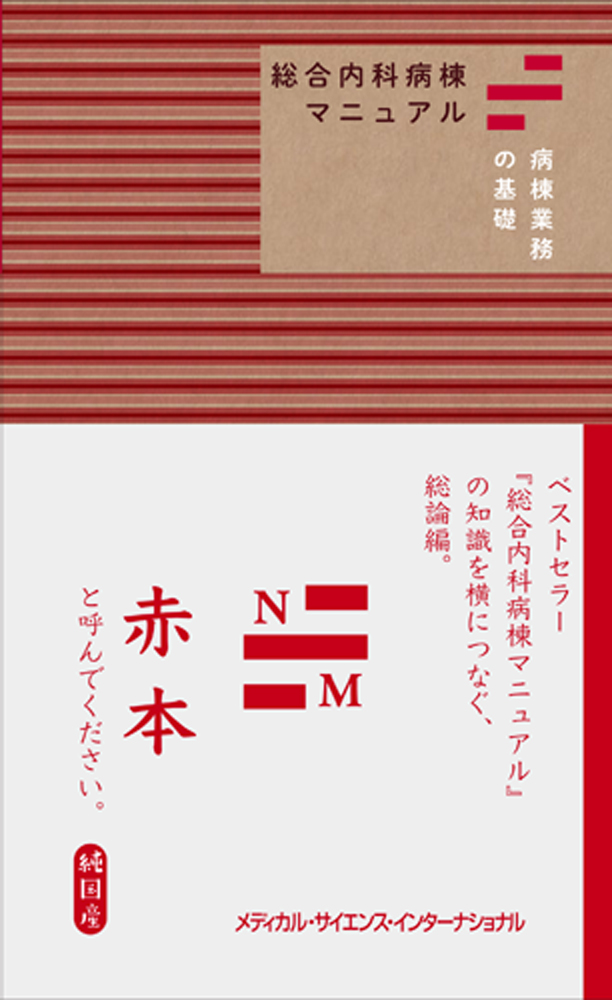
- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-
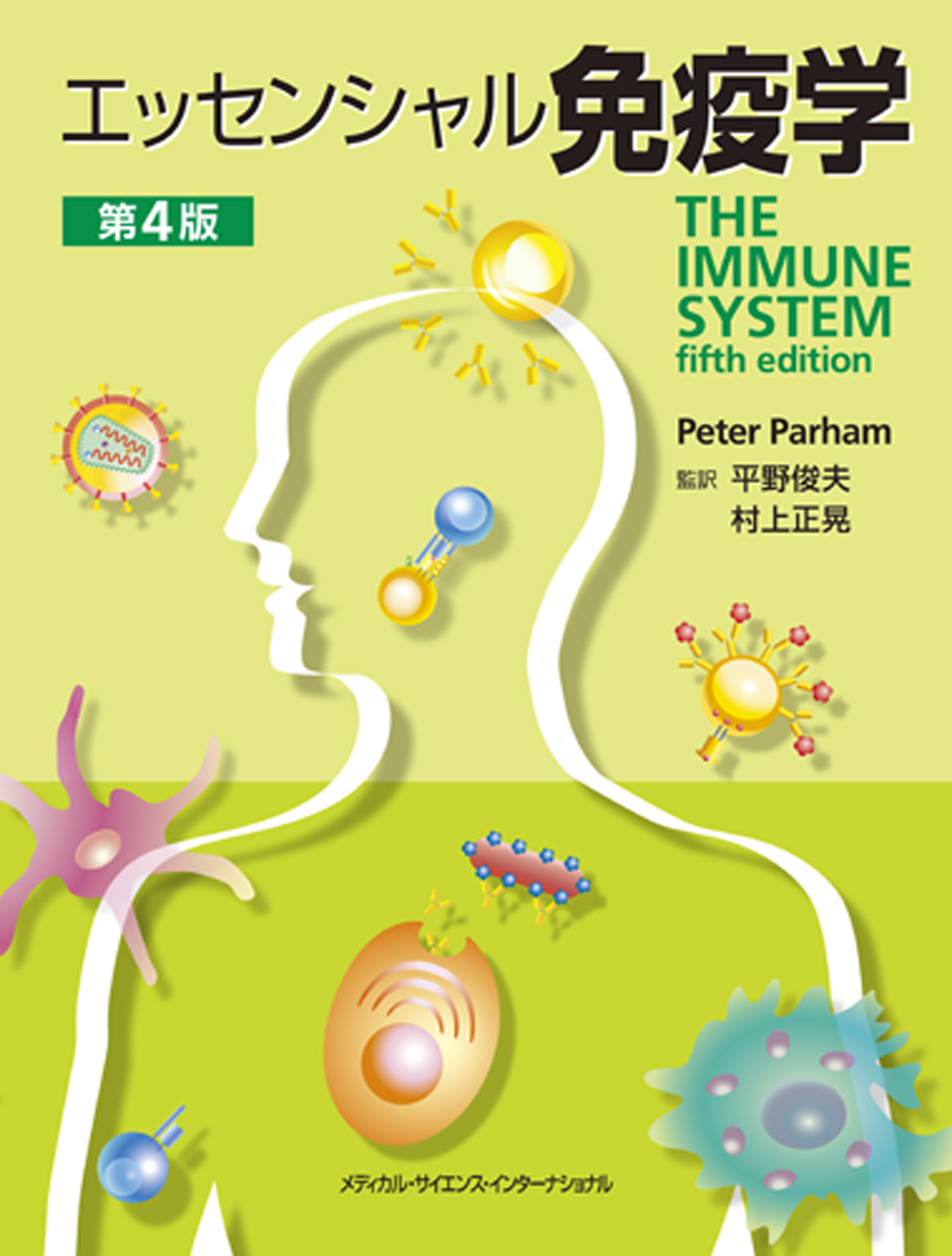
- エッセンシャル免疫学 第4版
- ¥7,150
-
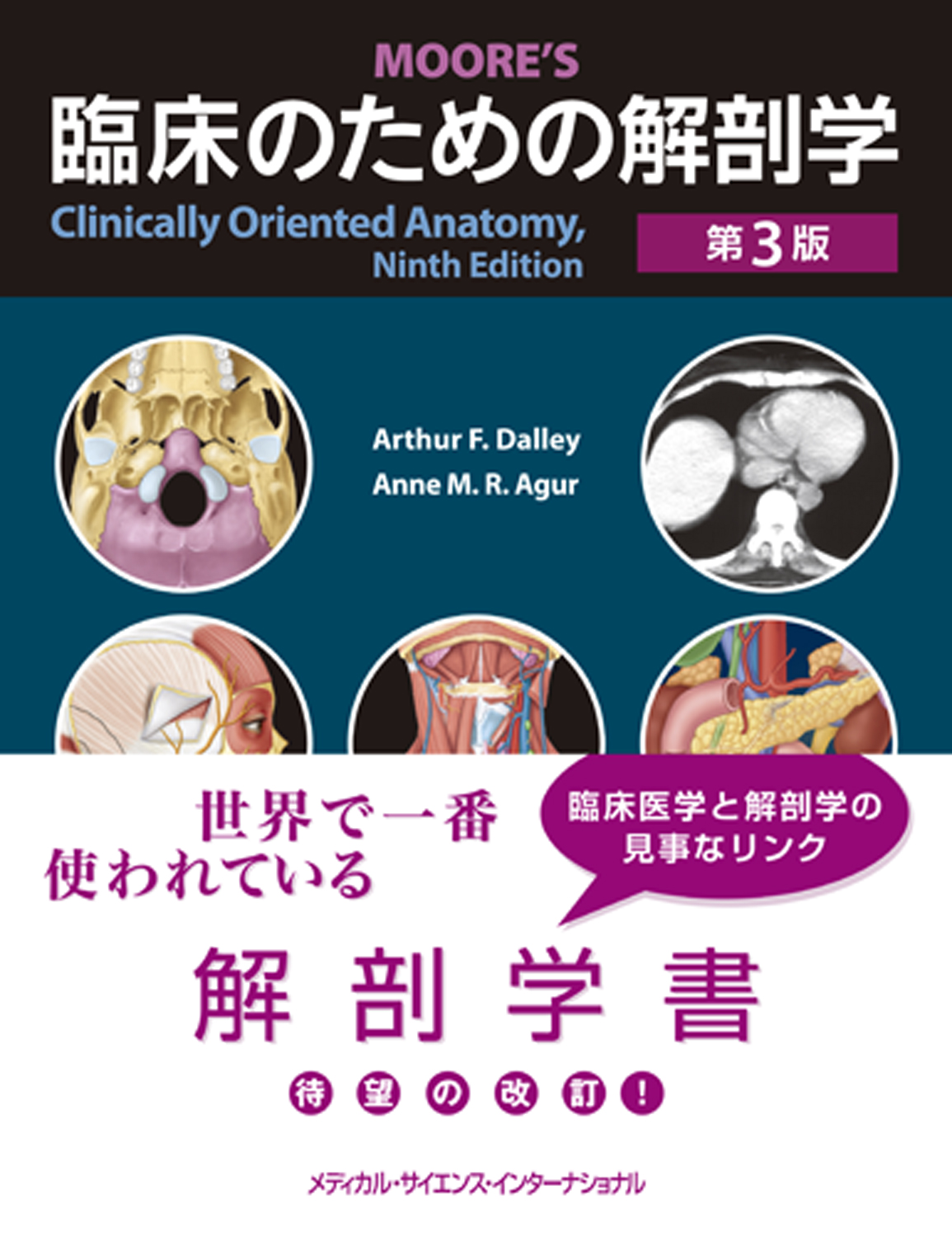
- 臨床のための解剖学 第3版
- ¥15,950
-
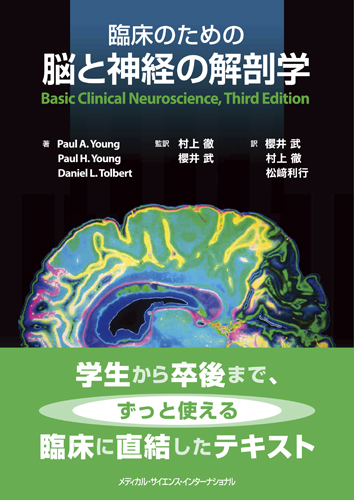
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-
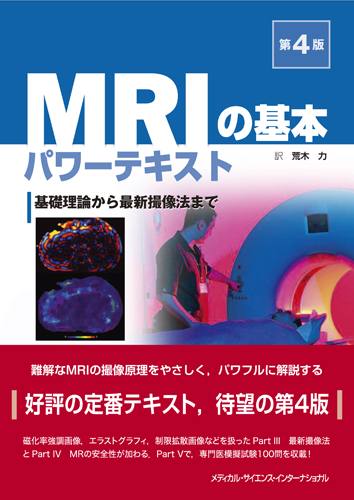
- MRIの基本パワーテキスト 第4版
- ¥7,150
-
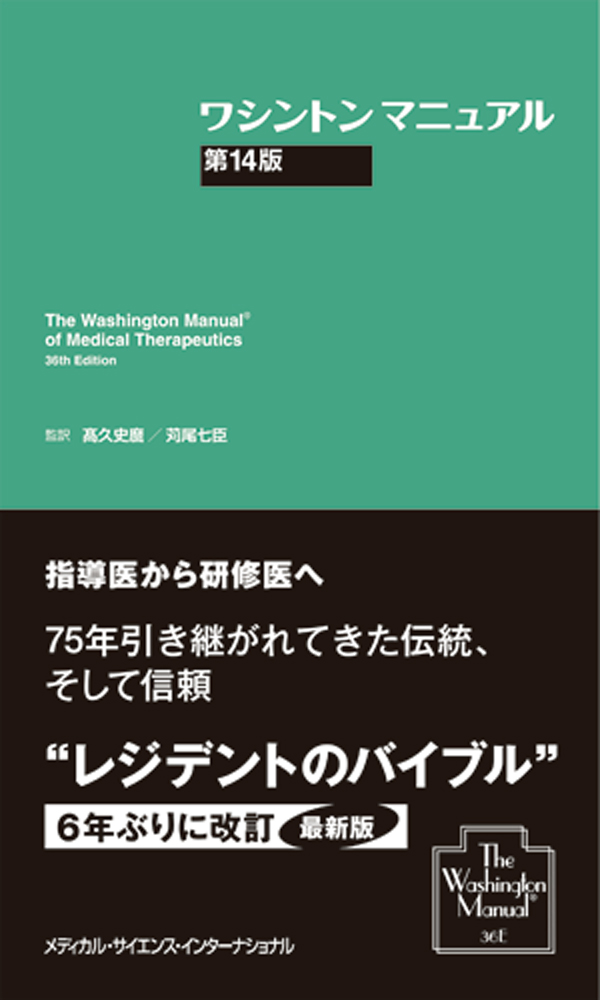
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-

- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-
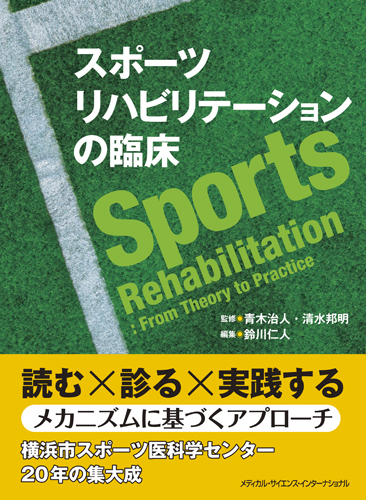
- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-
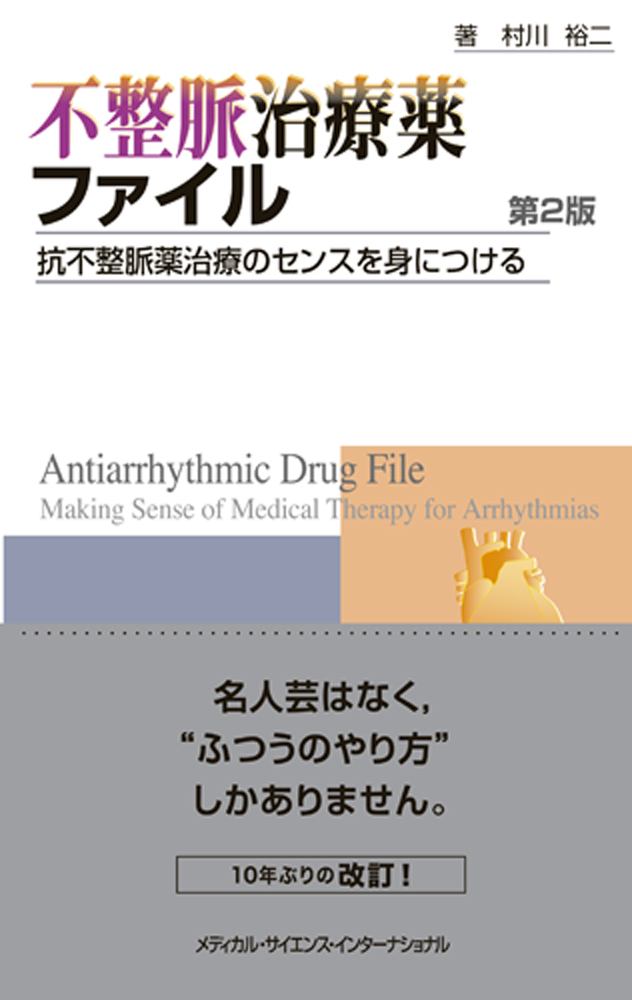
- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
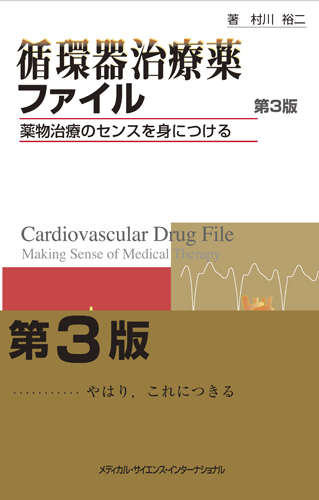
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-
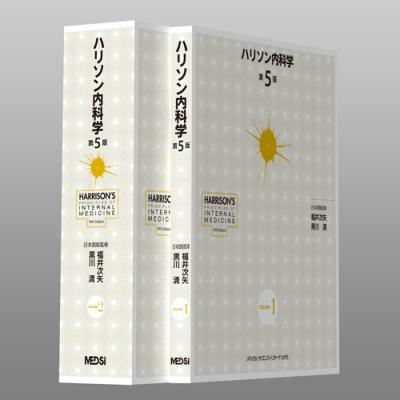
- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
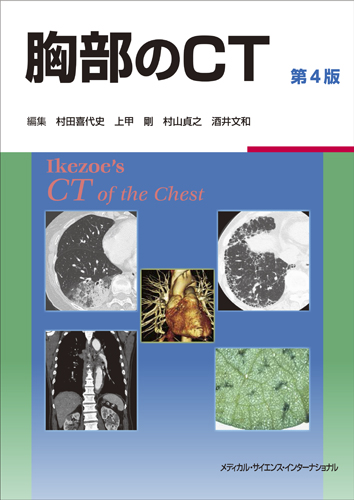
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
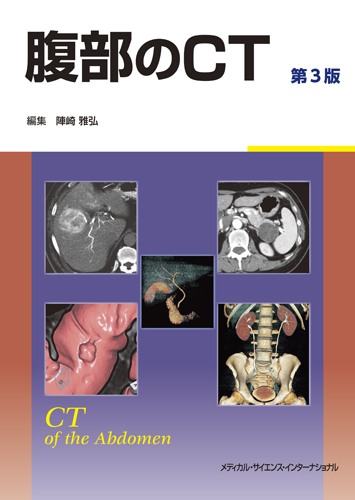
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
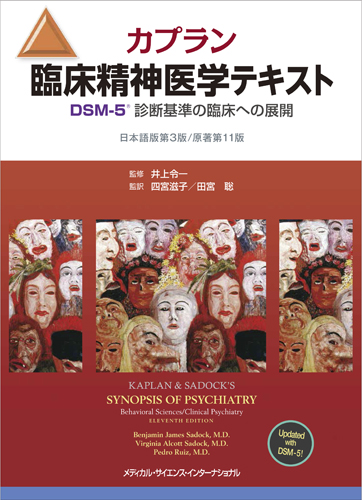
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000