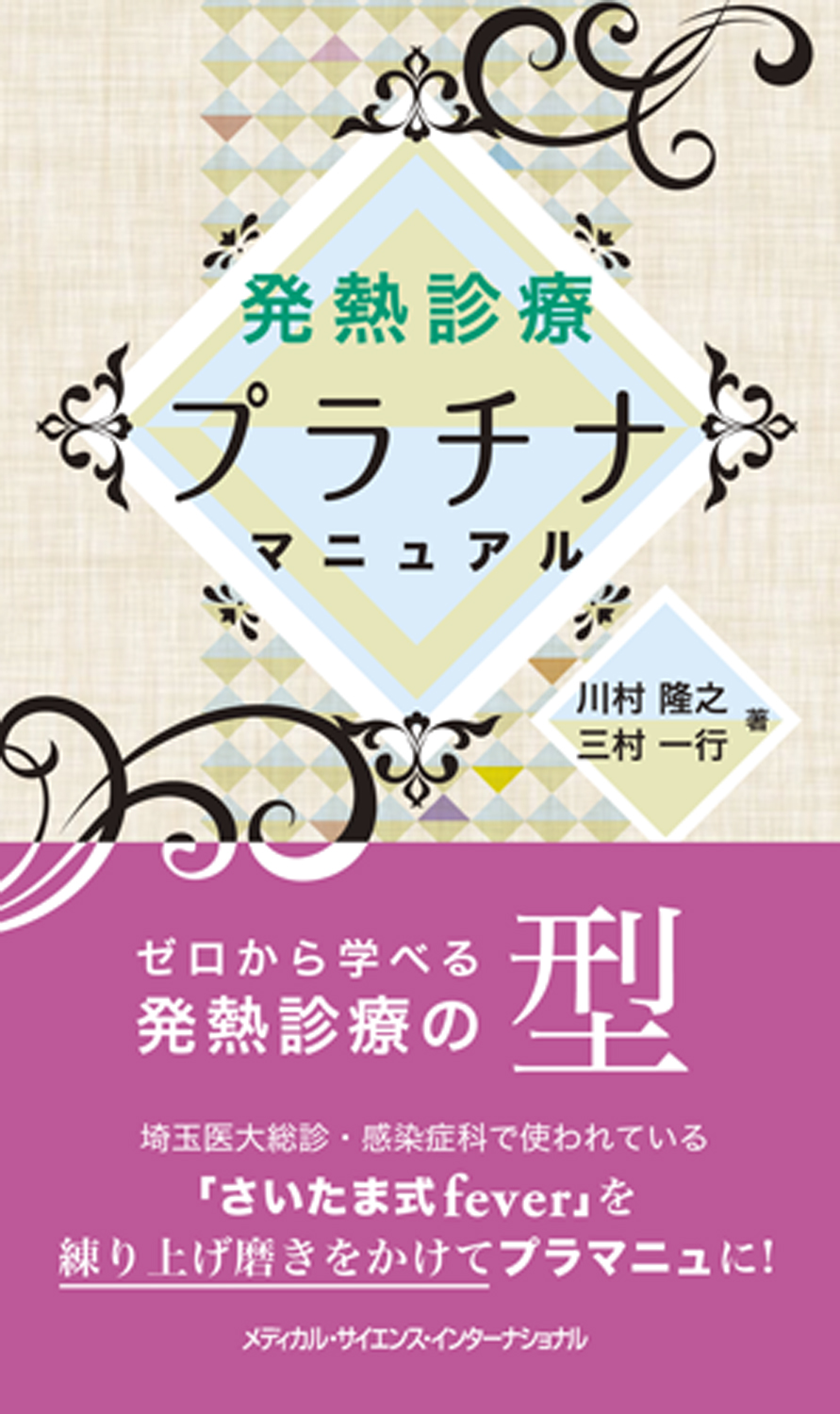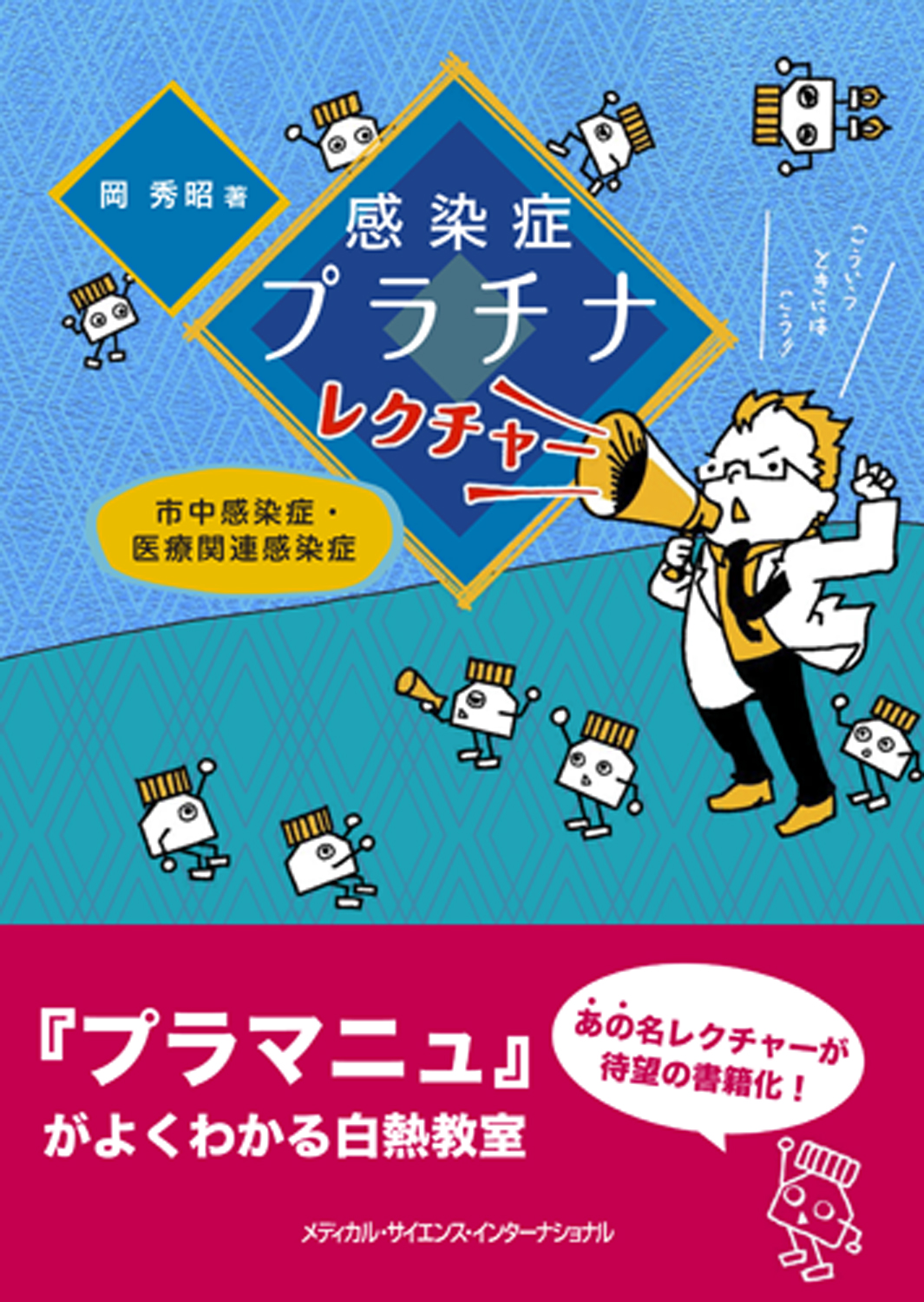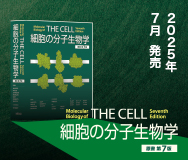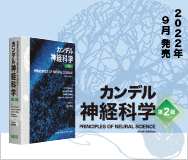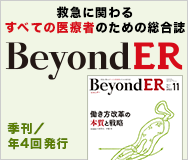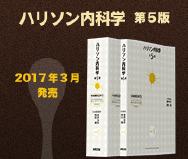発熱診療プラチナマニュアル
埼玉医大総診・感染症科で使われている
「さいたま式fever」をブラッシュアップ
ゼロから学べる,究極の発熱診療マニュアル,ここに誕生!!!
「発熱診療の型」をessentialな知見とともにsimpleに説明
埼玉医大総診・感染症科の「さいたま式fever」がブラッシュアップされて、プラチナシリーズに仲間入り。「誰でも、正しく」をモットーに、体系化された「発熱診療の型」を10章構成で解説。感染症診断に重点を置きつつ、悪性腫瘍や膠原病などの鑑別にも触れる。研修医や若手医師をはじめとした、内科系の医療従事者への実践的な指南書。
第1章 発熱診療のために必要な前提となる考え方1
■ ステップ1 発熱を認識して,発熱診療のスタートラインに立つ
◎炎症性マーカーの誤用を防ぐ3大原則
■ ステップ2 問診した患者の情報を客観化し,吟味する必要がある
◎問診を行う際の大原則
■ ステップ3 検査前確率,検査後確率の考え方を知る
◎発熱診療における検査の原則
■診断がつくための枠組みを理解する
■まとめ
第2章 さいたま式発熱診療7ステップ
●発熱診療7ステップ
◎鑑別が特殊になる可能性がある事項
■ ステップ1 まずは発熱していることを認識する
■ ステップ2 発熱が生じてからどれくらいの期間かを「急性」と「慢性」に区別する(時間因子を確認する)
◎症状の発症経過
◎発熱の発症経過で考えるべきこと
■ ステップ3 まれな感染症の鑑別のために,特別な曝露歴(患者背景)がないかを確認する
◎感染症の鑑別を挙げるために必須な特別な曝露歴=STAST
■ ステップ4 プラス α の症状を利用して炎症の首座を推定する
■ ステップ5 炎症の首座を特定する(身体診察と検査)
■ ステップ6 炎症の首座が単一の場合クラスター化を試みる
■ ステップ7 クラスター化ができない場合は「複数フォーカス型」「フォーカス不明型」の可能性を考える
■まとめ
第3章 診察の基本
◎診察の前の準備
◎基本的な感染対策
◎発熱患者に対する身体診察で大切なこと
◎ルーチンの身体診察
頭頸部(HEENT:頭,眼,耳,鼻,喉)/ 胸背部/ 腹部/ 四肢
■まとめ
第4章 鑑別のための患者背景の考え方
●特別な曝露歴の考え方と鑑別
■(1)sick contact
■(2)Tb contact
■(3)animal contact
◎問診で確認したい事項
■(4)sex contact
■(5)travel contact
◎travel contact に関する問診事項
■(6)その他の問診事項
■まとめ
第5章 特殊な状況における鑑別
■(1)フォーカス不明な急性発熱
-◎フォーカス不明になりやすい感染症BIG 8
◎フォーカス不明型発熱をきたす感染症を考慮した場合の検査セット
■(2)入院中の発熱(院内発熱)
■(3)透析患者の発熱
■(4)免疫不全者関連の不明熱
■(5)悪性腫瘍患者の発熱
■(6)古典的不明熱(継続する慢性発熱)と再発性不明熱( 増悪と寛解を繰り返す慢性発熱)
第6章 感染症判断基準
●急性上気道炎
●急性副鼻腔炎
●急性中耳炎
●急性咽頭炎
●急性気管支炎
●急性肺炎
●急性腸炎
●急性胆管炎
●急性胆囊炎
●尿路に関する感染症~腎盂腎炎
●下部尿路に関する感染症
●骨盤内炎症性疾患(PID)
●軟部組織感染症
●化膿性関節炎
●骨髄炎
●感染性心内膜炎(IE)
●カテーテル関連血流感染症(CRBSI)
●髄膜炎
●細菌性腹膜炎
■まとめ
第7章 クラスター分類
◎副鼻腔炎クラスター:フォーカスが副鼻腔の炎症である
◎中耳炎クラスター:フォーカスが中耳である
◎咽頭炎クラスター:フォーカスが咽頭である
◎気管支炎クラスター:呼吸器系にフォーカスがあるが,胸部X線,胸部CTで陰影がない状態
◎肺炎クラスター:臨床的に肺炎の可能性がある患者に,胸部画像(胸部X線,CT)で陰影がある状態
◎腸炎クラスター:吐き気・腹痛・発熱などを伴う下痢症(1日3行以上の排便)
◎肝・胆道系酵素機能異常クラスター:血液検査で明らかな肝・胆道系酵素機能障害があり,他にフォーカスがない場合
◎膀胱炎クラスター:排尿時のX(例:違和感,疼痛など)を呈する状態
◎古典的腎盂腎炎クラスター:側腹部の疼痛+CVA 叩打痛+発熱を呈する状態
◎蜂窩織炎クラスター:皮膚に局所的な炎症所見がある
◎中毒疹クラスター:SFTS はフォーカス不明のくくりへ,肺炎球菌は関節炎のくくりへ
◎筋炎クラスター
◎関節炎/ 関節周囲炎クラスター
◎骨髄炎クラスター:MRI で骨髄に病変を認める
◎髄膜炎クラスター
◎脳炎クラスター:脳炎症状(意識障害,性格変容,神経障害など)があり,頭部MRIで脳炎を示唆する所見がある
◎腹膜炎クラスター:腹膜が炎症の首座と思われる場合
◎リンパ節腫脹クラスター:フォーカスとしてリンパ節腫脹がメイン症状の場合
◎ブドウ膜炎クラスター
■まとめ
第8章 複数フォーカス型になる疾患
◎大血管炎:「古典的不明熱」+「四肢の跛行/多臓器障害/ フォーカス不明」の状態
◎中血管炎:多臓器の炎症所見を認める古典的不明熱
◎小血管炎
◎成人Still病
◎SLE(全身性エリテマトーデス)
◎血栓性微小血管症(TMA)
◎炎症性病変が多発している状態
第9章 時系列に沿ったアプローチ
◎発熱2週目までに見逃したくない病態
■ 1 発熱1週目(day 0~7):Critical,Commonな疾患を見逃さない
◎Criticalな疾患
◎Commonな疾患(非感染症含む)
■ 2 発熱2週目(day 8~14):敗血症くずれ(フォーカス不明型発熱をきたす感染症)を見逃さない
◎フォーカス不明型発熱になる要因
◎フォーカス不明型発熱をきたす感染症を考慮した場合の検査セット
■ 3 発熱3週目(day 15~21):敗血症くずれを考慮しつつ不明熱としての対応を開始する
◎不明熱時ルーチンワーク 199
■ 4 発熱4週目(day 22~):不明熱として対応する
◎古典的不明熱
◎不明熱の分類と定義
◎発熱様式
◎有熱期にCRP陰性の場合の鑑別疾患
■まとめ
第10章 各論ひとくち解説
◎副鼻腔炎クラスター
侵襲性真菌性副鼻腔炎
◎咽頭炎クラスター
扁桃周囲膿瘍,咽後膿瘍/ Lemierre 症候群/ Lugwig-angina / 急性喉頭蓋炎/ 亜急性甲状腺炎/ 化膿性甲状腺炎/ Basedow病
◎腸炎クラスター
顕微鏡的腸炎/ Whipple病/ アミロイドーシス/ セリアック病
◎肝炎クラスター
循環血漿量に関連した肝機能障害/ 肝梗塞/ α1-アンチトリプシン欠乏症(AAT 欠乏症)/ Wilson 病/ ヘモクロマトーシス/ 自己免疫性肝炎(AIH)/Budd-Chiari 症候群(肝内静脈,肝に流入する上/ 下大静脈の血栓症)/薬剤性肝障害(DILI)/ 妊娠性急性脂肪肝(AFLP)/ 肝類洞閉塞症候群(SOS)/ アルコール関連肝炎/ MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)
◎胆管炎クラスター
原発性硬化性胆管炎(PSC)/ 原発性胆汁性胆管炎(PBC)/ 肝移植後の虚血性胆管症/ AIDS 胆管炎/ 胆管炎クラスターになる寄生虫感染症
◎膀胱炎クラスター
泌尿器系結核(腎結核,膀胱結核)/ 出血性膀胱炎/ 膀胱がんに対するBCG 注入療法による局所感染合併症/ 気腫性膀胱炎/ ビルハルツ住血吸虫症/ 腟炎
◎古典的腎盂腎炎クラスター
急性巣状細菌性腎炎(AFBN)/ 腎膿瘍/ 気腫性腎盂腎炎/ 腎囊胞感染/腎細胞がん/ 腎梗塞/ 黄色肉芽腫性腎盂腎炎/ 腎マラコプラキア
◎蜂窩織炎クラスター
壊死性軟部組織感染/ 伝染性膿痂疹/ 帯状疱疹/ ライム病/ 豚丹毒/血管内の異常/ 薬疹/ 結節性紅斑(EN)/ アトピー性皮膚炎(湿疹)/ 接触性皮膚炎/ 虫咬傷/ カルシフィラキシス/ 肢端紅痛症/ Sweet病/ 好酸球性蜂窩織炎
◎中毒疹クラスター
侵襲性髄膜炎菌感染/ リケッチア症(日本紅斑熱,ツツガムシ病,その他リケッチア症)/ トキシックショック症候群
◎筋炎クラスター
化膿性筋炎/ ウイルス性筋炎/ 旋毛虫症/ 皮膚筋炎/ 封入体筋炎/ 薬剤性ミオパチー/ 免疫介在性壊死性ミオパチー
◎関節炎/ 関節周囲炎クラスター
ウイルス性関節炎/ 侵襲性肺炎球菌感染/ 関節リウマチ/ RS3PE(remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema syndrome)/リウマチ熱/ 脊椎関節炎/ SAPHO 症候群/ 結晶誘発性関節炎/ リウマチ性多発筋痛症(PMR)/ 化膿性滑液包炎/ 石灰沈着性腱炎/播種性淋菌症
◎骨髄炎クラスター
Langerhans 細胞組織球症/ 慢性非細菌性骨髄炎(CNO)
◎髄膜炎クラスター
ウイルス性髄膜炎/ リステリア脳髄膜炎/ 結核性髄膜炎/ クリプトコッカス脳髄膜炎/ 寄生虫による好酸球性髄膜炎/ 神経梅毒/ 原発性中枢神経系リンパ腫(PCNSL)/ 薬剤性髄膜炎 / 再発性髄膜炎( Mollaret 髄膜炎)/ 原発性中枢神経系血管炎(PACNS)
◎脳炎クラスター
単純ヘルペス性脳炎/ 脳トキソプラズマ症/ 進行性多巣性白質脳症(PML)/ 節足動物媒介性脳炎/ 囊虫症/ ニパウイルス感染/ リッサウイルス感染(狂犬病など)/ マラリア/ ヒトアフリカトリパノソーマ病/ 自由生活性アメーバーによる脳炎/ Creutzfeldt-Jakob 病/ 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)/ 自己免疫性脳炎
◎腹膜炎クラスター
腹膜透析関連腹膜炎/ 感染性膵壊死(急性膵炎)
◎リンパ節腫脹クラスター
伝染性単核球症(EBV 感染)/ 急性トキソプラズマ症(リンパ節腫脹クラスター)/ 慢性活動性EBV 感染症(CAEBV)/ 菊池病/ 悪性リンパ腫/ 免疫不全に伴うリンパ増殖性疾患/ PFAPA / 川崎病/ 木村病/ Rosai-Dorfman病/ Castleman病
◎ブドウ膜炎クラスター
Vogt─小柳─原田病/ TINU症候群
◎院内不明熱を呈する疾患
CDAD(CD 腸炎)/ 血腫吸収熱/ 無石性胆囊炎/ 薬剤熱とその類縁疾患
◎炎症性塞栓クラスターを呈する疾患
コレステロール塞栓症/ 左房粘液腫
◎血栓性微小血管症(TMA)を呈する疾患
TTP(血栓性血小板減少性紫斑病)/ 志賀毒素媒介性溶血性尿毒症症候群(ST-HUS)/ HELLP症候群
◎CRP 陰性の不明熱を呈する疾患
高体温/ 機能性高体温症
◎炎症性病変が多発している場合
サルコイドーシス/ サルコイド反応/ 粟粒結核,播種性NTM(非結核性抗酸菌)症/ IgG4 関連疾患/ Sjögren 症候群/ 再発性多発性軟骨炎/VEXAS 症候群/ 炎症性偽腫瘍(炎症性筋線維芽細胞性腫瘍)
参考文献
索引
皆さん,こんにちは。埼玉医科大学総合医療センター感染症科・感染制御科の川村隆之と申します。この度は,本書を手に取っていただき,感謝申しあげます。
これまで発熱・不明熱系統の医学書は数多く出版されていますが,発熱初心者の方が,ゼロから学ぶことができる本は少ないのではないかと思います。私自身も,研修医のころから,発熱や感染症に興味をもち,既存の教科書を読み漁りましたが,最終的には「発熱診療って,結局検査ベースにやるしかないのでは?」と誤った結論にたどり着いてしまいました。
埼玉医科大学総合医療センターに赴任したのは2019 年でしたが,この「検査ベースの発熱診療」を行っていたところ,私の上司である岡秀昭先生から「検査前確率を無視したアプローチは感心しない」と指導いただいたことをよく覚えています。高名な先生がおっしゃるのだから間違いないと考え,さらに教科書や総説を読み込み,現在の発熱診療の型にたどり着くことができました(まだ高みにはたどり着いていませんが)。
発熱診療には体系化された型があり,それを学べば,ある程度の再現度をもって診療を行うことが可能です。しかし,この分野が苦手な研修医・専門医の先生たちとディスカッションしていると,その「体系化された型」が抜け落ちていると感じます。そこで,院内向けに私が作成したものが「さいたま式fever」という怪しいタイトルのマニュアルです。
難しい不明熱の症例を含め,発熱患者はすべての医師が遭遇すると思います。しかし,発熱診療全般にただよう「選ばれた者しか,きちんと発熱診療をこなすことはできない」という風潮はよくないと思います。そこで「さいたま式fever」では「誰でも,正しく」をモットーに作成し,院内ではそれなりに好評を得ることができました。
幸運なことに,この「さいたま式fever」が岡秀昭先生の目に留まり,書籍化を勧めていただいたことが,本書作成のきっかけになりました。「さいたま式fever」はよくも悪くも「適当」なつくりであり,さすがにそのまま世に出すのは憚られました。そこで,本書作成に際して,私が普段から信頼している,当院総合診療内科・感染症科の三村一行先生にご協力いただき,ブラッシュアップすることができました。
本書では,発熱診療をステップに分け,正確な鑑別を挙げるための方法論を記載しています。また,発熱診療で最も皆さんが遭遇する疾患は「感染症」ですので,感染症の診断についても,詳細に記載しています。発熱の鑑別は,感染症・悪性腫瘍・膠原病など多岐にわたりますが,まずは感染症を明確に区別することが最重要です。また,本書を作成するときに最も注意したこととして,疾患の各論解説です。発熱系統の教科書に記載されている鑑別をみて「この疾患,聞いたことないんだけど,何??」という気持ちになったことはないでしょうか。本書では,なるべく,そのようなモヤモヤした気持ちにならないように,疾患の各論解説を簡単に行っています(すべての発熱疾患が網羅されているわけではありませんが…)。感染症専門医が膠原病などの疾患解説を行うことには違和感を感じると思いますが,診断について留意すべきことについて記載いたしました。
本書が学習者の学びになればとてもうれしいです。また本書は,あの偉大な『感染症プラチナマニュアル』と同様,「プラチナマニュアル」の名を冠しています。今はまだ,虎の威を借る狐の状態ですが,本書が偉大な先輩と同様,「発熱で困ったらとりあえず,プラチナマニュアルをみてみるか」といわれるような代物になれば幸いです。
最後に,本書の作成に当たり,辛抱強くおつきあいいただいたメディカル・サイエンス・インターナショナルの佐々木由紀子氏,不器用な私をいつも温かく応援してくれる共著者の三村一行先生,私のエネルギー源となっている妻や子どもたちには深く感謝申しあげます。
2025 年7 月
川村 隆之
皆さん,こんにちは。埼玉医科大学総合医療センター総合診療内科/ 感染症科・感染制御科で副診療部長兼教育主任をしております三村一行と申します。
この本は,当院の感染症科・感染制御科で勤務している川村隆之先生が,当院の初期研修医や内科専攻医の先生達向けに作成した,「さいたま式 Fever」という発熱患者に対する基本的なアプローチをまとめたマニュアルをもとに作成されました。
川村先生と最初に出会ったのは,私が埼玉医科大学総合医療センターに着任した2019 年4 月でした。川村先生も富山大学附属病院から同時に着任されたことがきっかけです。そして,川村先生と一緒に働くなかで私が最初に抱いた印象は,「若い世代からすごい人が出てきたな」というものでした。
それは,川村先生が感染症や発熱診療が大好きであり,これらの分野に関して自分が何を知らないのか,また何を知るべきなのかを理解するために,さまざまな二次資料や医学書籍などを読み漁りながら日々自己研鑽に励む姿や,自分が学んだことを,まだ感染症や発熱診療が得意ではない若手医師たちに対して理解できるまでていねいに説明する,労を惜しまない親切心を身近で見てきたからです。
川村先生のこれまでの努力する姿を上司かつ同僚として見てきた印象としては,彼自身は決して器用なほうではありません。しかし,私が思う川村先生の際立った個性は,自分自身が器用ではないことや,自分の立ち位置が感染症専門医という内科系専門医のなかでは少数派であることを自覚したうえで,多数派である感染症以外の専門医や専門医を目指す若手医師たちに対し決して背を向けることなくまっすぐに自分の考えを伝え,自分の手元へ手繰り寄せようと努力する点にあると思っています。そのような姿を日々拝見し,同じ感染症専門医としてオープンマインドな少数派でいたいと常々思っていた私は,すぐに川村先生のファンになりました。
本書は,川村先生が日々の自己研鑽,トライ&エラーを繰り返しながら得た発熱診療において,理解しておくべき必要不可欠(essential)な知見を手抜きなくできる限りsimple に,でもeasy にはならないよう,自分自身が納得できる内容を一生懸命説明したものとなっています。川村先生と一緒に本書を作るなかで,最初にできあがった原稿を読むことができたことは,川村先生のいちファンとしては幸甚の極みでした。
この本が,日々発熱診療や感染症診療に悪戦苦闘している若手医師やプライマリケアに携わっている先生方,抗菌薬適正使用支援チーム(antimicrobial stewardship team:AST)で活動されている医師やメディカル・スタッフ(看護師,薬剤師,臨床検査技師)などの皆様の一助となり,また,本書を偶然手に取った方が,川村先生や私のように発熱診療や感染症診療が面白いと感じるきっかけになれば望外の喜びです。
最後になりましたが,ご多用のなか,一緒に執筆活動を行っていただきました川村隆之先生に心より感謝申しあげます。
また,編集の労をとって下さいましたメディカル・サイエンス・インターナショナルの佐々木由紀子さんの多大なる御尽力と雅量にも改めて御礼申しあげます。
2025 年7 月
三村 一行
-
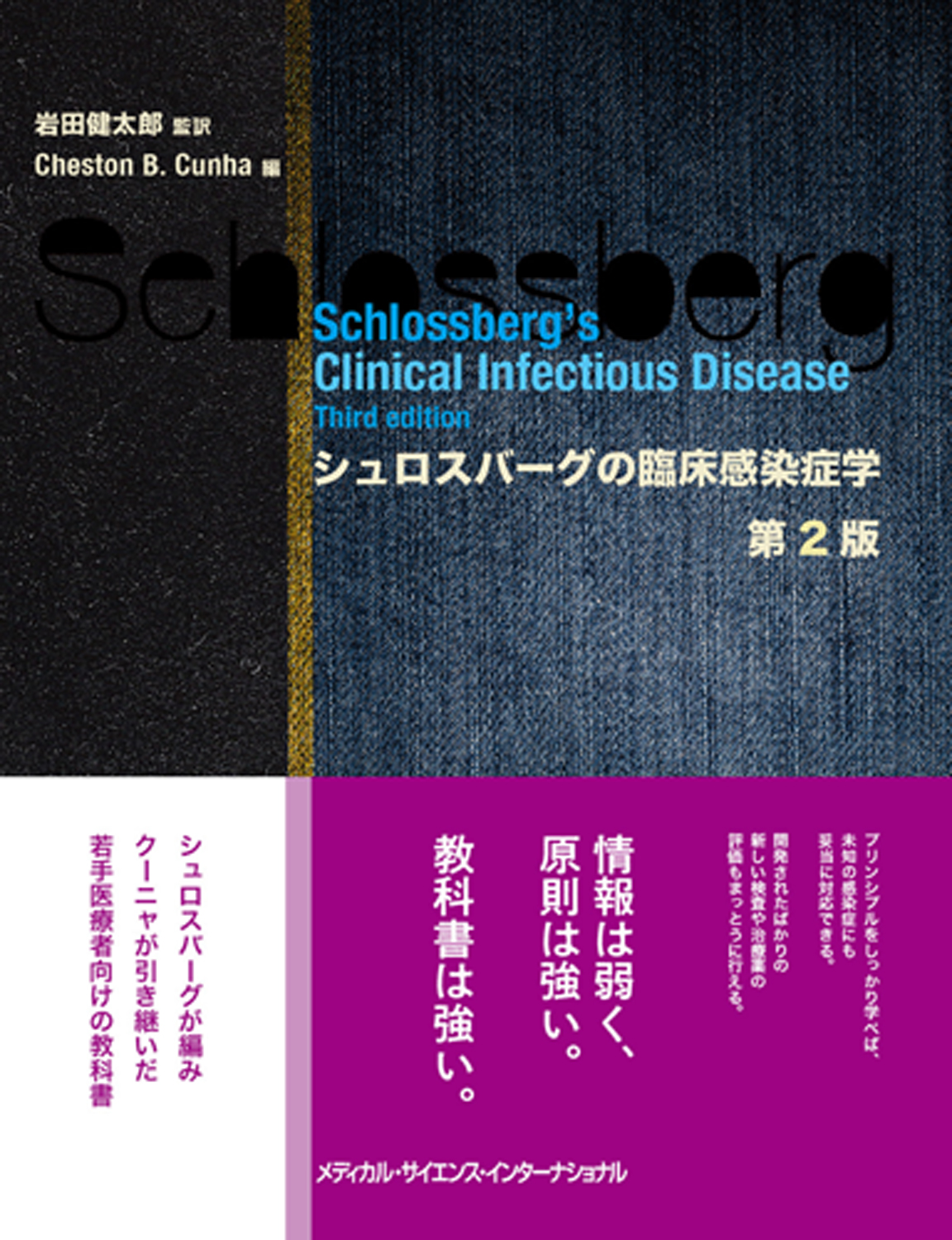
- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版
- ¥25,850
-
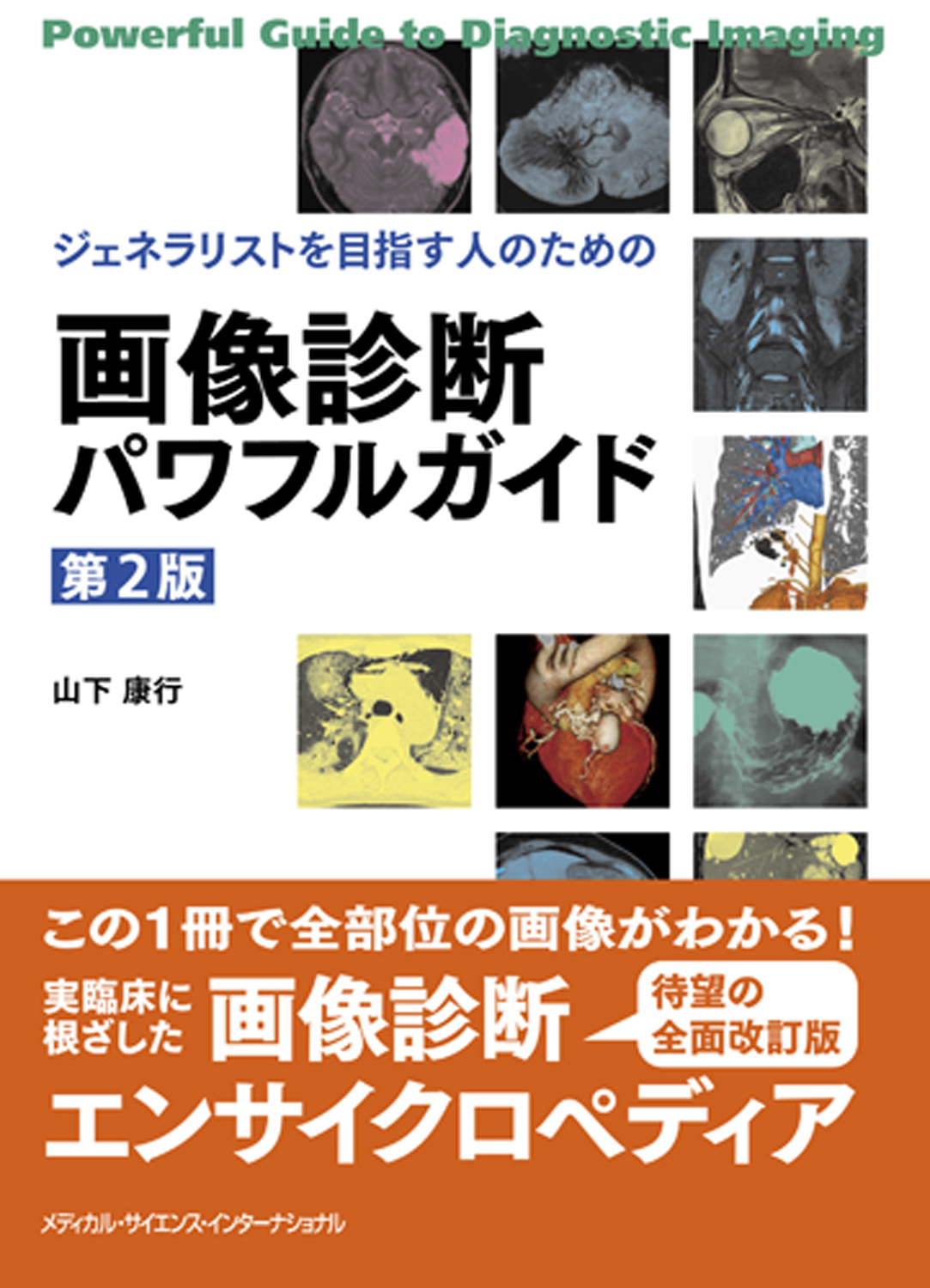
- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版
- ¥12,100
-
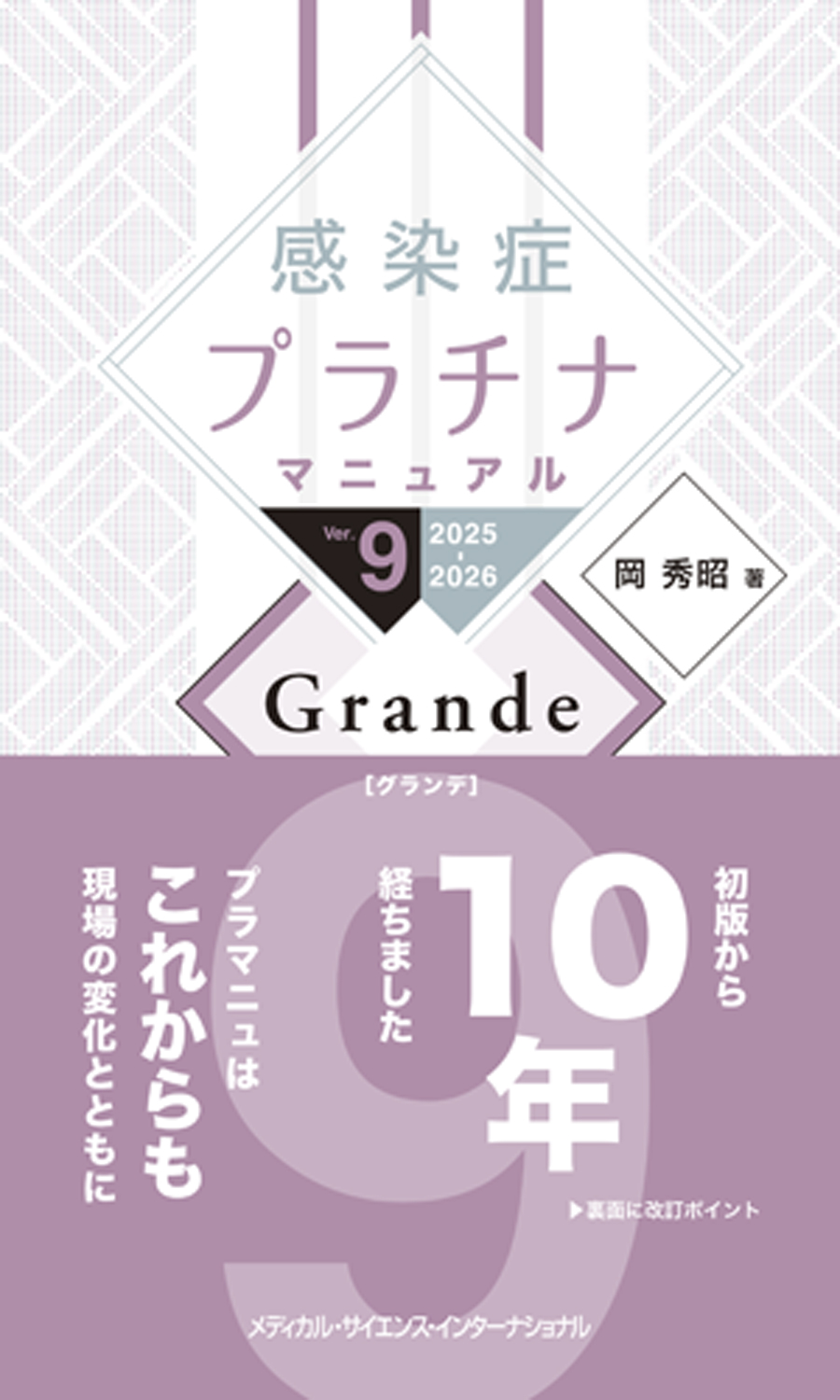
- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande
- ¥4,180
-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版
- ¥8,250
-
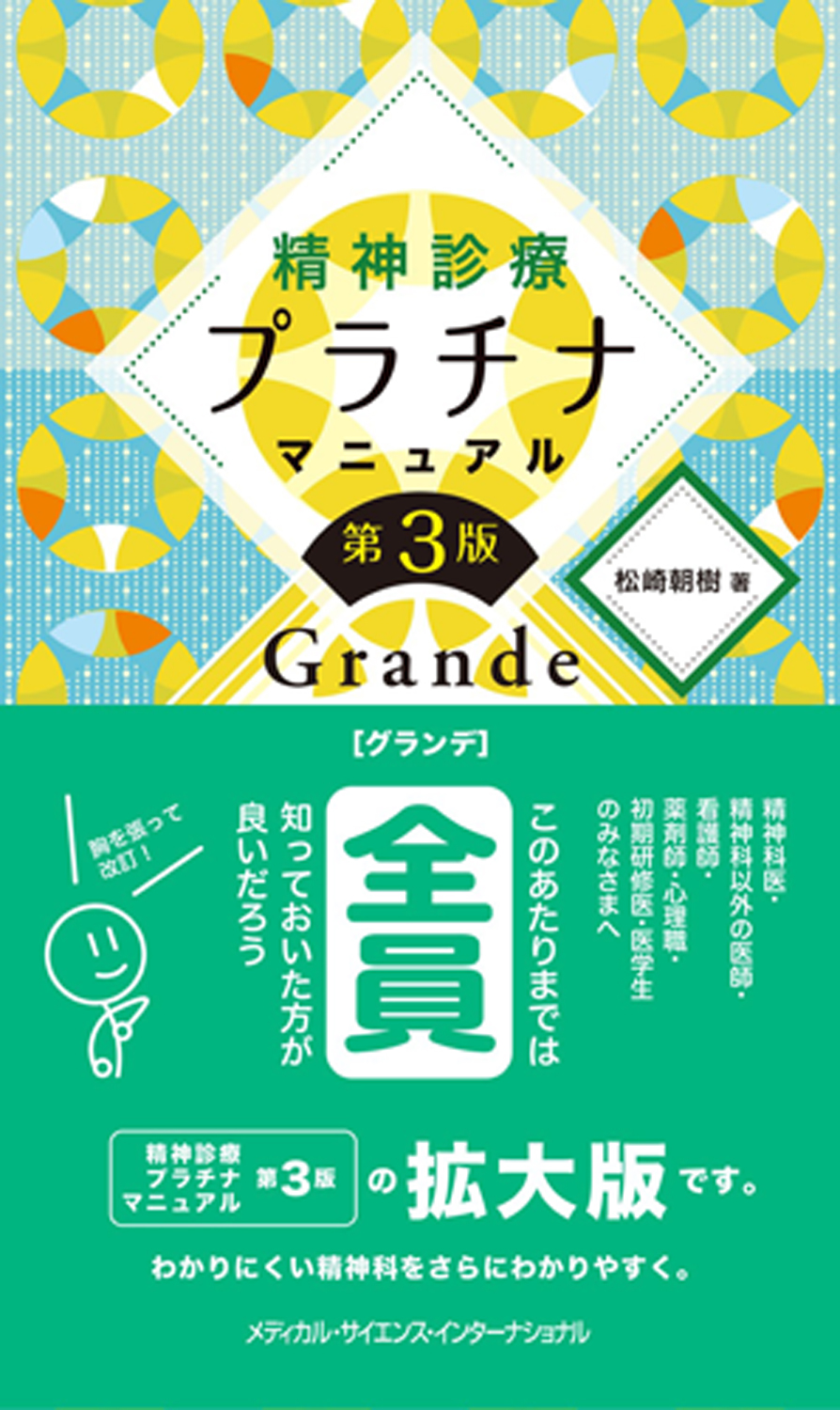
- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版
- ¥3,960
-
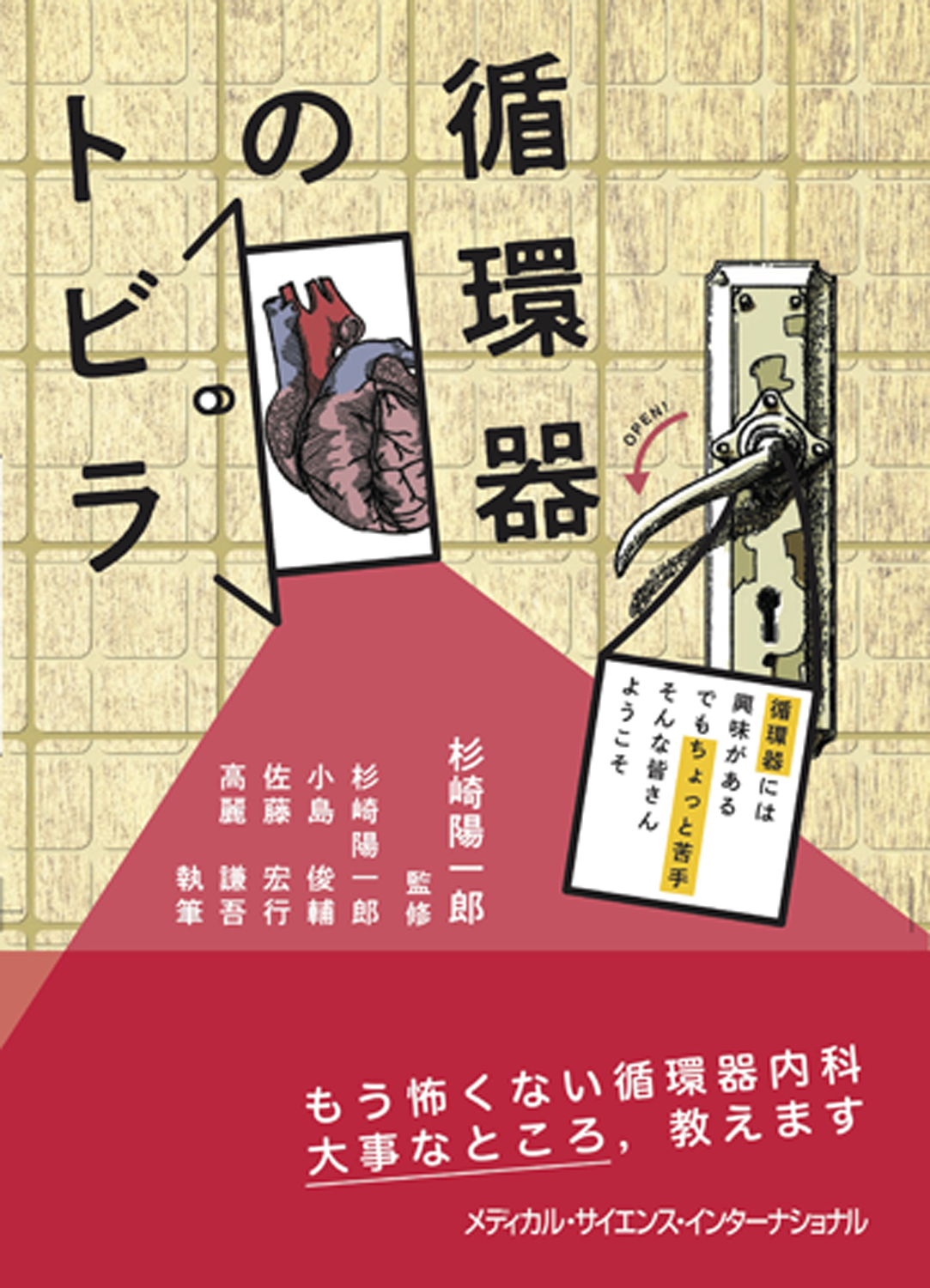
- 循環器のトビラ
- ¥5,940
-
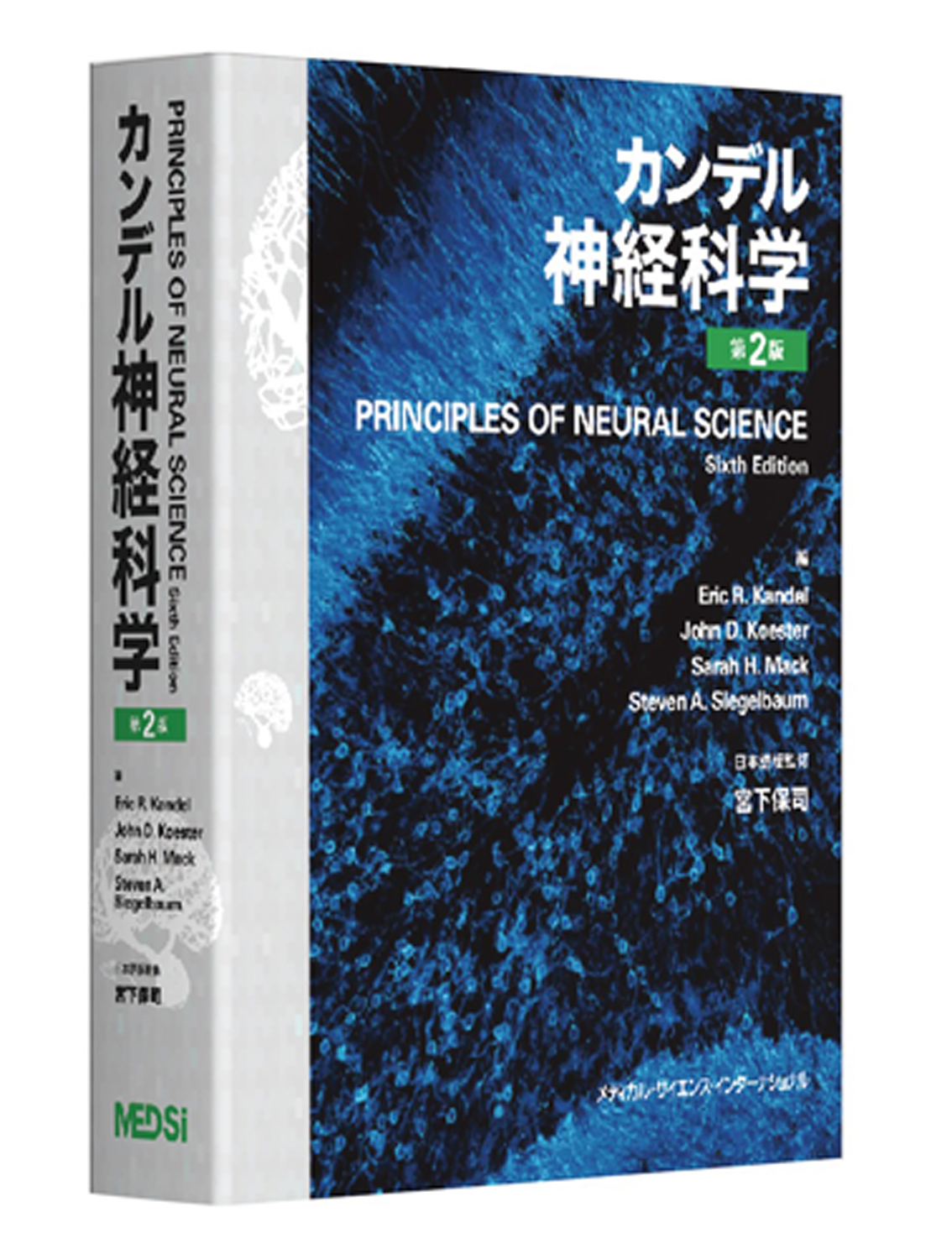
- カンデル神経科学 第2版
- ¥15,950
-
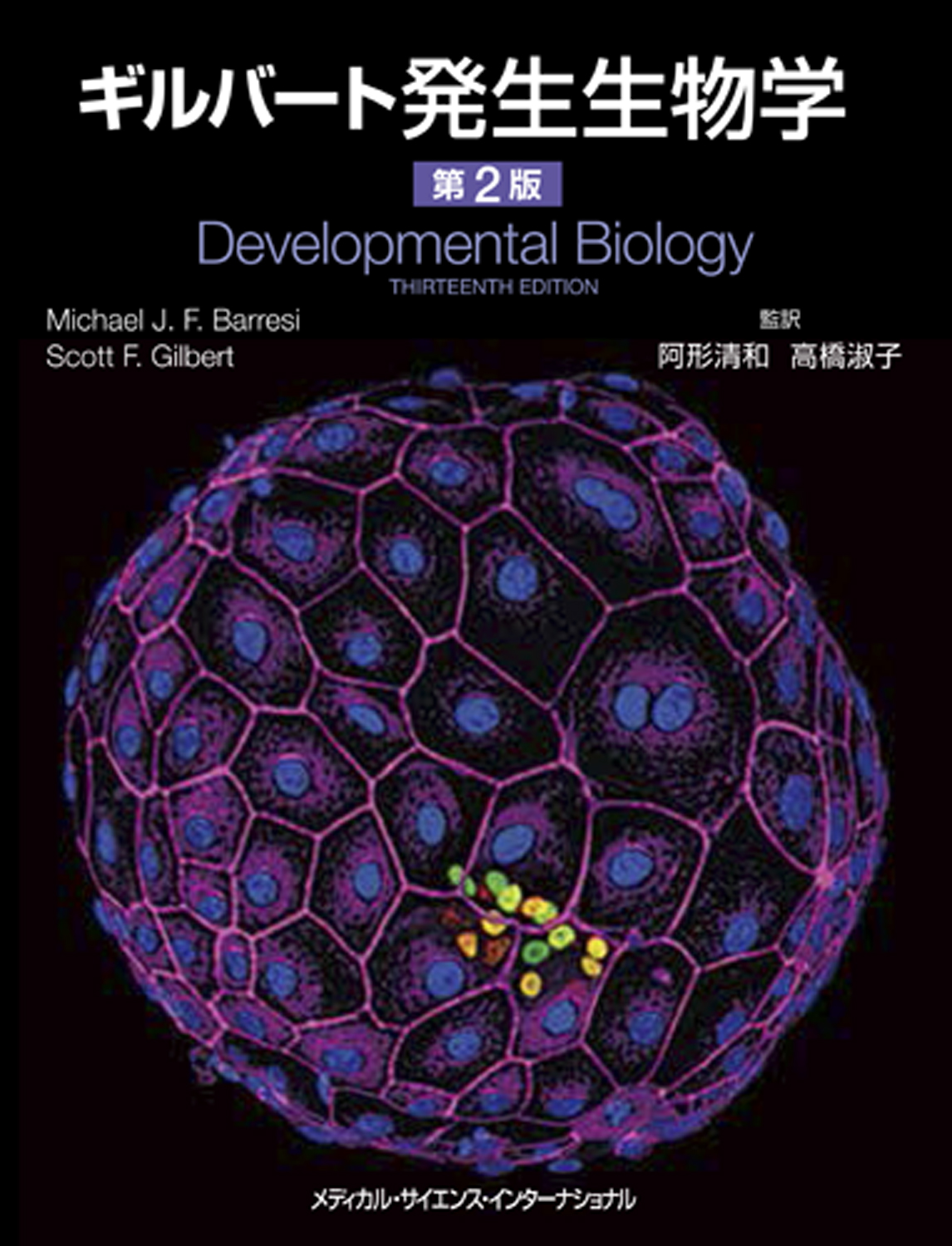
- ギルバート発生生物学 第2版
- ¥13,750
-
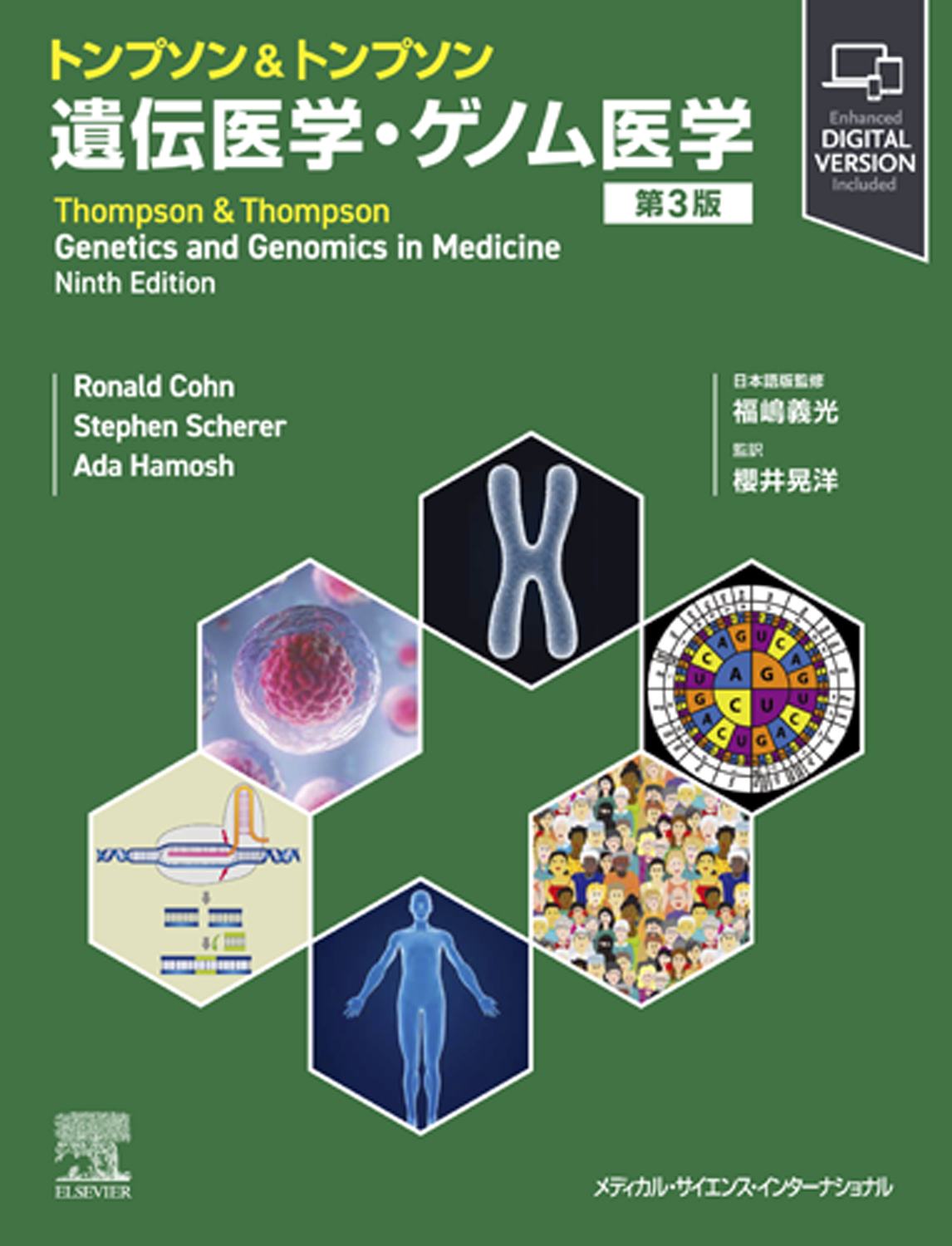
- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版
- ¥12,100
-
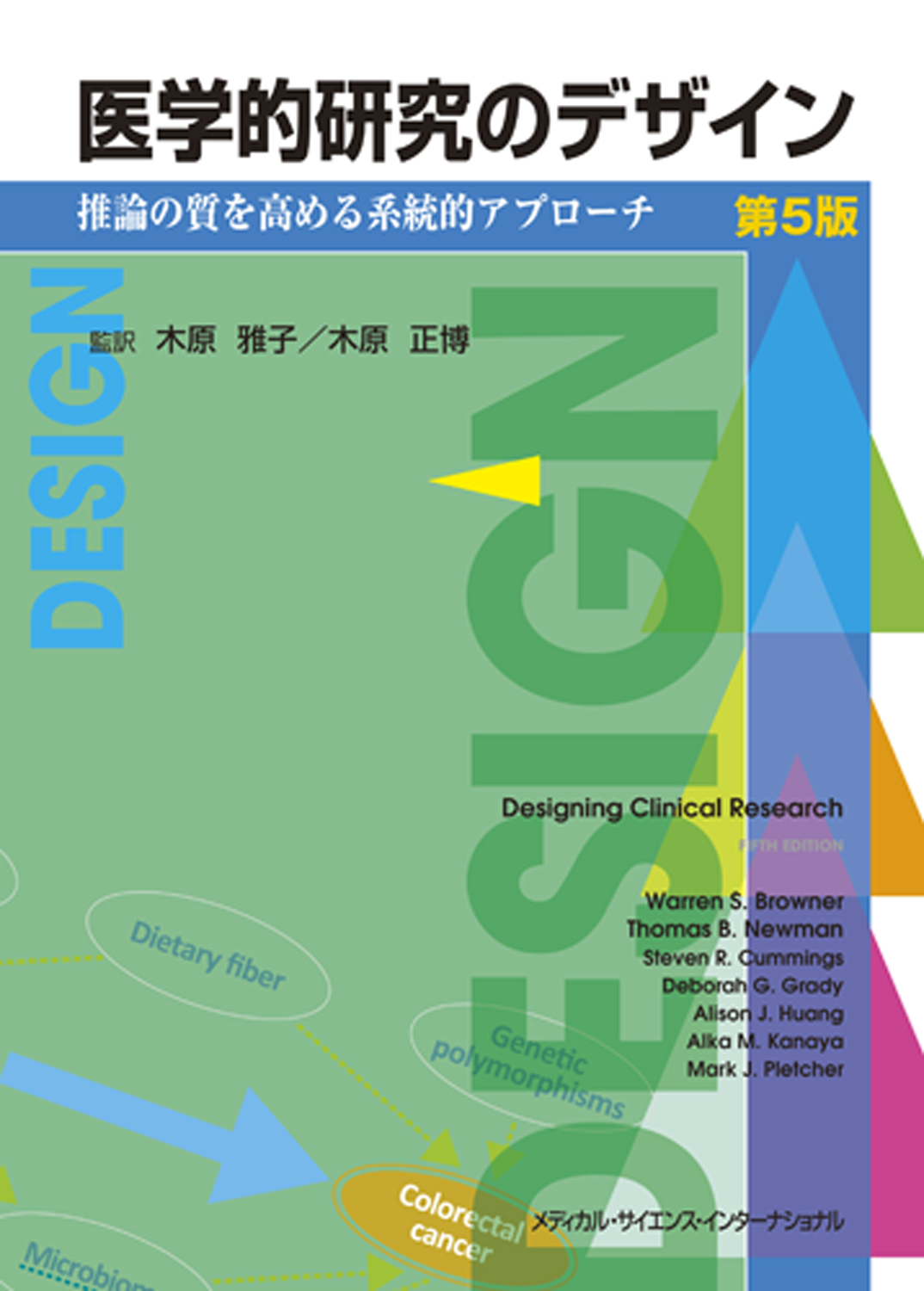
- 医学的研究のデザイン 第5版
- ¥6,270
-
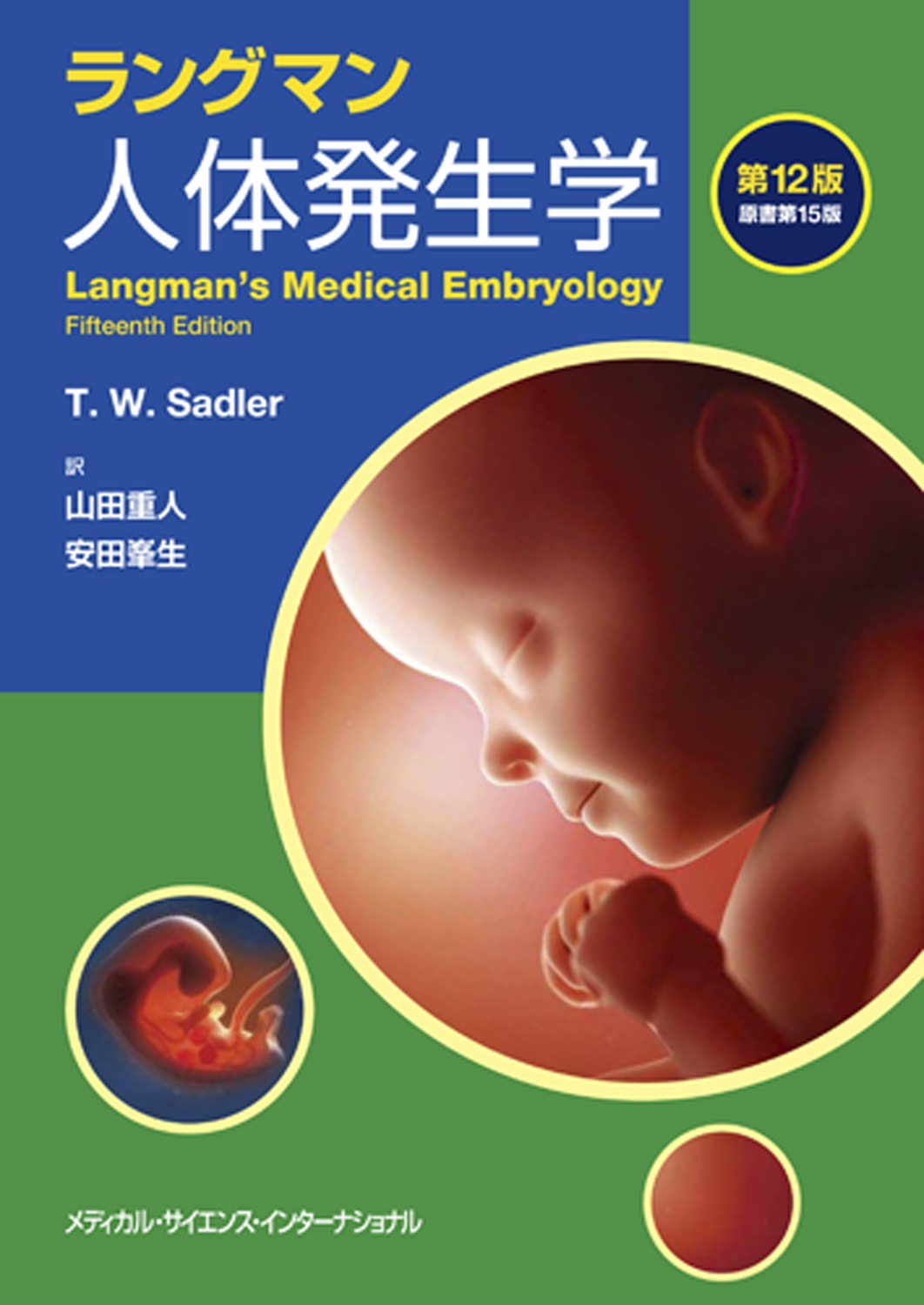
- ラングマン人体発生学 第12版
- ¥9,350
-
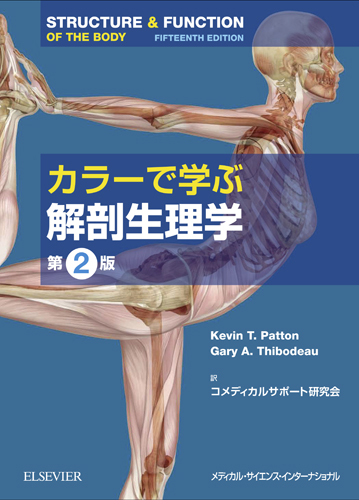
- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版
- ¥6,160
-
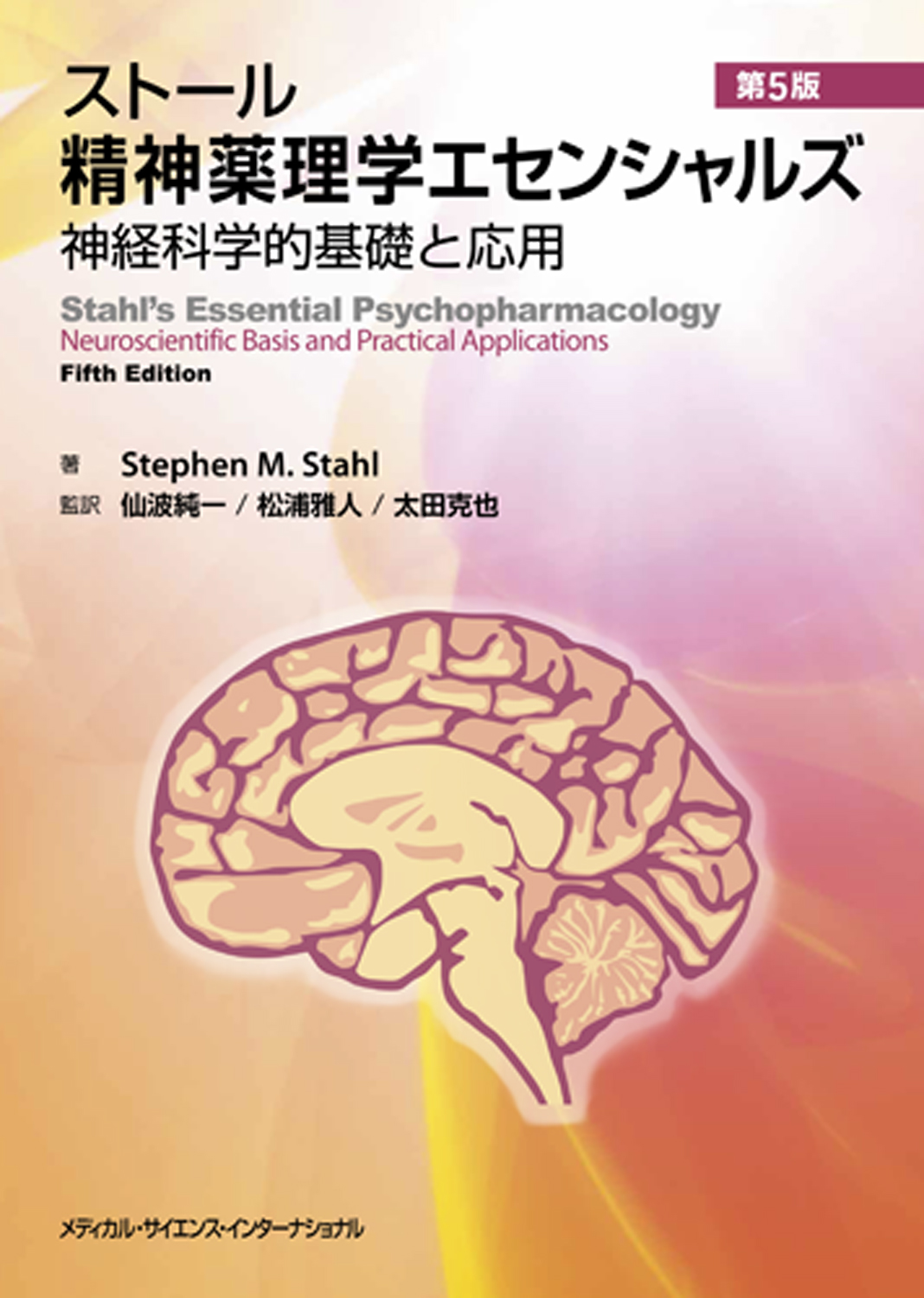
- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版
- ¥13,750
-
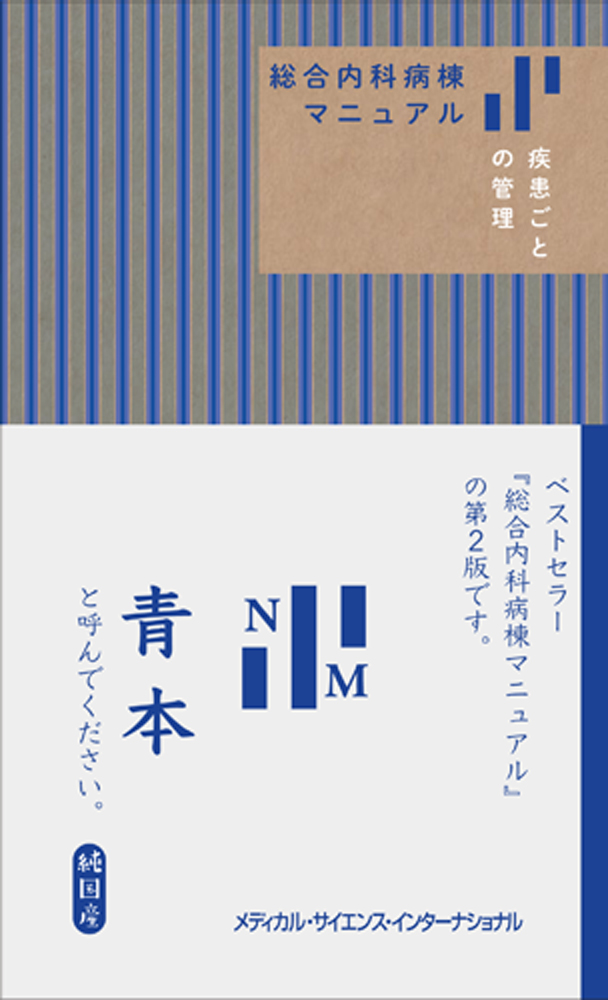
- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-
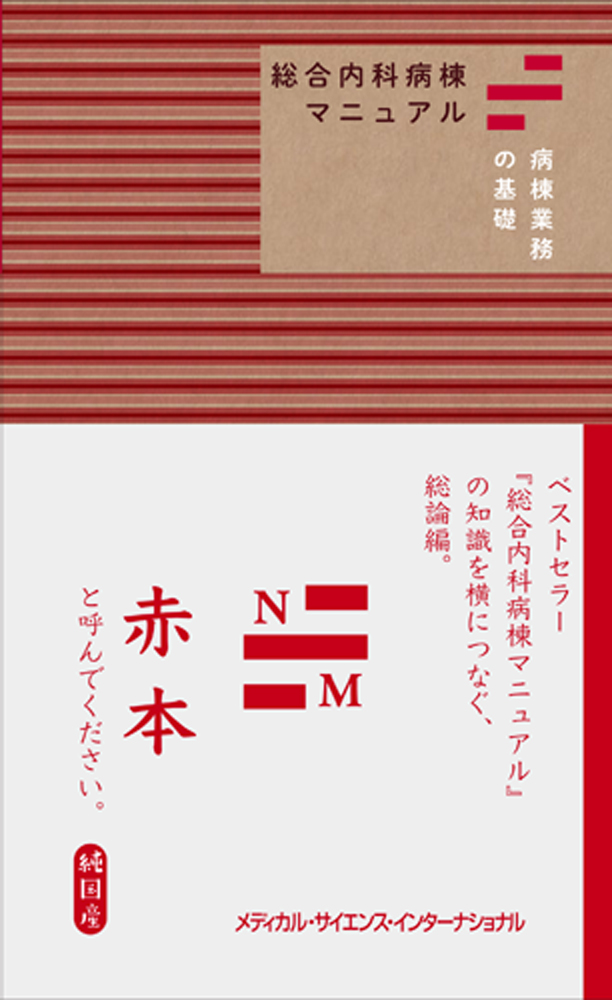
- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-
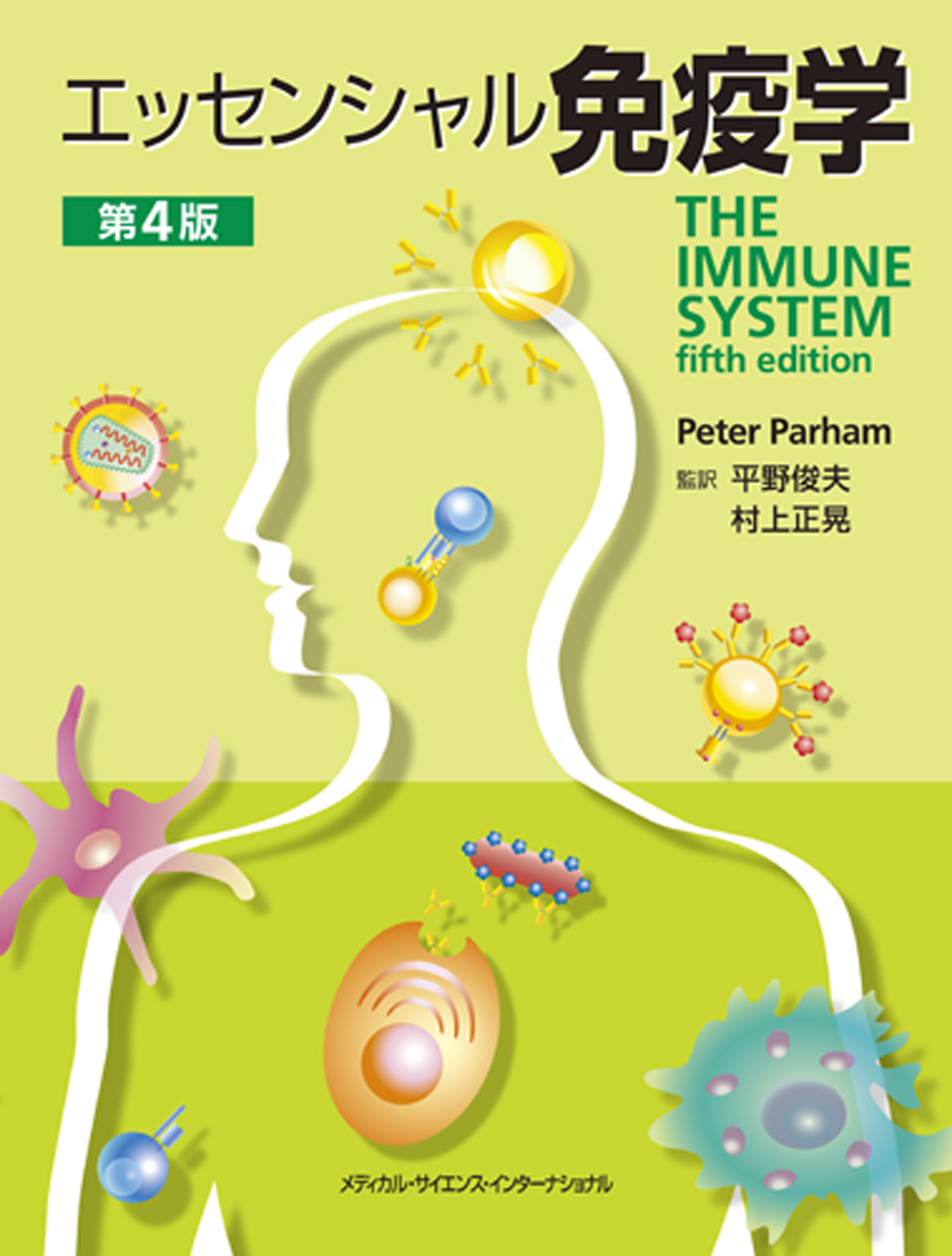
- エッセンシャル免疫学 第4版
- ¥7,150
-
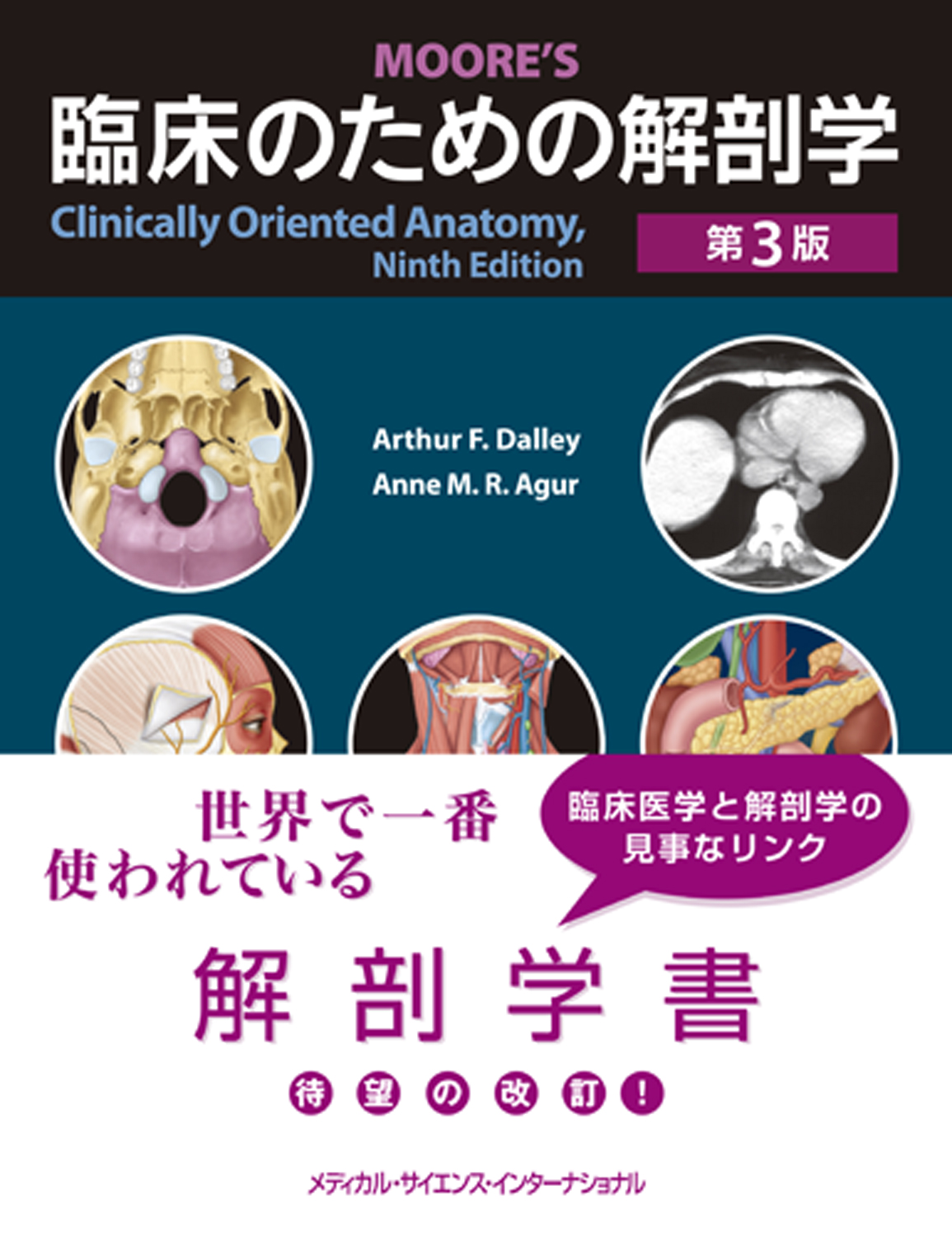
- 臨床のための解剖学 第3版
- ¥15,950
-
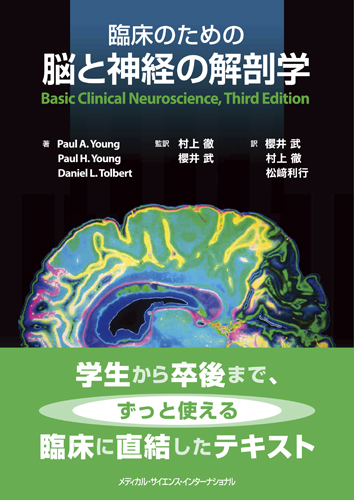
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-
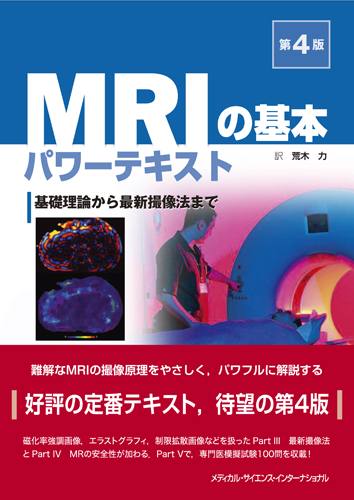
- MRIの基本パワーテキスト 第4版
- ¥7,150
-
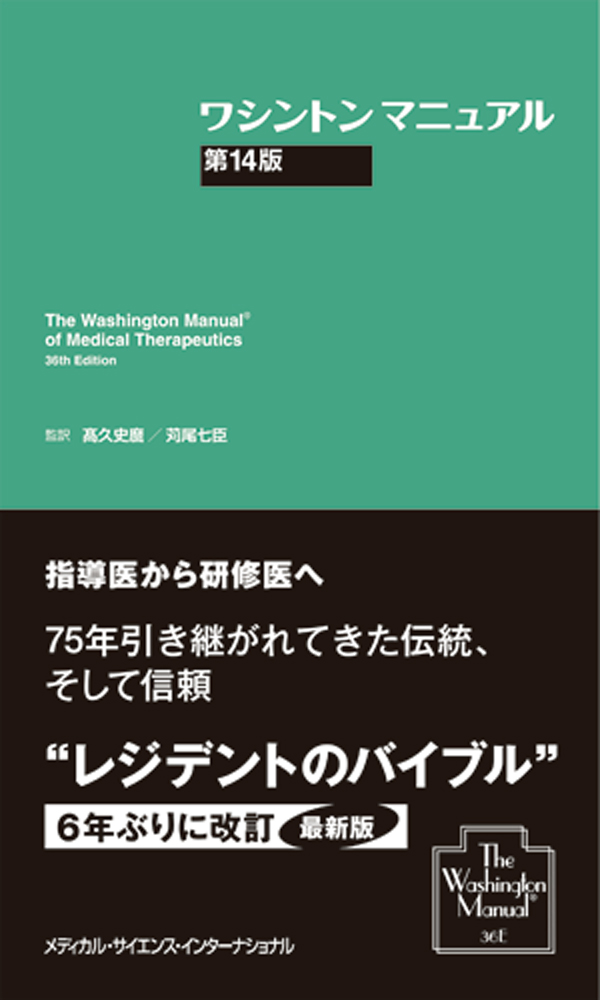
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-

- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-
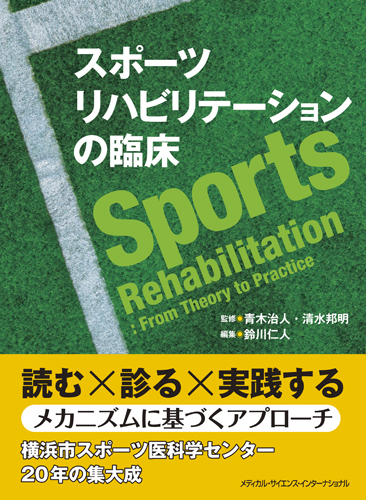
- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-
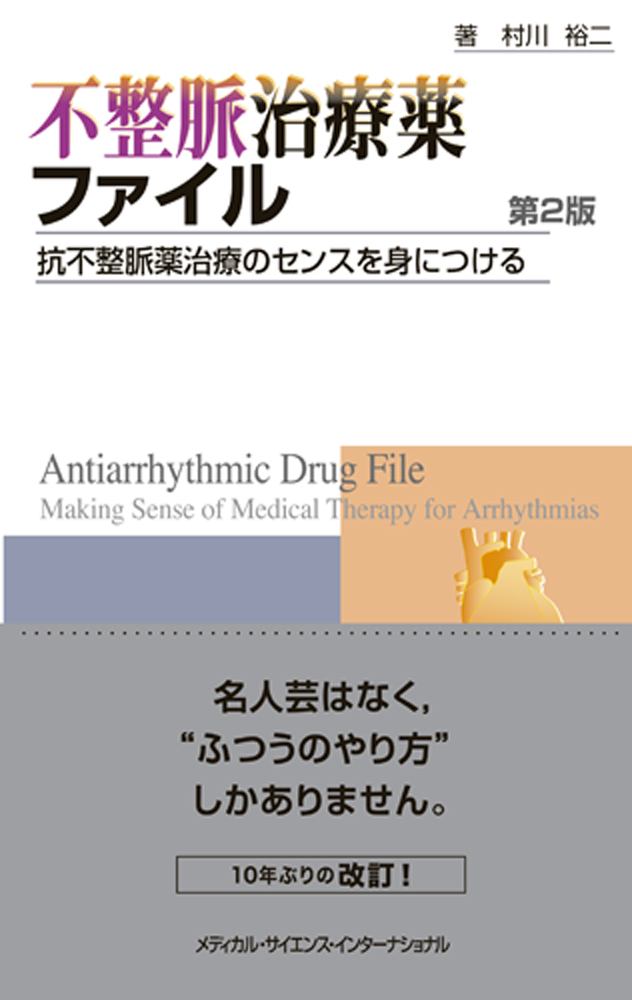
- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
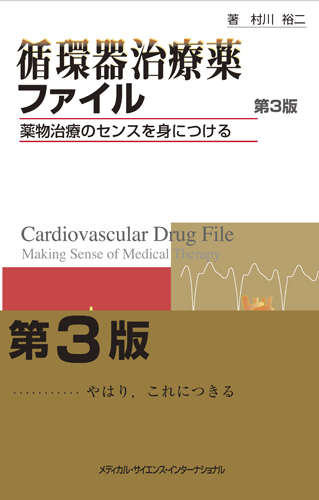
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-
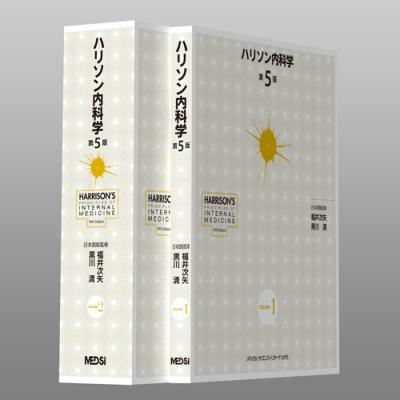
- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
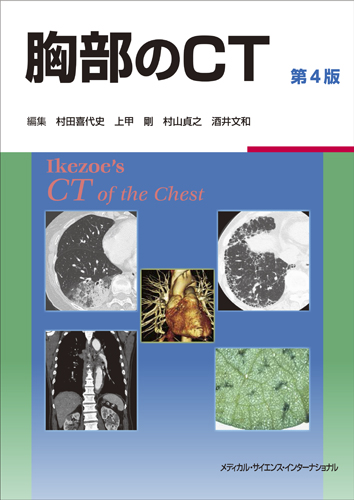
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
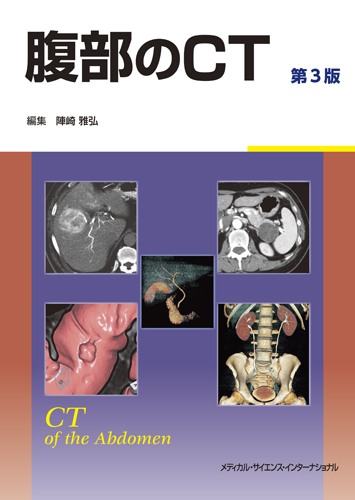
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
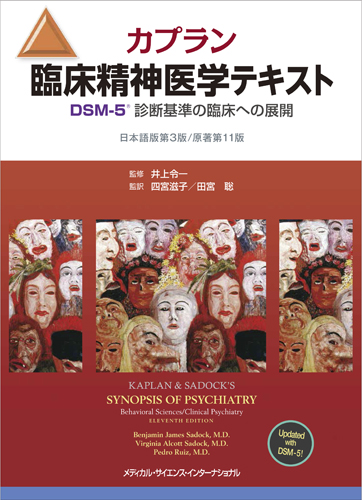
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000